公務員試験対策
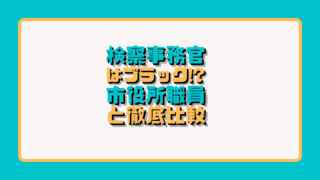
【検察庁はブラック?】民間企業・市役所勤務経験のある元検察事務官が徹底解説こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今この記事を見ている方は以下のような悩みを...
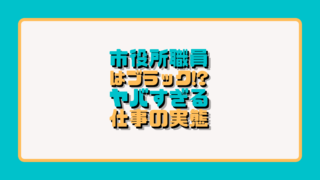
【死ぬほどブラック!】ヤバすぎる市役所職員の勤務実態を元検察事務官が徹底解説こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今この記事を見ている方は以下のような悩みを...
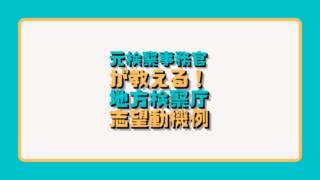
元検察事務官による志望動機の作り方&志望動機例【4選】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今この記事を見ている方は以下のような悩みを...
検察事務官の仕事内容
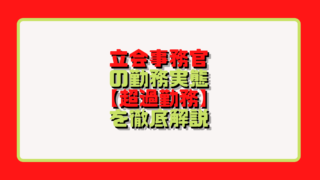
立会事務官の超過勤務(残業)について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、...

立会事務官の週休日等の勤務(休日出勤)について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、...

立会事務官の有給休暇(年次・夏季)の取得実態について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、...
検察事務官の各種制度
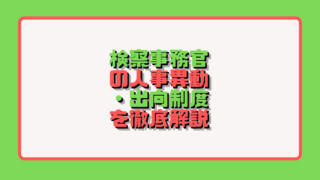
検察事務官の人事異動・出向の概要について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は、検察事務官の人事異動・出向の概要に...
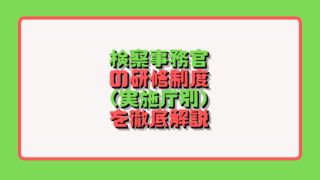
検察事務官の研修制度の概要について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、検察事務官の研修制度の概要につ...
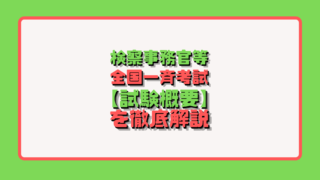
検察事務官等全国一斉考試の試験概要について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、検察事務官等全国一斉考試の試験...
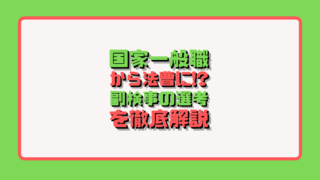
国家一般職から法曹に!?副検事の概要となり方について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、副検事の概要となり方について詳...
検察事務官の福利厚生
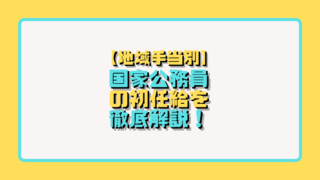
国家公務員の初任給(地域手当別)について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の初任給について詳し...
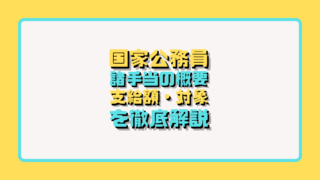
国家公務員の諸手当の概要(支給対象者・支給額)について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の諸手当の概要(支給...
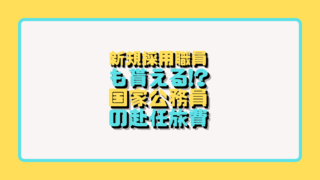
新規採用職員も貰える!?国家公務員の赴任旅費について【元検察事務官が徹底解説】こんにちは。元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は,国家公務員が転居を伴う異動の際に貰える...

