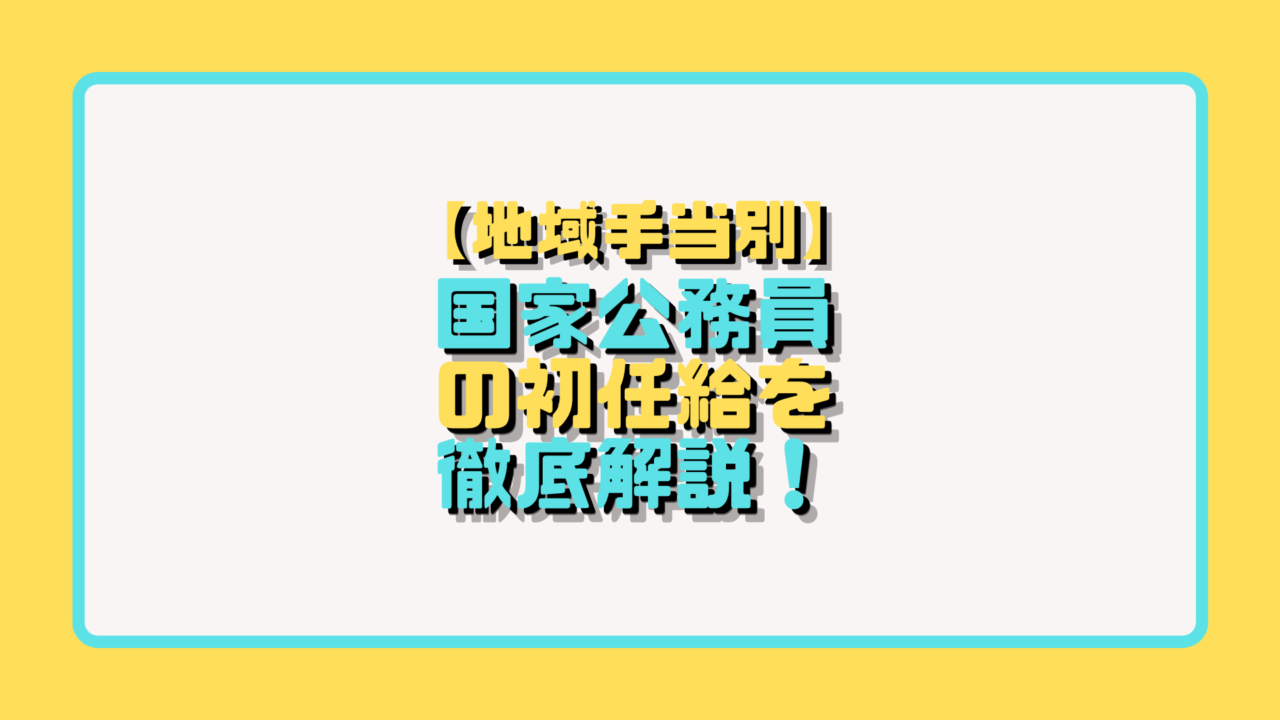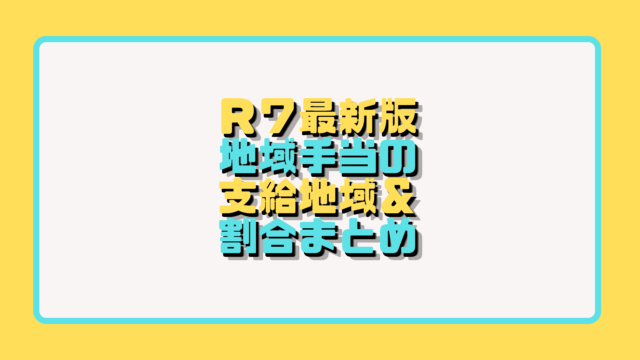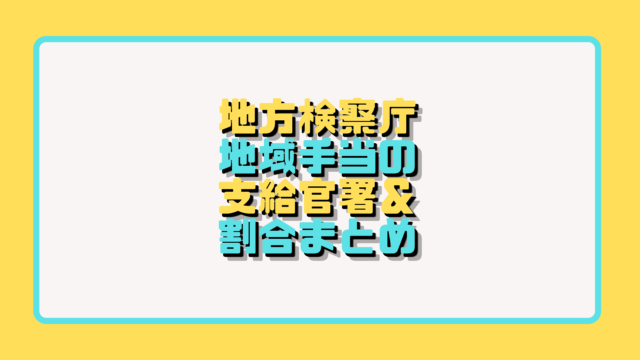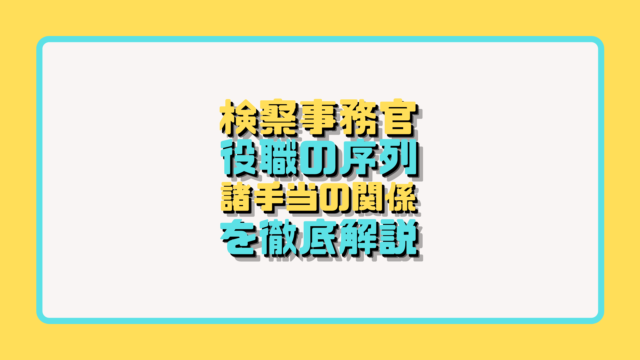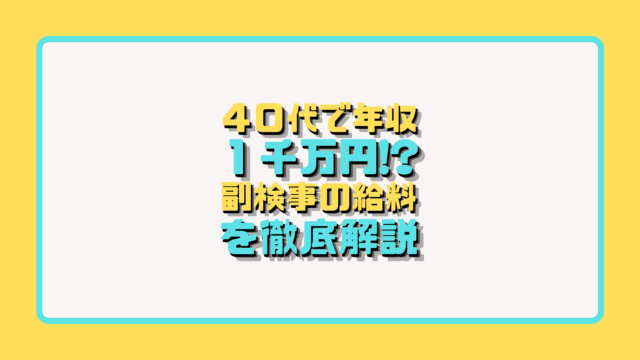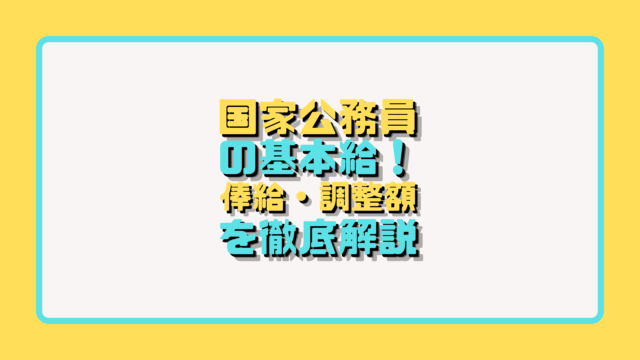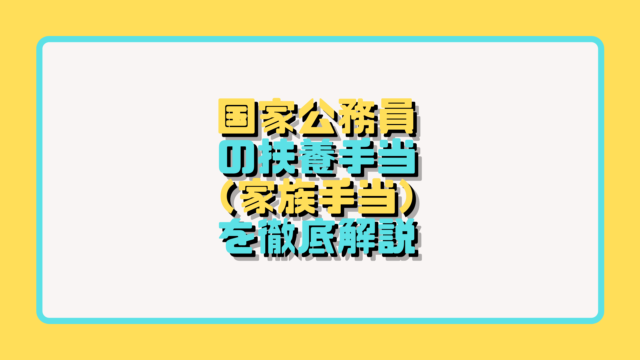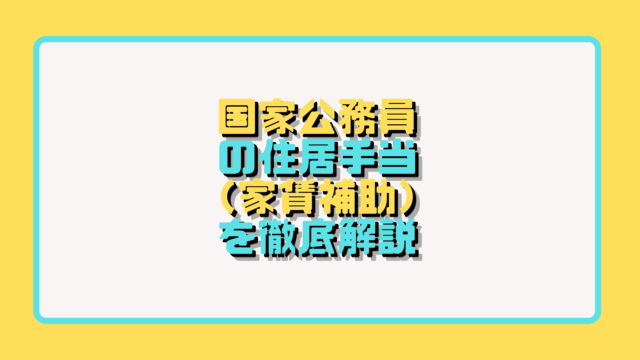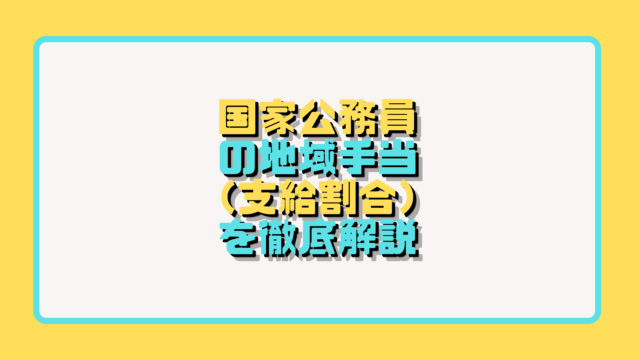こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の初任給について詳しく紹介していきます。
初任給は内定者のみならず公務員受験生も気になるポイントだと思いますので、是非参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和7年4月1日時点のものとなります。
初任給の概要について
国家公務員の給料は「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」や各種人事院規則などによって定められています。
そして、初任給は基本給である「俸給」と「諸手当」で構成されますので、それぞれ見ていきたいと思います。
俸給(基本給)
俸給とは国家公務員の基本給に当たりますが、適用される俸給表・職務の級・号俸によって俸給月額が決まります。
- 俸給表
職務、勤務条件などの類似性に応じて分類 - 職務の級
職務の複雑・困難・責任の度合いに応じて決定 - 号俸
職員の能力や経験、実績等に応じて決定
適用される俸給表は「人事院規則9-2(俸給表の適用範囲)」で定められていますが、一般の国家公務員が適用される俸給表は行政職俸給表(一)となります。
検察事務官は、採用時は行政職(一)、一定の勤務経験後(※)は公安職(二)が適用される。
※大卒程度:1年、高卒程度:5年
初任給については「人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)初任給基準表」により、採用試験の区分や学歴等によって〇級〇号俸からスタートするかが決まります。
- 国家総合職(院卒)
2級11号俸:244,800円 - 国家総合職(大卒)
2級 1号俸:230,000円 - 国家一般職(大卒)
1級25号俸:220,000円
- 国家一般職(高卒)
1級 5号俸:188,000円
また、俸給月額は「給与法別表第一~第十一」により俸給表別に職務の級と号俸に対応する月額が定められています。
上位の職務の級への変更を昇格、上位の号俸への変更を昇給と言う。
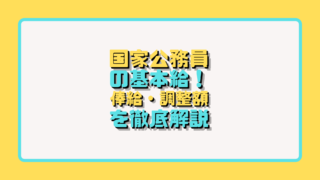
なお、入庁前の学歴や職歴によって初任給は調整されますので、それぞれ見ていきたいと思います。
上位の学歴等を有する場合
上位の学歴等を有する場合ですが「人事院規則9-8第14条」により初任給の調整方法が定められています。
具体的には、下記表を用いて算出した加算数を初任給の号俸に加算する方法となります。
| 博士課程修了 | 21 | |
| 修士課程修了など | 18 | |
| 大学専攻科卒 | 17 | |
| 大学4卒 | 大学卒 | 16 |
| 短大3卒 | 15 | |
| 短大2卒 | 短大卒 | 14 |
| 短大1卒など | 13 | |
| 高校3卒 | 高校卒 | 12 |
| 高校2卒 | 11 | |
| 中学卒 | 9 |
加算額は、上記表の自身の学歴等に対応する数から採用試験の区分・学歴等に対応する数を減じた数に4を乗じた数となります。
- 修士課程修了→国家一般職(大卒)
加算額:(18-16)×4=8
初任給:1級33号俸(25+8) - 短大2卒→国家一般職(高卒)
加算額:(14-12)×4=8
初任給:1級13号俸(5+8)
号俸は一般的に毎年4号俸ずつ昇給していきますので、採用区分より上位の学歴に費やした年数分、一般的な昇給をしていたという扱いとなります。
職歴等の経験年数を有する場合
職歴等の経験年数を有する場合ですが「人事院規則9-8第15条、同条の2」により初任給の調整方法が定められています。
具体的には、経験年数に4号俸を乗じた数を初任給の号俸に加算する方法となりますが、「人事院規則9-8別表第四経験年数換算表」により経験年数を調整します。
| 経歴 | 換算率 |
| 公務員など | 100/100 |
| 民間企業など | 80/100 |
| 学校等の在学期間 | 100/100 |
| その他の期間 | 25/100 |
上記表は簡易化したものになりますが、公務員100%、民間80%、無職25%とおおよそ理解してもらえればと思います。
- 民間5年の場合(※)
60×0.8=48月
48÷12=4年
4×4=16
初任給:1級41号俸(25+16) - 民間1年、無職2年の場合(※)
12×0.8+24×0.25=15.6月
16÷12=1.33…年
1×4=4
初任給:1級29号俸(25+4)
※国家一般職(大卒)区分
ちなみに、経験年数の調整方法には細かい手順がありますので、入庁前に自身の正確な初任給をどうしても知りたい場合は人事担当者に確認してもらえればと思います。
- 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について
第15条の2関係
諸手当
国家公務員の諸手当には6種類、23個の手当がありますが、新規採用職員でも支給対象となる手当は多くあります。
- 生活補助給的手当
住居手当、通勤手当など - 地域給的手当
地域手当、寒冷地手当など - 職務の特殊性に基づく手当
特殊勤務手当など - 時間外勤務等に対し支給する手当
超過勤務手当、休日給など - 賞与等に相当する手当
期末手当、勤勉手当 - その他
本府省業務調整手当など
上記手当の中でも、勤務官署に応じて毎月固定額が支給される下記手当についてそれぞれ見ていきたいと思います。
地域手当
地域手当とは、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当になります。
(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合
支給割合は4%~20%の範囲の5段階で設定されているが、主な支給地域と支給割合は以下となります。
| 給地 (支給割合) |
都道府県 | 中核市 |
| 1級地 (20%) |
東京都特別区 | |
| 2級地 (16%) |
東京都 | 横浜市 大阪市 など |
| 3級地 (12%) |
神奈川県 大阪府 |
さいたま市 千葉市 名古屋市 など |
| 4級地 ( 8%) |
愛知県 京都府 |
仙台市 静岡市 神戸市 広島市 福岡市 など |
| 5級地 ( 4%) |
茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 静岡県 三重県 滋賀県 兵庫県 奈良県 広島県 福岡県 |
札幌市 岡山市 高松市 など |
なお、地域手当額は他の手当(期末・勤勉手当、超過勤務手当など)の算定にも用いられるため、地域手当の有無が初任給に与える影響は大きくなります。
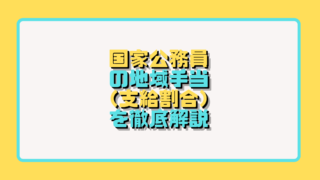
本府省業務調整手当
本府省業務調整手当とは、本府省の業務に従事する職員に支給される手当になります。
俸給表及び職務の級に応じて定められた額を支給
本府省業務調整手当の支給額は「人事院規則9-123(本府省業務調整手当)別表」で定められていますが、行政職(一)俸給表の支給額は以下となります。
| 職務の級 | 支給額 |
| 1級 | 7,200円 |
| 2級 | 8,800円 |
| 3級 | 17,500円 |
| 4級 | 22,100円 |
| 5級 | 37,400円 |
| 6級 | 39,200円 |
| 7級以上 | 41,800円 |
国家総合職の場合、職務の級は2級からスタートしますので、本府省業務調整手当として月額8,800円が支給されることになります。
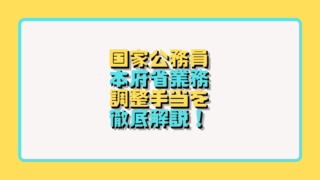
- 初任給は採用試験の区分・学歴等によって決まる。
- 上位の学歴や職歴がある場合は号俸が調整される。
- 新規採用職員でも支給対象となる諸手当(地域手当・本府省業務調整手当など)がある。
では、次に、地域手当の支給割合別の初任給の算定例について見ていきたいと思います。
初任給の算定例について
地域手当の支給割合別の初任給の算定例について、下記の場合について見ていきたいと思います。
国家総合職の初任給
国家総合職の初任地は中央省庁(霞が関勤務)になりますので、初任給は俸給+地域手当(支給割合20%)+本府省業務調整手当(月額8,800円)で算定しています。
| 支給 割合 |
2級1号俸 (大卒程度) |
2級11号俸 (院卒程度) |
| 20% | 284,800円 | 302,560円 |
| 0% | 230,000円 | 244,800円 |
参考に俸給月額のみの金額も掲載しましたので、手当が与える影響の大きさを比較してみてください。
国家一般職の初任給
国家一般職の初任給は、俸給月額+地域手当で算定しています。
| 支給 割合 |
1級5号俸 (高卒程度) |
1級25号俸 (大卒程度) |
| 20% | 225,600円 | 264,000円 |
| 16% | 218,080円 | 255,200円 |
| 12% | 210,560円 | 246,400円 |
| 8% | 203,040円 | 237,600円 |
| 4% | 195,520円 | 228,800円 |
| 0% | 188,000円 | 220,000円 |
地域手当の有無によって、高卒程度で約3万7千円、大卒程度で4万4千円の差がありますので、地域手当の影響がいかに大きいか分かると思います。
【参考】国家一般職(大卒)2年目
本記事を読んでいる方の多くは検察事務官に興味がある方だと思いますので、参考に検察事務官(大卒)の2年目の給料も紹介したいと思います。
| 支給 割合 |
公(二) 1級24号 |
行(一) 1級28号 |
差額 |
| 20% | 305,280円 | 269,160円 | 36,120円 |
| 16% | 295,104円 | 260,188円 | 34,916円 |
| 12% | 284,928円 | 251,216円 | 33,712円 |
| 8% | 274,752円 | 242,244円 | 32,508円 |
| 4% | 264,576円 | 233,272円 | 31,304円 |
| 0% | 254,400円 | 224,300円 | 30,100円 |
大卒区分の検察事務官は2年目から公安職(二)俸給表が適用されますので、一般の行政職公務員と比べて約3万円~3万6千円も給料がアップします。
ちなみに、俸給月額は期末・勤勉手当(ボーナス)や様々な手当の算定基礎となりますので、年収ではさらに大きな差がつくことになります。
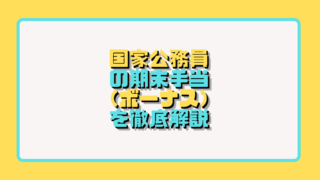
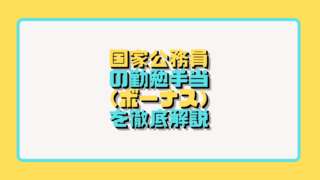
おわりに
今回は国家公務員の初任給について紹介してきました。
初任給額は進路を決める上で重要な要素となりますので、理解した上で自身のキャリアプランニングに活かしてもらえればと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。