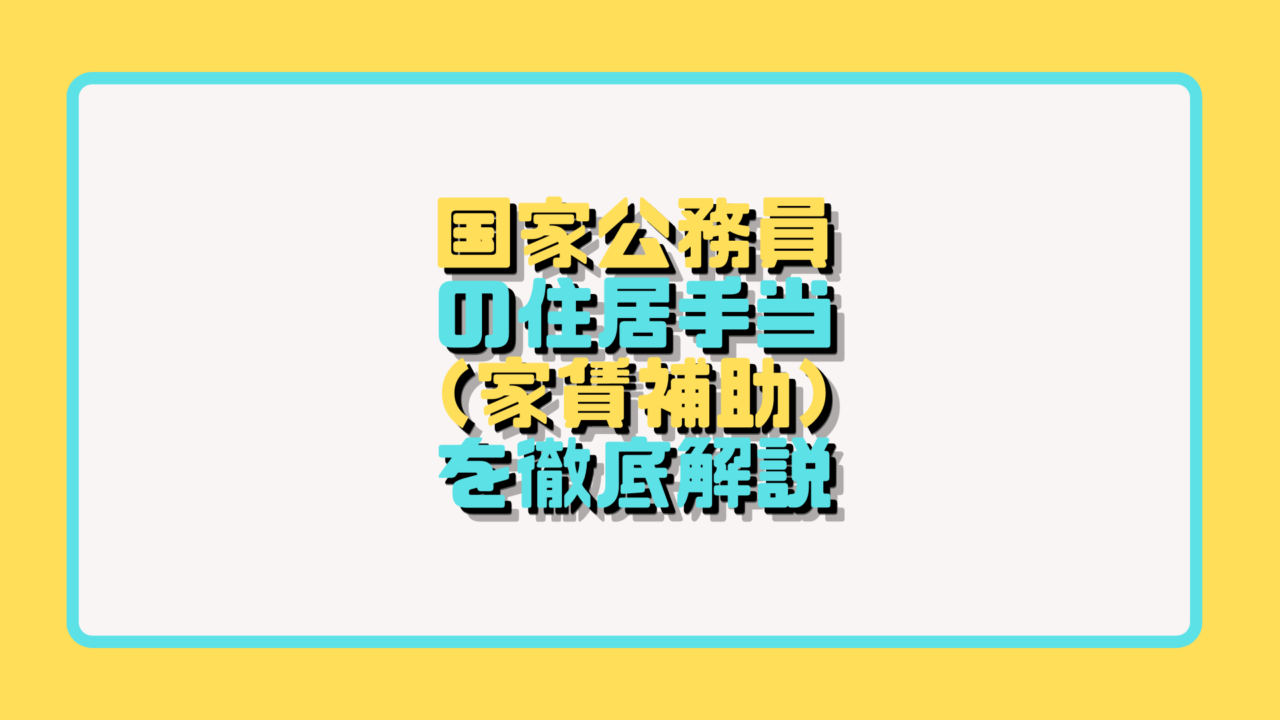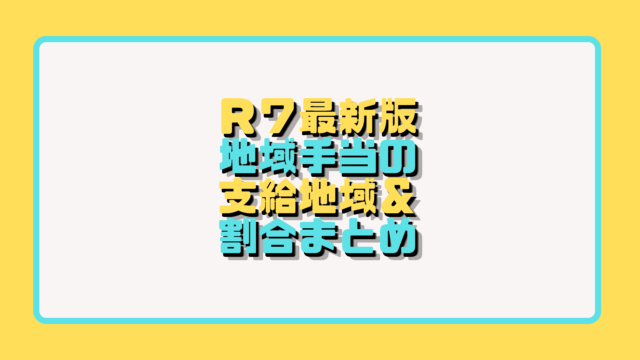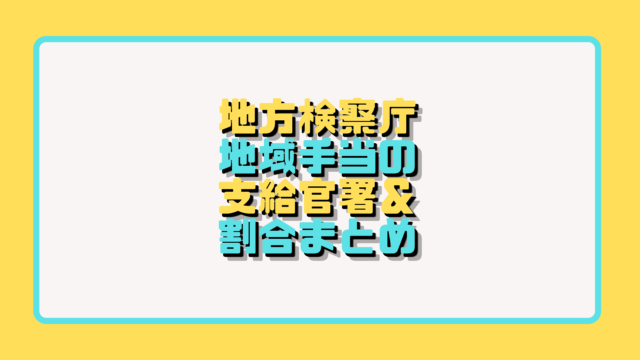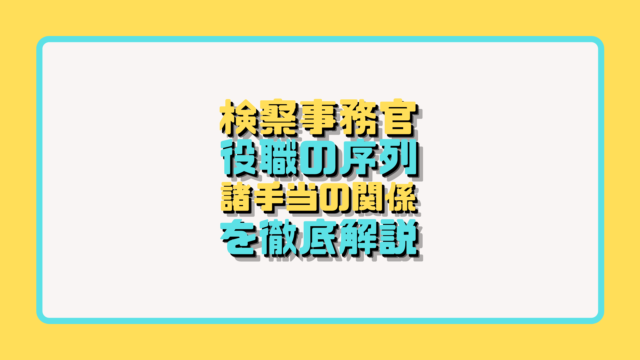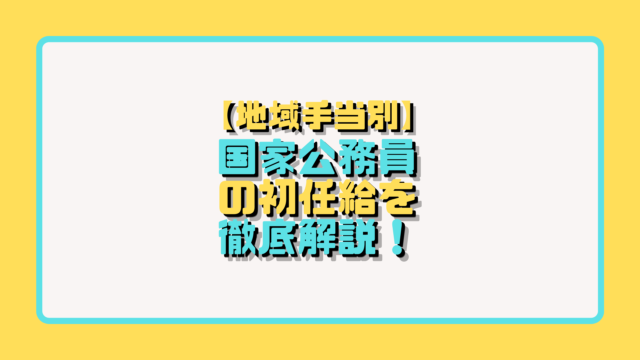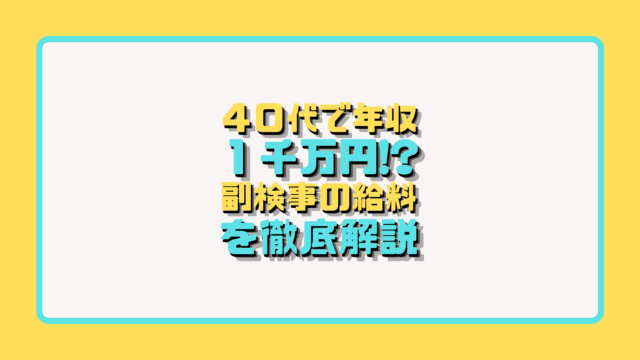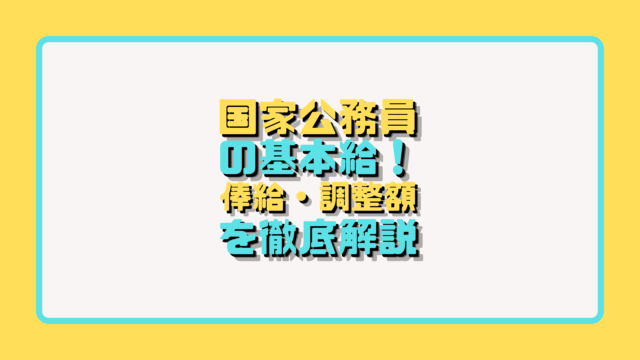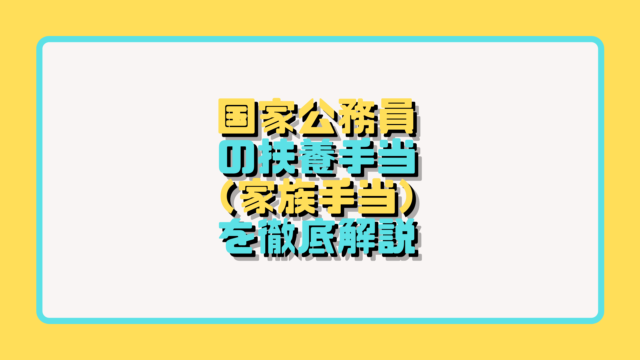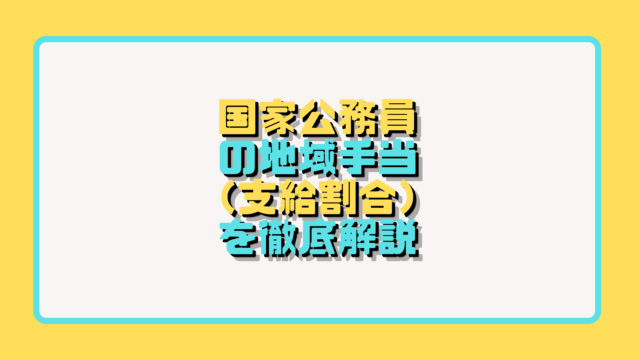こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では国家公務員の住居手当(家賃補助)について詳しく紹介していきます。
賃貸住まいの方が多い若手国家公務員にとって身近な手当となりますので、現職の方はもちろん、内定者や受験生の方も参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和6年4月1日時点のものとなります。
住居手当の概要について
住居手当とは借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給される手当になりますが、手当の概要として下記項目を見ていきます。
住居手当の支給対象者
住居手当の支給対象者ですが、賃貸住宅を借り受け、月額1万6千円を超える家賃を支払っている職員が対象になりますが、「自ら居住するため」だけでなく「配偶者等が居住するため」の住宅も対象となります。
-
自ら居住するため住宅を借り受け、月額1万6千円を超える家賃を支払つている職員
- 単身赴任手当を支給される職員で、配偶者等が居住するための住宅を借り受け、月額1万6千円を超える家賃を支払つているもの
では、支給要件として下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
賃貸の目的
まず、賃貸の目的ですが、「自ら住宅するため」だけではなく「配偶者等が居住するため」に住宅を借り受ける場合も支給対象となります。
なお、配偶者等が居住するための場合、単身赴任手当を支給される職員である必要があります。
- 異動に伴い配偶者と別居。
- 別居理由は介護などやむを得ない事情による。
- 通勤距離が原則60㎞以上。
また、配偶者等には、配偶者の他に18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子も含まれます。
賃貸住宅
次に、賃貸住宅ですが、全ての賃貸住宅が住居手当の対象となるわけではなく、支給対象外となる賃貸住宅があります。
- 有料官舎
- 扶養親族が所有する住宅
- 扶養親族ではない職員の配偶者、父母、配偶者の父母が所有又は借り受けて居住している住宅
なお、賃貸住宅の契約名義人が職員単独名義ではなくても以下の場合は支給対象者となります。
- 職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員
- 配偶者等(扶養親族・職員の配偶者・一親等の血族又は姻族)と協同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合に、その生計を主として支えている職員
家賃の月額
最後に、家賃の月額ですが、人事院通達により家賃に含まれないものが規定されています。
- 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
- 電気、ガス、水道等の料金
- 団地内の児童遊園、街燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
- 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る賃料
勘違いされる方も多いですが、住居手当の要件上、共益費は家賃に含まれないとされています。
また、家賃と食費等を併せて支払っている場合で家賃の額が明確でない場合がありますが、その場合の家賃の月額は以下となります。
- 食費等を含む場合
→支払額の40%に相当する額 - 電気ガス水道料金を含む場合
→支払額の90%に相当する額
住居手当の支給額
次に、住居手当の支給額ですが、以下の計算式で算定されます。
-
家賃月額27,000円以下の場合
家賃月額-16,000円 -
家賃月額27,000円を超える場合
(家賃月額-27,000円)÷2+11,000円
※配偶者等の場合は2分の1の額
なお、住居手当の支給額の上限は28,000円(配偶者等の場合は14,000円)となりますので、家賃月額61,000円以上で住居手当の上限が支給されます。
不動産管理会社によっては共益費を賃料に含めて契約してくれる場合があるため、共益費を含めることで住居手当額が上がるのであれば交渉する余地あり。
- 賃料55,000円、共益費6,000円
→住居手当25,000円 - 賃料61,000円、共益費0円
→住居手当28,000円
住居手当の関係法規
最後に、住居手当の関係法規についてですが、根拠条文を確認されたい方は是非参考にしてください。
- 一般職の給与に関する法律
11条の10、19条の8
住居手当の支給関係について
住居手当の支給関係については、下記項目について見ていきます。
住居手当の要件確認
まず、住居手当の要件確認ですが、支給を受けるための届出時の要件確認と継続して支給を受けるための受給者に対する現況確認があります。
届出時の要件確認
住居手当を受給するためには住居届と証明書類を提出する必要があります。
- 賃貸借契約書のコピー
- 家賃の支払いが分かるもの
→領収書・口座明細など - 住民票の写し
住居手当の支給開始月にも関わってきますので、この届出は速やかに行う必要があります。
なお、引越して賃貸住宅が変更した場合や家賃の額等に変更があつた場合も同様となります。
受給者に対する現況確認
住居手当の受給者に対しては、毎年1回、受給要件を欠いていないか現況確認が行われます。
現況確認では2~3か月分の家賃支払いを証明するために引落口座の明細などを提出する必要があります。
不正受給が発覚すると、不正受給額の還付はもちろん、懲戒処分となる。
→免職にならずとも職種によっては自主退職せざるを得なくなる。
住居手当の支給の始期・終期
次に、住居手当の支給の始期・終期ですが、支給要件を満たした日の属する月の翌月(1日の場合は当月)から開始し、支給要件を欠いた日の属する月(1日の場合は前月)に終わります。
なお、届出が速やかに行われた場合は要件具備の日が基準となりますが、要件具備から15日経過した後に届出された場合は届出日が基準となります。
- 4月20日要件具備、5月2日届出
→5月から支給(要件具備日基準) - 4月20日要件具備、5月7日届出
→6月から支給(届出日基準)
住居手当の支給停止
最後に、住居手当の支給停止ですが、支給要件を具備していても以下に該当するときはその期間中は支給されないこととなります。
- 懲戒処分で停職にされた場合
- 所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合
- 育児休業している場合
- 交流派遣されている場合
- 自己啓発等休業をしている場合
- 配偶者同行休業をしている場合
ちなみに、育児休業期間中は給与も支給されませんが、育児休業手当金として標準報酬月額の50%(180日までは67%)が最長2年間支給されます。
おわりに
今回は国家公務員の住居手当について紹介してきました。
給与制度は国家公務員として理解しておくべき制度になりますので、理解した上でライフプランニング等に活用してもらえたらと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。