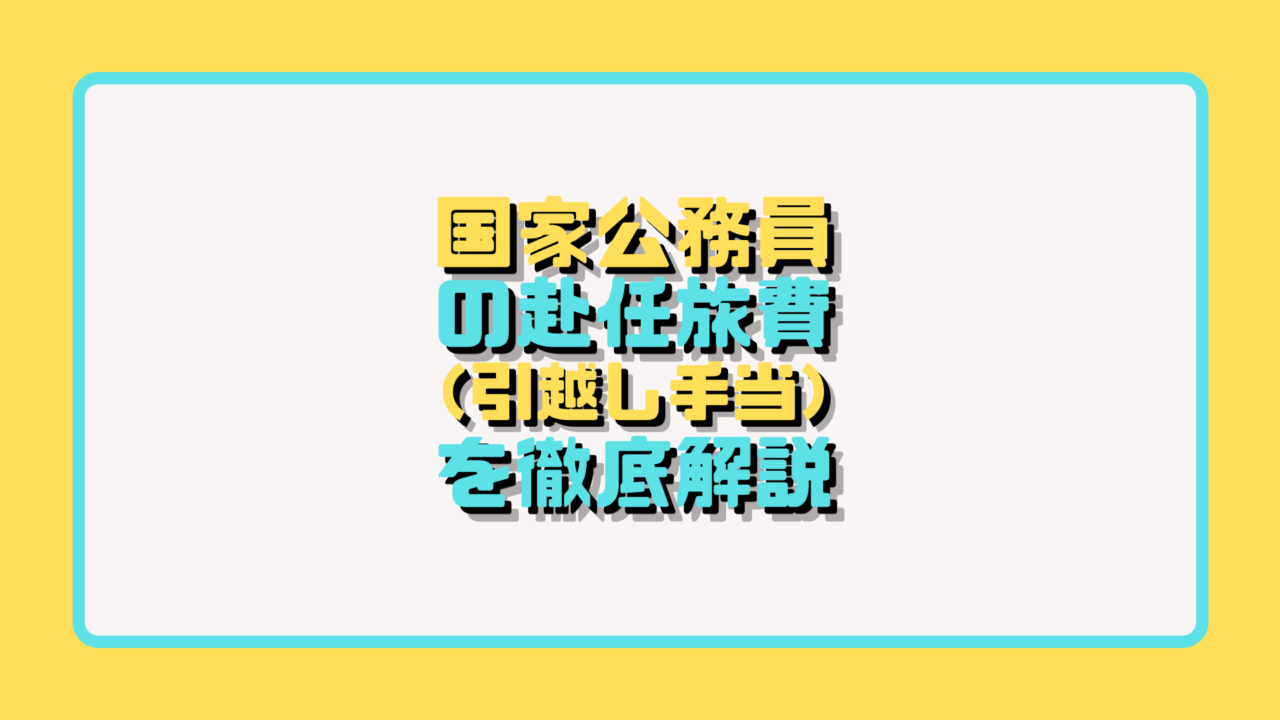こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では国家公務員の赴任旅費について詳しく紹介していきます。
国家公務員には引っ越しを伴う異動がありますので、現職の方はもちろん、内定者や受験生の方も参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和6年4月1日時点のものとなります。
赴任旅費の概要について
国家公務員は出張又は赴任した場合に旅費が支給されますが、赴任に伴い支給される旅費のことを総称して「赴任旅費」といいます。
- 交通費
- 移転料(引っ越し代)
- 着後手当
- 扶養親族移転料
では、赴任旅費の概要として下記項目を見ていきます。
赴任旅費の支給対象者
まず、赴任旅費の支給対象者ですが、文字通り赴任した職員が支給対象となります。
- 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行すること。
- 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行すること。
赴任には採用に伴う移転も含まれますので、新規採用職員も赴任旅費の支給対象となります。
赴任と引っ越しの時期がずれる場合、赴任を伴う移転には当たらないため、赴任旅費は支給されない。
【例】
新規採用で4月は実家から官署まで通勤、5月から官署近くに引っ越した場合
→赴任旅費の支給対象外。
赴任旅費の支給額
次に、赴任旅費の支給額ですが、赴任旅費を構成する下記旅費ごとに見ていきます。
交通費
赴任に伴い支給される交通費ですが、旧在勤官署(新規採用は旧住居)から新在勤官署までの旅程に応じた下記交通費が支給されます。
- 鉄道賃
- 船賃
- 航空賃
- 車賃
鉄道賃については職員が実際に支払った実費ではなく最も経済的で通常の経路と認定される費用が支給されます。
なお、距離によっては急行料金や座席指定料金の支給もありますので、新幹線を利用することも可能となります。
- 急行料金の支給要件
特別急行列車:片道100km以上
普通急行列車:片道 50km以上 - 座席指定料金の支給要件
特別急行料金:片道100km以上
普通急行列車:片道100km以上
※特別車両料金は指定職のみ
航空賃については職員が実際に支払った実費が支給されますが、航空機の利用には条件があります。
- 鉄道による移動時間が○時間以上※かかる。
※法務省は4時間 - 鉄道で移動する通常の鉄道賃より相当に安くなる。
そのため、航空機の利用が可能かどうか不明瞭である場合は事前に旅費担当者に確認しておくことが望ましいです。
移転料
移転料ですが、いわゆる引っ越し代に当たる旅費になります。
- 引っ越し業者に依頼
- 宅配便を利用
- 自家用車・レンタカー等を利用
移転料は実際にかかった実費が支給されますが、移動距離と職務の級によって上限が設定されています。
| 区分 | 3級以下 | |
| 定額 | 定額の3倍 | |
| 50㎞未満 | ( 46,500) 93,000 |
(139,500) 279,000 |
| 50㎞以上 100㎞未満 |
( 53,500) 107,000 |
(160,500) 321,000 |
| 100㎞以上 300㎞未満 |
( 66,000) 132,000 |
(198,000) 396,000 |
| 300㎞以上 500㎞未満 |
( 81,500) 163,000 |
(244,500) 489,000 |
| 500㎞以上 1000㎞未満 |
(108,000) 216,000 |
(324,000) 648,000 |
| 1000㎞以上 1500㎞未満 |
(113,500) 227,000 |
(340,500) 681,000 |
| 1500㎞以上 2000㎞未満 |
(121,500) 243,000 |
(364,500) 729,000 |
| 2000㎞以上 | (141,000) 282,000 |
(423,000) 846,000 |
職務の級が3級以下の場合、上記表の定額の3倍の金額が移転料の上限※となります。
※単身の場合は()書きの金額
なお、4級以上の移転料は以下となります。
| 区分 | 4~6級 | |
| 定額 | 定額の3倍 | |
| 50㎞未満 | ( 53,500) 107,000 |
(160,500) 321,000 |
| 50㎞以上 100㎞未満 |
( 61,500) 123,000 |
(184,500) 369,000 |
| 100㎞以上 300㎞未満 |
( 76,000) 152,000 |
(228,000) 456,000 |
| 300㎞以上 500㎞未満 |
( 93,500) 187,000 |
(280,500) 561,000 |
| 500㎞以上 1000㎞未満 |
(124,000) 248,000 |
(372,000) 744,000 |
| 1000㎞以上 1500㎞未満 |
(130,500) 261,000 |
(391,500) 783,000 |
| 1500㎞以上 2000㎞未満 |
(139,500) 279,000 |
(418,500) 837,000 |
| 2000㎞以上 | (162,000) 324,000 |
(486,000) 972,000 |
| 区分 | 7級以上、指定職 | |
| 定額 | 定額の3倍 | |
| 50㎞未満 | ( 63,000) 126,000 |
(189,000) 378,000 |
| 50㎞以上 100㎞未満 |
( 72,000) 144,000 |
(216,000) 432,000 |
| 100㎞以上 300㎞未満 |
( 89,000) 178,000 |
(267,000) 534,000 |
| 300㎞以上 500㎞未満 |
(110,000) 220,000 |
(330,000) 660,000 |
| 500㎞以上 1000㎞未満 |
(146,000) 292,000 |
(438,000) 876,000 |
| 1000㎞以上 1500㎞未満 |
(153,000) 306,000 |
(459,000) 918,000 |
| 1500㎞以上 2000㎞未満 |
(164,000) 328,000 |
(492,000) 984,000 |
| 2000㎞以上 | (190,500) 381,000 |
(571,500) 1,143,000 |
着後手当
着後手当ですが、赴任先に着任した後の諸雑費に充てるために支給される旅費になります。
- 日当定額の5日分に相当する額
- 赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額
日当と宿泊料の定額については職務の級により以下の通りとなります。
| 区分 | 日当 | 宿泊料 | |
| 甲地 | 乙地 | ||
| 3級以下 | 1,700 | 8,700 | 7,800 |
| 4~6級 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |
| 7級以上 | 2,600 | 13,100 | 11,800 |
| 指定職 | 3,000 | 14,800 | 13,300 |
なお、各省庁が定める旅費取扱規程には減額調整が定められていますが、以下の場合、着後手当は減額されることになります。
- 新在勤地に到着後直ちに職員のための国設宿舎又は自宅に入る場合
→日当2日分、宿泊料2夜分 - 赴任に伴う移転の路程が鉄道50㎞未満の場合
→日当3日分、宿泊料3夜分
- 赴任に伴う移転の路程が鉄道50㎞以上100㎞未満の場合
→日当4日分、宿泊料4夜分
そのため、官舎入居で前居住者の都合で3日以上ホテル宿泊が余儀なくされた場合などを除き、着後手当は原則2日分の支給となります。
扶養親族移転料
扶養親族移転料ですが、赴任の際に扶養親族が随伴する場合に扶養親族一人ごとに支給される旅費になります。
- 12歳以上
職員相当の交通費全額及び着後手当の3分の2に相当する額 - 6歳以上12歳未満
12歳以上の金額の2分の1に相当する額 - 6歳以下
職員相当の着後手当の3分の1に相当する額
※3人以上の場合、3人目からは職員相当の鉄道賃・船賃の2分の1に相当する金額を加算
なお、着後手当が減額調整される場合、扶養親族移転料の着後手当相当分も減額されます。
赴任旅費の関係法令
最後に、赴任旅費の関係法令ですが、根拠条文を確認されたい方は是非参考にしてください。
では次に、赴任旅費の請求手続について見ていきたいと思います。
赴任旅費の必要書類について
赴任旅費の支給を受けるためには転居の事実や各種支払の証明書類が必要となりますので、下記必要書類について見ていきます。
住民票(転入先)
赴任旅費の支給を受けるためには、転居の事実を証明するために必ず転入先の住民票が必要となります。
転入先の住民票を入手するためには市区町村への転入手続が必要となりますが、転入手続は内示日以降に行う必要があります。
内示日前に転入手続を行うと、異動に伴う転居ではなく自己都合による転居とみなされ可能性あり。
→赴任旅費の支給対象外となる。
ちなみに、赴任旅費の支給対象者に対しては旅費担当者から具体的に○○日以降に転入手続を行うよう指示されますので、注意してもらえればと思います。
大学生等で実家から旧住居に住民票を移していない場合、旧住居から転居した事実を証明するために旧住居居住の実態を証明する書類(旧住居の賃貸借契約書など)が必要になる可能性あり。
交通費の必要書類
次に、交通費の必要書類ですが、航空機を利用した場合に下記書類を提出する必要があります。
- 航空券の領収書原本
- 搭乗券若しくは搭乗レシート原本
※eチケット控えは不可
領収書は職員が支払った実費を確認するために、搭乗券や搭乗レシートは航空機の利用を確認するために必要となります。
搭乗券や搭乗レシートを紛失した場合、搭乗証明書の提出が必要。
ちなみに、航空機の利用に際しては下記のような注意事項があります。
- 旅行代理店、格安航空券の販売サイトは利用不可
- 格安航空会社(LCC)の利用不可
- マイレージの取得禁止
- 座席アップグレード分は不支給
- パック旅行は利用不可
そのため、航空券はANAやJALの公式サイトから直接購入する必要があります。
移転料の必要書類
次に、移転料の必要書類ですが、引っ越し方法によって必要書類が異なります。
引越し業者の場合
引っ越し業者の利用が一般的になると思いますが、引っ越し業者利用の場合は下記書類が必要となります。
- 引っ越し業者発行の領収書
- 見積明細書(最低3社分)
領収書は職員が支払った実費や対象外経費の確認のために、見積明細書は安価な業者を利用しているか確認するために必要となります。
大手引っ越し業者の場合、国家公務員は3社見積もりが必要なことを把握しているため、見積依頼の際に国家公務員である旨を伝えるとスムーズ。
なお、領収書・見積明細書共に費用の内訳の記載が必要となりますが、対象外経費が含まれる場合は移転料の上限に収まるとしても対象外経費分の支給はされません。
- 個人的趣味の大型なものを運搬等する際の追加費用
※ピアノなど - 荷造り・荷解きに係る追加費用
- 工事・設置等に係る追加費用
※エアコン・ガス機器は支給対象
宅配便の場合
単身者で荷物が少ないと宅配便を利用する場合もあると思いますが、宅配便利用の場合は下記書類が必要となります。
- 領収書
- 配送伝票控え
領収書は職員が支払った実費の確認のために、配送伝票は旧住居から新住居に送付されているか確認するために必要となります。
宅配便の送料が高額になる場合、引っ越し業者との比較が必要になる場合あり。
自家用車・レンタカー等の場合
自家用車やレンタカー等の利用は基本的に認められませんが、やむを得ない事情で認められる場合は下記書類が必要となります。
- ガソリン代、高速料金などの領収書
- レンタカー代の明細書
自家用車等は基本的に認められないことから、上記費用も必要最低限の利用に限り移転料が支給されることになります。
着後手当の必要書類
最後に、着後手当の必要書類ですが、3日分以上の支給となる場合は下記書類が必要となります。
- 宿泊ホテルの領収書
なお、ホテル宿泊が2日以内の場合は領収書の提出は不要となります。
ホテルに宿泊しない場合も2日分の着後手当は支給される。
おわりに
今回は国家公務員の赴任旅費について紹介してきました。
引っ越しの金銭的負担は大きいので、転居を伴う異動がある職員は制度を理解した上でキャリアプランニング等に活用してもらえたらと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。