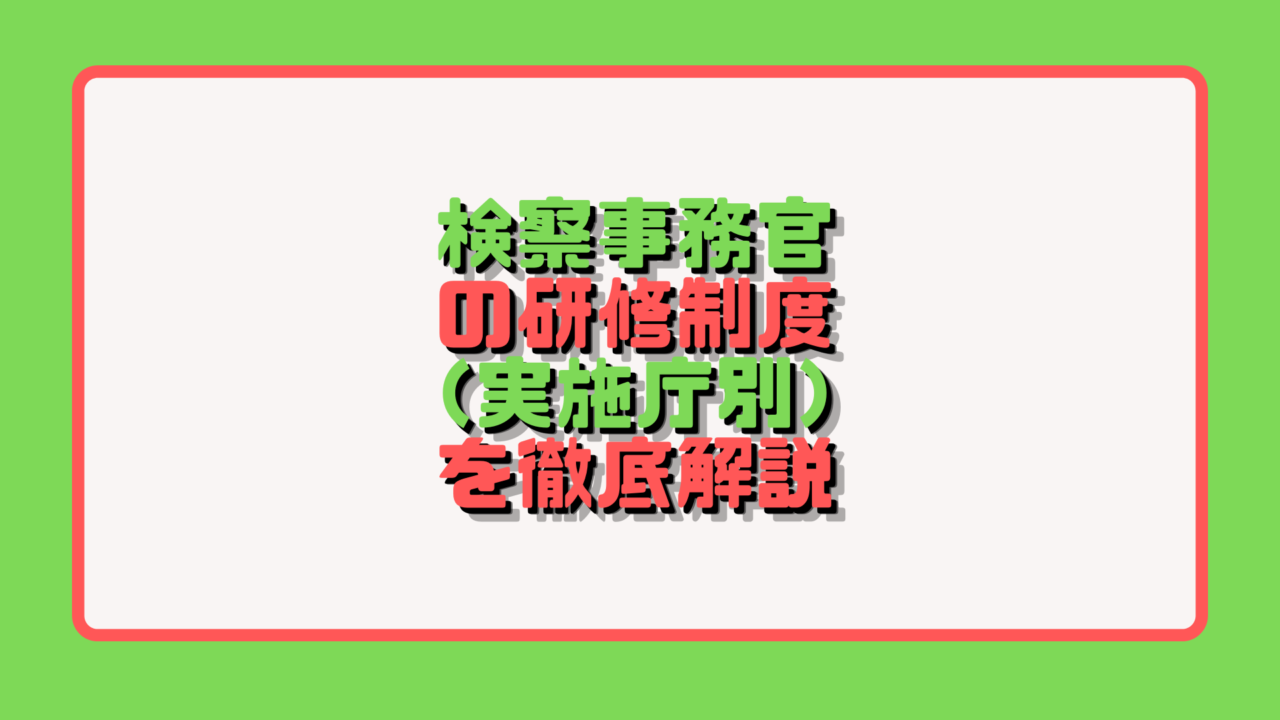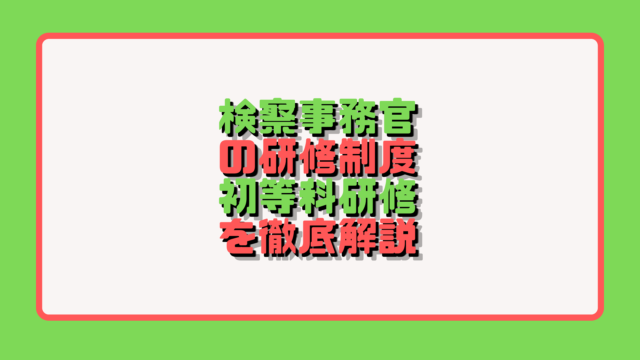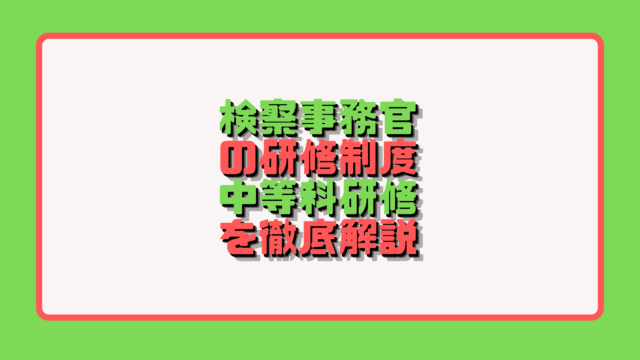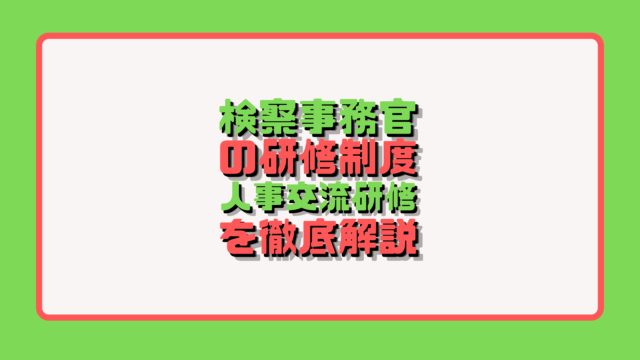こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、検察事務官の研修制度の概要について詳しく紹介していきたいと思います。
研修制度はキャリアプランを考える上で重要な要素になりますので、検察庁内定者の皆さんはもちろん、検察事務官志望の方も是非参考にしてもらえればと思います。
研修制度の概要について
検察事務官の研修制度ですが、研修事業を所管する「法務総合研究所」が本所と全国7か所の支所で各種研修を取り行っています。
また、各検察庁でも各種研修を取り行っていますので、実施庁別に分類すると3種類の研修体系となります。
- 中央研修:法務総合研究所
- 地方研修:法務総合研究所各支所
※各高等検察庁 - 自庁研修:各検察庁
ではまず、検察事務官の地方研修について見ていきたいと思います。
地方研修について
検察事務官の地方研修についてですが、各高等検察庁が高検管内の研修対象者を一同に集める集合方式で、全寮制の研修となります。
研修対象者が少ない高検の場合、他の高検と合同で研修が実施される。
研修・宿泊場所については、東京高検管内は法務省浦安総合センター、他高検管内は法務総合研究所各支所となります。
地方研修には下記4つの研修がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
初等科研修
初等科研修は、新たに検察庁に入庁した新規採用職員が研修対象者となります。
行政職俸給表(一)の新規採用職員を対象とし、検察事務官として必要な基礎的知識及び技能を習得させて、事務能率及び人格識見の向上を図ることを目的とする。
新規採用職員は検察庁に入庁したばかりで右も左も分からない状態ですので、初等科研修では検察事務官に必要な基礎的知識を学ぶことになります。
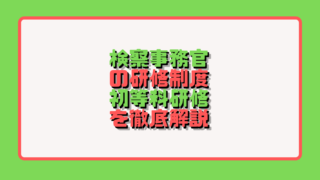
中等科研修
中等科研修は、大卒程度は採用3年目、高卒程度は採用5年目の職員が研修対象者となります。
初等科研修を終了後ほぼ5年を経過した者若しくは国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)合格者で採用後ほぼ2年を経過した者を対象とし、検察事務官として必要な比較的高度の知識及び技能を習得させて、事務能力の向上を図るとともに捜査・公判の実務能力を育成し、かつ、人格識見の向上を図ることを目的とする。
中等科研修では、他官庁からの聴講生(国税査察官や麻薬取締官など)や法務省内人事交流による出向者も研修に参加します。
また、成績優秀者には特別昇給(2号俸昇給)がありますので、研修員の勉強へのモチベーションが高い研修となります。
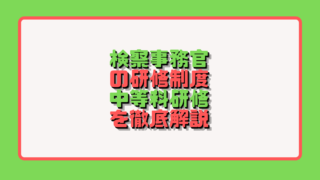
専修科研修
専修科研修は、大卒程度は採用7年目、高卒程度は採用9年目の職員が研修対象者となります。
中等科研修を終了後ほぼ4年ないし7年を経過した者を対象とし、検察事務官として必要な専門的知識及び技能を修得させて、職務の遂行に不可欠な実務的で高度な執務能力を涵養し、かつ、人格識見の向上を図ることを目的とする。
専修科研修が同期全員で受講する最後の集合研修になります。
また、成績優秀者には中等科研修みたいに特別昇給はありませんが、海外研修(FBIナショナルアカデミー)への参加資格が与えられます。
特別科研修
特別科研修は、検察官事務取扱検察事務官(通称「検取(けんとり)」)発令を受けた職員が研修対象者となります。
専修科研修を終了又は任官後ほぼ10年を経過した検察事務官を対象として、検察行政事務、検務事務及び捜査・公判事務に関し、検察事務官として必要な専門的知識及び技能を修得させて、事務能率及び人格識見の向上を図ることを目的とする。
検取になると比較的軽微な事件(交通切符や軽犯罪法違反など)を担当し、自身で取調べから刑事処分まで行う必要があります。
そのため、特別科研修では取調べのやり方や捜査・公判の問題点など、検取として必要なスキルを学ぶことになります。
- 地方研修は高検単位の集合方式の全寮制の研修。
- 初等科・中等科・専修科研修は全ての検察事務官が受講する。
- 特別科研修は検取発令を受けた職員が受講する。
では次に、検察事務官の中央研修について見ていきたいと思います。
中央研修について
検察事務官の中央研修についてですが、全国各地の検察庁から研修対象者を東京に集める集合方式で、全寮制の研修となります。
宿泊場所は法務省浦安総合センターになりますが、研修場所は講義に応じて法務省赤れんが棟でも行われます。
中央研修には下記6つの研修がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
- 特別専攻科研修
- 裁判員裁判担当中核事務官研修
- 高等科研修
- 統括捜査科研修
- 管理科研修
- 管理研究科研修
- 組織間人事交流研修【参考】
なお、組織間人事交流研修は検察事務官のみが対象の研修ではありませんが、研修対象者となる検察事務官も少なくないので、参考に紹介します。
また、統括捜査科研修・管理科研修・管理研究科研修は一定の役職に就いた職員が参加する研修になりますので、説明を省略します。
- 統括捜査科研修:統括捜査官
- 管理科研修 :課長
- 管理研究科研修:事務局長
特別専攻科研修
特別専攻科研修は、副検事の選考受験予定かつ合格見込みのある職員が研修対象者となります。
検察官事務取扱検察事務官等で将来検察事務(捜査・公判)に専従する志望を有している者に対し、これに必要な高度の専門的知識及び技能を修得させるとともに、人格識見の向上を図ることを目的とする。
講義もありますが、答練がメインの研修になりますので、勉強合宿をイメージしてもらえればと思います。
ちなみに、特別専攻科研修は1度しか参加できませんので、副検事の選考に落ち続けていても2回目の研修に参加することはできないです。
中核事務官研修
裁判員裁判担当中核事務官研修は、名前の通り裁判員裁判担当中核事務官に任命された職員が研修対象者となります。
検察事務官の中核として、裁判員裁判対象事件の捜査・公判等において重要度や裁量性の高い業務を遂行するための専門的知識及び技能を修得させるとともに、人格識見の向上を図ることを目的とする。
中核事務官には、裁判員に分かりやすい証拠として複数の証拠を組み合わせた「統合捜査報告書」の作成など、高度な専門知識が求められます。
そのため、中核事務官はキャリアを重ねれば誰でもなれる職種というわけではなく、優秀な検察事務官しか任命されない職種になります。
高等科研修
高等科研修は、将来の幹部候補生の職員が研修対象者となります。
将来の幹部検察事務官育成のため、高度の知識及び技能を修得させ、管理・指導能力の育成を図るとともに、捜査・公判部門、事務局部門、検務部門、企画調査部門に関する能力と素養を涵養し、かつ、人格識見の向上を図ることを目的とする。
高等科研修は毎年2回実施されますが、各回約60人~70人が参加する研修となります。
また、高等科研修を修了しないと統括検察官以上の役職に就けませんので、検察事務官として出世するための登竜門になります。
組織間人事交流研修【参考】
組織間人事交流研修は、翌年度に法務省内組織間人事交流対象者として出向する職員※が研修対象者となります。
組織間人事交流前に法務省の各組織の所管事務及び各組織間の関連について基礎的知識を習得させるとともに、研修員の相互理解を通じて法務省職員としての一体感を培うことによって、人事交流対象者の士気を高揚させ、法務省内組織人事交流の円滑な導入・運営に資することを目的とする。
法務省内組織間人事交流は検察官署・法務官署・保護官署・出入国在留管理官署が対象となりますので、検察事務官以外の他官庁の職員も研修員となります。
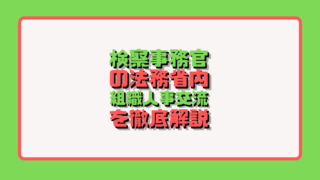
研修期間は3日間となりますが、出向先の知識を学ぶために出向者同士での意見交換会や出向経験者への質疑応答などが行われます。
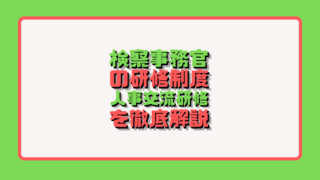
- 中央研修は全国から研修対象者を東京に集める全寮制の研修。
- 地方研修とは異なり、特定の職種に任命されるか優秀な職員でないと研修に参加できない。
- 高等科研修は検察事務官として出世するための登竜門。
では最後に、検察事務官の自庁研修について見ていきたいと思います。
自庁研修について
検察事務官の自庁研修についてですが、各検察庁が自庁職員を対象として以下の研修を取り行っていますので、それぞれ見ていきたいと思います。
中間期研修
中間期研修とは中等科研修終了後の翌年と翌々年に行われる研修で、研修内容は論述課題の提出と検務部門でのOJTとなります。
- 論述課題
答案を作成・提出し、検察官の添削と解説講義を受ける。 - 検務部門OJT
未経験の検務事務を1日か2日ずつ勤務体験をする。
採用4年目~7年目だと検務事務を0~2つ程度しか経験していませんが、OJTで一通り検務事務を経験することで検察庁の仕事の理解をより深めることができます。
実務研修
実務研修は様々ありますが、代表的な実務研修として以下の研修があります。
立会事務官研修
立会事務官研修とは、新規採用職員を対象に立会事務官をOJTさせる研修となります。
研修期間は約1週間程度になりますが、検察官と立会事務官のペアに付きっきりで実際の仕事内容を見学でき、取調べでの供述調書の作成も体験させてもらえます。
立会事務官には早くて採用半年後から任命されますので、早期に立会事務官の仕事を経験できる有意義な研修となります。
デジタルフォレンジック研修
デジタルフォレンジック研修とは、東京と大阪にあるDFセンターでデジタルフォレンジックの知識を学ぶ研修で、主に中堅職員が研修対象者となります。
押収したスマートフォンやパソコン等に保存されているデジタルデータを適正な手続に基づき抽出し、抽出したデータを解析して犯罪立証のための証拠を見つける手法・技術。
デジタル化が進んでいる現在では捜査・公判においてもDF業務の重要性は増していますので、捜査・公判部門でキャリアを積むなら是非とも受講したい研修となります。
検察庁によっては、支部の業務を体験する支部研修や、軽微な事件の取調べから事件処理まで担当させる捜査研修を取り行っている。
資格研修
資格研修とは資格取得を目的とする研修で、代表的に以下の2つの研修があります。
- 簿記研修
- 外国語研修
資格研修は公募制の研修になりますので、研修担当課から回付される募集案内に対し、志望動機などを記載して自ら申し込む形となります。
また、研修方法は資格専門予備校への通所かオンライン受講で、各自で勉強して資格取得を目指す形となります。
簿記研修では簿記2級か簿記3級、外国語研修ではTOEFL○○○点を目指すコースなどに分かれていますので、自身の実力に応じて研修を選ぶことができます。
おわりに
今回は、検察事務官の研修制度の概要について紹介しました。
検察事務官のメリットの一つが充実した研修制度になりますので、検察事務官内定者の方はもちろん、検察事務官志望の方はキャリア選択の参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。