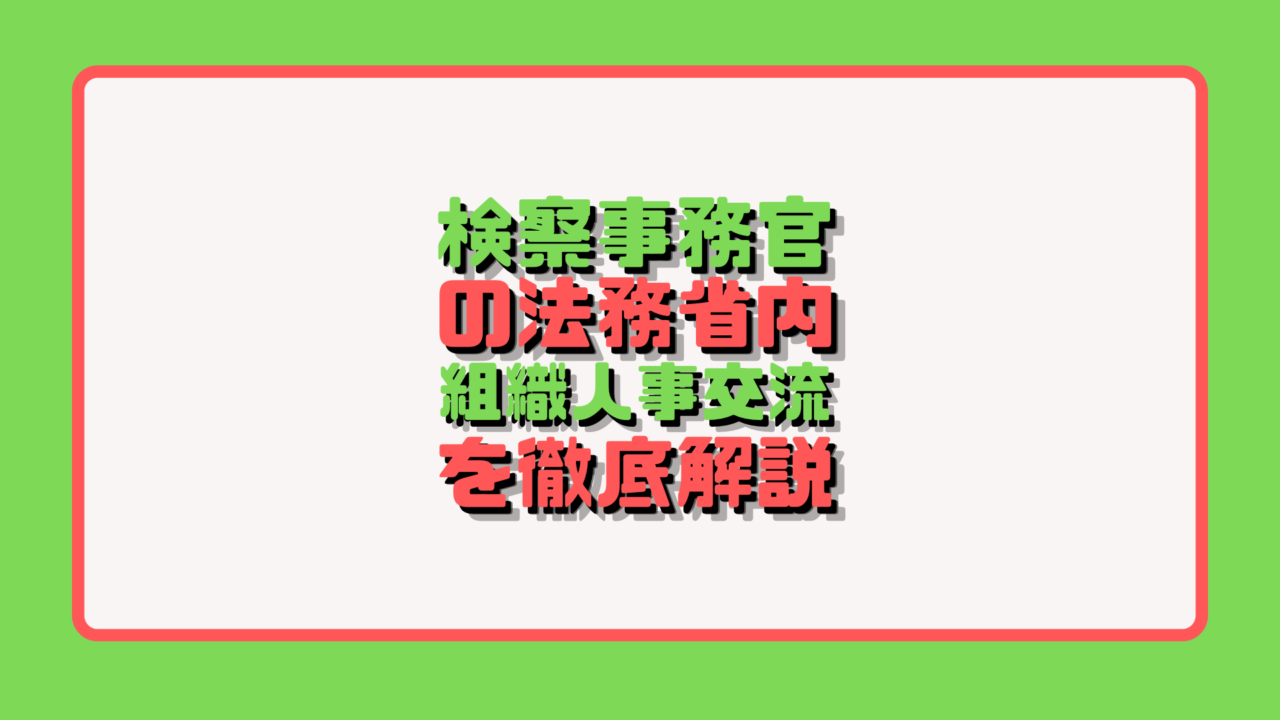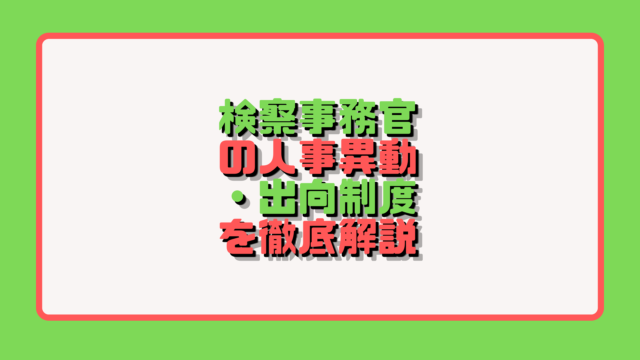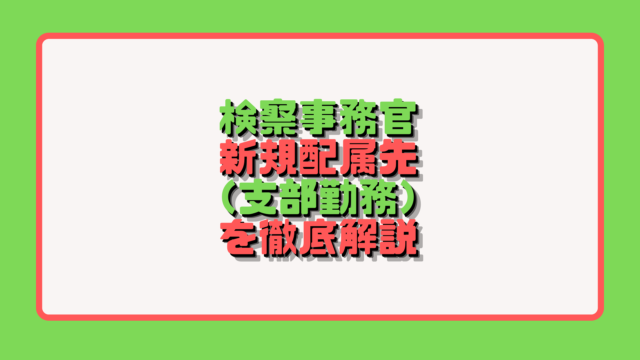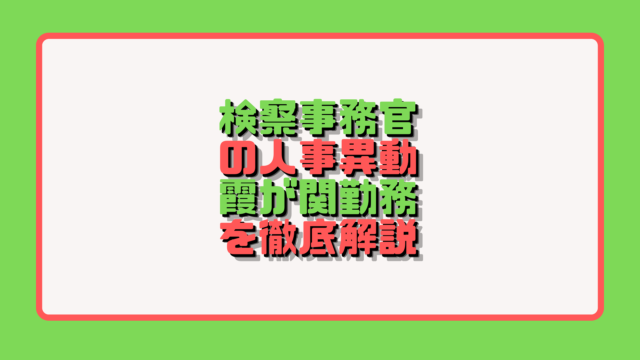こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は、検察事務官の人事異動の内、法務省内組織間人事交流による出向について詳しく紹介していきたいと思います。
検察事務官の魅力の一つにキャリアの幅広さがありますで、現役の検察事務官の皆さんはもちろん、検察事務官志望の方も是非参考にしてもらえればと思います。
本記事の内容は令和6年1月時点のものとなります。
組織間人事交流の概要について
法務省内組織間人事交流の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
出向対象者
組織間人事交流の出向対象者ですが、法務省の地方支分部局である出先機関や外局に勤務する職員が対象となります。
- 検察官署
検察庁など - 法務官署
法務局など - 矯正官署
刑務所・少年院など - 保護官署
保護観察所など - 出入国在留管理官署
出入国在留管理庁など
また、出向対象者は職務の級が2級の職員に限られますので、興味がある方は早いうちから希望するのが望ましいです。
出向期間
組織間人事交流の出向期間ですが、2年間と決まっています。
希望しても出向期間の延長はできませんが、所属庁を変更して出向先に残る「転籍」という制度もあります。
転籍の条件は不明だが、他官庁から検察庁への転籍の場合、副検事の選考を受験予定かつ合格可能性が高い優秀な人が転籍している。
実際に転籍できるかどうかは分かりませんが、出向先に残りたいと思ったら転籍希望を是非申しでてみてください。
研修制度
組織間人事交流の対象者になると、「組織間人事交流研修」という事前研修に参加することになります。
研修期間:3日間
研修場所:法務省赤れんが棟
宿泊場所:法務省浦安総合センター
出向対象者の士気を高揚させ、円滑な人事交流が行われることを目的とした研修になりますが、研修内容は以下となります。
- 組織間人事交流に関する講義
- 研修員意見交換会
- 班別討議など
出向先の担当者や出向経験者からの業務内容の説明や、研修員同士で職場環境などの情報交換も行われますので、出向に対する不安を和らげることができます。
また、全国各地から組織間人事交流対象者が集まり、短い期間ですが共同生活を送りますので、他官庁との人脈が広がる有意義な研修になります。
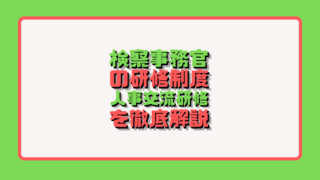
- 組織間人事交流の対象者は法務省の出先機関や外局の2級職員。
- 出向期間は2年間。
- 出向前に組織間人事交流研修に参加し、出向先の業務内容や基礎知識を習得できる。
では次に、法務省内組織間人事交流の業務内容について見ていきたいと思います。
出向先の業務内容について
法務省内組織間人事交流による出向先の業務内容について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
検察庁への出向
検察庁への出向についてですが、出向者の業務内容は以下のように決められていますので、それぞれ見ていきたいと思います。
検務事務【出向1年目】
検察庁への出向者の1年目は検務事務のいずれかを担当することになります。
- 事件事務
- 令状事務
- 証拠品事務
- 執行事務
- 徴収事務
- 記録事務
- 犯歴事務
どの検務事務を担当させてもらえるかは受入庁次第となりますが、刑事事件の入口と出口に関わる事件事務が一般的かなと思います。
なお、1年間に1か所とは限らず、半年交代などで複数の検務事務を経験させてもらえることもあります。
出身庁によっては出身庁の業務内容と親和性のある検務事務を担当する。
【例】矯正管区→執行担当、徴収担当
また、出向1年目には、大卒3年目と高卒5年目の検察事務官を対象とした中等科研修に出向者も参加させてもらえます。
中等科研修では検察事務官に求められる高度な知識(法律や実務)を修得できますので、出向者にとって有意義な研修となります。
ちなみに、検察事務官と組織間人事交流出向者の他に他官庁からの聴講生も参加します。
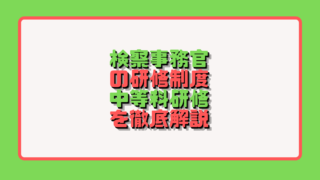
立会事務【出向2年目】
検察庁への出向者の2年目は立会事務官に任命されます。
立会事務官の仕事は検察庁のほぼ全ての業務に通じていますので、立会事務官を経験することで検察庁の業務内容をほぼ網羅することができます。
なお、立会事務官の仕事を無事にこなせるか不安に思うかもしれませんが、中等科研修同期が助けてくれるので安心してもらえればと思います。
- 出向1年目は検務事務(事件担当が一般的)を担当。
- 出向1年目に中等科研修に参加。
- 出向2年目は立会事務官に任命。
検察庁からの出向
検察庁からの出向についてですが、出向先別に業務内容をそれぞれ見ていきたいと思います。
法務官署への出向
取材中のため後日更新予定
矯正官署への出向
取材中のため後日更新予定
保護官署への出向
取材中のため後日更新予定
出入国在留官署への出向
取材中のため後日更新予定
おわりに
今回は、検察事務官の人事異動の内、法務省内組織間人事交流による出向について紹介しました。
組織間人事交流制度自体を知らない人も多いと思いますので、制度を知ったうえで自身のキャリア選択の参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。