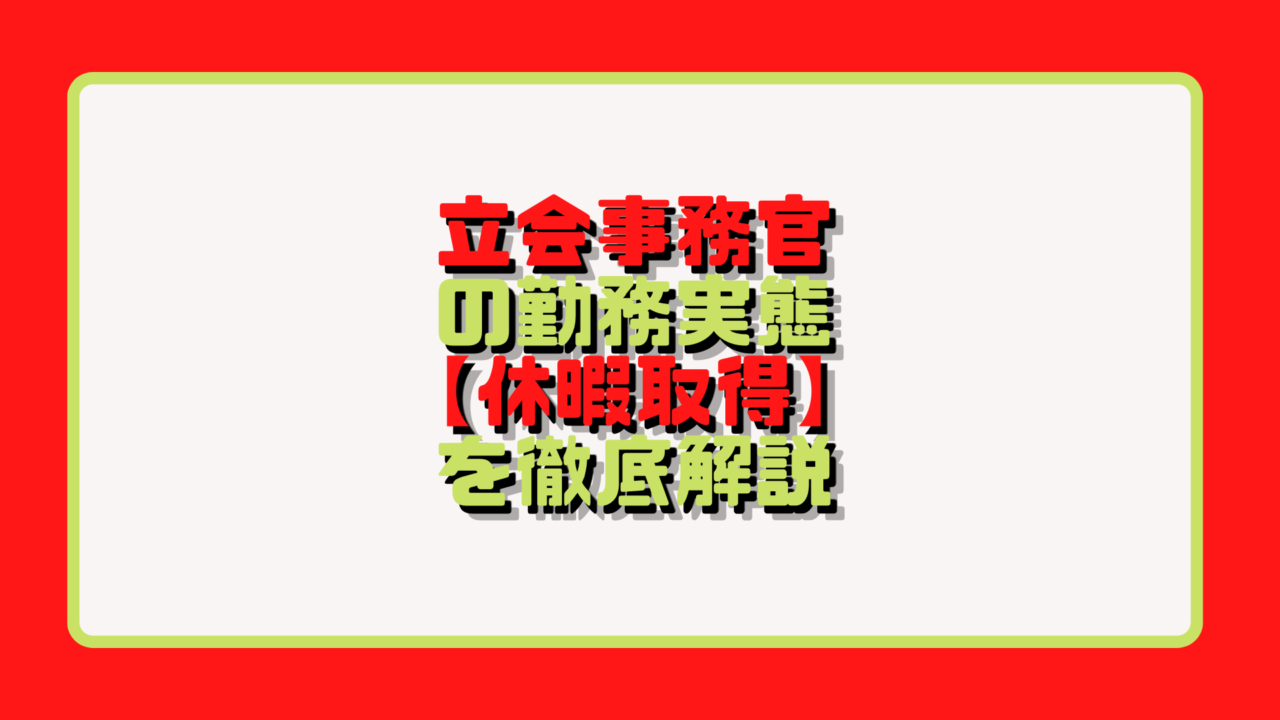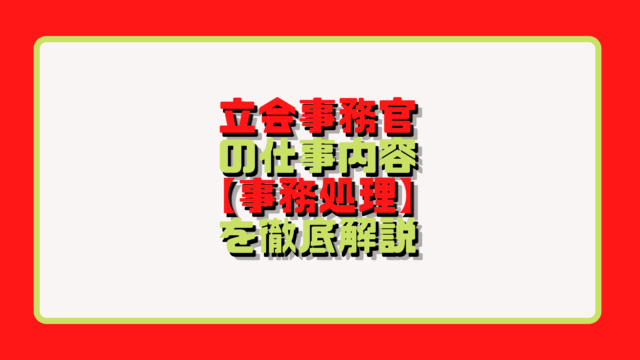こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、有休休暇を自由に取れないというイメージを持っている方も多いと思います。
そこで、本記事では、立会事務官の有給休暇(年次・夏季)について詳しく紹介していきたいと思います。
実際に立会事務官として勤務した経験を基に有給休暇事情のリアルをお伝えしますので、是非参考にしてもらえればと思います。
年次・夏季休暇の概要について
国家公務員の休暇にはいくつか種類がありますが、なじみ深い休暇として年次休暇や夏季休暇がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
年次休暇
国家公務員の年次休暇については、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(勤務時間法)」や「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」などによって定められています。
では、年次休暇の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
付与日数
年次休暇の付与日数についてですが、毎年1月1日付けで在職期間に応じた日数が付与されます。
| 在職期間 | 日数 |
| 一月に達するまで | 2日 |
| 一月を超え二月に達するまで | 3日 |
| 二月を超え三月に達するまで | 5日 |
| 三月を超え四月に達するまで | 7日 |
| 四月を超え五月に達するまで | 8日 |
| 五月を超え六月に達するまで | 10日 |
| 六月を超え七月に達するまで | 12日 |
| 七月を超え八月に達するまで | 13日 |
| 八月を超え九月に達するまで | 15日 |
| 九月を超え十月に達するまで | 17日 |
| 十月を超え十一月に達するまで | 18日 |
| 十一月を超え一年未満 | 20日 |
昨年の1月1日から勤務している職員は20日間の年次休暇が付与されますが、新規採用職員は採用日によって付与日数は異なります。
4月1日採用:15日
10月1日採用: 5日
翌年への繰り越し
年度内中に使いきれなかった年次休暇ですが、最大で20日間を翌年に繰り越すことができます。
そのため、新たに付与される20日と合わせ最大40日間の年次休暇を取得することが可能となります。
ちなみに、1日未満の有給休暇は翌年に繰り越すことができませんので、無駄なく繰り越すには計画的に有休消化する必要があります。
申請方法
年次休暇の申請方法ですが、個人個人に用意されている休暇簿に必要事項を記入して申請します。
- 期間(年次休暇取得期間)
※1時間単位から取得可能 - 残日数・時間
- 自身の確認印
- 請求月日
【参考】休暇簿(年次休暇用)
年次休暇の取得には理由は必要ありませんので、仕事が無くて暇だから時間休を取るということも可能です。
- 1月1日に年次休暇20日間付与
※4月採用職員には15日間付与
※10月採用職員には5日間付与 - 翌年への繰りしは最大20日間
- 1時間単位で取得可能
夏季休暇
国家公務員の夏季休暇については、年次休暇と同様、「勤務時間法」や「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」などによって定められています。
では、夏季休暇の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
付与日数
夏季休暇の付与日数については、毎年3日間付与され、7月~9月の期間内に連続して取得することができます。
国家公務員の夏休みは、夏季休暇3日間に年次休暇を何日か追加して夏休みを取得することになります。
ちなみに、世間一般にいう盆休みは国家公務員にはありません。
計画表
国家公務員の夏休み(夏季休暇+年次休暇)は連続する長期休暇になりますので、計画表を用いて職員間で夏休みの取得日を調整します。
計画表は5月~6月頃にかけて回付されますので、早めに夏休みの予定を立てることができます。
ちなみに、検察官と立会事務官の場合は、他のペアと二組か三組の中で被らないように夏休みを取得します。
- 夏季休暇は7月~9月の連続する3日間。
- 国家公務員に盆休みはない。
- 夏休みの計画表は5月~6月頃に回付される。
では、次に、立会事務官の有給休暇について見ていきたいと思います。
立会事務官の有給休暇について
立会事務官の有給休暇ですが、実は年次休暇はめちゃくちゃ取りやすいですし、夏休みもめちゃくちゃ長く取れますので、それぞれの実態について見ていきたいと思います。
年次休暇の取得実態
立会事務官は年次休暇を取りにくいイメージがあると思いますが、以下の場合などに割と自由に年次休暇を取得することが可能です。
- 担当検察官が不在の場合
- 取調べがない場合
担当検察官が不在の場合、まず取調べがありませんし、新たに事件処理の決裁もありませんので事務処理も増えません。
そのため、担当検察官がいないと立会事務官の仕事はありませんので、自由に年次休暇を取ることができます。
- 休暇取得
→年次休暇・振替休日等 - 研修参加
→内部研修・外部研修等 - 会議・勉強会参加
検察官が休暇や研修参加で終日不在の場合は1日休暇を取れますし、午後から会議や勉強会があり、急ぎの事務処理もない場合は午後から時間休を取ることができます。
また、日によっては取調べがない日もありますが、検察官が出勤していても急ぎの事務処理がなければ年次休暇を取っても問題ありません。
取調べがある日でも、他の立会事務官に代わってもらうことで年次休暇を取ることが可能。
→取調べ時の調書作成はどの立会事務官でも対応可能なため。
ちなみに、検察官が不在の日に必ず年次休暇を取らなければいけないわけではありませんので、その場合はのんびり事務処理を進めることが可能ですね。
- 検察官が不在の日は休める。
- 取調べが無い日も休める。
- 取調べがあっても他の立会事務官に代わってもらえると休める。
夏季休暇の取得実態
立会事務官の夏季休暇の取得実態ですが、社会人としてはあり得ないですが、年次休暇と合わせて2週間~3週間の夏休みを取ることができます。
なぜ2週間~3週間の夏休みが取れるのかというと以下の理由があるからです。
- 夏休みは担当検察官と日程を合わせて取得する。
- 検察官は2週間から3週間夏休みを取得する。
年次休暇の取得実態でも説明しましたが、立会事務官は基本的に検察官がいないと仕事がありませんので、夏休みも検察官と合わせて取得します。
そして、検察官は日々多忙でなかなか休みが取れない代わりに夏休みは2週間~3週間取るのが一般的なので、立会事務官も2週間~3週間夏休みを取ることができます。
夏休みは夏季休暇3日+年次休暇○日
- 夏休み2週間の場合
夏季休暇3日+年次休暇7日 - 夏休み3週間の場合
夏季休暇3日+年次休暇12日
夏休みをいつ取得するかは、仕事に支障が出ないように他のペアとグループを組んで夏休みが被らないようにします。
そのため、他のペアが夏休みを取得している間は自身の事件配点数が増え、自身が夏休みを取得している間は他のペアの事件配点数が増えることになります。
そうすると夏休み取得中に仕事が溜まるということもありませんので、仕事を気にすることなく思いっきり夏休みを満喫することができます。
- 夏休みは2週間~3週間。
→長期旅行も可能。
- 夏休み中に仕事は溜まらない。
→気兼ねなく夏休みを満喫可能。
おわりに
今回は、立会事務官の有給休暇(年次・夏季)について紹介してきました。
立会事務官はなかなか休みを取れないと思っていた方も、立会事務官が年次休暇を取りやすく、長期の夏休みも取れるなど、有休休暇事情を理解してもらえたと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。