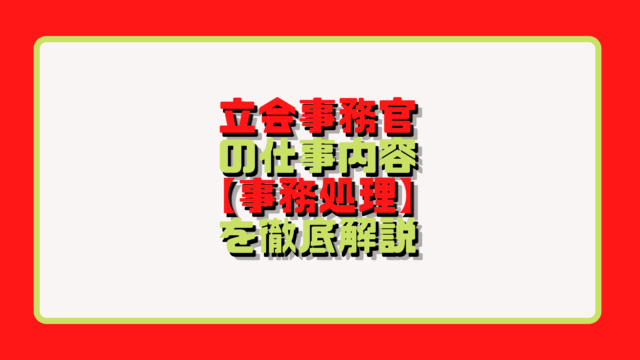こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は、立会事務官の仕事内容の内、取調べ事務について詳しく紹介していきたいと思います。
検察庁の捜査の中心は取調べとなりますので、検察庁内定者の方はもちろん、検察事務官志望者の方も是非参考にしてもらえればと思います。
検察庁の取調べ概要について
検察庁の取調べの概要として、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
事件の種類
刑事事件の種類ですが、身体拘束の有無で以下の2種類に分けられます。
身柄事件
身柄事件の場合、身体拘束できる期間が決まっていますので、起訴・不起訴の判断(事件処理)をする時間は限られています。
- 逮捕期間:72時間
48時間以内に地検送致 - 勾留期間:10日間
- 延長期間:最大10日間
被疑者の逮捕・勾留場所は警察署の留置場になり、送致後は警察と検察で共同で捜査を行います。
身柄事件の被疑者取調べは、全件で録音・録画を実施する。
在宅事件
在宅事件とは、被疑者が身体拘束されていない書類送検されてきた事件になります。
身柄事件とは異なり、警察での捜査が終結してからの送致となりますので、送致後は基本的に検察庁のみの捜査となります。
在宅事件の事件処理は事件配点後3か月~6か月以内に処理することとされており、期間を超えると長期未済事件として報告しなければならない。
取調べ環境
刑事事件の取調べ環境ですが、個室か相部屋かで以下の2種類に分けられます。
単独執務室
単独執務室ですが、検察官と立会事務官のワンペア専用の執務室となります。
通常、単独執務室には録音・録画機が設置されていますので、全ての取調べは自身の執務室で行うことになります。
共同執務室
共同執務室ですが、検察官と立会事務官のツーペアかスリーペアで使用する相部屋の執務室となります。
共同執務室には録音・録画機が設置されていませんので、身柄事件の被疑者取調べの際は録音・録画機が設置されている執務室を利用することになります。
- 身柄事件は逮捕後48時間以内に送検、勾留期間は通常10日間、延長最大10日間の計20日間となる。
- 身柄事件の被疑者取調べは全件で録音・録画を実施。
- 単独執務室には録音・録画機が設置されているが、共同執務室には設置されていない。
では次に、立会事務官の取調べ前の仕事内容について見ていきたいと思います。
取調べ前の仕事内容について
立会事務官の取調べ前の仕事内容としては、以下2つの仕事があります。
被疑者・参考人の呼出し
取調べは基本的に検察庁で行いますので、取調べを行う際は聴取対象者を呼出す必要があります。
身柄事件の被疑者
身柄事件の被疑者の呼出しですが、警察署の留置場に留置されていますので、留置管理担当者か事件の担当刑事に押送を依頼します。
- 集中押送
押送車が複数の警察署を回り、検察庁から呼出しを受けた被疑者をまとめて検察庁に押送する方法 - 単独押送
怪我や病気などで集団での行動が困難であるなどの理由により、当該被疑者を捜査担当者が個別に押送する方法
警察では取調べや実況見分などの引き当たり捜査を連日行いますので、検察庁での取調べ日程は早めに連絡する必要があります。
検察庁での取調べは基本的に2回~3回で、警察での供述内容を確認してから行われる。
- 勾留手続きにおける弁解録取
- 勾留期間延長前の取調べ
- 終局処分前の取調べ
在宅事件の被疑者
在宅事件の被疑者の呼出しですが、身体拘束を受けていない一般生活を送っている人になるため、書面か電話で行います。
呼出し方法は検察官の好みによって異なりますが、急ぎでない場合は書面、急ぎの場合は電話での呼出しが一般的となります。
在宅事件の被疑者の取調べは平日の開庁時間内に行うので、夜間や休日の取調べ希望は受け付けない。
なお、被疑者が呼出しに応じない場合もありますが、出頭しないと身体拘束する旨を伝えて説得することになります。
ちなみに、全く連絡がつかない場合は所在捜査で被疑者がどこにいるのか捜索しなければならなくなります。
被害者等の参考人
被害者や目撃者等の参考人の呼出しですが、被疑者と違い捜査に協力してもらう立場になりますので、検察官からの電話連絡が基本となります。
身柄事件の被害者の場合、警察から連絡し、検察庁への送り迎えまでしてくれる場合もある。
なお、被害者等の参考人の取調べは被害者等の都合に合わせますので、夜間や休日の取調べになることもしばしばあります。

取調べの事前準備
取調べを円滑に進めるための事前準備としては、例えば以下のものがあります。
供述調書の入力準備
取調べでは聴き取り内容をまとめた供述調書を作成しますが、作成方法は検察官が読み上げる文章を立会事務官が入力する口述(くじゅ)方式となります。
そのため、立会事務官はスムーズに入力できるよう事件内容を事前に把握しておく必要があります。
また、供述調書には供述人の情報などを記載しなければなりませんので、事前に入力して準備しておく必要があります。
- 住所・氏名・生年月日・年齢
- 本籍(被疑者の場合)
- 供述した日にち・場所
ちなみに、供述調書作成に使用する「一太郎」では単語登録ができますので、よく使う言い回しは事前登録しておくと便利です。
検察辞太郎が登録していた単語例
- 「私は、」→「w」
- 「このとき本職は、」→「kh」
- 「問」→「q」、「答」→「a」
証拠品の仮出し
取調べでは供述者に証拠品を見せる場合がありますので、事前に証拠品担当から証拠品の仮出しをしておく必要があります。
- 防犯カメラ等の映像
- 押収した書類等
なお、映像を見せる場合は証拠品再生専用のノートパソコンも借りる必要があります
検察庁の隠語では証拠品を「ブツ」という。
- ブツ読み
証拠品を精査すること - ブツ当て
証拠品を供述人に見せること
録音・録画の準備
身柄事件の被疑者取調べでは全件で録音・録画を実施しなければなりませんので、録音・録画室の予約やセッティングをする必要があります。
- 検察官と供述人が映るよう画角の調整
- 音声が入るかマイクチェック
- 録音・録画されるかテスト撮影
録音・録画の映像は証拠の一つになりますので、不備がないよう入念にセッティングする必要があります。
通訳人の手配
供述人が外国人で日本語が話せない場合は、通訳人を手配し、取調べに同席してもらう必要があります。
通訳人への直接の依頼は事件管理が行いますので、立会事務官は事件管理に依頼文書を提出する形になります。
- 供述人の国籍・言語
- 取調べの日時
- 事件の概要
送致書のコピーを添付
なお、英語や中国語などは通訳人も多くいますが、タガログ語などは通訳人が少ないので、珍しい言語の場合は早めに依頼する必要があります。
- 被疑者取調べは平日日中のみ、参考人取調べは参考人の都合を優先し夜間・休日の対応も可能。
- 在宅被疑者が音信不通になった場合、被疑者の所在捜査をしなければならない。
- 取調べを円滑に進めるため、供述調書の入力準備や証拠品の仮出しなどの事前準備が必要。
では次に、立会事務官の取調べ中の仕事内容について見ていきたいと思います。
取調べの仕事内容について
立会事務官の取調べの仕事内容としては、以下3つの仕事を見ていきたいと思います。
取調べ開始時の仕事
取調べの開始方法ですが、取調べ対象者の身体拘束の有無で対応が変わってきます。
身体拘束されている場合
身柄事件の被疑者などは検察庁への押送後は身柄待機場所にいますので、立会事務官が電話連絡して取調室まで連行してもらいます。
- 立会事務官が身柄待機場に電話連絡し、被疑者名と取調室番号と共に取調べ開始を伝える。
- 留置管理職員か担当刑事が手錠・腰縄がかけられた状態※の被疑者を取調室まで複数名で連行。
※手錠と腰縄は連結している。 - 入室後は連行職員が被疑者の手錠を外し、被疑者が座るパイプ椅子に手錠をかけて被疑者とパイプ椅子を連結。
- 連行してきた職員の一人は取調室後方に待機※し、、残りが退出してから取調べ開始。
※逃亡等防止のため
なお、録音・録画は被疑者が取調室に入室するタイミングでスタートさせます。
身体拘束されていない場合
在宅事件の被疑者や参考人は自分の足で検察庁に来庁しますので、来庁後は立会事務官が取調室まで案内します。
- 受付からの来庁連絡(内線電話)後、立会事務官が受付かエレベーター前に迎えに行く。
- 取調べ開始の場合は取調室にそのまま案内し、開始しない場合は待合室に案内。
- 検察官が身分証で人定確認してから取調べ開始。
なお、来庁者には受付で身体検査が行われますが、カッターなどの危険物を持っている場合は立会事務官が取調べ終了まで預かる対応をとります。
検察官の聴取中の仕事
取調べ開始後の検察官の聴取中ですが、立会事務官の仕事のスタンスは以下の2パターンに分かれます。
- 聴取内容を聞かず、自身の事務処理に専念する。
- 聴取内容を聞き、自身も取調べに参加する。
どちらのパターンが多いかというと、私の経験上、別の事件の事務処理をしている立会事務官が圧倒的に多いです。
というのも、1日の大半は取調べに時間を取られますので、事務処理の時間を捻出しないと仕事が終わらないからです。
ドラマなどで描かれる立会事務官の間違ったイメージ
- 検察官が聴取する内容を逐一タイピングで記録する。
- 立会事務官も被疑者等に質問したり、自身の意見をぶつける。
取調べに参加する場合ですが、私の場合、聴取内容で疑問に思ったことを共有モニターにタイピングして情報共有していました。
立会事務官の取調べ参加のスタンスは検察官によって異なりますので、ペアを組んだ当初に確認しておくことが望ましいですね。
供述調書作成時の仕事
検察官の聴取が一通り終わった後は供述内容をまとめた供述調書を作成しますが、作成方法は以下の手順で行われます。
口述内容の入力
供述調書の作成は、検察官が文章を口頭で読み上げ立会事務官がタイピングする口述方式で作成されます。
そのため、立会事務官にはタイピングスキルが必須となります。
なお、検察官は立会事務官のタイピング内容を共有モニターで確認しながら口述します。
供述調書は数枚、多い時で10枚以上にも及ぶため、タイピングスピードによって取調べ時間は大きく変わる。
→タイピングスピードが遅いと検察官の仕事の時間を奪うことになる。
また、供述調書の作成には細かいルールがありますので、慣れないうちは注意が必要となります。
- 文頭は1文字空ける。
- 文章は一文ごと「。」で改行。
- 会話文はインデントをずらす。
- 漢字表記は公用文にならう。
- 用紙の最終行で終わらせない。
など
供述人への読み聞け
検察官の口述を入力し終えた後ですが、専用用紙に供述調書を印刷し、供述調書を供述人に手渡します。
そして、供述人に供述調書の内容に誤りがないか確認させるため、検察官が録取内容を読み上げ、供述人は文章を確認します。
供述調書の読み聞かせのことを「読み聞け(よみきけ)」という。
なお、供述内容に誤りや訂正して欲しい部分がある場合は、読み聞けの最中に検察官に訂正を申し立てることになります。
供述調書の訂正
読み聞けの際に供述人が訂正を申立てた場合ですが、パソコンで供述調書を作成し直すのではなく、印刷した供述調書の最終行の次行に手書きで訂正内容を記入します。
供述人の目の前で、上記のとおり口述して録取し、読み聞かせ、かつ、閲読させたところ、次のとり訂正(追加)を申し立てた。
供述人の申立て内容⇦手書き
定型文はゴム印を使用しますが、申立て内容は立会事務官が手書きで記入しなければなりませんので、ある程度の漢字は書ける必要があります。
ちなみに、単に誤字や脱字に留まる場合は、供述人の目の前で該当箇所に二重線と押印をした上で付記する訂正方法でも大丈夫です。
供述人による署名・押印
供述人から録取内容の確認を得た後ですが、供述調書最終行の次行に署名と押印(印鑑又は指印)、供述調書が複数ページの場合は各ページの欄外右下にも押印してもらいます。
供述人が身体拘束を受けている者の場合、取調べ時間等を記載した「取調べ状況等報告書」を供述人に確認させ、取調べ終了時に署名・押印をもらう。
署名用のペンや朱肉を供述人に差し出すのは一般的に立会事務官になりますので、スムーズに提供できるよう事前に準備しておく必要があります。
供述人の署名・押印を貰えば取調べは終了となりますので、供述人に取調室から退出してもらいます。
取調べ終了後の仕事
立会事務官の取調べ終了後の仕事ですが、供述調書に「奥書(おくがき)」を記入し、製本する仕事があります。
奥書には供述人が署名・押印を拒否した場合など様々なパターンがありますので、調書作成要領などで書き方を確認しておく必要があります。
奥書記入後は、供述調書が複数ページある場合は前ページ裏面と次ページ表面に割り印を行い、供述調書を製本します。
- 検察官の聴取中、立会事務官の多くは他の事件の事務処理を行っている。
- 供述調書は検察官が読み上げる文章を立会事務官がタイピングする口述方式で作成。
- 供述調書には文章の体裁や訂正方法など様々なルールがある。
おわりに
今回は、立会事務官の仕事の内、取調べ事務について詳しく紹介してきました。
取調べ事務は基本的に毎日ある立会事務官のメイン仕事になりますので、検察事務官を志望する上で参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。