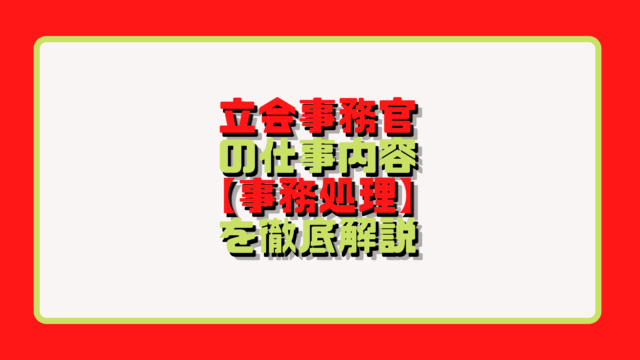こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は、立会事務官の仕事内容の内、司法解剖立ち会いについて詳しく紹介していきたいと思います。
検察事務官の業務の中でも心理的に辛い業務の一つになりますので、検察庁内定者の方はもちろん、検察事務官志望者の方も是非参考にしてもらえればと思います。
司法解剖の概要について
司法解剖とは刑事訴訟法168条による死体の解剖になりますが、犯罪の捜査を目的に行われます。
- 犯罪の立証
損傷の部位、形状、程度、凶器の種類、加害方法及び凶器と損傷との因果関係等を明らかにする。 - 犯罪性の有無の判断
犯罪による死亡の疑いのある死体について、体内の状況等を調べて犯罪の有無を明らかにする。
では、司法解剖の概要について下記項目を見ていきたいと思います。
司法解剖の実施の流れ
司法解剖の実施の流れですが、死体発見時の状況によって司法解剖実施までのプロセスが若干異なります。
犯罪死体の司法解剖
犯罪死体とは死亡が殺人等の犯罪によることが明らかな死体のことで、犯罪死体はほぼ100%、司法解剖が実施されます。
- 犯罪死体の発見
- 検証又は実況見分の実施
- 鑑定処分許可状の発付
- 司法解剖の実施
なお、警察から検察庁には①犯罪死体発見時に速やかに情報共有がなされます。
警察本部捜査1課が担当する強盗殺人事件などの重大事件発生時は、本部係検事と担当立会事務官が現場臨場。
変死体の司法解剖
変死体とは死亡が犯罪に起因するか不明もしくは疑われる死体のことで、検視を行い、犯罪の関与が否定できない場合は司法解剖が実施されます。
- 変死体の発見
- 検視の実施
- 鑑定処分許可状の発付
- 司法解剖の実施
なお、警察が検視を行うには検察官の指揮が必要ですので、警察から検察庁に速やかに変死体発見報告がなされます。
検察官が検視を行う(刑事訴訟法229条1項)とされているが、検察官に検視スキルは無いため、司法警察員に代行検視(229条2項)してもらう。
司法解剖に立ち会う場合
検察官と立会事務官が司法解剖に立ち会う場合ですが、全ての司法解剖に立ち会うわけではありません。
司法解剖に立ち会うかどうかは事件を配点する決裁官が決定し、検察官に司法解剖立ち会いを指示することになります。
司法解剖には事件の担当検察官が立ち会うが、身柄事件の送致と日程が被った場合は弁解録取手続を優先するため、別の検察官が応援で立ち会う。
おそらくですが、解剖執刀医の法医学者に話を聞く必要があるかないかが司法解剖に立ち会いの判断根拠の一つだと思います。
ちなみに、立会事務官が司法解剖に立ち会う頻度は完全に人によるので、中には定年まで一度も経験しない人もいます。
司法解剖立ち会い時の手当
国家公務員の手当には、著しく危険、不快、困難等著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当として特殊勤務手当があります。
特殊勤務手当は業務内容別に27種類ありますが、司法解剖立ち会いは「死体処理手当」に該当し、1日1,000円支給されます。

1,000円だと割に合うとは思えませんが、貰えるだけましだと思うしかないですね。
- 司法解剖が行われるのは、死亡が犯罪によることが明らかな場合と犯罪の疑いがある場合。
- 司法解剖の目的は犯罪性の有無の判断と犯罪の立証。
- 全ての司法解剖に検察官が立ち会うわけではない。
では次に、司法解剖の立ち会い業務について見ていきたいと思います。
司法解剖の立ち会い業務について
司法解剖に立ち会う際の立会事務官の業務について、下記場面別に見ていきたいと思います。
司法解剖前の業務内容
司法解剖の立ち会いが決まると事件管理から日時と場所が伝えられますので、立会事務官は事前準備を行います。
なお、司法解剖は大学病院の法医学教室で行われるのが一般的となります。
交通手段の確保
司法解剖は開始時間が決まっていますので、開始時間に間に合うよう交通手段を確保する必要があります。
- 公共交通機関
- タクシー
- 公用車
解剖立ち会いは急に決まることが多いので、タクシー利用が多くなると思います。
白衣等の準備
司法解剖立ち会いの際にはスーツの上に白衣等を着用しますので、大学病院に持っていく解剖立ち会いセットを準備する必要があります。
- ディスポキャップ
- 白衣
- 不織布マスク
- ゴム手袋
- 長靴
事件管理によって解剖立ち会いセットが用意されることが一般的かと思いますが、自分で用意する際は忘れ物がないよう注意が必要となります。
マニュアルの確認
私が所属していた検察庁では各大学病院のマニュアルが整備されていましたので、時間的余裕がある場合はマニュアルを確認しておいたほうがいいです。
というのも、執刀医の法医学者は気難しい人が多いので、地雷を踏まないように注意しなければならないからです。
なお、司法解剖立ち会いは急に決まることが多いため、立会事務官になったらいつでも解剖に行けるよう余裕をもってマニュアルを確認しておくことが望ましいです。
司法解剖中の業務内容
司法解剖の執刀医は法医学者、解剖補助者は法医学教室の助手と警察官の体制で実施されますが、基本的に検察官と立会事務官はただ見学するだけとなります。
司法解剖立ち会い後に作成する報告書に添付する写真は解剖補助者の警察官から貰えるので、立会事務官が写真撮影する必要はない。
なお、法医学者によっては執刀中に検察官に説明をしてくれることもあるので、適宜メモを取る場合もあります。
- 司法解剖開始
- ご遺体の外表観察
- ご遺体の頭蓋腔・胸腔・腹腔内観察
→刺し傷は深さなどを計測 - 各臓器の摘出・観察
→大きさ・重さの測定 - 各臓器の分割・内部確認
→うっ血の有無等を確認
→一部は薬物検査 - 胃・腸の内容物の確認
- ご遺体内に各臓器を戻す
→切開部は縫合 - 司法解剖終了
司法解剖の所要時間は短くても2時間はかかり、ご遺体の状態によっては8時間かかるなんてこともあります。
ちなみに、気分が悪くなった場合は解剖室から退出することも可能ですので、無理をする必要はありません。
司法解剖後の業務内容
司法解剖が終了すると、執刀医である法医学者から死因等の所見を聞く機会があります。
立会事務官はただ同席しているだけで大丈夫ですが、メモを取るなどして体裁を保っていた方がいいと思います。
なお、法医学者から聴き取った内容は帰庁後に検察官が報告書にまとめますので、立会事務官が作成する書類は特殊勤務の届出のみとなります。
- 司法解剖立ち会いは急に決まるため、必要なものなど事前に把握しておくことが望ましい。
- 司法解剖中、検察官と立会事務官は基本的に見学しているだけ。
- 気分が悪くなったら解剖室から自由に退出できる。
おわりに
今回は、立会事務官の仕事の内、司法解剖立ち会いについて詳しく紹介してきました。
司法解剖立ち会いの一連の流れを理解して貰えたと思いますので、検察事務官を志望する上で参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。