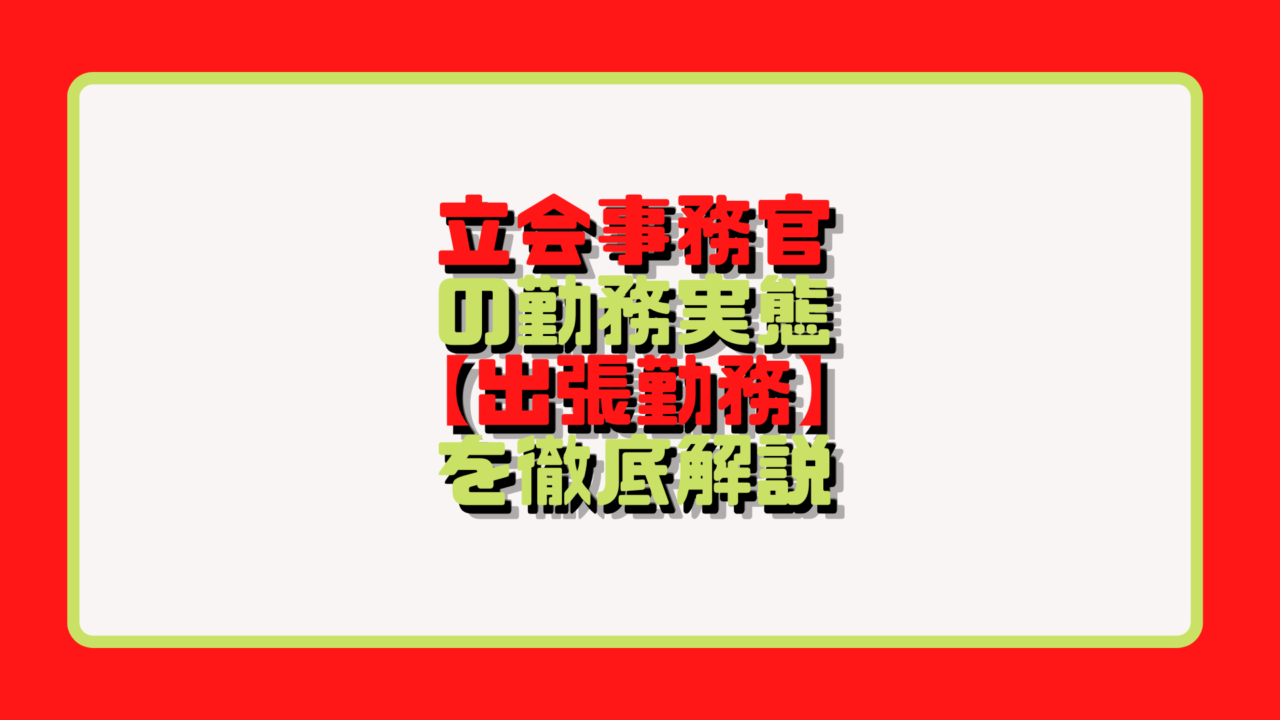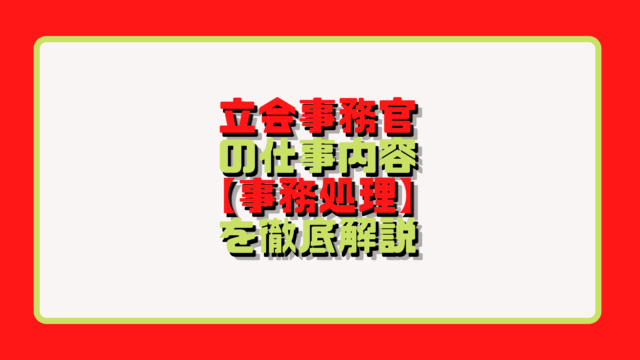こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、捜査のために出張が多いイメージを持っている方も多いと思います。
そこで、本記事では、立会事務官の出張勤務について詳しく紹介していきたいと思います。
実際に立会事務官として勤務した経験を基に出張勤務のリアルをお伝えしますので、是非参考にしてもらえればと思います。
出張勤務を行う場合について
国家公務員の出張勤務ですが、「国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)」により出張の定義が定められています。
職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
なお、在勤官署から8キロメートル以内は在勤地となり、在勤地内の勤務は出張の範囲外のいわゆる外勤となります。
外勤で交通機関を利用する場合は、官署管理のICカードを利用するか、立替払いによる後日清算により交通費を賄う。
では、検察官と立会事務官が出張勤務を行う場合についてそれぞれ見ていきたいと思います。
参考人等の取調べ
参考人等の取調べは基本的には来庁を依頼しますが、どうしても来庁してもらえない場合は直接出向いて取調べを行うことになります。
- 遠方に引越している事件の目撃者
- 遠方の刑務所に収監されている犯罪グループの元仲間
- 長距離移動が難しい被疑者の親族
など
出張先での取調べ場所についてはケースバイケースになりますが、優先順序としては以下の順番で供述人と交渉します。
- 供述人最寄りの検察庁
- 供述人最寄りの警察署・交番
- 供述人の自宅・勤務先
検察庁や警察署の場合は取調べに必要な機材(パソコン・プリンター・録音録画機など)が揃っていますので、出張の負担を軽減することができます。
- 録音録画が必要な場合は移動式の録音録画機もあるが、大容量のスーツケースサイズになる。
- 供述調書のフォーマットは各検察庁で異なる。
ちなみに、出張取調べが立会事務官の出張のほとんどを占めますが、頻度としては大体年に数回あるかなという感じになります。
なお、立会事務官の取調べ時の仕事内容については下記記事で紹介していますので、合わせて見てもらえればと思います。

専門家からの聴取
事件の内容によっては専門家の意見を聴取する場合がありますが、専門家は忙しい方が多いため、アポイントを取って勤務先にて聴取させてもらいます。
聴取する専門家は医者や研究者がほとんどとなりますので、聴取場所は大学や大学病院が多くなります。
地方の大学や大学病院は交通アクセスが悪い場所にあることも多く、出張先でレンタカーを借りる場合もある。
証拠品の押収手続
証拠品によっては押収手続のために出張を行う場合があります。
代表的なものとして通信事業者が保有する利用者履歴などがありますが、書面での捜査関係事項照会では応じてもらえないため、東京本社まで差押えに行く必要があります。
身柄事件では警察等の司法警察員が証拠品を押収するが、在宅事件の送致後や検察庁独自捜査事件では検察庁職員で証拠品を押収する。
なお、立会事務官の捜査の仕事内容については下記記事で紹介していますので、合わせて見てもらえればと思います。

- 出張勤務は出張取調べの場合がほとんど。
- 出張取調べの頻度は年に数回程度。
では次に、立会事務官の出張勤務の事務手続について見ていきたいと思います。
出張勤務の事務手続について
立会事務官の出張勤務の事務手続ですが、出張前後で行わなければならない事務手続がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
旅行命令
国家公務員が出張を行う場合は旅行命令権者から事前に旅行命令を受ける必要があります。ので、立会事務官は旅行命令の決裁書類を作成しなければなりません。
- 出張計画書
- 旅行命令簿
- 旅程表
決裁書類の内、旅程表には在勤官署から目的地までの具体的な交通経路を記載しなければなりませんので、立会事務官はインターネットで調べる必要があります。
出張勤務で遅刻は厳禁ですので、余裕を持った旅程の作成が必須となります。
宿泊を伴う出張は旅行会社のパック商品利用が基本であるが、取調べ等は急に決まるため、検察庁ではパック商品を利用しない場合がほとんど。
公共交通機関の手配からホテルの予約といったアテンド業務のような仕事も立会事務官には必要ということになります。
旅費請求手続
出張勤務後は出張に伴う旅費請求手続を行う必要がありますので、旅費に応じた必要書類を添付して旅費精算請求書を作成しなければなりません。
なお、旅費請求手続に問題がなければ、請求から約2週間程度で登録口座に旅費が振り込まれることになります。
給与の振込口座は大手銀行を登録できるが、旅費等の振込口座はゆうちょ銀行しか登録できない。
では、出張勤務で対象となる旅費についてそれぞれ見ていきたいと思います。
鉄道賃
鉄道賃は鉄道に乗車して旅行する費用に充てる旅費(旅行運賃・急行料金・座席指定料金)になります。
鉄道賃は旅程から一律計算になりますので、ら旅費請求手続において乗車券等の証明書類は不要となります。
新幹線利用は指定席料金が支給される。
→証明書類不要のため、自由席を利用することも可能。
航空賃
航空賃は飛行機等に搭乗して旅行する費用に充てる旅費になりますが、航空賃は料金が日によって変動することから実費支給となります。
そのため、旅費請求手続では航空券購入時の領収書と搭乗券の半券が必要となります。
航空会社会員の場合、飛行機搭乗でマイルを貯めることができるが、国家公務員公務で個人のマイルを貯めないよう注意喚起されている。
宿泊料
宿泊料は旅行中の宿泊費及び宿泊に伴う諸雑費を賄う旅費になりますが、宿泊料は実費精算ではなく、下記表で定められる一夜当たりの定額で支給されます。
| 区分 | 宿泊料 (一夜につき) |
|
| 甲地方 | 乙地方 | |
| 指定職の職務にある者 | 14,800円 | 13,300円 |
| 7級以上の職務にある者 | 13,100円 | 11,800円 |
| 6級以上3級以上の職務にある者 | 10,900円 | 9,800円 |
| 2級以下の職務にある者 | 8,700円 | 7,800円 |
上記表を見ると、職位と宿泊地(甲乙)によって宿泊料に違いがあることが分かります。
- 甲地方
東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、千葉市、名古屋市、大阪市、堺市、京都市、神戸市、広島市、福岡市 - 乙地方
その他の地域
なお、検察官の区分については以下の表の通りとなりますので、参考にして貰えればと思います。
| 指定職 行(一) |
検察官 |
|
| 検事 | 副検事 | |
| 指定職 | 8号以上 | 2号以上 |
| 9級 | 9号、10号 | 3号~5号 |
| 8級 | 11号、12号 | 6号、7号 |
| 7級 | 13号、14号 | 8号、9号 |
日当
日当は目的地内を巡回する場合の交通費及び諸雑費を賄う旅費になりますが、一日当たりの定額で支給されます。
| 区分 | 日当 (一日あたり定額) |
| 指定職の職務にある者 | 3,000円 |
| 7級以上の職務にある者 | 2,600円 |
| 6級以下3級以上の職務にある者 | 2,200円 |
| 2級以下の職務にある者 | 1,700円 |
なお、以下のような場合、支給される日当は半額となります。
- 鉄道100キロメートル未満
- 水路50キロメートル未満
- 陸路25キロメートル未満
なお、上記の近距離出張の場合でも、公務上等の理由で宿泊を要する場合は定額の日当が支給されます。
- 出張前の事務手続は旅行命令決裁。
→旅程の確定・確保も仕事 - 出張後の事務手続は旅費精算手続。
→飛行機利用は証明書類が必要。
おわりに
今回は、立会事務官の出張勤務について紹介してきました。
立会事務官は出張勤務が多そうだと思っていた方も、実際にどういった場合に出張勤務をするか、頻度がどれくらいになりそうか理解して貰えたと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。