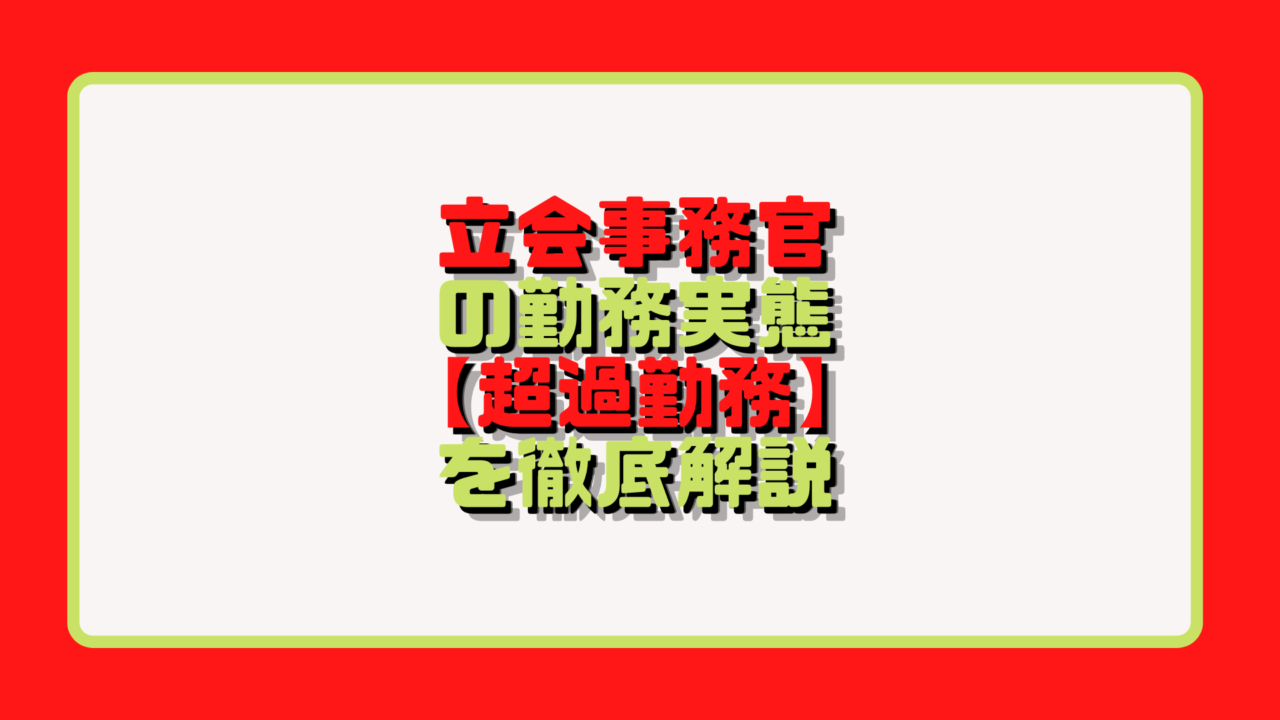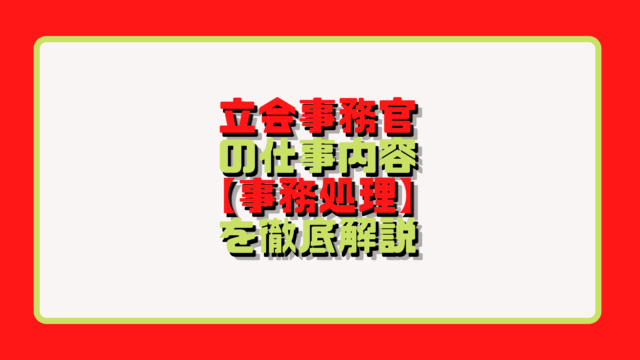こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、めちゃくちゃ激務で超過勤務(残業)が多いイメージを持っている方も多いと思います。
そこで、本記事では、立会事務官の超過勤務(残業)について詳しく紹介していきたいと思います。
実際に立会事務官として勤務した経験を基に超過勤務のリアルをお伝えしますので、是非参考にしてもらえればと思います。
超過勤務の概要について
国家公務員の勤務時間は法律等で定められていますが、1日に割り振られた正規の勤務時間(1日7時間45分)を超える勤務のことを超過勤務といいます。
勤務日 :月曜日~金曜日の5日間
勤務時間:1日7時間45分
1週間当たり38時間45分
※休憩時間を除く
休憩時間:60分
検察庁では8時30分~17時15分が正規の勤務時間(※)になるので、8時30分より前と17時15分より後の勤務が超過勤務となります。
※時差通勤実施庁の勤務時間は異なる
では、超過勤務の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
なお、勤務時間制度については下記記事で詳しく紹介していますので、合わせて見てもらえればと思います。
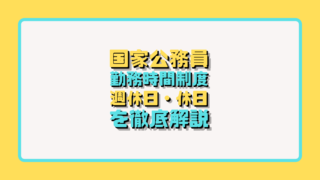
超過勤務の申請方法
国家公務員が超過勤務を行う場合、事前申請を行い、命令権者から超過勤務を命じられてから超過勤務を行うというのが一般的な流れになります。
しかし、検察庁では、退勤時間を事後申告するだけで、特に事前申請は行っていません。
申告方法は庁によって異なりますが、庶務担当者が管理する紙の出勤簿やExcelファイルに出勤時間と退勤時間を記入する形となります。
超過勤務の命令権者(上司)は事件管理の次席捜査官などで、担当検察官ではない。
超過勤務した場合の取扱い
超過勤務を行った場合は、超過勤務手当が支給されることになります。
勤務1時間当たりの給与額×支給割合×勤務時間数
勤務1時間当たりの給与額には地域手当も含みますので、都市部の方が超過勤務手当の単価は高くなります。
支給割合については以下となります。
| 勤務日 | 支給割合 | |
| 平日 | 通常 | 125/100 |
| 深夜 | 150/100 | |
| 週休日等 |
通常 | 135/100 |
| 深夜 | 160/100 | |
| 60時間超 |
通常 | 150/100 |
| 深夜 | 175/100 | |
なお、超過勤務手当については下記記事で詳しく紹介していますので、合わせて見てもらえればと思います。
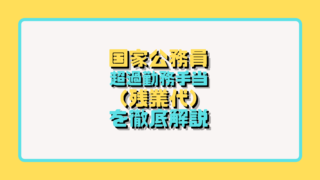
超過勤務手当が100%支給されるかどうかについては、予算の関係上、超過勤務の多くなる大規模庁ほど実際に支給される割合は低くなる傾向があります。
ちなみに、私が働いていた地検では、実際に超過勤務した時間の40%が超過勤務手当の支給対象でしたね。
- 超過勤務とは割り振られた正規の勤務時間を超える勤務のこと。
- 検察庁での超過勤務の申請は翌勤務日に退勤時間を記入するだけ。
- 超過勤務手当が100%支給されるかどうかは所属庁の予算次第。
では、次に、立会事務官がどのような場合に超過勤務をするのかについて見ていきたいと思います。
超過勤務する場合について
立会事務官が超過勤務する場合についてですが、基本的には以下の場合に超過勤務をすることになりますので、それぞれ見ていきたいと思います。
参考人取調べ・証人テスト
事件の被害者や目撃者である参考人取調べや裁判で証言してもらう証人との打ち合わせである証人テストは、基本的には平日の勤務時間内に行われます。
しかし、参考人の場合は仕事や通学などの事情を考慮してますので、勤務時間外に参考人取調べや証人テストを行う場合があります。
どれくらい超過勤務を行うかについては事案によってまちまちですが、だいたい1時間から長くても2時間程度になります。
ちなみに、予定があって定時に帰らないといけない日は他の立会事務官に代わってもらえますので、プライベートの予定を事前に入れられないということはありませんね。
勾留請求等の判断待ち
被疑者の身柄を拘束している身柄事件の場合、裁判所に対して引き続き身柄を拘束するために勾留請求や勾留延長請求を行います。
この勾留請求等を認容するか却下するかの判断は裁判官が行いますが、請求する時間が遅くなると裁判官の判断が出るのが勤務時間外になることもあります。
- 勾留請求決定後の流れ:
勾留状発付→検察官指揮印押印→被疑者収容(警察) - 勾留請求却下後の流れ:
勾留請求却下の裁判→被疑者釈放手続or準抗告の申立て
また、勾留請求等の認容に対する準抗告(弁護人)や却下に対する準抗告(検察官)が申し立てられた場合は、別の裁判官が新たに準抗告の認容又は棄却の判断を行うことになります。
頻度としては月に1回か2回あるかないか程度です。
準抗告の判断は遅いと22時や23時とかになる場合もありますので、準抗告となったら長時間の超過勤務は覚悟する必要があります。
ちなみに、判断待ちの間は釈放手続きの準備くらいしか仕事がないので、別の事件の事務処理などを進めて超過勤務時間を有効活用することになりますね。
繁忙期等の事務処理
立会事務官の仕事には捜査もありますが、事務処理がメインの仕事となります。
事務処理は取調べの合間などにも行うことができますので、基本的には勤務時間外にまで事務処理に追われる状態にはならないです。
ただ、立会事務官には事件の処理件数が増える繁忙期がありますので、繁忙期には事務処理のための超過勤務が増えることになります。
年末や年度末は、在宅事件の未済件数をゼロに近づけるために取調べと事件処理が増えるため、立会事務官の繁忙期となる。
ちなみに、立会事務官の仕事量は重大な事件も軽微な事件もさほど変わらないので、担当する事件数が多くなるほど仕事量が多くなります。
- 事件の重要度
シニア検事>A庁検事>副検事 - 事件の配点数
シニア検事<A庁検事<副検事
一般的に重大な事件を担当するシニア検事の立会事務官より軽微な事件を多く担当する副検事の立会事務官の方が忙しいです。
事件着手時の特別捜査部【参考】
事件着手とは被疑者を逮捕・勾留して身柄を拘束することをいいますが、事件着手時の特別捜査部(特別刑事部)の立会事務官は終電近くまで超過勤務することになります。
事件着手中は毎日チームミーティングを行いますが、身柄担当が拘置所から帰庁してから行われるため、毎日夜遅くから終電近くまでミーティングが行われます。
当然、立会事務官もチームミーティングが終わるまで待機しなければなりませんので、事件着手中の超過勤務はめちゃくちゃ多いです。
そのため、特捜部はワークライフバランスとかけ離れた部署と言わざるを得ませんが、政治家の汚職事件や大企業の脱税事件など特捜部でしか経験できない貴重な体験ができますので、非常にやりがいはあります。
https://moto-kensatsujimukan.com/special-inestigation-depaetment/
ちなみに、特捜部だと週休日等の勤務も多く、振り替えた週休日等も超過勤務扱いで勤務しますので、超過勤務手当等で基本給を余裕で超えるなんてこともざらにありますね。
- 予定がある場合、参考人取調べは他の立会事務官に代わってもらえる。
- 勾留請求等で準抗告となった場合は、裁判官の判断待ちで夜遅くまで残らないといけない。
- 繁忙期は年末と年度末。
おわりに
今回は、立会事務官の超過勤務(残業)について紹介してきました。
立会事務官は超過勤務が多そうと思っていた方も、実際に立会事務官がどういった場合に超過勤務をするか、頻度がどれくらいになりそうか理解してもらえたと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。