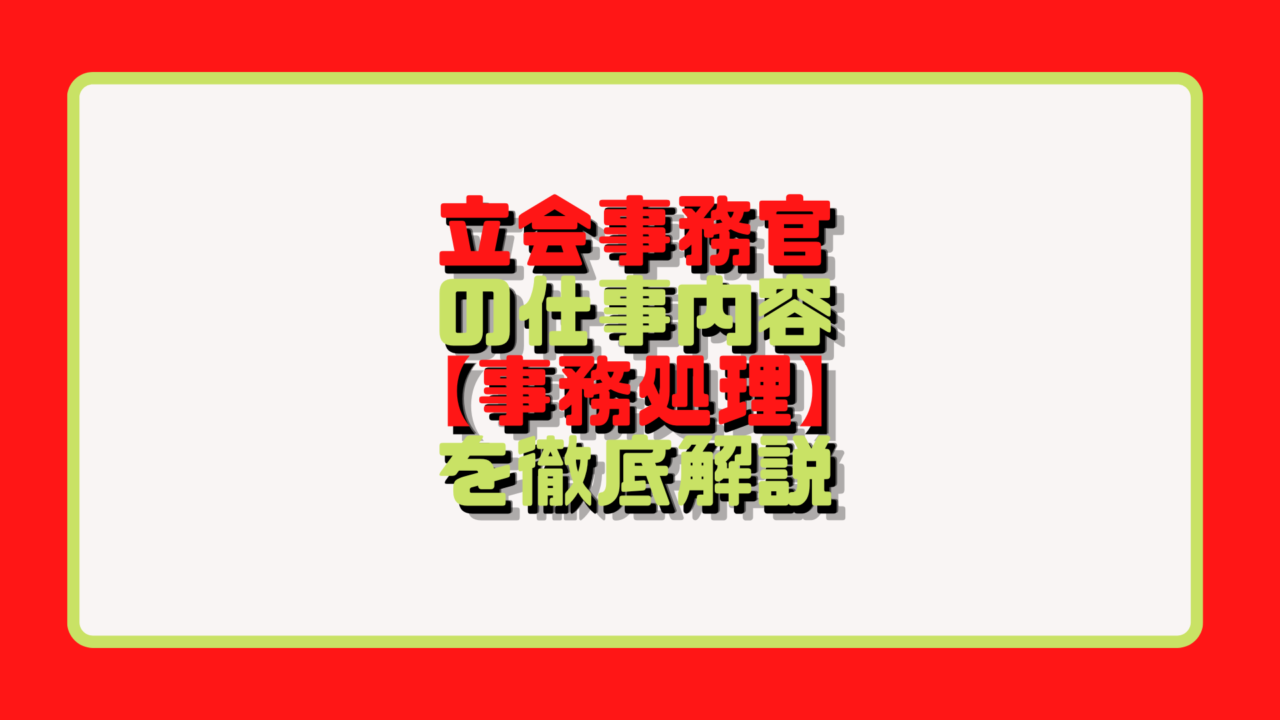こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は、立会事務官の仕事内容の内、事務処理について詳しく紹介していきたいと思います。
立会事務官の仕事は捜査より事務処理がメインとなりますので、検察庁内定者の方はもちろん、検察事務官志望者の方も是非参考にしてもらえればと思います。
事件配点時の事務処理について
立会事務官の事件配点時の事務処理ですが、代表例として以下の仕事がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
事件記録の点検
事件管理の配点担当から事件記録を受け取った際は、まず公訴時効の確認を行います。
犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなる制度。
公訴時効確認の取扱いは各検察庁で異なりますが、私の所属していた地検では表紙に公訴時効満了年月日を記載し、検察官の確認印を押印する取り扱いでした。
公訴時効を完了させてしまったり、公訴時効が完了しているのに公訴を提起してしまうと過誤となる。
時効期間は罪の種類(人を死亡させたか否かと法定刑)によって決まっていますので、罪名別の早見表などで時効期間を確認します。
前科照会
前科調書は警察が照会して事件記録に編綴されていますが、在宅事件などで回答日から時間が経過している場合は改めて前科照会をかける必要があります。
一般前科:所属庁の犯歴担当
道交前科:被疑者本籍地の犯歴担当
また、前科照会によって被疑者の前科が発覚した場合には以下の事務処理も必要となります。
前科記録・判決謄本の取寄せ
被疑者に前科があった場合は前科記録と判決謄本等が必要になりますので、事件記録を管理している検察庁の記録担当に依頼して取寄せを行います。
事件記録に編綴されている前歴調書に不起訴処分歴がある場合は不起訴記録の取寄せも行う。
なお、前科記録等には保存期間があり、期間が過ぎると廃棄となりますので、取寄せ依頼をかける前に検察システムで保存期間内か確認する必要があります。
罰金未納者等の通報関係
前科調書の記載内容によっては、下記のような各種通報・通知を行う必要があります。
- 罰金未納者の通報
→徴収未済検察庁の記録担当 - 保護観察者等の再犯通知
→保護観察所(執行担当経由) - とん刑者等(逃亡者)の通報
→登録を行った担当事務官
罰金未納者・とん刑者等の通報は電話連絡になりますが、保護観察者等の再犯通知の場合は「仮釈放者再犯通知書」や「保護観察者再犯通知書」を作成する必要があります。
前科調書の補正
前科調書記載の氏名や本籍が戸籍謄本と相違している場合がありますが、その場合は戸籍謄本の写し等の疎明資料を添付して犯歴担当に補正の依頼をします。
場合によっては被疑者の転籍前の戸籍謄本も必要になりますので、転籍前の市区町村役場に身上調査照会を行います。
身上調査照会
戸籍謄本等も警察が照会して事件記録に編綴されていますが、在宅事件などで回答日から時間が経過している場合は改めて身上調査照会をかける必要があります。
日本国籍を有する者 :戸籍謄本
日本国籍を有しない者:住民票の写し
なお、急ぎの場合は電話で本籍地を確認して「電話聴取書」を作成することもありますが、市区町村によっては応じてくれないところもあるので注意が必要となります。
- 事件配点時は公訴時効満了日を確認し、公訴時効完成による過誤を起こさないよう注意する。
- 前科照会や身上調査照会を適宜かけ、前科調書や戸籍謄本など捜査に必要な資料を取り寄せる。
では次に、立会事務官の事件処理時の事務処理について見ていきたいと思います。
事件処分時の事務処理について
検察官は事件について必要な捜査を遂げた後に、公訴を提起するか否かの事件処分を行います。
- 公訴の提起を行う場合
公判請求、即決裁判手続、略式命令請求 - 公訴の提起を行わない場合
不起訴処分、家庭裁判所送致、中間処分
立会事務官の事件処分時の事務処理を決裁前後でそれぞれ見ていきたいと思います。
決裁前の事務処理
検察官が事件処分を行う際は決裁官から決裁を貰いますが、立会事務官は決裁に際して必要となる書類を準備します。
決裁書類の作成
検察官が事件処分をする際には決裁官からの決裁が必要となりますが、決裁官から押印を貰う書類は立会事務官が作成します。
- 公判請求
起訴状、公判引継事項書 - 略式命令請求
起訴状、請書 - 不起訴処分
不起訴裁定書、釈放指揮書 - 家庭裁判所送致
送致書
決裁書類ですが、検察システムに必要事項と事件処分の種類を入力することで自動的にフォーマットが出力されます。
起訴状の「公訴事実」と不起訴裁定書の「事実及び理由」は検察官が作成。
→人事評価上、立会事務官の方で素案を作成することが望ましい。
求刑資料の出力
公訴を提起する場合は求刑(懲役〇年、罰金〇円など)決裁も受けますので、求刑の根拠となる求刑資料を用意する必要があります。
基本的には検察官自身で求刑資料を準備しますが、検察システムを使いこなせない検察官は立会事務官に準備を頼むことになります。
検察システムで類似事件を検索(罪名、被害者の人数、示談の有無など)し、求刑と判決内容を出力する。
決裁後の事務処理
検察官が決裁官からの決裁を貰った後ですが、下見担当のチェックを受け、最終的には事件担当で事件処理されます。
- 決裁官による決裁
- 事件管理下見担当による点検
- 令状担当による点検
※身柄事件の場合 - 事件担当による点検・事件処理
立会事務官は事件処理が行えるよう事件処分ごとの決められた事務処理を行う必要があります。
事件記録等の体裁を整える
事件処分の種類によって事件記録の体裁は異なりますので、各ルールに従って体裁を整える必要があります。
また、起訴状の公訴事実などの記載内容が証拠に基づいているか点検されますので、根拠となる箇所にふせんを貼る必要があります。
誤字脱字や同じミスの繰り返しなどが多いと人事評価に影響する。
→下見担当への回付前は入念なセルフチェックを行うことが望ましい。
なお、訂正があると都度、事件記録が返却され、書類等を作り直さなければなりませんので、訂正が多いと事務処理の手間が増えてしまいます。
通知書等の作成
事件の事案によっては事件処理の際に通知・通報などを行う必要がありますが、書面は立会事務官が作成します。
- 告訴・告訴人らに対する通知
- 被害者等通知制度による処分通知
- 出入国在留管理庁への通報
- 性犯罪、覚せい剤の再犯情報通知
など
通知関係は作成漏れし易い箇所になりますので、事件受理時に通知が必要になるかどうか確認しておくのが望ましいですね。
- 決裁前は、事件処分に必要な決裁書類等を準備する必要がある。
- 決裁後は、事件記録の体裁や通知文書を整え、下見担当などの点検をクリアしなければならない。
- 起訴状公訴事実の積極的な作成や事件処分時の事務処理の正確性は人事評価につながる。
おわりに
今回は、立会事務官の仕事の内、事務処理について詳しく紹介してきました。
事務処理が立会事務官のメイン仕事となりますので、立会事務官の仕事をイメージする上で参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。