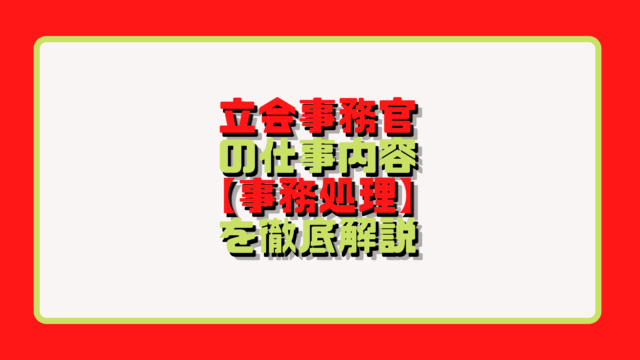こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
捜査に従事する立会事務官のイメージとして、何か事件が発生したら現場に臨場しなければならないなど、休日出勤が多いイメージを持っている方も多いと思います。
そこで、本記事では、立会事務官の週休日等の勤務について詳しく紹介していきたいと思います。
実際に立会事務官として勤務した経験を基に週休日等の勤務のリアルをお伝えしますので、是非参考にしてもらえればと思います。
週休日等の勤務の概要について
世間一般的に休みの日に働くことを休日出勤などといいますが、国家公務員の場合は「週休日等の勤務」といいます。
「週休日等」とは法律で定義されている「週休日」と「休日」のことを指します。
週休日:日曜日及び土曜日
休 日:①祝日法による休日
②年末年始の休日
→12月29日~1月3日
※祝日法による休日を除く
では、週休日等の勤務の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
なお、週休日等については下記記事で詳しく紹介していますので、合わせて見てもらえればと思います。
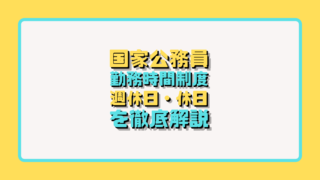
週休日等の勤務の届出
週休日等に勤務する必要が生じた場合は、事前に週休日等勤務届を提出し、勤務予定日や勤務の内容などを届け出る必要があります。
週休日に勤務する場合:1日or4時間
休 日に勤務する場合:1日
勤務日当日は、日直担当者に引継がれている週休日等勤務届に出勤時刻と退勤時刻を記入し、届出通りに勤務していることの確認を受けることになります。
週休日等に勤務した場合の取扱い
週休日等に勤務した場合は、基本的に「週休日の振替」や「代休日の指定」を受けることになります。
要するに、週休日等に勤務した代わりに別の勤務日に休みを取るということになります。
勤務した週休日等を起算日として
週休日の振替:前4週間~後8週間
代休日の指定:後8週間
なお、振り替えた週休日や代休日に勤務することとなった場合は、再振替や再代休の指定はできませんので、勤務した時間分の超過勤務手当や休日給が支給されることになります。
- 週休日等に勤務する場合は事前の届け出が必要。
- 勤務時間は週休日は1日or4時間、休日は1日単位。
- 週休日の振替や代休日の指定を受けることが基本。
では、次に、立会事務官がどのような場合に週休日等に勤務するのかについて見ていきたいと思います。
週休日等に勤務する場合について
立会事務官が週休日等に勤務する場合についてですが、基本的には以下の場合に週休日等に勤務することになりますので、それぞれ見ていきたいと思います。
参考人の取調べ
立会事務官が週休日等に勤務する場合のほとんどは、参考人(被害者・目撃者など)の取調べ対応になります。
取調べは基本的に平日の日中に行いますが、参考人の場合は仕事や通学等の事情を考慮しますので、土日などの週休日等に取調べを行うことがあります。
取調べの時間は調書作成の時間を含めて1時間~2時間程度になりますので、週休日の場合は4時間勤務を行うことになります。
なお、週休日等に参考人取調べを行う頻度は、私の経験上、月に1回あるかないかでしたので、週休日等の勤務はそう多くはありません。

ちなみに、参考人取調べが入った週休日等に予定がある場合は、他の立会事務官に週休日等の勤務を代わってもらうことができますので、プライベートとの両立は可能ですよ。
勾留請求手続き
週休日等の勾留請求手続きは、基本的に日直担当の検察官が行っています。
ただ、以下の場合は担当検察官自らが勾留請求手続きを行うこともありますので、勾留請求手続きのために週休日等に勤務する場合があります。
- 担当事件の被疑者の再逮捕。
- 相談事件の被疑者の逮捕。
週休日等に送致される事件の担当検察官は、通常、休み明けに決まります。
しかし、上記の場合は送致前に担当検察官が決まっていますので、担当検察官が初期の証言が重要などと判断した場合は自ら勾留請求手続きを行うことになります。
- 検察官による弁解録取手続
- 裁判官による勾留質問
- 裁判官による勾留状の発付or勾留却下
- 検察官による勾留状の執行指揮or釈放手続
勾留請求手続きは上記①~④の流れで行われますが、検察庁では①と④を行います。
平日の勾留請求手続きの場合は④まで担当検察官が対応しますが、週休日等の場合は担当検察官は①のみ行い④は日直担当検察官に任せる場合もあります。
①のみの場合は30分~1時間程度で終わりますので、週休日等の勤務は4時間勤務で済みます。
ちなみに、弁解録取手続も取調べも立会事務官の仕事はほぼ変わりませんので、参考人取調べと同様、予定がある場合は別の立会事務官に代わってもらうことができます。
重大事件発生時の現場臨場
各地方検察庁には、各都道府県警本部の捜査1課が扱う重大事件を担当する本部係の検事が1名います。
※東京や大阪などには本部係補助検事もいる
本部係の検事と立会事務官は、捜査1課が扱う重大事件(強盗殺人事件など)が発生した場合は、夜間・休日問わず現場に臨場しなければなりません。
事件現場では、検事と共に事件現場の確認や検視の立会などを行うことになります。
ちなみに、本部係補助がいる地検では立会事務官同士で担当日の調整が可能ですが、本部係補助がいない地検では本部係の立会事務官のプライベートは制約されてしまいますね。
※地検によっては当番制にしているかも?
事件着手時の特別捜査部【参考】
事件着手とは被疑者を逮捕・勾留して身柄を拘束することをいいますが、事件着手時の特別捜査部(特別刑事部)の立会事務官には週休日等の休みはありません。
特捜部では検察庁独自捜査や国税局等からの告発事件を担当しますが、警察よりマンパワーが足りませんので、事件着手時は週休日等も休まず毎日取調べを行います。
そのため、特捜部はワークライフバランスとかけ離れた部署と言わざるを得ませんが、政治家の汚職事件や大企業の脱税事件など特捜部でしか経験できない貴重な体験ができますので、非常にやりがいはあります。
https://moto-kensatsujimukan.com/special-inestigation-depaetment/
ちなみに、特捜部だと振り替えた週休日と代休日も基本的に休めませんので、超過勤務手当等で基本給を余裕で超えるなんてこともざらにありますね。
- 週休日等に勤務する場合は参考人取調べがほとんど。
- 予定がある場合、参考人取調べ等では他の立会事務官に代わってもらえる。
- 重大事件発生時の現場臨場は本部係のみ。
おわりに
今回は、立会事務官の休日出勤について紹介してきました。
立会事務官は週休日等の勤務が多そうと思っていた方も、実際に立会事務官がどういった場合に週休日等に勤務するか、頻度がどれくらいになりそうか理解してもらえたと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。