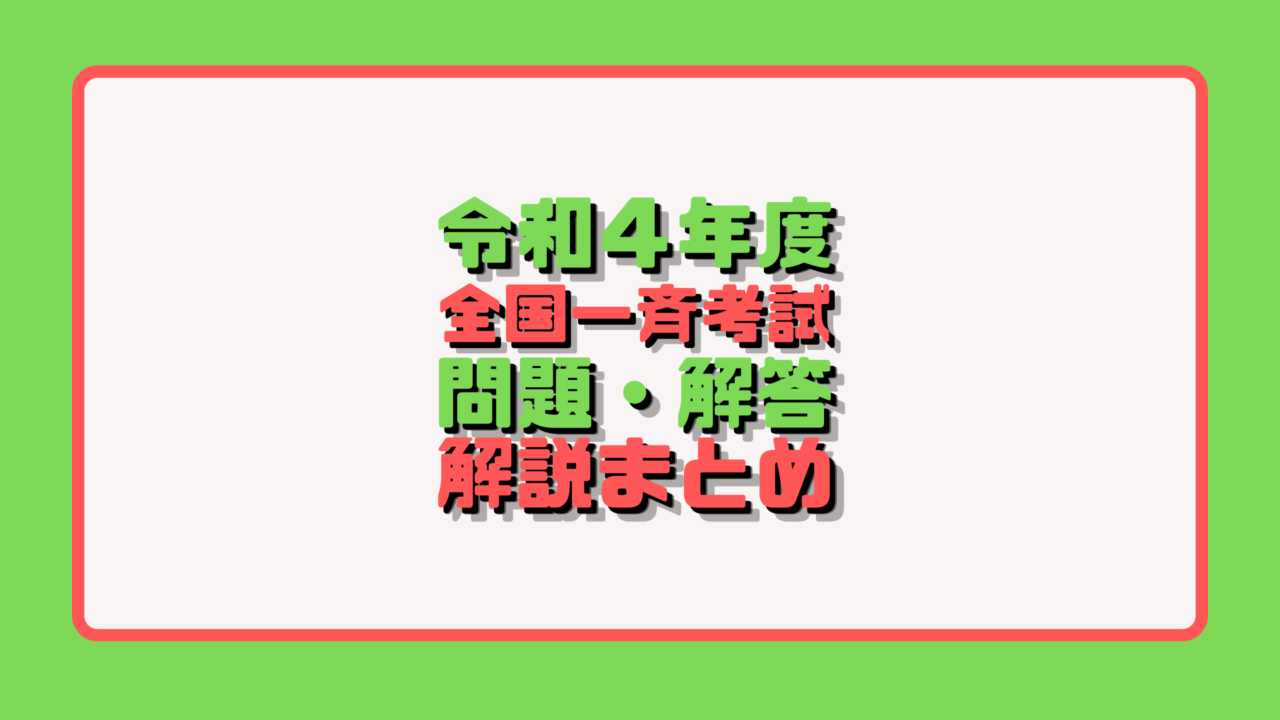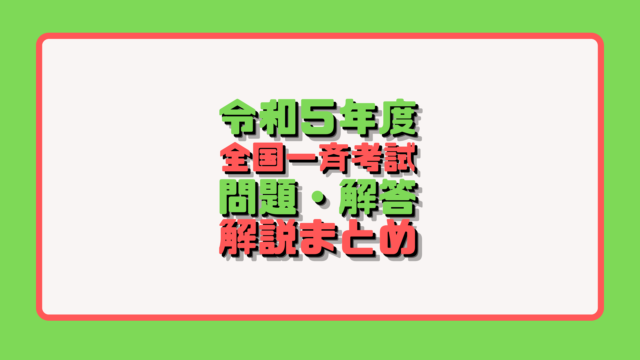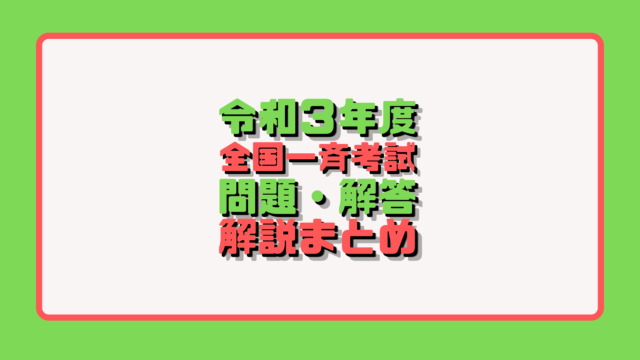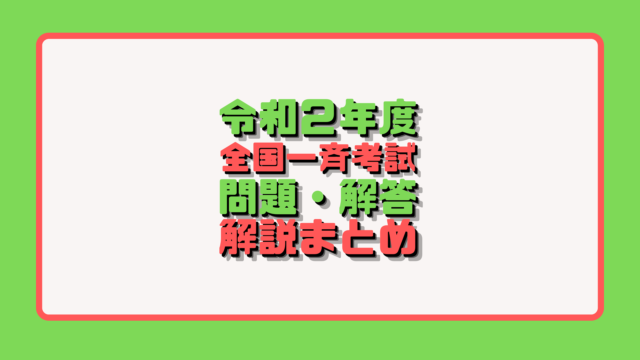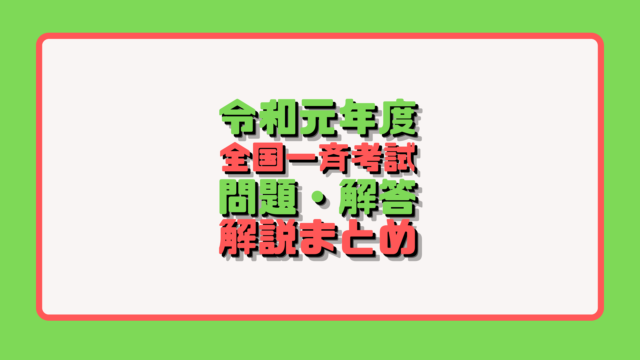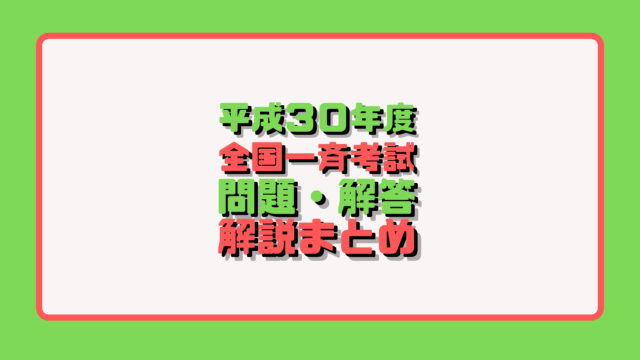憲法・検察庁法
第1問
経済的自由権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 経済的自由権は、自由国家的公共の福祉による制約の対象となるだけでなく、政策的な要請からの社会国家的公共の福祉による制約の対象ともなる。
(○) そのとおり(研修教材・五訂憲法146、147ページ、研修858号82ページ)。
⑵ 憲法22条1項が職業選択の自由を保障するというなかには、いわゆる営業の自由を保障する趣旨も包含している。
(○) そのとおり。最大判昭47.11.22刑集26・9・586は、「憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであ」ると判示している(研修教材・五訂憲法149ページ)。
⑶ 外務大臣が、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者に対する一般旅券の発給を拒否することは、憲法22条2項に違反する。
(×) 最大判昭33.9.10民集12・13・1969は、外務大臣が一般旅券の発給を拒否することができること及び拒否できる場合を定めた旅券法の規定が憲法22条2項に違反しないかが争われた事案において、「憲法22条2項の『外国に移住する自由』には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。」とした上で、「旅券発給を拒否することができる場合として、旅券法13条1項5号(注:当時。現13条1項7号)が、『著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者』と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ」るとして、同規定は憲法22条2項に違反するものではないと判示した(研修教材・五訂憲法147、148ページ)。
⑷ 憲法29条1項は、個人が現に有する具体的な財産権を保障するだけでなく、個人が財産権を享有し得る法制度をも保障するものである。
(○) そのとおり(研修教材・五訂憲法155ページ)。
⑸ 私有財産を公共のために用いる場合、憲法29条3項による「正当な補償」として、常に、収用される財産の客観的な市場価格全額が完全に補償されなければならない。
(×) 憲法29条3項が要求する「正当な補償」がどの程度の補償であるかについて、完全補償説(収用される財産の収用時の客観的な市場価格の全額補償を要するとする説)と相当補償説(常に完全な補償である必要はなく、社会・経済状況など諸般の事情を考慮して相当と認められる価値の補償で足りるとする説)の対立があるが、この点につき、最大判昭28.12.23民集7・13・1523は、「正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではないと解するを相当とする。」と判示した(研修教材・五訂憲法157~159ページ)。
第2問
社会権、参政権、国務請求権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法25条1項は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない。
(○) そのとおり。憲法25条が保障する生存権の法的性格については、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説といった諸説の対立がある。判例は、「この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」とした上、具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された法律によって、初めて与えられているというべきであるとする(最大判昭42.5.24民集21・5・1043)(研修教材・五訂憲法160~163ページ、研修862号57~59ページ)。
⑵ 憲法26条1項は、全ての国民に、等しく教育を受ける権利を保障しているので、学力の違いに応じて異なる取扱いをすることも許されない。
(×) 憲法26条1項は、「すべて国民は、……その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めており、学力など、教育を受けるのに直接に必要とされる能力により異なる取扱いをすることは容認される(研修教材・五訂憲法164ページ。教育基本法4条も参照。)。
⑶ 公務員にも労働基本権が保障されるので、その争議行為を禁止することは憲法28条に違反する。
(×) 公務員の労働基本権の制約の合憲性及びその根拠については、判例の変遷があったところではあるが、最大判昭48.4.25刑集27・4・547において、国家公務員法における争議行為の禁止規定について、憲法28条には違反しないとの判断が示された(研修教材・五訂憲法173~177ページ、研修882号81、82ページ)。
⑷ 憲法15条1項は、公務員の選定罷免権を国民固有の権利としているが、ここでいう「公務員」には、地方公共団体の事務を担当する公務員を含む。
(○) そのとおり(研修教材・五訂憲法178ページ)。
⑸ 法律によって民事訴訟における上告理由を制限する(ただし、憲法81条の規定するところを除く。)ことは、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に反するものではない。
(○) そのとおり。改正民事訴訟法(平成10年施行)が上告理由を憲法解釈の誤りその他の憲法違反及び重大な手続違反に制限したことにつき、憲法32条に違反しないかが争われた事案において、最判平13.2.13判時1745・94は、「いかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であって、憲法が81条の規定するところを除いてはすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである」「その趣旨に徹すると、所論の民訴法の規定が憲法32条に違反するものでないことは明らかである。」と判示した(研修教材・五訂憲法187ページ)。
第3問
違憲審査権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 違憲審査権の主体は、最高裁判所のみであり、下級裁判所は違憲審査権を持たない。
(×) 違憲審査権の主体は、最高裁判所のみではなく、下級裁判所も違憲審査権を持つ。憲法81条の「終審裁判所である」との文言は前審を予定していると解される。判例も「憲法81条は、……下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨をもっているものではない」(最大判昭25.2.1刑集4・2・73)と判示している(研修教材・五訂憲法260、261ページ、研修872号50ページ)。
⑵ 裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有する。
(×) 判例は、警察予備隊違憲訴訟事件において、「最高裁判所は、法律命令等に関し、違憲審査権を有するがこの権限は司法権の範囲内において行使されるものであり」「具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。」(最判昭27.10.8民集6・9・783)と判示している(研修教材・五訂憲法260ページ、研修872号51、52ページ)。
⑶ 最高裁判所は、最高裁判所が定めた規則が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する。
(○) 憲法81条は、「一切の法律、命令、規則又は処分」が違憲審査権の対象となると規定しており、最高裁判所の規則についても違憲審査権の対象となる(研修教材・五訂憲法266ページ、研修874号50ページ)。
⑷ 憲法の最高法規性を定めた98条1項には条約が列挙されていないこと、同条2項が国際協調主義をとり、条約遵守義務を定めていること等から、条約は憲法に優位し、最高裁判所は条約に対する違憲審査権を有しない。
(×) ①条約が憲法に優位すると解すると、内容的に憲法に反する条約が締結された場合には、法律よりも簡易な手続によって憲法が改正されることとなること、②98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規性を宣言した規定であるから条約が列挙から除かれているのは当然であること、③98条2項の国際協調主義は、違憲の条約まで遵守することを求めていないこと等から、憲法優位説が通説・判例である(研修教材・五訂憲法266、267ページ)。
⑸ ある法令が最高裁判所によって違憲と判断された場合、その効力は当該事件に関してのみ生じ、その法令自体の効力まで否定されない。
(○) 裁判所で違憲と判断された法律は、客観的に効力を失い、議会による廃止手続なくして存在を失うとする考え方(一般的効力説)と、その事件に限ってその法律の適用が排除されるにすぎず、違憲判断は他の事件には適用されない、とする考え方(個別的効力説)があるが、裁判の効力は具体的事件の解決に限定されるべきものと解すべきであるから、個別的効力説が妥当である(研修教材・五訂憲法269ページ、研修874号52ページ)。
第4問
地方自治に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 議院内閣制に倣って、都道府県知事を、その都道府県の議会で選出するという法律は、憲法に違反する。
(○) 憲法93条2項は、「地方公共団体の長……は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と定めており、都道府県の長を議会で選出する旨の法律は憲法違反となる(研修教材・五訂憲法284ページ、研修876号68~70ページ)。
⑵ 地方公共団体は条例制定権を有するが、これは国会単独立法の原則に対する憲法上の例外である。
(×) 国会中心立法の原則に対する例外である(研修教材・五訂憲法196ページ)。
⑶ 憲法は、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができると定めているので、地方公共団体が条例を制定するには、個々の法律による授権・委任が必要である。
(×) 「法律の範囲内で」とは、法律の規定と矛盾、抵触する規定を設けることはできないという趣旨であり、条例の制定について個々の法律による授権・委任を必要としない(研修教材・五訂憲法286、287ページ)。
⑷ 憲法は、地方公共団体に法律の範囲内で条例制定権を認めているので、特定事項についてこれを規律する国の法令が存在する場合には、当該事項に関する条例は制定できない。
(×) 最大判昭50.9.10刑集29・8・489は、「特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえない」と判示した(研修教材・五訂憲法289、290ページ)。
⑸ 憲法は、地方公共団体に法律の範囲内で条例制定権を認めているから、法律をもって条例制定権を奪うことも可能である。
(×) 条例制定権は、憲法94条にその根拠を置くものであるから、法律でこれを奪うことはできない(研修教材・五訂憲法286、287ページ、研修876号70ページ)。
第5問
検察庁法に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 区検察庁の検察官であっても、地方裁判所の事物管轄に属する事件を捜査することができる。
(○) そのとおり。検察庁法6条は、事物管轄の制限を解除しており、区検察庁の検察官であっても、地方裁判所の事物管轄に属する事件を捜査することができる。ただし、区検察庁の検察官は、これを地方裁判所に対して起訴することはできないことから、最終処理の前に管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に移送する必要がある(研修教材・七訂検察庁法40ページ。)。
⑵ 地方裁判所の支部が設けられても、必要と認めなければ、これに対応する地方検察庁の支部を設けなくてもよい。
(○) そのとおり。法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して、高等検察庁又は地方検察庁の支部を設けることができる(検察庁法2条4項)。したがって、裁判所の支部がないのに、検察庁の支部だけを設けることは許されないが、法務大臣が必要と認めなければ、裁判所の支部が設けられても、検察庁の支部は設けなくてもよい(研修教材・七訂検察庁法55ページ。)。
⑶ 法務大臣は、検察官に具体的事件の報告を求める場合は、検事総長を通じてこれを求めなければならない。
(×) 法務大臣は、検察官を一般に指揮監督することができるが、検察官の行う個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるにとどまる。一般にとは、一般的にということで、具体的にと相対する概念であり、検察事務処理についての一般的方針や基準を訓示したり、法令の行政解釈を示したり、個々の具体的事件について報告を求めたりすることである(研修教材・七訂検察庁法23ページ)。
⑷ 検察官の起訴は、上司の決裁を受けなくとも、法律的には有効となる。
(○) そのとおり。検察官は、一人一人が独立の官庁(独任制官庁)として検察事務に関する権限を行使するのであるから、仮に上司の決裁を受けずに捜査を開始したり、上司が不起訴処分に付するように指揮したのに、これを起訴したりしても、その捜査や起訴が違法、無効となることはない(ただし、上司の指揮監督権に反した場合、それが国家公務員法上の懲戒処分の理由になることはあり得る。)(研修教材・七訂検察庁法28、29ページ)。
⑸ 検事も副検事も置かれていない区検察庁においては、その庁の検察官事務取扱検察事務官が庁務を掌理し、職員を指揮監督する。
(○) そのとおり。検察官事務取扱検察事務官(検察庁法附則第36条(令和5年4月1日以降は、同法附則第2条))しか置かれていない区検察庁においては、その検察事務官が庁務を掌理し、職員を指揮監督する(研修教材・七訂検察庁法60ページ)。
民法(総則・債権)
第6問
意思表示に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bが経営する店で売られていた絵画を、画家Cの作品であると思い、購入したが、その後、同絵画の作者はCではないことを知った。同絵画の作者がCではなかった以上、Aは、常に、同絵画を購入する旨の意思表示を取り消すことができる。
(×) Aの錯誤は、民法95条1項2号の「法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤」(動機の錯誤)に該当するが、同条2項は、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」としている。Aが絵画を購入することとした事情(動機)が表示されていなかった場合は、Aは、錯誤を理由に絵画購入の意思表示を取り消すことはできないので、Aが常に意思表示を取り消すことができるとしている点で本間は誤り(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)119、120ページ、研修881号67~70ページ)。
⑵ Aは、Bの詐欺によって、自己が所有する腕時計をBに売却し、これをBに引き渡した。その後、Aは、詐欺による意思表示の取消しをしたが、Bは、その取消し後に、同時計の所有者はBであると過失なく信じたCに同腕時計を売却し、これをCに引き渡した。この場合、Cは、同腕時計の所有権を取得しない。
(×) 判例・通説は、民法96条3項によって保護される第三者は、意思表示の取消し前に利害関係に入った者に限られると解しており、取消し後にBから腕時計を購入したCは、同項で保護される第三者には当たらない。もっとも、Cは、取消しにより無権利者となったBから善意無過失で動産を譲り受けたことになるから、民法192条による即時取得が認められる。よって、Cが腕時計の所有権を取得しないとする本間は誤り(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)127~131ページ)。
⑶ Aは、第三者であるCに強迫され、自己が所有する甲土地をBに売り渡した。 強迫の事実につきBが善意無過失であった場合でも、Aは、強迫による意思表示の取消しをすることができる。
(○) そのとおり。第三者の強迫による意思表示の場合、第三者の詐欺による意思表示の場合とは異なり、相手方の知・不知等にかかわらず、常にその意思表示を取り消すことができる(民法96条2項の反対解釈。研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)133ページ)。
⑷ 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力が発生するので、 相手方と同居する家族に通知の内容が記載された書面が交付されただけでは、意思表示の効力は発生しない。
(×) 民法97条1項の「到達」は、一般取引上の通念により相手方の了知し得るようにその勢力範囲に入ることをいい、相手方が了知することまでは必要としない(最判昭36.4.20民集15・4・774、最判昭50.6.27判時784・65)したがって、郵便受に投入されたり、同居の家族・雇人に交付されれば、本人が了知しなくても到達したことになる(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)136、137ページ)。
⑸ 意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとしても、相手方が意思能力を回復し、その意思表示を知った後は、その意思表示をもって相手方に対抗することができる。
(○) そのとおり(民法98条の2ただし書2号、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)138ページ)。
第7問
代理に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Bは、自己が所有する家屋について、Aに代理権を付与した。Bがその代理権につき具体的権限を定めていなかったとしても、Aは、Bの代理人として、同家屋を修繕する権限を有する。
(○) 民法103条は、権限の定めのない代理人について、「保存行為」「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」のみをする権限を有するとする。ここでいう「保存行為」とは、財産の現状を維持する行為をいい、例えば、家屋を修繕することがこれに該当する(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)143ページ)。
⑵ Aは、Bから、Bが所有する土地に抵当権を設定する代理権を与えられていたが、Bに無断で、Bの代理人として、Cとの間で同土地の売買契約を締結した。Cは、Aがその代理権の範囲外の行為をしているとは知らなかったが、知らなかったことについて過失があった。この場合、AがCとの間で締結した土地売買契約について、Bはその責任を負わない。
(○) そのとおり。民法110条の「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」とは、第三者が善意無過失であったときを意味する。Cに過失があった以上、民法110条(及び民法109条1項本文)は適用されず、Bは、AがCとの間でした土地売買契約について責任を負わない(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)156~160ページ、研修885号41~43ページ)。
⑶ Aは、Bから代理権を付与されたことがないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cから腕時計を購入する契約を締結した。その後、Aに代理権がなかったことを知ったCは、Bに対し、1か月の期間を定めて、無権代理行為を追認するかどうかを確答するよう催告した。Bが1か月以内に確答をしなかったときは、BはAの無権代理行為を追認したものとみなされる。
(×) 無権代理行為の相手方からの催告に対して、本人が期間内に確答をしなかったときは、追認を拒絶したものとみなされる(民法114条)。
⑷ 無権代理人(ただし、行為能力者であることを前提とする。)は、自己に代理権がないことを知っていた場合には、無権代理人であると相手方が知らなかったことにつき相手方に過失があっても、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うことがある。
(○) そのとおり。民法117条1項は、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、(中略)相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」と規定しているところ、たとえ、無権代理人であることを相手方が過失によって知らなかった場合であっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、同項の規定が適用される(相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うことがある)こととなる(民法117条2項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)165、166ページ)。
⑸ Aは、Bから代理権を付与されたことがないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間で、Bが所有する土地の売買契約を締結した。Bは、Aによる無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、AがBを相続した。この場合、本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰属するので、Aの無権代理行為は有効となる。
(×) 判例は、本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に本人が死亡し、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効とはならないとする。なお、その理由として、無権代理人がした行為について、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができないことを挙げている(最判平10.7.17民集52・5・1296、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)167、168ページ)。
第8問
Aが、Bとの間で、Aが所有する特定物である絵画甲をBに売却する旨の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 売買契約の締結時、甲がA方に存在していた場合、AB間に別段の意思表示がない限り、甲の引渡場所はA方である。
(○) そのとおり。Aは、売買契約に基づき、Bに対し、特定物である絵画甲の引渡し債務を負うところ、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは「債権発生の時にその物が存在した場所において」しなければならない(民法484条1項、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)135ページ)。よって、甲の引渡場所は、売買契約の締結時、甲が存在していたA方である。
⑵ Aは、Bに受領遅滞があった場合であっても、甲の引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって甲を保存しなければならない。
(×) 特定物の引渡し債務を負う債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもってその物を保存する義務を負うが(民法400条)、債権者に受領遅滞があった場合は、その保存義務が軽減され、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りる(民法413条1項、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)54、55ページ)。
⑶ 売買契約の締結時、代金支払債務と甲の引渡債務の履行期を同一とする旨の合意がなされた。履行期の到来後、Bが代金支払債務の履行の提供をせずに甲の引渡しを請求したときは、Aは甲の引渡しを拒むことができる。
(○) そのとおり。双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権、民法533条本文)。なお、同時履行の抗弁権の行使には、相手方の債務が履行期にあることが必要であるところ(同条ただし書)、本設問ではBの債務が履行期にあることが前提となっている(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)173~175ページ)。
⑷ 甲の引渡しを先履行とする旨の合意がなされたが、Aは履行期に甲の引渡しをせず、かつ、甲の引渡しを拒絶する意思を明確に表示した。この場合において、Bは、相当期間を定めた履行の催告をすることなく、直ちに売買契約を解除することができる。
(○) そのとおり。民法542条1項2号に該当し、BはAに催告をしないで直ちに契約の全部を解除できる(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)185ページ、研修875号76ページ)。
⑸ 売買契約の締結後、Aが甲を引き渡す前に、甲が天災により滅失したときは、 Bは代金の支払を拒むことができない。
(×) 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対債務の履行を拒むことができる(民法536条1項)。Aの甲の引渡債務は、天災という当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となっており、Bは反対給付である代金の支払いを拒むことができる(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)176~178ページ)。
第9問
Aが、Bとの間で、Bが所有する甲建物を賃借する旨の契約を締結し、甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aの責めに帰することができない事由により甲建物が修繕を要する状態となり、AがBに修繕が必要である旨遅滞なく通知したにもかかわらず、Bが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Aは、自らその修繕をすることができる。
(○) そのとおり。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民法606条1項、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでない(同条1項ただし書))。賃借物が修繕を要するときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならず(民法615条)、賃貸人がその旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、賃借人は、その修繕をすることができる(民法607条の2第1号、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)215ページ)。
⑵ Aが甲建物の引渡しを受けた後、BがCに甲建物を譲渡し、CがAに対し、甲建物から退去するよう求めた。この場合、Aは、甲建物から退去しなければならない。
(×) Aは、甲建物の引渡しを受けているため、借地借家法31条により賃貸借の対抗要件を備えている。Cは、その後になって建物甲を譲り受けているので、Aは、建物賃借権をCに対抗することができる。よって、Aが退去しなければならないとしている点で誤りである(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)216、217ページ、研修871号57~60ページ)。
⑶ Aが甲建物の引渡しを受けた後、BがCに甲建物を譲渡した場合において、CがAに対し自己へ賃料の支払いを求めるには、Cは甲建物の所有権移転登記を備えなければならない。
(○) そのとおり。不動産の賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は当然にその譲受人に移転するが(民法605条の2第1項)、賃貸人が賃借人に対し、賃料請求するなど賃貸人の地位が移転したことを対抗するためには、賃貸物である不動産の所有権移転登記が必要である(同条の2第3項、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)216、217ページ、研修871号60ページ)。
⑷ AB間の賃貸借契約が終了し、Aが甲建物をBに返還する場合において、Aは、通常の使用によって生じた日照によるクロスの変色についても原状に復する義務を負う。
(×) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、これを原状に回復する義務を負うが、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗や賃借物の経年変化については原状回復義務を負わない(民法621条本文)。よって、通常の使用によって生じた日照によるクロスの変色は、Aの原状回復義務の範囲に含まれない(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)220ページ、研修871号57、62、63ページ)。
⑸ AB間の賃貸借契約が終了した場合において、Aは、Bに対し、Bに差し入れていた敷金の返還を受けるまでは甲建物の明渡しを拒むことができる。
(×) 賃貸人の敷金返還債務の発生時期については、民法622条の2第1項が、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき(同項1号)又は、②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき(同項2号)に、賃貸借に基づいて生じた金銭債務を敷金の額から控除した残額の敷金返還債務が発生することを規定している。すなわち、敷金返還と賃借物の明渡しは同時履行の関係には立たず、賃借物の明渡しが先履行である(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)221ページ、研修871号57、63、64ページ)。よって、Aが敷金の返還を受けるまで甲建物の明渡しを拒むことができるとしている点で誤りである。
第10問
AのBに対する100万円の金銭債権(甲債権)とBのAに対する100万円の金銭債権(乙債権)との相殺に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 甲債権の弁済期が到来したが、乙債権の弁済期が到来していない場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
(×) ①債権の対立があること、②両債権が同種の目的を有すること、③両債権が弁済期にあること、④双方の債権が相殺の意思表示当時有効に成立すること、⑤債権の性質が相殺を許さないものでないことの各要件を満たす場合に相殺適状にある(民法505条1項)。もっとも、③自動債権が弁済期にあれば、受動債権は必ずしも弁済期にあることは必要ではない。なぜなら、債務者は期限の利益を放棄することができる(民法136条2項本文)からである(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)149ページ、研修875号73~75ページ)。よって、Aは、乙債権の期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権を相殺することができる。
⑵ 乙債権が、AがBの身体を傷害したことにより生じた損害賠償債権であった場合、Aは、甲債権を自働債権、乙債権を受働債権とする相殺をもってBに対抗することはできない。
(○) そのとおり。受動債権が、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債権である場合、その債務者の側から、相殺をもって債権者に対抗することができない(509条柱書本文、2号)。これは、被害者に現実の給付を得させるという趣旨によるもので、損害賠償の中でも、生命、身体の損害を重大な損害として被害者の救済を重視するものである(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)150、151ページ)。
⑶ 相殺適状にある甲債権と乙債権について、AとBいずれからも相殺の意思表示がなされないまま甲債権が時効消滅した場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
(×) 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、相殺をすることができる(民法508条)。相殺適状にある債権を有する者は、ほとんどその債務関係が決済されたものと考えるのが常であるから、この信頼を保護する趣旨である(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)149ページ)。よって、Aは相殺することができる。
⑷ 甲債権が差押えを禁じたものであるときは、Bは、乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができない。
(○) そのとおり(民法510条、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)151ページ)。
⑸ Aの債権者であるCが甲債権を差し押えた。この場合、その差押え前に乙債権を取得していたBは、乙債権と甲債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば、相殺をもってCに対抗することができる。
(○) そのとおり。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる(民法511条1項後段)。自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)151、152ページ)。
刑法
第11問
間接正犯に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、麻薬施用者である医師Bの診察を受けた際、激しい胃痛や腹痛があるかのように装って麻薬の注射を求め、Bに治療のためAに麻薬を注射する必要があると誤診させて、麻薬をAに注射させた。この場合、Aに麻薬施用の罪の間接正犯が成立する。
(○) Bは麻薬施用者である医師であり、麻薬施用の罪は成立しない。このように、被利用者の行為が適法である場合にも、間接正犯が成立する。判例は、同様の事案で麻薬施用の罪の間接正犯を認めたものと解されている(最決昭44.11.11刑集23・11・1471、研修教材・七訂刑法総論257、258ページ)。
⑵ 公務員Aは、公文書の作成権限を有する公務員Bを補佐して公文書の起案をする立場にあった。Aは、行使の目的で、Bに虚偽の事実を報告して内容虚偽の公文書を起案して提出し、情を知らないBに記名、捺印させて、当該公文書を完成させた。この場合、Aに虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
(○) 非公務員が公務員に内容虚偽の報告をして、内容虚偽の公文書を作成させた場合、虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない(最判昭27.12.25刑集6・12・1387)。これは、公正証書原本等不実記載罪が虚偽公文書作成罪の間接正犯を特別に規定しているので、それ以外の虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しないと解されているからである。しかし、設問は、起案を担当していた公務員が作成権限を有する公務員を利用した場合であり、同様の事案で、判例は、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するとしている(最判昭32.10.4刑集11・10・2464、研修教材・七訂刑法総論259ページ、研修889号80、81ページ)。
⑶ 医師Aは、患者B を殺害しようと考え、毒薬を治療薬と偽って情を知らない看護師Cに命じてBに飲用させてBを殺害した。この場合、Aに殺人罪の間接正犯が成立する。
(○) Cに殺人罪の故意はなく、殺人罪は成立しない。このように、被利用者に故意がない場合(故意のない道具の利用)にも、間接正犯が成立する(研修教材・七訂刑法総論253、256ページ)。
⑷ 行使の目的があるAは、印刷工Bに、演劇の小道具に使う旨のうそを言い、その旨誤信させて偽の一万円札を造らせた。この場合、Aに通貨偽造罪の間接正犯が成立する。
(○) Bに故意はあるが、行使の目的がなく、Bに通貨偽造罪は成立しない。このように、被利用者が目的なき故意ある者の場合にも、間接正犯が成立する(研修教材・七訂刑法総論256、257ページ、研修853号60ページ)。
⑸ Aは、12歳のBに命じて窃盗を行わせた。この場合、Bに是非善悪の判断能力があるときは、Aに窃盗罪の間接正犯が成立することはない。
(×) 是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用して犯罪を実現した場合であっても、利用者が被利用者の意思を抑圧して犯罪を実行させたような場合、間接正犯が成立するというのが判例の立場である(最決昭58.9.21刑集37・7・1070、研修教材・七訂刑法総論254、255ページ)。是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用した場合、未成年者の意思を抑圧するに足りる程度であれば間接正犯、その程度に至らなければ共同正犯又は教唆犯の成立が認められると思われる(研修853号60ページ)。
第12問
被害者の承諾に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、B の承諾を得て、BがAの自動車を盗んだ旨の虚偽の事実を警察官に申告し、処罰を求めた。この場合、Aに虚偽告訴罪は成立しない。
(×) 被害者の承諾により犯罪が成立しない根拠は、法益の主体たる被害者が、自己の法益を放棄した点に求められるので、放棄する法益は、被害者自ら処分し得る個人的法益に関するものであることが必要である(研修教材・七訂刑法総論148ページ)。虚偽告訴罪は、一般に国家的法益、国家の審判・懲戒作用を侵害する犯罪として把握されており(研修教材・三訂刑法各論(その2)230ページ)、Bが承諾したとしても、犯罪は成立する(研修883号100、101ページ)。
⑵ Aは、別荘の所有者であるBの承諾を得て、人が居住しておらず、現に人がいない同別荘に放火して焼損させ、公共の危険を生じさせた。この場合、Aに刑法109条1項の非現住建造物等放火罪が成立する。
(×) 本間の被害者の承諾は、承諾によって客体の法的性質に変更を生じ、別個の構成要件に該当するに至る場合であり、非現住建造物等が他人所有に係る場合であっても、所有者が焼損することに承諾したことにより、自己所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)に準じて処断されることになる(研修教材・七訂刑法総論147ページ、研修教材・三訂刑法各論(その2)20ページ)。
⑶ Aは、12歳のBの承諾を得て、Bと性交した。この場合、Aに強制性交等罪が成立する。
(○) 13歳未満の者に対する強制性交等罪(刑法177条)については、被害者の承諾が刑法上何ら意味を持たない場合であり、被害者の承諾があっても強制性交等罪が成立する(研修教材・七訂刑法総論146ページ)。
⑷ Aは、過失による自動車事故を装って保険金を詐取することを企て、自動車事故を装って傷害を負わせることについてBの承諾を得て、故意に自動車をBに衝突させて傷害を負わせた。この場合、Aに傷害罪は成立しない。
(×) 判例は、被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害を負わせた事案で、「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもつて、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。」(最決昭55.11.13刑集34・6・396)として傷害罪の成立を認めている(研修教材・七訂刑法総論149ページ、研修883号100~102ページ)。
⑸ Aは、Bの外出中、Bが一人で居住する家屋の部屋で火災が発生したことから、消火活動をするため、Bに無断で鍵を壊し、同家屋に侵入した。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。
(○) 現に被害者自身による承諾はないが、もし被害者がその事情を認識していたならば当然にそれについて承諾を与えていたであろうと客観的かつ合理的に判断される場合に行われる行為を推定承諾に基づく行為といい、被害者が事後に不承諾の意思を表示しても、推定された承諾は依然として有効であるとされている。本問では、留守中に火災が発生し、その消火活動のために住居に侵入しており、Bが当時これを知っていたなら当然立ち入りを承諾したであろうと客観的かつ合理的に判断されるので、住居侵入罪は成立しない(研修教材・七訂刑法総論150ページ、研修883号102ページ)。
第13問
建造物に対する罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 当該駅を管理する駅長が、構造上駅舎の一部である駅構内への出入りを制限し、又は禁止する権限を行使している場合、そこが同駅の営業時間中は乗降客のための通路として使用され、事実上人の出入りが自由な場所であっても、建造物侵入罪の「人の看守する建造物」 に該当する。
(○) 建造物侵入罪にいう「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入できる構造のものをいう(仙高判昭27.4.26判特22・126、研修教材・三訂刑法各論(その1)105ページ)。駅の構内は、乗降客のための通路部分であっても、建造物である(条解刑法〔第4版〕408ページ)。また、判例は、設問と同種の駅構内につき、同駅長がその管理権の作用として同駅構内への立入りを制限し、又は禁止している場合、同所は「人の看守する建造物」に当たるとして、同所への無断立入りは建造物侵入罪が成立するとしている(最判昭59.12.18刑集38・12・3026、研修教材・三訂刑法各論(その1)106ページ、条解刑法〔第4版〕409ページ)。
⑵ 警察署長の意思に反して、警察署の建物とその敷地を他から明確に画するとともに外部からの干渉を排除する作用を果たしているコンクリート塀の上部に上っても、建造物侵入罪は成立しない。
(×) 建造物侵入罪(刑法130条)が成立する。判例は、設問と同種の事案で、当該コンクリート塀を建造物の一部としている(最決平21.7.13刑集63・6・590、研修教材・三訂刑法各論(その1)105、106ページ)。
⑶ 建物を取り巻く竹垣を損壊しても、建造物損壊罪は成立しない。
(○) そのとおり。建造物損壊罪(刑法260条)にいう「建造物」とは、屋蓋を有し、障壁又は柱材で支持されて土地に定着し、その内部に人が出入できる構造を持つ家屋その他これに類する工作物をいう(大判大3.6.20録20・1300、研修教材・三訂刑法各論(その1)282ページ)。竹垣は、本条の建造物には当たらない(大判明43.6.28録16・1309、研修教材・三訂刑法各論(その1)282ページ)。
⑷ 住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていても、適切な工具を利用すれば損壊せずに取り外しが可能である限り、これを損壊しても、建造物損壊罪は成立しない。
(×) 近時の判例は、刑法260条の建造物性につき、当該物と建造物の接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮し決すべきであるとし、同種の事例で、玄関ドアの建造物性を認めた(最決平19.3.20刑集61・2・66、研修教材・三訂刑法各論(その1)283ページ)。
⑸ 現に人の居住するマンションにおいて、その内部に設置された、居住者が各階間の昇降に常時利用している共用部分であるエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁を焼損させた場合でも、現住建造物等放火罪は成立する。
(○) 放火罪の客体としての「建造物」の定義は、建造物損壊罪のそれと同義と解されている(前田雅英「刑法各論講義〔第7版〕」333、334ページ、なお、研修教材・三訂刑法各論(その2)12ページ)。判例は、同種の事例で、建造物との一体性を認め、現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するとしている(最決平元.7.7判時1326・157、研修教材・三訂刑法各論(その2)11ページ)。
第14問
背任罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 背任罪のいう「財産上の損害」には、本人が本来取得できたはずの利益が取得できなかったことは含まれない。
(×) 背任罪のいう財産上の損害は、消極的損害も含む(最決58.5.24刑集37・4・437研修教材・三訂刑法各論(その1)257ページ)。
⑵ 背任罪の「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目的」 には、自己の信用・面目を保持する目的も含む。
(○) 背任罪の図利加害目的について、判例は設問のとおり解している(最決昭63.11.21刑集42・9・1251、研修教材・三訂刑法各論(その1)260、261ページ)。
⑶ 森林組合の組合長が、組合の所有ではあるが、委託の趣旨からいかなる用途にも絶対に流用支出することのできない金を業務上保管中、専ら第三者の利益を図り、これを同組合名義で貸し付けた場合、背任罪が成立する。
(×) 判例は、その使途が厳格に制限されていかなる使途にも流用支出することができない金を流用した場合、背任罪ではなく、業務上横領罪に当たるとする(最判昭34.2.13刑集13.2.101、研修教材・三訂刑法各論(その1)266ページ)。それが委託の趣旨から絶対許されず、本人の所有権に対する侵害行為と認められる場合には、その処分行為は権限に基づかない処分と認められ、自己の計算においてした行為としたものと解される(研修教材・三訂刑法各論(その1)265ページ)。
⑷ 自ら所管する事務について任務に背いた行為をした場合には、それが決裁権を有する上司の決定・指示によるものであり、自らはそれについて反対又は消極的意見を具申したとしても、背任罪のいう「任務違背行為」がなかったとはいえない。
(○) そのとおり。判例は、同種の事案において、「任務違背行為」を認めた(最決昭60.4.3刑集39・3・131、研修教材・三訂刑法各論(その1)255ページ)。
⑸ 会社の取締役が、株主の配当利益を図る目的で、配当すべき利潤がないのに、これがあったように仮装して、株主に配当した場合、背任罪は成立しない。
(×) 判例は、このような場合にも任務違背行為に当たるとする(大判昭7.9.12刑集11・1317、研修教材・三訂刑法各論(その1)256ページ)。
第15問
国家の作用に対する罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 緊急逮捕されたAが、逮捕状が発せられる前に看守者に暴行を加えて逃走した場合、Aには、加重逃走罪が成立する。
(×) 加重逃走罪(刑法98条)の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」(97条)又は「勾引状の執行を受けた者」であり、緊急逮捕されて逮捕状が発せられる前の者は含まれない(研修教材・三訂刑法各論(その2)208ページ)。
⑵ Aは、Bが道路交通法違反、過失運転致死の各罪を犯した者と知りながら、Bとの間で、前記犯行に使用した車両が前記犯行の前に盗まれていたことにする旨口裏合わせをして、Bが逮捕された後、警察官に対し、参考人として前記口裏合わせどおりの供述をした。この場合、Aには、犯人隠避罪は成立しない。
(×) この場合でも、国家の刑事司法作用を害するから、犯人隠避罪(刑法103条)が成立する(最決平29.3.27刑集71・3・183、研修教材・三訂刑法各論(その2)215ページ)。
⑶ 県議会特別委員会において、審議内容に不満を持つAが同委員会委員長に対して暴行を加えた場合、既に同委員会委員長が休憩を宣言するとともに、審議の打切りを告げて席を離れて出入口に向かおうとしていても、委員会の秩序を保持し、紛議に対処するための職務を現に執行していたと認められるときには、Aには、公務執行妨害罪が成立する。
(○) 判例は、同種の事案において、県議会特別委員会委員長は、休憩宣言後も、委員会の秩序を保持し、紛議に対処するための職務を現に執行していたとして、公務執行妨害罪の成立を認めた(最決平元.3.10刑集43・3・188、研修教材・三訂刑法各論(その2)174、175ページ)。
⑷ 公立中学校の教諭Aが、担任する生徒の父兄らから商品券を受領しても、それが同教諭の職務行為を離れた、私的な学習上の指導に対する感謝の趣旨と、同教諭に対する敬慕の念に発する儀礼の趣旨に出たものと認められる場合は、Aには、収賄罪は成立しない。
(○) そのとおり。判例は、同種の事例で、教諭が、父兄らから贈答用小切手を受領した行為につき、収賄罪は成立しないとした(最判昭50.4.24判時774・119、研修教材・三訂刑法各論(その2)244ページ、前田雅英「刑法各論講義〔第7版〕」507ページ)。
⑸ 執行官が強制執行を行うに当たって、Aが執行官に暴行を加えて、その執行行為を妨害した場合、Aには公務執行妨害罪は成立せず、強制執行行為妨害罪が成立する。
(○) そのとおり。強制執行行為妨害罪(刑法96条の3第1項)のみが成立する。公務執行妨害罪の成立も考えられるが、両罪の保護法益は重なり合う上、強制執行行為妨害罪の「威力」は、暴行を含む概念であることから、公務執行妨害罪は、法定刑の重い(3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科)強制執行行為妨害罪に吸収される(研修教材・三訂刑法各論(その2)193、194ページ)。
刑事訴訟法
第16問
捜索差押え等に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 捜索をする場合は、捜索差押許可状の執行に着手する前に、処分を受ける者にこれを示さなければならず、どのような事情があっても、捜索差押許可状の執行に着手した後の呈示は許されない。
(×) 令状は、原則、あらかじめ処分を受ける者に示さなければならない(刑訴法222条1項、110条)。しかし、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚醒剤事犯の前科もある被疑者において、直ちに覚醒剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあった事案において、最高裁は、「以上のような事実関係の下においては、捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑訴法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。また、同法222条1項、110条による捜索差押許可状の呈示は、手続の公正を担保するとともに、処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって適法というべき」と判示し、執行着手後の令状呈示が許される場合があり得るとしている(最決平14.10.4刑集56・8・507、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)182、188、189ページ)。
⑵ 私人が被疑者を現行犯逮捕した場合、当該私人は、当該逮捕の現場において、令状によらない捜索差押えをすることができる。
(×) 刑事訴訟法220条1項により、被疑者を現行犯逮捕した場合に、当該逮捕の現場において、令状によらない捜索差押えをすることができるのは、検察官、検察事務官又は司法警察職員であり、私人はこれをすることはできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)130ページ)。
⑶ 被疑者方居室に対する捜索差押許可状により、同居室内を捜索中、宅配便の配達員によって被疑者宛てに配達され、同居室内で同人が受領した荷物については、同許可状に基づく捜索はできない。
(×) 設問記載と同様の事案において、最高裁は、「警察官が、被告人に対する覚せい剤取締法違反事件につき、捜索場所を被告人方居室等、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき、被告人立会いの下に上記居室を捜索中、宅配便の配達員によって被告人あてに配達され、被告人が受領した荷物について、警察官において、これを開封したところ、中から覚せい剤が発見されたため、被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し、逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。……警察官は、このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である」と判示している(最決平19.2.8刑集61・1・1、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)191ページ)。
⑷ 強制採尿のための捜索差押許可状の発付を受けて、被疑者を採尿場所まで同行しようとしたが、被疑者が任意に採尿場所まで赴かない場合、捜索差押許可状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。
(○) そのとおり。最高裁は、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当」と判示している(最決平6.9.16刑集48・6・420、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)194、195ページ。
⑸ 宅配便を利用した覚醒剤譲渡事犯の捜査において、宅配業者が運送中の荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、その内容物を調べる必要がある場合、 外部からエックス線を照射してその射影を観察する程度の検査は、荷送人と荷受人双方の承諾を得ずに、任意捜査として実施することが可能である。
(×) 設問と同様の事案において、最高裁は、「本件エックス線検査は、荷送人の依頼に基づき宅配業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」と判示している(最決平21.9.28刑集63・7・868、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)201、202ページ)。
第17問
被疑者・被告人の接見交通及び弁護人選任に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 身体の拘束を受けている被疑者は、弁護人及び弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができ、いかなる場合であっても、これらの者との接見を禁止することはできない。
(○) そのとおり。刑事訴訟法39条1項は、身柄の拘束を受けている被疑者及び被告人は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる旨規定しており、弁護人及び弁護人となろうとする者との接見を禁止することはできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)156ページ)。
⑵ 検察官は、被告人について、弁護人及び弁護人になろうとする者以外の者との接見を禁止する請求をすることができない。
(×) 刑事訴訟法81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ」と規定し、被告人についても、検察官において接見禁止請求できることを定めている。
⑶ 被疑者の妻は、被疑者の意思に反して、弁護人を選任することができる。
(○) そのとおり。刑事訴訟法30条2項は、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と定めている(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)28、29ページ)。
⑷ 被疑者の弁護人の数は、特別の事情があると認めて裁判所が許可した場合を除いては、3人を超えることができない。
(○) そのとおり。刑事訴訟法35条が委任する刑事訴訟規則27条1項は、「被疑者の弁護人の数は、各被疑者について3人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。」と規定している(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)30、31ページ)。
⑸ 簡易裁判所における被告事件については、裁判所の許可があれば、弁護士でない者のみを被告人の弁護人に選任することができる。
(○) そのとおり。刑事訴訟法31条2項は、「簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。」と規定しているので、簡易裁判所の場合は、裁判所の許可さえあれば、弁護士でない者のみを弁護人(特別弁護人)に選任することが可能である。
なお、被疑者については、特別弁護人を選任することはできない(最決平5.10.19刑集47・8・67、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)31ページ)。
第18問
訴因に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 訴因の明示は、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定してこれをしなければならず、覚醒剤使用事件において、使用方法を「自己の身体に注射又は服用し」との記載をすることは許されない。
(×) 証拠上、具体的な日時・場所・方法を特定できない場合には、多少幅をもって抽象的に記載することも許される。覚醒剤使用罪について、使用日時を「○月○日頃から〇月〇日頃までの間」、使用場所を「○県○郡○町内及びその周辺」、使用量を「若干量」、使用方法を「自己の身体に注射又は服用して使用した」と記載したものでも、「検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上」、訴因の特定に欠けるところはない(最決昭56.4.25刑集35・3・116、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)171ページ)。
⑵ 被告人につき、Aの腕時計1個を窃取したという窃盗の訴因で起訴がされていたところ、審理の結果、窃盗を実行したのは被告人ではなくBであり、被告人に対しては、本件被害に近接した日時・場所において、Bから前記腕時計1個を盗品と認識しながら購入したという盗品等有償譲受けの訴因が認定可能となった場合、 窃盗から盗品等有償譲受けに訴因を変更することはできる。
(○) 公訴事実の同一性については、基本的な事実関係を同じくするかどうかで判断され、日時・場所・被害者・被害物件等の近接性・同一性の有無・程度などが判断の基準となり得る。また、判例は、「択一関係」という基準も示し、各訴因が両立しない関係にある場合には公訴事実の同一性があるとしている。窃盗罪と盗品等罪との間には公訴事実の同一性を認めた判例が複数ある(最決昭27.10.30刑集6・9・1122、最判昭29.9.7刑集8・9・1447、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)181~183ページ)。
⑶ 殺人未遂の訴因で起訴された事件について、審理の結果、裁判所が、殺意以外の事実は認定できるものの、殺意の認定には難があり、傷害の限度で事実を認定できるとの心証を得た場合、裁判所が傷害の事実を認定するには、訴因変更の手続が必要である。
(×) 事実の差異が犯罪の構成要件に変化をもたらす場合であっても、裁判所の認定する事実が訴因の中に含まれている場合、すなわち、訴因を縮小的に認定する場合には、被告人の防御に不利益を生じないから、訴因の変更を要しない(最決昭28.11.20刑集7・11・2275、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)185ページ、研修860号63~66ページ)。
⑷ 訴因変更は検察官の権限であり、検察官の訴因変更の請求があれば、裁判所の許可がなくとも、直ちに効力を生じる。
(×) 訴因の追加、撤回及び変更は、検察官の権限であるが、検察官の訴因変更等の請求に対しては、裁判所の許可・不許可がなされる。訴因変更等の請求は、裁判所の許可があって、初めてその効力を生じる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)188、189ページ)。
⑸ 控訴審では、訴因変更を行うことはできない。
(×) 訴因変更等の時期については制限がないのが一般的な原則である。判例・通説は、控訴審での訴因変更を肯定している(最判昭30.12.26刑集9・14・3011、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)191、192ページ、研修862号64~66ページ)。
第19問
被害者参加制度に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ いわゆる特殊詐欺事件により高額の現金を詐取された被害者は、被害者参加制度により、当該被告事件の手続に参加することができる。
(×) 被害者参加人として被告事件の手続への参加が許されるのは、刑事訴訟法316条の33第1項に規定された被告事件の被害者等又は当該被害者の法定代理人であり、詐欺事件の被害者は、被害金額の多寡にかかわらず、被害者参加人となることはできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)159ページ)。
⑵ 被害者参加人は、証人尋問において、犯罪事実に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項については尋問することができない。
(○) 被害者参加人等による証人尋問については、刑事訴訟法316条の36に規定されている。証人尋問が許される事項については、「情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項」とされている。例えば、示談や謝罪の状況など一般情状に関する尋問はできるが、犯行の態様・動機・結果など犯情に関する尋問はできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)160、161ページ、研修858号89、90ページ)。
⑶ 被害者参加人は、刑事訴訟法316条の37の規定により被告人に対して質問することを許される場合において、犯罪事実に関する事項についても質問することができる。
(○) 被害者参加人による被告人質問については、刑事訴訟法316条の37に規定されている。証人尋問についての、条文のように、質問事項を限定する規定はなく、犯罪事実に関する質問もできる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)161、162ページ、研修858号90ページ)。
⑷ 被害者参加人は、事実又は法律の適用について公判期日で意見を陳述する場合には、傷害致死罪で起訴された事件につき、「被告人には殺意が認められるので、殺人罪が成立する。」との意見を陳述することができる。
(×) 被害者参加人等は、裁判所から許可された場合、事実又は法律の適用について意見を陳述することができるが、その内容は、「訴因として特定された事実の範囲内」とされている(刑事訴訟法316条の38第1項)。よって、傷害致死の訴因で起訴された事件で、被告人には殺意が認められるので殺人罪が成立するとの意見を陳述することは「訴因として特定された事実の範囲」を超えることになり、許されない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)162、163ページ、研修858号91ページ)。
⑸ 公判期日に出席した被害者参加人は、旅費、 日当及び宿泊料の支給を受けることができる。
(○) 従前、被害者参加人が公判期日等に出席する際の旅費等については、自己負担とされていたが、被害者等の経済的負担を軽減し、より公判期日等に出席して訴訟活動ができるようにするため、被害者参加人等に対する旅費等の支給制度が整備され、旅費、日当及び宿泊料が支給可能となった(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律5条第1項)(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)163、164ページ)。
第20問
証拠に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 公判においては、経験則上明らかな法則であっても、証明が必要である。
(×) 特別の知識・経験により初めて認識し得るものについては、鑑定などによる証明が必要だが、経験則上明らかな法則については、証明を要するものではない(最決昭33.4.18刑集12・6・1101、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ15ページ)。
⑵ 証拠能力のない証拠であっても、証明力の高い証拠であれば、公判で公訴事実を証明するための証拠とすることができる場合がある。
(×) 公訴事実は厳格な証明を要する。「証拠能力」とは、厳格な証明の対象となる事実の認定資料として、その証拠を用いることができる証拠の形式的な資格であり、「証明力」とは、その証拠が裁判官に心証を形成させることのできる証拠の実質的な価値である。証拠能力のない証拠は、いかに証明力が高くても、厳格な証明の資料とすることはできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ20、52ページ、研修864号68ページ)。
⑶ 検察官請求に係る供述調書は、証拠とすることに被告人が同意すれば、弁護人の同意がなくても、刑事訴訟法326条1項の定めるところにより証拠とすることができる。
(○) 刑事訴訟法326条1項の同意ができるのは、「検察官及び被告人」であり、弁護人の同意は被告人の代理人たる地位で代理権の行使としてなされるものであるから、被告人の意思に反することはできない。被告人が同意すれば、弁護人の同意がなくても同意の効力が生じる(福岡高判昭24.10.10特報1・249、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ193ページ)。
⑷ AとBが共謀して窃盗をしたという事案で、AとBの公判が分離されている場合、BがBの公判において被告人質問で供述した内容が録取されたBの被告人質問調書は、Aの公判において、刑事訴訟法321条1項1号により証拠とすることができる「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
(○) 刑事訴訟法321条1項1号の被告人以外の者の裁判官の面前における供述を録取した書面には、その者が他事件の公判において被告人としてした供述を録取した書面も含まれる(最決昭57.12.17刑集36・12・1022、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ152ページ、研修第872号56ページ)。
⑸ 刑事訴訟法321条1項2号の特信情況と同項3号の特信情況は、同じ意味である。
(×) 設問は、刑事訴訟法321条1項2号と同項3号の特信情況(特信性)に関するものである。同項2号の特信情況は、先になされた検面供述と後でなされた法廷供述を比較して、前者の方がより信用できる情況の下でされたといういわば相対的な特信性を意味し、同項3号の特信情況は、比較すべき法廷供述は存在しない場合なので、いわば絶対的な特信性が求められる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ156、157、162ページ)。したがって、両者の意味は異なる。
執行事務
第21問
裁判の把握に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 執行担当事務官は、死刑や自由刑に限らず罰金又は科料の裁判のほか、無罪、免訴又は公訴棄却の裁判の結果について、検察総合情報管理システム (以下「検察システム」という。)により管理する。
(○) そのとおり(十訂特別研修資料2号・執行事務解説60、61ページ、研修888号41ページ)。
⑵ 執行担当事務官は、公判担当事務官から判決の宣告又は決定による終局裁判の結果について通知を受けて検察システムにより当該終局裁判の結果の内容を管理する場合、裁判所に照会して、当該終局裁判の結果の内容について確認することとされているが、その照会・確認方法は、各庁の実情に応じて、電話、口頭その他適宜の方法で行うことで差し支えない。
(○) そのとおり(執行事務規程3条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説59、60ページ、研修888号42ページ)。
⑶ 執行担当事務官は、検察システムに入力された裁判結果の内容を裁判所に照会した結果、内容を修正する必要が生じた場合は、当該事項を自ら修正しなければならない。
(×) 修正する必要が生じた場合は、当該事項を入力した公判担当事務官に対して修正の依頼をする(平25.3.19法務省刑総406号刑事局長通達・記第3、2、十訂特別研修資料2号・執行事務解説60ページ、研修888号42ページ)。
⑷ 執行担当事務官は、裁判所から裁判書(裁判を記載した調書を含む。)の謄本等が送付されたときは、これと検察システムにより管理している裁判結果の内容とを対照し、その記載内容に相違がないかどうかを確認しなければならない。
(○) そのとおり(執行事務規程4条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説61ページ、研修888号46ページ)。
⑸ 第一審の実刑判決に対して高等裁判所に控訴の申立てがあり、その後控訴の取下げにより裁判が確定したときは、当該高等裁判所に対応する高等検察庁の検察官が常に下級の裁判所の裁判の執行を指揮することとなるので、当該高等検察庁の執行担当事務官は、控訴の取下げがあった旨及び第一審の裁判の主文の要旨を検察システムにより管理しなければならない。
(×) 訴訟記録が上訴裁判所に送付された後、被告人が上訴を取り下げたことにより下級の裁判所の裁判が確定した場合、上訴裁判所に対応する検察庁の執行担当事務官は、上訴の取下げがあった旨及び下級の裁判所の裁判の主文の要旨を検察システムにより管理することとなるが、訴訟記録が上訴裁判所に送付される前に上訴が取り下げられて下級の裁判所の裁判が確定した場合は、下級の裁判所に対応する検察庁の執行担当事務官がこれらを管理する(刑事訴訟法472条2項、十訂特別研修資料2号・執行事務解説62、63ページ、研修888号46、47ページ)。
第22問
裁判の確定に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 判決に対する上訴の提起期間は14日と定められているので、この期間内に、検察官及び被告人側のどちらからも上訴の放棄や上訴の申立てがない場合は、判決は、上訴の提起期間の最終日の翌日に確定する。
(○) そのとおり。いわゆる自然確定である(刑事訴訟法373条、414条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説3ページ、研修890号54~56ページ)。
⑵ 刑事施設に収容されている被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を当該刑事施設の長に差し出したときは、その上訴申立書が上訴の提起期間内に原裁判所に到達しなくても、上訴の提起期間内に上訴したものとみなされる。
(○) そのとおり(刑事訴訟法366条1項、刑訴規則228条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説2、3ページ、研修890号54ページ)。
⑶ 上訴権は、上訴提起期間の経過又は上訴の放棄若しくは取下げによって消滅するが、法定刑が死刑又は無期刑に当たる罪については上訴の放棄はできない。
(×) 放棄することができないのは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴であり、法定刑に対するものではない(刑事訴訟法360条の2、十訂特別研修資料2号・執行事務解説4ページ、研修890号57ページ)。
⑷ 刑事訴訟法361条の規定により、上訴の取下げをした者はその事件について更に上訴することができないとされているので、上訴の提起期間の経過後に被告人が上訴を取り下げた場合には、検察官の上訴がなされていない限り、その裁判は被告人の上訴の取下げのあった日の翌日に確定する。
(×) 被告人の上訴の取下げが上訴の提起期間経過後であれば、検察官の上訴がなされていない限り、その取下げの日が裁判確定の日となる(十訂特別研修資料2号・執行事務解説5ページ、研修890号57、58ページ)。
⑸ 上告審である最高裁判所がした裁判は最終審であり、これ以上の上訴はないので、上告審の判決は、その宣告があった日に確定する。
(×) 上告審の判決については、判決訂正の申立てができるので、判決訂正の申立てがない場合にはその申立期間である10日を経過したときに、判決訂正の申立期間内に判決訂正の申立てがなされた場合において、その申立てが棄却されたときは棄却決定が告知された日に、実際に訂正の判決があったときは訂正判決の日にそれぞれ確定する(刑事訴訟法415、418条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説5、6ページ、研修890号58、59ページ)。
第23問
裁判の執行に関する次の記述のうち、 正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 自由刑の執行指揮をする場合には、執行指揮書によらなくても、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
(×) 自由刑の執行指揮は、必ず書面(執行指揮書)で行い、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない(刑事訴訟法473条、執行事務規程19条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説78~81ページ、研修892号53ページ)。
⑵ A事件では勾留されておらず、別のB事件で勾留中の被告人に対して、A事件について懲役刑(実刑)の言渡しがあり、その裁判が確定した。後日、B事件で勾留中の被告人について、A事件の裁判の執行指揮をした。この場合、刑法23条1項の規定によりB事件の裁判が確定した日が刑の起算日となる。
(×) 被告人が拘禁されている場合の刑期は裁判確定の日から起算する(刑法23条1項)が、拘禁中であるか否かは、執行されるべき刑に関連して決められる。本間のように、別事件で勾留中の者について勾留されていない当該事件で自由刑(実刑)の判決が確定したときの刑の起算日は、執行指揮の日となる(十訂特別研修資料2号・執行事務解説41、42ページ、研修892号57ページ)。
⑶ 勾留中の被告人について、上訴申立期間と勾留期間が同時に満了する場合やその他やむを得ない事由がある場合には、判決確定に先立ち、判決確定の上執行すべき旨を明らかにして刑の執行を指揮することになる。この場合には、上訴申立ての有無について特に注意し、その申立てがあったときは、直ちに執行指揮を取り消さなければならない。
(○) そのとおり。いわゆる条件付執行指揮である(執行事務規程17条2項、十訂特別研修資料2号・執行事務解説77ページ、研修892号58、59ページ)。
⑷ 詐欺の罪により懲役10年の刑に処せられて服役中の者に対し、この罪と併合罪の関係にある窃盗の罪により懲役7年の刑が確定した。この事例の場合、執行指揮書に現在執行中の刑に引き続いて執行されたい旨を付記して記載する執行すべき刑期は、懲役7年となる。
(×) 両刑に係る罪が併合罪の関係にある場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを超えることはできないとされている(刑法51条2項)。本間の場合、併合罪の関係にある詐欺罪と窃盗罪は、いずれも法定刑の長期が10年であることから、その2分の1である5年を加えた懲役15年を超えて執行することができないことになる。したがって、執行すべき刑期は、懲役7年のうち5年となる(十訂特別研修資料2号・執行事務解説17ページ、研修892号64ページ)。
⑸ 有期刑の執行中に無期刑の執行を指揮する場合において、刑法51条1項ただし書の適用があるときは、無期刑を指揮するとともに、有期刑については、刑執行取止指揮書によりその執行を取りやめる旨を指揮するとされているが、その後取りやめの原因となった無期刑が恩赦により有期刑に減刑されたときは、取りやめられた有期刑を再び執行することができる。
(×) 「執行を取りやめる」ということは執行の中止ではないから、将来、取りやめの原因となった無期刑が恩赦により有期刑に減刑されても、取りやめられた有期刑が再び執行されることはない(執行事務規程16条2号ただし書、十訂特別研修資料2号・執行事務解説75ページ、研修892号62ページ)。
第24問
未決勾留日数の本刑通算(算入)に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 未決勾留日数の本刑通算の制度には、 裁定算入と法定通算の二つがあるが、 裁判において本刑に算入する未決勾留日数を言い渡すのは、裁定算入日数である。
(○) そのとおり。未決勾留日数の算入又は通算には、裁定算入(刑法21条)と法定通算(刑事訴訟法495条)の二つがあり、裁判において本刑に算入する未決勾留日数を言い渡すのは裁定算入日数である。法定通算は当然本刑に通算されるので、裁判所の裁量によるものではない(十訂特別研修資料2号・執行事務解説24ページ、研修893号51、52ページ)。
⑵ 裁定算入又は法定通算の対象となる未決勾留日数には、逮捕されていた日数、鑑定留置中の日数及び少年鑑別所に収容中の日数も含まれる。
(×) 刑事訴訟法167条に規定する鑑定留置の日数及び少年法17条1項2号の規定による観護措置として少年鑑別所に収容された日数は未決勾留とみなされるが、逮捕中の日数、逃走中の日数、保釈釈放中の日数、勾留執行停止による釈放中の日数は含まれない(刑事訴訟法167条6項、少年法53条、十訂特別研修資料2号・執行事務解説25ページ、研修893号52、53ページ)。
⑶ 未決勾留日数の通算(算入)を受ける本刑は宣告刑をいい、刑のうち、死刑、無期刑及び没収は除かれる。
(×) 通算(算入)を受ける本刑は宣告刑をいい、刑のうち、死刑及び没収は除かれるが、無期の自由刑は、後に恩赦によって有期刑に変更された場合に通算(算入)することができる(十訂特別研修資料2号・執行事務解説26、27ページ、研修893号54ページ)。
⑷ 懲役刑(実刑)の判決宣告の日に当該事件で勾留されている場合において、判決宣告の日は、その日に被告人が上訴の申立てをしなければ法定通算の対象となり、その日に被告人が上訴の申立てをすれば上訴審において原判決が破棄されない限り裁定算入の対象となる。
(○) そのとおり。上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行する(刑事訴訟法358条)から、実刑判決の宣告の日に被告人が勾留されている場合は、判決宣告の日は、上訴の提起期間中の未決勾留の存する日に当たり、その日に被告人が上訴の申立てをしなければ法定通算の対象となる(刑事訴訟法495条1項)。判決宣告の日に被告人が上訴の申立てをした場合には、上訴審において破棄されない限り、その日は上訴審における裁定算入の対象となる。ただし、上訴審において原判決が破棄されたときは、法定通算の対象となる(刑事訴訟法495条2項2号、十訂特別研修資料2号・執行事務解説30、33ページ、研修893号53ページ)。
⑸ 勾留中の被告人について、令和5年2月9日(木)に第一審裁判所において実刑判決の言渡しがあり、被告人は同月16日(木)に控訴の申立てをしたが、同月17日(金)に控訴の取下げをした。検察官は上訴の放棄も控訴の申立てもせず、同判決は確定した。なお、同月23日(木)は、国民の祝日に関する法律に規定する休日である。この場合における本刑に通算すべき法定未決勾留日数は、14日である。
(×) 判決言渡しの日(2月9日)から控訴申立ての日の前日(2月15日)までの7日と、控訴取下げの日(2月17日)から上訴の提起期間の満了日(2月24日)までの8日を合わせた15日が通算すべき法定未決勾留日数である。なお、本間における上訴の提起期間の満了日は、2月23日が天皇誕生日であるため、刑事訴訟法55条3項本文により2月24日となる(十訂特別研修資料2号・執行事務解説33、34ページ、研修893号58、59ページ)。
第25問
刑の執行猶予の取消し等に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 刑の執行猶予の言渡しが取り消され、その刑の執行指揮をする場合、執行指揮書の「確定の日」欄には、当該刑の執行猶予を言い渡した裁判の確定日を記載する。
(○) そのとおり。刑執行猶予言渡し取消決定は、当初被告事件の裁判において言い渡された刑を現実に執行する効果を生ぜしめるものであることから、執行指揮するのは、当初の被告事件について刑を言い渡した裁判である。したがって、執行指揮書の「確定の日」欄に記載する裁判の確定日は、原裁判(刑執行猶予の言渡しをした裁判)の確定日である(十訂特別研修資料2号・執行事務解説81、82ページ、研修892号54、55ページ、895号62、63ページ)。
⑵ 一部の執行を猶予された刑(以下「一部執行猶予刑」という。)のうち執行猶予されなかった部分(以下「実刑部分」という。)の期間の最終日の翌日以後に、刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消された場合に、一部執行猶予刑のうち執行猶予された部分の期間の執行指揮を行うときは、その執行指揮書の「執行すべき刑名刑期」欄に刑名及び猶予部分の期間を記載し、「(一部執行猶予刑の猶予部分)」 と付記する。
(○) そのとおり。本間の場合、執行指揮書の「刑名刑期」欄には、刑名及び一部執行猶予刑の猶予期間の記載はもちろん、「(一部執行猶予刑の猶予部分)」を付記することとされている(十訂特別研修資料2号・執行事務解説82、85ページ、研修892号65、66ページ、895号62、63ページ)。
⑶ 刑の一部の執行猶予を言い渡した判決が確定した後、その執行猶予期間の経過前に、更に犯した罪について禁錮以上の刑が確定したときには、実刑部分の期間の執行を終える前に罪を犯した場合であっても、執行猶予期間中に罪を犯した場合であっても、当該刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(○) そのとおり(平28.4.28法務省刑制43号刑事局長依命通達・記第2、6、⑴、十訂特別研修資料2号・執行事務解説123ページ、研修895号53、54ページ)。
⑷ 刑の執行猶予の言渡しの取消決定がなされ、同取消決定に対する即時抗告申立期間の満了日と執行猶予期間の満了日とが同日である場合は、執行猶予期間経過後に同取消決定が確定するため、執行猶予の言渡しが取り消された刑を執行することはできない。
(○) そのとおり(十訂特別研修資料2号・執行事務解説135、136ページ、研修895号57、58ページ)。
⑸ 保護観察付一部執行猶予者について、実刑部分の期間の最終日以前又は実刑部分の期間に引き続いて執行される他の懲役又は禁錮の執行中に執行猶予の言渡しが取り消された場合、刑執行猶予言渡し取消通知書によりその者の住居地を管轄する保護観察所の長に通知しなければならない。
(×) 刑の執行猶予の言渡しを取り消された者が刑法25条の2・1項、27条の3・1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律4条1項の規定により保護観察に付されていたものであるときは、執行担当事務官は、刑執行猶予言渡し取消通知書により、その者の住居地を管轄する保護観察所の長に通知することとなるが(執行事務規程46条2項)、同項にいう「保護観察に付されていたもの」とは、執行猶予の言渡しが取り消されたときに保護観察に付されていたものを指すため、刑の一部の執行猶予の言渡しを受け猶予の期間中保護観察に付することとされた者について、その猶予の期間が起算される前に執行猶予の言渡しが取り消された場合においては、通知は不要である(平28.5.2法務省刑総572号刑事局長依命通達・記第2、5、十訂特別研修資料2号・執行事務解説138ページ、研修895号64ページ)。