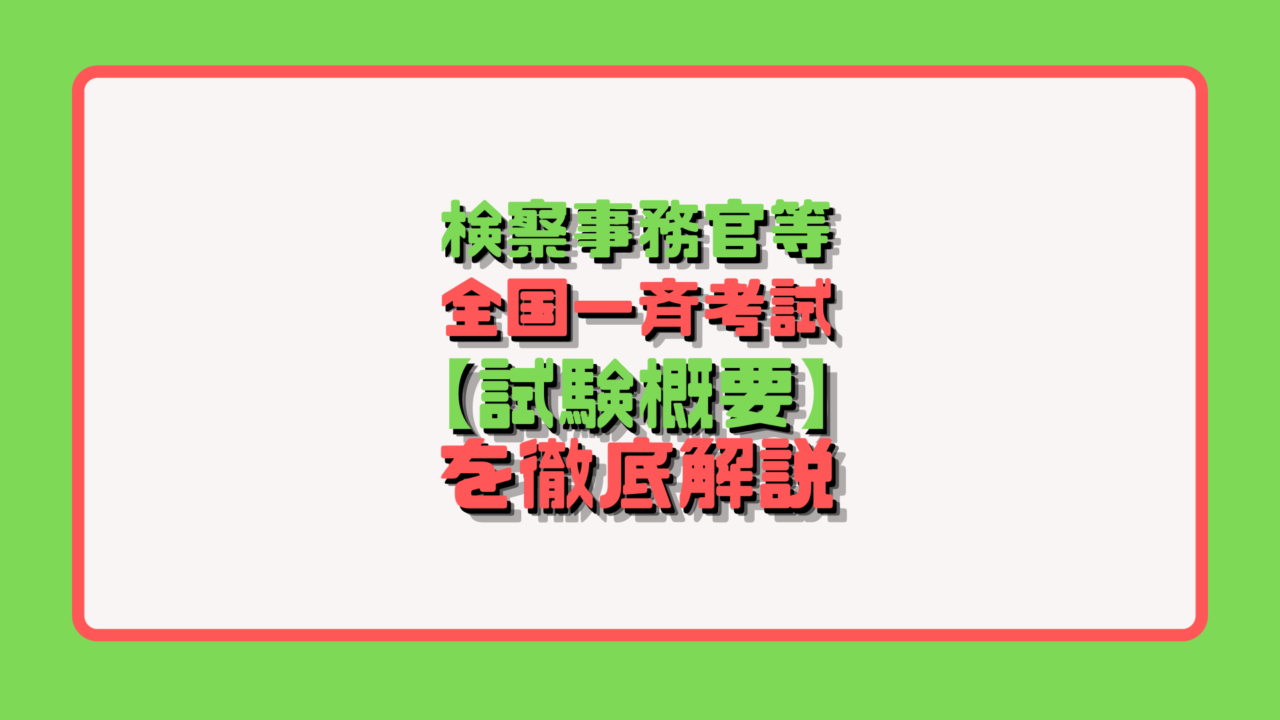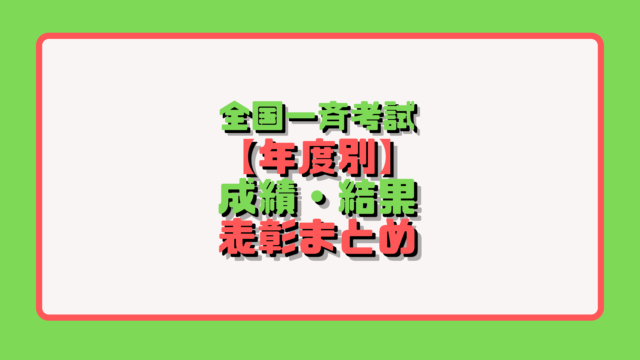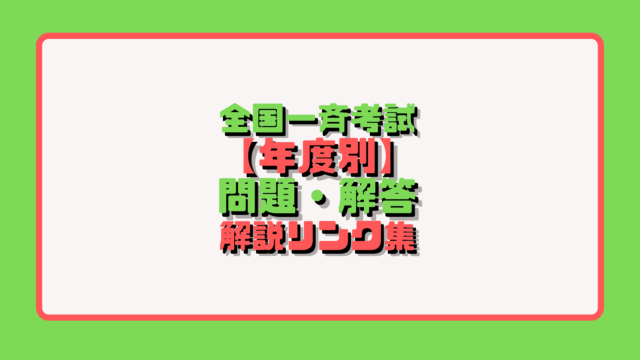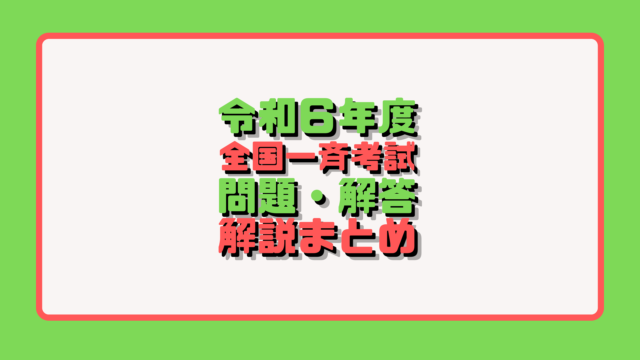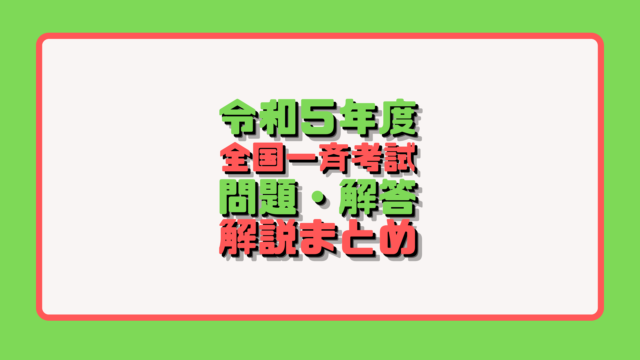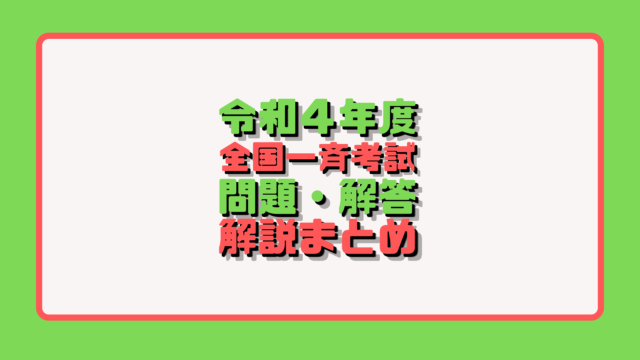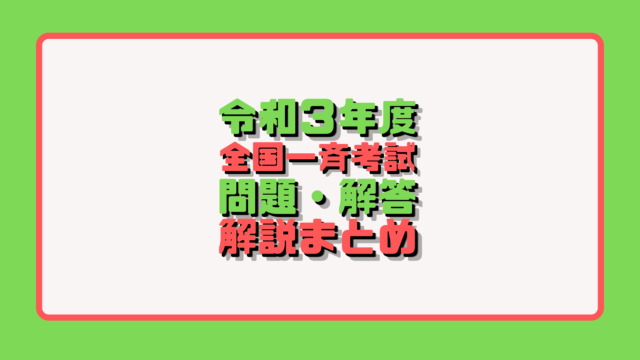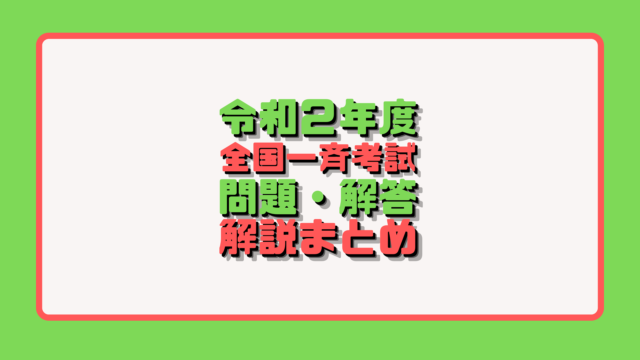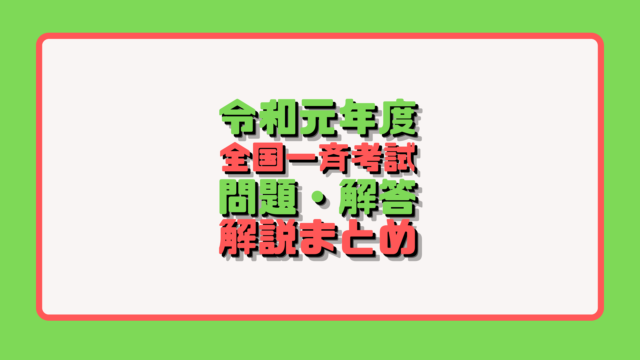こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、検察事務官等全国一斉考試の試験概要について詳しく紹介していきたいと思います。
全国一斉考試は若手検察事務官が毎年受験する内部試験になりますので、検察庁内定者の皆さんはもちろん、検察事務官志望の方も是非参考にしてもらえればと思います。
全国一斉考試の概要について
全国一斉考試の概要について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
受験対象者
全国一斉考試の受験対象者ですが、職務の級が3級未満の若手検察事務官となります。
- 大卒程度
1級→2級:3年
2級→3級:4年(計7年) - 高卒程度
1級→2級:8年
2級→3級:4年(計12年)
3級への昇格は、最短で大卒程度で8年目、高卒程度で13年目となります。
検察事務官の3級への昇格は、採用10年目以降が一般的。
そのため、全国一斉考試は20代~30代半ばまで毎年受験し続ける試験となります。
試験日
全国一斉考試の試験日ですが、例年2月下旬に実施されています。
令和6年度:令和7年2月25日(火)
令和5年度:令和6年2月20日(火)
令和4年度:令和5年2月22日(水)
試験時間は午後2時~5時までの3時間となりますが、早めに回答し終えれれば終了時間前に退出することも可能です。
ちなみに、全国一斉考試は通常業務より優先されますので、試験時間には仕事が入らないよう調整してもらえます。
試験科目
全国一斉考試の試験科目ですが、以下5科目となっていますので、それぞれ見ていきたいと思います。
なお、全国一斉考試は1問4点で1科目25問、5科目計125問が出題されますので、500点満点の○✕方式の試験となります。
憲法・検察庁法
憲法・検察庁法の問題数の配分は以下の通りとなります。
- 憲法 :20問(80点)
- 検察庁法: 5問(20点)
民法
民法の体系は総則・物権・債権・親族・相続の5編で構成されていますが、全国一斉考試では総則・物権・債権のみが試験範囲となります。
また、総則は毎年出題されますが、物権と債権は隔年で交互に出題されますので、試験勉強するときに注意が必要です。
令和7年度:民法(総則・物権)
令和6年度:民法(総則・債権)
令和5年度:民法(総則・物権)
刑法
刑法の体系は総論と各論で構成され、全国一斉考試でも両方出題されていますが、問題数の配分は以下の通りとなります。
- 刑法総論:10問(60点)
- 刑法各論:15問(40点)
刑事訴訟法
刑事訴訟法は基本的にほぼ全てが出題範囲となりますが、「上訴」は除くとされています。
検務事務
全国一斉考試で出題される検務事務は以下4科目となります。
- 事件事務(令状事務含む)
- 証拠品事務
- 徴収事務
- 執行事務
毎年1科目ずつ順番で出題されますので、自身が受験するときにどの検務事務が出題されるか確認しておく必要となります。
令和7年度:徴収事務
令和6年度:証拠品事務
令和5年度:事件事務(令状事務含む)
令和4年度:執行事務
- 全国一斉考試の受験対象者は3級未満の若手検察事務官。
- 試験日は毎年2月下旬で、試験時間は午後2時~5時の3時間。
- 試験科目は憲法・検察庁法・民法・刑法・刑事訴訟法・検務事務で、1問4点、全125問の500点満点。
では次に、全国一斉考試の結果について見ていきたいと思います。
全国一斉考試の結果について
全国一斉考試の結果について、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
表彰制度
全国一斉考試には表彰制度がありますが、成績上位者に対して「法務総合研究所長表彰」が受賞されます。
- 令和6年度
480点以上の上位得点者36名
- 令和 5年度
484点以上の上位得点者39名 - 令和 4年度
480点以上の上位得点者30名 - 令和 2年度
488点以上の上位得点者34名 - 令和 元年度
488点以上の上位得点者29名
※令和3年度は各自受験で表彰なし
過去の表彰対象者の点数を見ると、最低でも120問/125問(96%)以上の正答率が必要なことが分かります。
ちなみに、過去には表彰者に対して海外研修への参加特典などがありましたが、今では実施されていないみたいですね。
人事評価との関係
全国一斉考試と人事評価との関係ですが、表面上は関係がないと言われています。
しかし、仕事上ではなかなか優劣が付けられないですが、全国一斉考試の得点では明確に優劣が付いてしまうので、人事評価に全く関係がないとは言えないです。
地検によっては個別の勉強会を開くなど職員の得点向上に力を入れているので、検察事務官としての出世を望むなら高得点を目指すのがベター。
【年度別】成績・結果
全国一斉考試の結果・成績ですが、過去5年度分の最高点・最低点・平均点は以下となります。
- 最高点:496点
- 最低点:212点
- 平均点:400.2点
憲法・検察庁法:81.6点
民法 :79.6点
刑法 :80.2点
刑事訴訟法 :73.6点
証拠品事務 :85.3点
- 最高点:500点
- 最低点:224点
- 平均点:339点
憲法・検察庁法:79.9点
民法 :73.1点
刑法 :82.8点
刑事訴訟法 :76.3点
事件事務 :86.9点
- 最高点:496点
- 最低点:204点
- 平均点:396.3点
憲法・検察庁法:82.1点
民法 :80.3点
刑法 :73.1点
刑事訴訟法 :79.9点
証拠品事務 :80.9点
- 最高点:500点
- 最低点:256点
- 平均点:412.4点
憲法・検察庁法:86.5点
民法 :79.7点
刑法 :81.3点
刑事訴訟法 :78.5点
証拠品事務 :86.3点
- 最高点:500点
- 最低点:260点
- 平均点:418点
憲法・検察庁法:88.2点
民法 :74.0点
刑法 :83.8点
刑事訴訟法 :83.0点
事件事務 :89.0点
全国一斉考試の成績・結果の詳細については、下記記事で紹介しています。
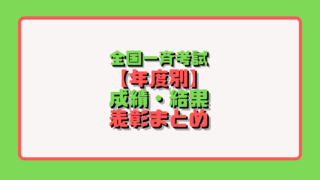
- 成績上位者になると法務総合研究所長表彰が受賞される。
- 表彰されるには最低でも96%以上の正答率が必要。
- 検察事務官として出世したいなら高得点を取っておきたい。
では次に、全国一斉考試の勉強方法について見ていきたいと思います。
全国一斉考試の勉強方法について
全国一斉考試の勉強方法については、下記項目をそれぞれ見ていきたいと思います。
研修教材
研修教材とは、法務総合研究所が発刊している法律や検務事務を詳しく解説した教材となります。
- 六訂 憲法
- 八訂 検察庁法
- 八訂 民法Ⅰ(総則)
- 八訂 民法Ⅱ(物権・担保物件)
- 八訂 民法Ⅲ(債権法)
- 七訂 刑法総論
- 四訂 刑法各論(その1)
- 四訂 刑法各論(その2)
- 八訂 刑事訴訟法Ⅰ(捜査)
- 八訂 刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)
- 八訂 刑事訴訟法Ⅲ(公判)
- 九訂 事件事務解説
- 九訂 証拠品事務解説
- 十訂 執行事務解説
- 九訂 徴収事務解説
研修教材は非売品となりますが、検察事務官は新規採用職員のときに参加する初等科研修時に研修教材を配布してもらえます。
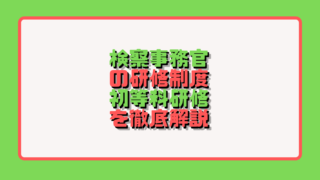
全国一斉考試の解説にも研修教材が用いられていますので、研修教材は全国一斉考試の教科書とも言えます。
研修誌
研修誌とは、法務総合研究所内にある誌友会事務局が発刊する月刊誌で、検察庁職員に毎月配布される雑誌になります。
- 論文
- 判例研究
- 判例紹介
- 新判例解説
- 各分野で活躍する検察職員
- 研修講座
研修誌のコラムですが、検察官も読むので判例に関する専門的なコラムが多いですが、検察事務官向けの研修講座もあります。
研修講座では全国一斉考試の試験科目が分野別に解説されていますので、試験対策の勉強に役立ちます。
検察庁の図書館に研修誌のバックナンバーが蔵書されているので、時間があるときに研修講座のコピーをとっておくと試験勉強に役立つ。
また、毎年5月号に法務総合研究所長表彰を受賞した職員が感想文を寄稿していますので、どのような勉強をしたのか参考になります。
過去問
試験勉強の定番ですが、全国一斉考試でも過去問を解くことが一番の試験対策となります。
特に、検察庁法と検務事務は過去に出題された問題が繰り返し出題されるので、過去問が一番試験対策になります。
過去問と解説は各検察庁の共有フォルダに配置されているので、全年度分を印刷しておくと試験勉強に役立つ。
検察庁内定者や現役検察事務官でスマホで過去問を勉強したい方は下記記事をご確認ください。
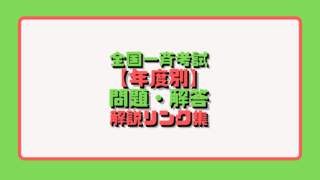
- 全国一斉考試の試験科目の教科書は研修教材。
- 研修誌には試験科目の講座の他に成績上位者の感想文などのコラムがある。
- 過去問は繰り返し出題されるので、過去問を解くことが一番の試験対策。
おわりに
今回は、検察事務官等全国一斉考試の試験概要について説明してきました。
検察事務官になると10年は受験しなければなりませんので、若手検察事務官はもちろん、検察庁内定者の方も是非参考にして勉強に励んでもらえればと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。