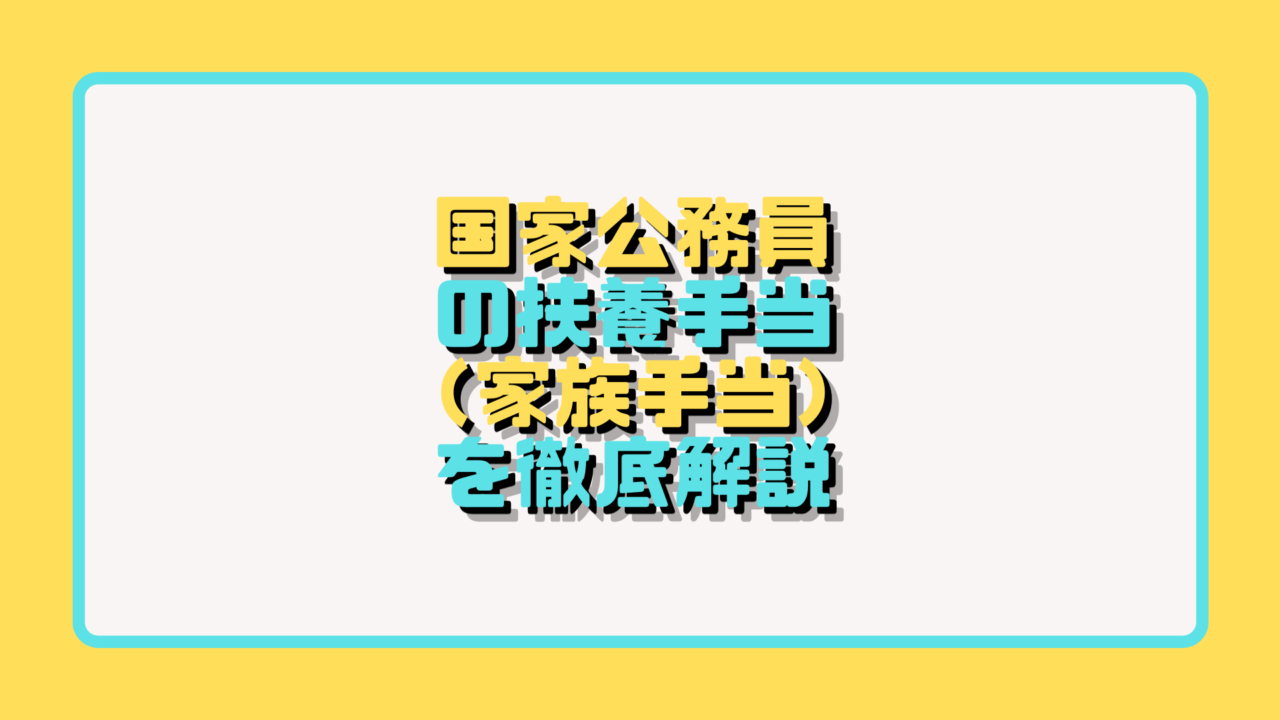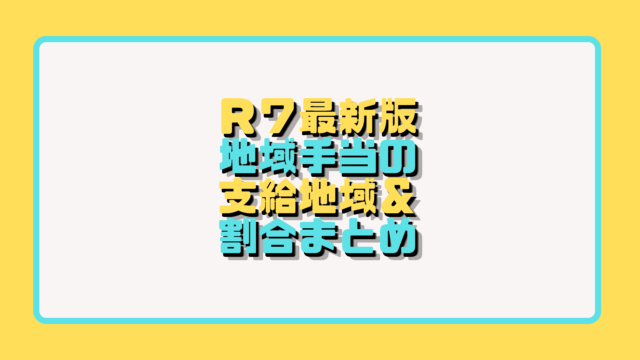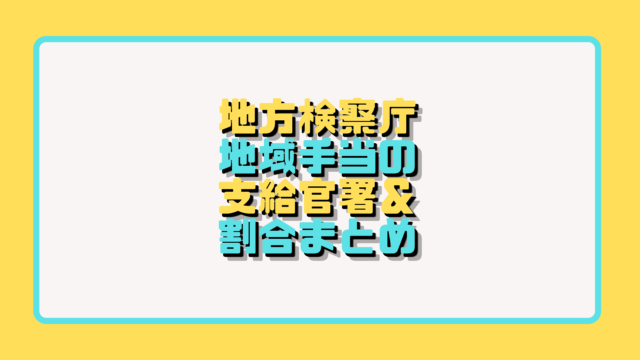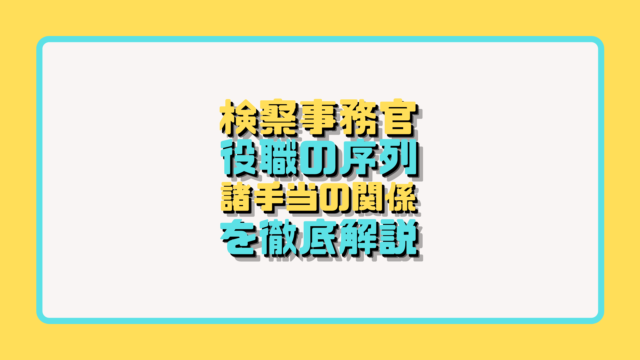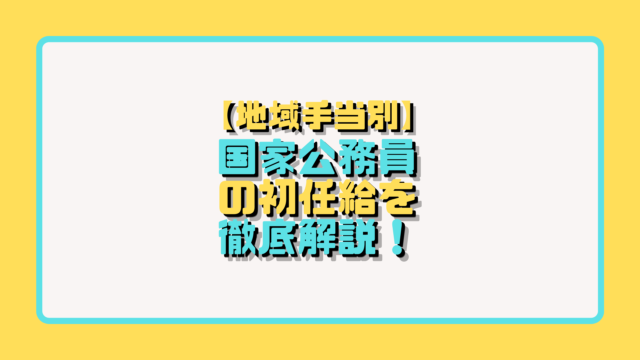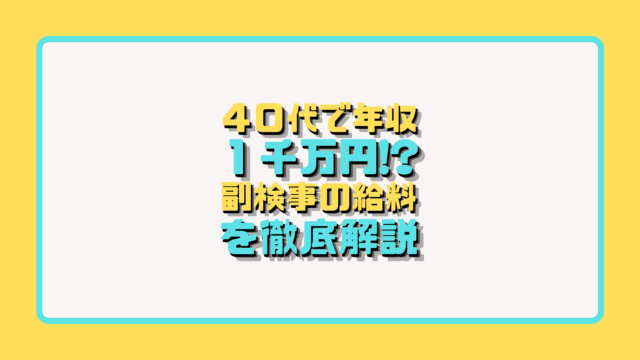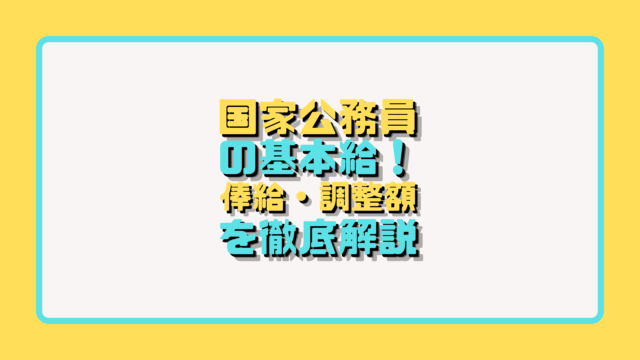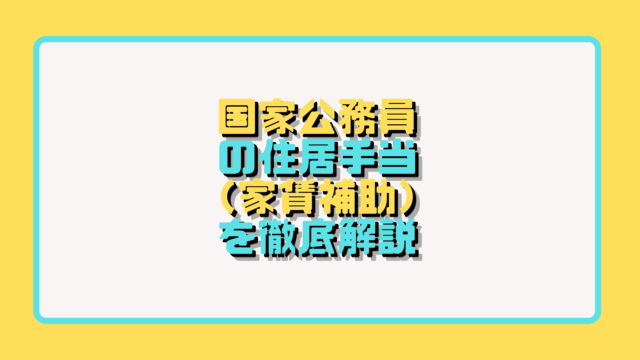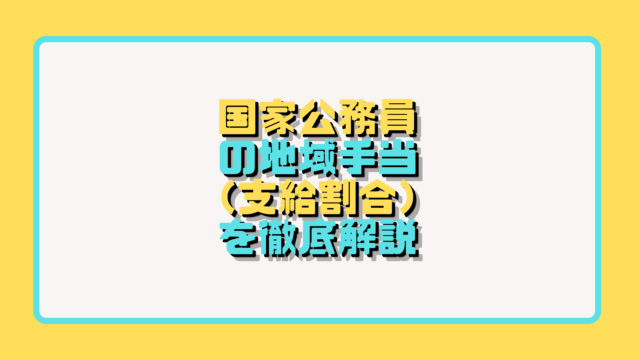こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
本記事では、国家公務員の扶養手当について詳しく解説します。
扶養手当は家庭を持つ方、家庭を持つ予定のある方にとって無関係ではない手当になるため、現職の方はもちろん、公務員を目指す方にもご覧いただければと思います。
本記事の内容は令和7年4月1日時点のものとなります。
扶養手当の概要について
扶養手当とは国家公務員の生活補助給的手当の一種であり、扶養親族のある職員に支給されます。
本章では、扶養手当の支給対象者や支給額の仕組みについて詳しく解説します。
扶養手当の支給要件
まず、扶養手当の支給要件ですが、職員が主たる生計者として親族を扶養することが条件となります。
- 配偶者(R7年度まで対象)
- 子(22歳の年度末まで)
- 孫(22歳の年度末まで)
- 父母、祖父母(満60歳以上)
- 弟妹(22歳の年度末まで)
- 重度心身障害者
ただし、職員の配偶者や兄弟姉妹が主たる生計者の場合や、扶養親族の恒常的な所得が年額130万円以上ある場合は、扶養手当の対象外となります。
年金受給者の所得制限額は180万円であるとの情報も散見されるが、これは誤情報であるため注意が必要。
→健康保険の扶養条件と混同している
扶養手当の支給額
次に、扶養手当の支給額ですが、扶養親族の続柄によって異なります。
| 扶養親族 | R7 | R8 |
| 配偶者(※1) | 3,000円 | 廃止 |
| 子(※2) | 11,500円 | 13,000円 |
| 父母等(※3) | 6,500円 | 6,500円 |
※1:行㈠8級以上の職員は支給対象外
※2:16~22歳は月額5,000円加算
※3:配偶者と子以外の扶養親族
行㈠9級以上の職員は支給対象外
扶養手当は平成28年から段階的に見直されてきたが、令和6年改正により、配偶者の扶養手当の廃止、子の扶養手当の引き上げと、大幅な変更となりました。
- 配偶者の扶養手当
6,500円→廃止 - 子の扶養手当
10,000円→13,000円
扶養手当の法的根拠(関係法規)
扶養手当の制度は法律や人事院規則などによって定められています。
制度の詳細や運用方針について確認したい方は、以下の関係法規をご参照ください。
- 一般職の給与に関する法律
11条、19条の8
- 人事院規則9-80(扶養手当)
- 人事院規則9-7(俸給等の支給)
8条、13条
- 一般職の職員の給与に関する法律の運用方針(給実甲第28号)
11条、19条の9関係 - 扶養手当の運用について(給実甲第580号)
- 扶養親族の認定について(給3-80)
- 扶養手当の運用(事業所得等の取扱い)について(給3ー95)
国家公務員は法令等に基づいて職務を遂行するため、根拠規定を確認する習慣を身につけることが望ましいです。
- 扶養手当の支給要件は、主たる生計者として親族(配偶者、子、父母等)の扶養が条件。
※恒常的所得:年130万円未満
※配偶者はR8から対象外
- 支給額は、子:13,000円(R7は11,500円)、父母等:6,500円
※16~22歳は5,000円加算
ここまでで扶養手当の基本的なポイントは押さえられたと思いますので、次の章では扶養手当についてのよくある質問について回答していきます。
扶養手当のよくある質問について
国家公務員の給与制度は一見して分かりにくいので、扶養手当についても多くの疑問が寄せられます。
そこで、本章では、よくある質問とその回答をまとめ、現職の方や国家公務員を目指す方が気になるポイントを解説します。
所得制限額の判定基準とは?
扶養親族に年額130万円以上の恒常的な所得があると扶養手当の対象外となります。
判定基準の主なポイントは、次の3つです。
所得が「恒常的」かどうか?
所得が「恒常的」か「一時的」かの判定基準は、毎月安定して収入があるかどうかです。
恒常的な所得の例
- 給与所得
- 年金所得
- 不動産所得(家賃収入)
- 株式等の譲渡所得(継続取引)
- 株式の配当所得
- 奨学金(学資に限定されない)
一時的な所得の例
- 退職所得
- 不動産所得(売却益)
- 株式等の譲渡所得(1回限り)
- 奨学金(学資に限定)
なお、事業所得で収入が不安定な場合では、2、3か月の平均収入額や前年度の所得などでケースバイケースで判断されます。
どの期間で判定するのか?
扶養手当の所得判定は、「扶養する事実が生じた日以降1年間の見込み額」で判断されます。
事実発生日前の所得は考慮しない
そのため、給与所得の場合は「月額108,333円」が基準となります。
(130万円÷12か月≒108,333円)
所得金額の算定方法は?
所得金額の算定では、事業所得や不動産所得の経費の取扱いがポイントとなります。
課税所得とは異なり、控除できる経費は「所得を得るために直接必要かつ最小限の範囲」に限られるため、注意が必要です。
控除可能な経費(OK)
- 仕入代
- 給料 など
控除不可な経費(NG)
- 減価償却費
- 接待交際費 など
そのため、課税所得は0円でも、扶養手当の所得判定では130万円を超える場合があり得ます。
扶養親族の判定基準とは?
扶養親族は、職員との関係や居住状況によって支給対象かどうか決まります。
判定基準の主なポイントは、次の2つです。
姻族(配偶者の親族)は含まれるのか?
姻族(配偶者の親族)は、扶養親族に含まれません。
そのため、配偶者の父母や連れ子を扶養していても、扶養手当の支給対象にはなりません。
姻族と養子縁組を結んでいる場合は扶養手当の支給対象となる。
なお、重度心身障害者については、親族でなくても支給対象となります。
別居していても支給対象になるのか?
別居している親族(配偶者と子を除く)は、所得制限に加え、職員が主たる生計者かどうかも判定基準となります。
仕送り額が親族の総収入(仕送りを含む)の3分の1以上であれば、扶養手当の支給対象になります。
兄弟姉妹も仕送りをしている場合、職員の仕送り額が最も多いことが条件。
なお、別居している配偶者と子については、特に仕送り額の条件は定められていません。
扶養手当はいつから支給される?
扶養手当は、職員が支給要件を満たした日の翌月から支給※されます。
※1日の場合は当月から
ただし、事実発生日から15日を過ぎて届出をした場合は、届出日が基準となるため注意が必要です。
扶養手当は他の手当に影響する?
扶養手当は以下の手当の算定基礎に含まれるため、支給に応じて手当額が増額されます。
- 地域手当
- 広域異動手当
- 特地勤務手当
- 特地勤務手当に準ずる手当
- 期末手当
特に、地域手当や期末手当は対象者も多いため、以下の記事で支給額の算定方法をぜひ確認してみてください。
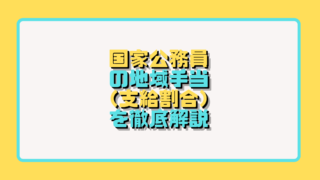
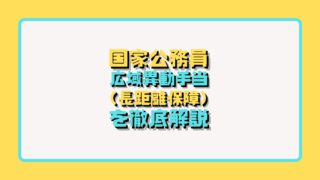
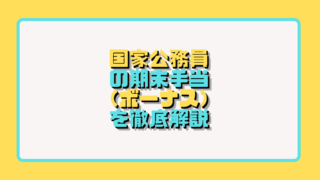
- 所得制限額(130万円)は、事実発生日以降1年間の見込み、毎月安定した収入(経費は必要最低限)かどうかにより判定。
- 姻族(配偶者の親族)は扶養親族に含まれない。別居している親族には仕送り条件(総収入の3分の1以上)がある。
- 支給開始は事実発生日の翌月(1日の場合は当月)からだが、届出が15日過ぎる場合は届出日が基準となる。
- 扶養手当は地域手当や期末手当の算定基礎となる。
おわりに
今回は、国家公務員の扶養手当についてご紹介しました。
給与制度は、国家公務員として知っておくべき重要な制度です。しっかり理解して、ライフプランニングなどに役立てていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。