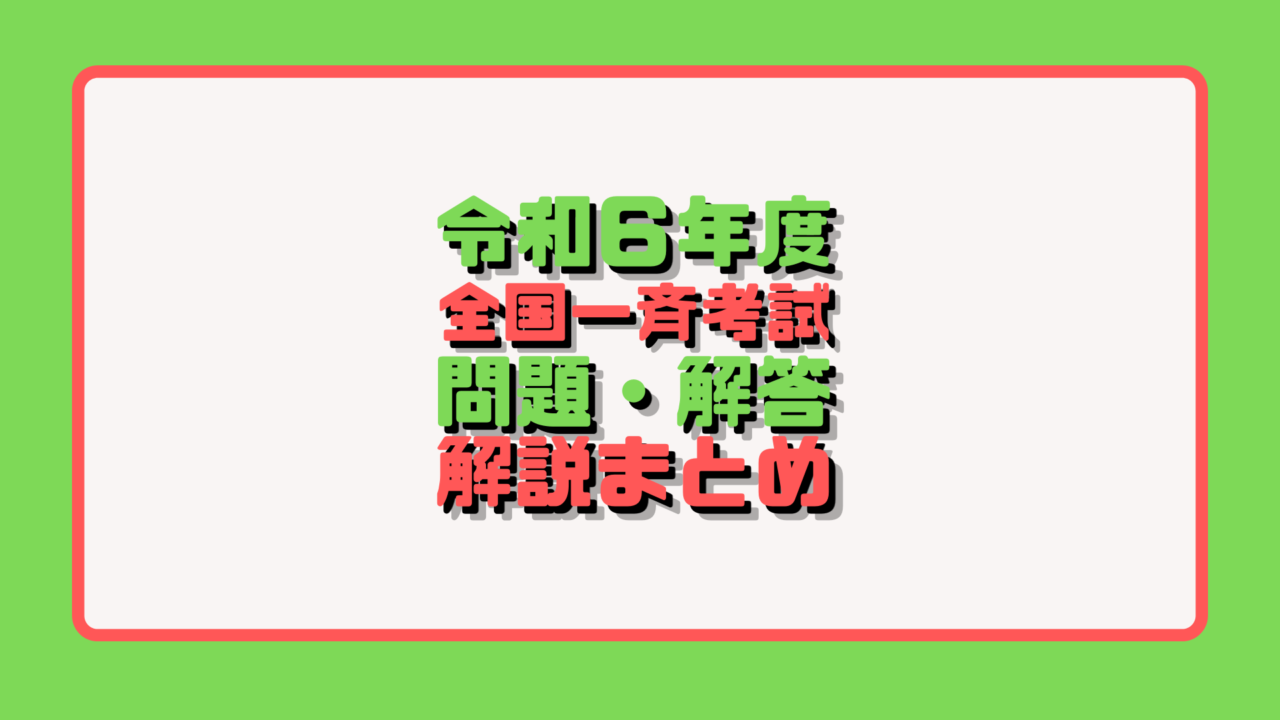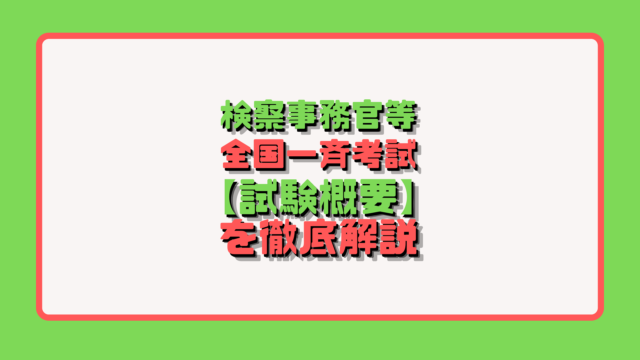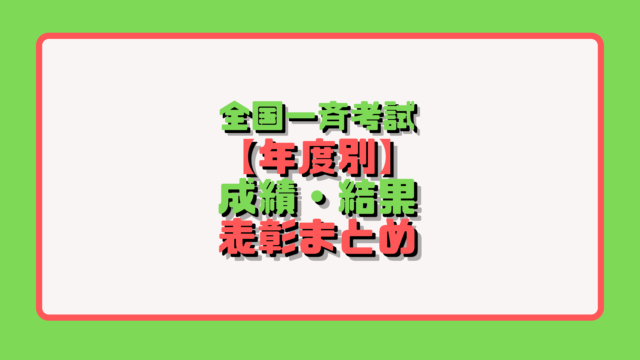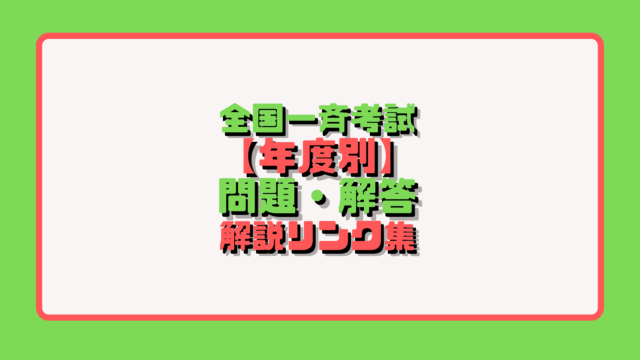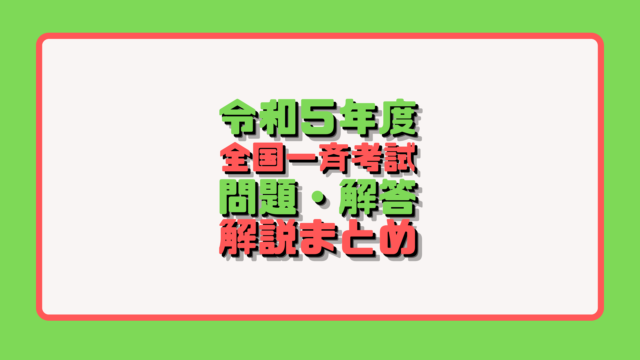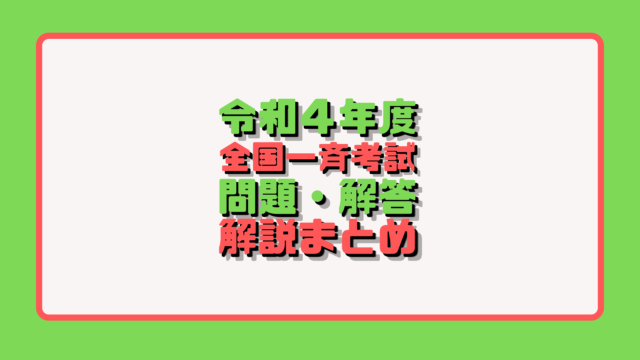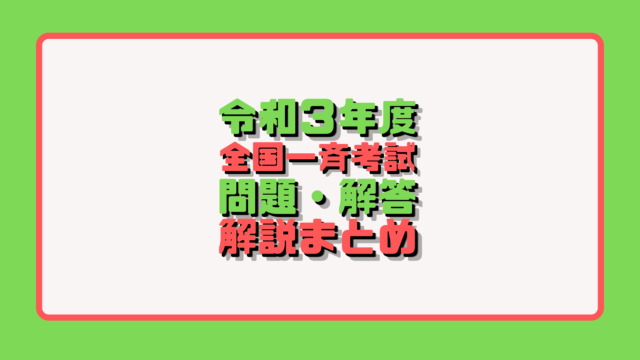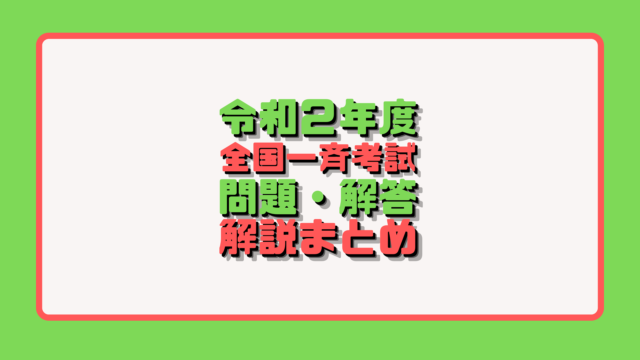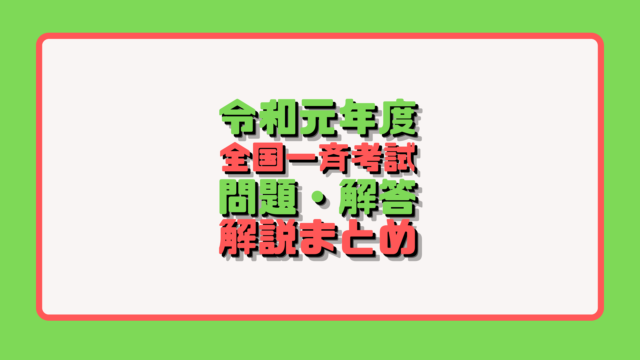憲法・検察庁法
第1問
外国人の人権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
(○) そのとおり。最高裁は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり」と判示している(いわゆるマクリーン事件、最判昭53.10.4民集32・7・1223、研修教材・六訂憲法62ページ)。
⑵ 外国人の再入国の自由は、憲法上、保障されていない。
(○) そのとおり。最高裁は、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国ヘ一時旅行する自由を保障されているものでない」から、再入国の自由も保障されないとした(いわゆる森川キャサリーン事件、最判平4.11.16裁判集民事166・575、研修教材・六訂憲法62、63ページ、研修846号40、41ページ)。
⑶ 永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上、許されない。
(✕) 最高裁は、「憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」としつつも、「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判示した(最判平7.2.28民集49・2・639、研修教材・六訂憲法63、64ページ)。
⑷ 国民主権の原理により、外国人は、全ての公務に就任することができない。
(✕) 公務就任権については、国民主権の原理から直ちに外国人が全ての公務に就任することができないと考える必要はなく、就任する公務と国民主権との関係が具体的に検討されるべきである(研修教材・六訂憲法64ページ)。
東京都職員が、管理職選考を受験しようとしたところ、日本国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったことから、東京都に慰謝料の支払等を求めて訴えを提起した訴訟において、最高裁は、「地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの」を「公権力行使等地方公務員」と呼び、その職務の遂行は、「住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上大きな影響を及ぼすなど、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである。それゆえ、国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」とした上で、「普通地方公共団体が、公務員制度を構築するに当たって、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことができるものというべきである。そうすると、普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも反するものではない」とした(最判平17.1.26民集59・1・128)。
⑸ 生存権等の社会権は、我が国に在留する外国人に、憲法上、当然には保障されていない。
(○) そのとおり。生存権等の社会権は、我が国に在留する外国人に当然には保障されず、当該外国人の国籍国により第一次的には保障されるべきものである。しかし、外国人に保障することを禁止されているとまでは解せず、財政上の支障のない限り法律によって外国人に社会権を保障することは憲法上問題はない(研修教材・六訂憲法65ページ)。
第2問
精神的自由権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 「宗教団体」(憲法20条1項)、「宗教上の組織若しくは団体」(憲法89条)とは、宗教と何らかの関わり合いのある行為を行っている組織ないし団体の全てを意味する。
(✕) 最高裁は、「憲法20条1項後段にいう『宗教団体』、憲法89条にいう『宗教上の組織若しくは団体』とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。」と判示した(いわゆる箕面市忠魂碑事件、最判平5.2.16民集47・3・1687、研修教材・六訂憲法106、107ページ)。
⑵ 宗教法人が公益法人や社会福祉法人と共に一定の免税措置を受けることは、国から特権を受けることには当たらず、憲法20条1項に違反しない。
(○) そのとおり。宗教法人は、法人税法、所得税法、地方税法などの規定により、一定の免税措置を受けるが、これは、内国公益法人一般に対する免税措置が具体的に適用されるー場面にすぎず、憲法20条1項に違反しないと解されている(研修教材・六訂憲法103、104ページ、研修888号49~52ページ)。
⑶ 公立学校の校長が、信仰上の理由により必修科目である体育の剣道実技に参加しなかった生徒に対し、代替措置として、他の体育実技を履修させるなどした上でその成果に応じて評価することは、憲法20条3項に違反する。
(✕) 信仰上の理由により、必修科目である体育の剣道実技に参加しなかったため、単位不認定により原級留置、退学の処分を受けた生徒が、この処分の取消しを求めた事件につき、最高裁は、「信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、・・・・・・原級留置処分をし、さらに・・・・・・退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会通念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。」とし、代替措置をとることは「その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果」もなく、憲法20条3項に違反しないとした(最判平8.3.8民集50・3・469、研修教材・六訂憲法101、102ページ、研修888号49~53ページ)。
⑷ 公立中学校において現実に子供の教育の任に当たる教師は、学問の自由を保障する憲法23条により、教授の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子供の教育内容を決定することができる。
(✕) 初等中等教育機関(下級教育機関)における教育従事者も学問の自由の保障を受けるが、そのうち「教授の自由」も認められるかについては問題があり、大学などの高等教育機関にあっては、受講者は批判能力を持ち、研究と教育が不可分の関係にあるが、心身の発達に応じた普通教育を施すことを使命とする下級教育機関においては、直接には「教授の自由」は妥当しないと解されている。最高裁は、普通教育の学校における教師について、「教授の具体的内容および方法につき、ある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」としながら、「しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない」と判示している(いわゆる旭川学カテスト事件、最判昭51.5.21刑集30・5・615、研修教材・六訂憲法135ページ)。
⑸ 憲法23条の学問の自由は、学問研究活動の自由と研究成果発表の自由を含む。
(○) そのとおり。学問の自由は、広く個人の①学問研究活動の自由、②研究成果発表の自由を意味し、学問が真理探究それ自体に向けられた論理的体系的知識に関わるものであることから、それぞれ思想・良心の自由、表現の自由に対していわば特別法的性格を有する(研修教材・六訂憲法134、135ページ)。
第3問
国会・内閣に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 条約の締結に必要な国会の承認については、衆議院に先議権がある。
(✕) 条約の締結は内閣の権限だが(憲法73条3号)、「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」(同号ただし書、研修教材・六訂憲法239、240ページ)。この国会の承認には、憲法上衆議院の優越が認められているが(憲法61条、60条2項)、衆議院に先議権があるのは予算についてであり(憲法60条1項)、条約の承認に衆議院の先議権はない(研修教材・六訂憲法210、211ページ)。
⑵ 内閣が総辞職したときは、国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣を指名する。
(○) そのとおり(憲法67条1項、研修教材・六訂憲法254ページ)。
⑶ 国務大臣は、その在任中は、内閣の承認がなければ訴追されない。
(✕) 憲法75条は、「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」と規定する。本問中、「内閣の承認」が誤り(研修教材・六訂憲法252ページ)。
⑷ 内閣総理大臣が自己の意思に基づいて辞職した場合、内閣は、総辞職をしなければならない。
(○) そのとおり。憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定する。ここでいう「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡、内閣総理大臣となる資格の喪失、辞職などの場合を指す(研修教材・六訂憲法253ベージ)。
⑸ 国務大臣は、両議院のいずれにも議席を有していなくても、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
(○) そのとおり(憲法63条前段)。
第4問
司法権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 裁判所には、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限はない。
(○) そのとおり。判例(いわゆる警察予備隊違憲訴訟、最判大昭27.10.8民集6・9・783)は、「裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。」「具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。」と判示している。したがって、裁判所には、事件と関係なく、抽象的に憲法その他の法令の解釈に関する争いを判定する権限はない(研修教材・六訂憲法259ページ)。
⑵ 憲法76条1項は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定しているところ、同項の「下級裁判所」に家庭裁判所は含まれない。
(✕) 家庭裁判所につき、判例は「すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するところであり、家庭裁判所はこの一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として裁判所法により設置されたものに他ならない」と判示している(最大判昭31.5.30刑集10・5・756、研修教材・六訂憲法269ページ)。
⑶ 最高裁判所の裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合と、公の弾劾による場合を除いては、罷免されることはない。
(✕) 裁判官の職権の独立(憲法76条3項)は、司法権の独立の原則の中核をなすものであり、裁判官の身分が高度に保障されていなければ、良心に従って公正な裁判をすることができない。そのため、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されないとされている(憲法78条)。この憲法78条に規定する例外に加えて、最高裁判所裁判官は、国民審査の結果罷免される場合がある(憲法79条3項、研修教材・六訂憲法277、278ページ)。
⑷ 最高裁判所は、国会が立法権を独占し、国会以外の者が立法するのを認めないという国会中心立法の原則の唯一の例外として、規則を定める権限を有する。
(✕) 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士・裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する(憲法77条1項)。この最高裁判所の規則制定権は、国会が唯一の立法機関であり(憲法41条)、国会以外の者が立法するのを認めないとする国会中心立法の原則に対する憲法上の例外の一つである。憲法上の例外としては、そのほか、議院の規則制定権に基づく議院規則(憲法58条2項)、地方公共団体の条例(憲法94条)などがある(研修教材・六訂憲法207、208、274ページ)。
⑸ 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合であっても、判決は常に公開しなければならない。
(○) そのとおり。憲法82条1項の裁判公開の原則の例外として、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、「対審」は公開しないで行うことができる(同条2項)。この場合でも、「判決」は常に公開の法廷で行われる(裁判所法70条)。なお、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、必ず公開しなければならない点に注意が必要である(憲法82条2項ただし書)。以上につき、研修教材・六訂憲法292ページ参照
第5問
検察庁法に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察庁法4条は、検察官の犯罪捜査権の根拠となるものではない。
(✕) 犯罪捜査権は、「公訴を行う」権限の必然的な前提として検察庁法4条に根拠があると解されている。そして、同法6条はそれを確認するとともに、同法5条による事物管轄の制限を解いているものと解されている。捜査は、その性質上、これを完結してみなければ、いかなる罪名に当たる犯罪であるか明らかにならないことが多いので、事物管轄の制限を置くことは、いたずらに検察官の捜査を制限することになる(研修教材・七訂検察庁法12~14、40、41ページ)。
⑵ 検察権の独立は、司法権の独立と同様に、他からの一切の影響を排除しようとするものである。
(✕) 検察権の独立は、司法権の独立のように他からの一切の影響を排除しようとするものとは異なり、他からの不当な影響を排除しようというものである。検察権の独立は、正しい統一的な国家意思が、司法に反映するように検察権が行使されなければならないための要請であり、もとより検察権の独善を容認するものではなく、行政権の一部である検察権は、内閣法、国家行政組織法、法務省設置法等の諸規定に基づいて、法務大臣の指揮監督の下行使されるのが原則である(研修教材・七訂検察庁法20~22ページ)。
⑶ 法務大臣の指揮監督権の行使は、検察事務と検察行政事務のいずれについても制限される。
(✕) 検察庁法1条1項の「検察官の行う事務」は、検察事務と検察行政事務の両者を含むものとされており、前者は同法4条及び6条に定める事務であり、後者は同法7条から10条までに定める事務とその他の行政事務である。同法14条は、「第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と規定し、検察事務に関する法務大臣の指揮監督権の行使を制限しているが、検察事務以外の事務についての指揮監督は組織法上の原則によるのであり、総務、会計、人事等に関する事務や、犯罪の防止その他刑事政策上の諸施策に関する事務についての法務大臣の指揮監督権の行使は制限されない(研修教材・七訂検察庁法22~24、49~53ページ)。
⑷ 検察官の適格審査制度は、検察官の職務と責任の特殊性から、検察官の身分を一般の国家公務員のそれに比して手厚く保障するために、検察庁法によって設けられた制度である。
(○) そのとおり(検察庁法23条、研修教材・七訂検察庁法81ページ)。
⑸ 法務大臣が必要と認めなければ、地方裁判所の支部が設けられても、これに対応する地方検察庁の支部を設けなくてもよい。
(○) そのとおり。法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して、高等検察庁又は地方検察庁の支部を設けることができる(検察庁法2条4項)。したがって、裁判所の支部がないのに、検察庁の支部だけを設けることは許されない。逆に、法務大臣が必要と認めなければ、裁判所の支部が設けられても、検察庁の支部を設けなくてもよい(研修教材・七訂検察庁法55ページ)。
民法(総則・債権)
第6問
意思表示に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、Bがこの土地をCに売却した。Cは、Bの詐欺を知らなかった。その後、Aが、Bの詐欺を理由に、Bに対する土地売却の意思表示を取り消した場合、Bの詐欺について知らなかったことにつきCに過失があるときは、Aは、この取消しをCに対抗することができる。
(○) そのとおり。相手方が詐欺を行った場合、表意者は常に意思表示を取り消すことができるが(民法96条1項)、その取消しの効果を善意・無過失の第三者に対抗できない(同条3項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)127ページ)。本問のCにはBの詐欺について知らなかったことに過失があるため、Aは、Bに対する土地売却の意思表示の取消しをCに対抗することができる。
⑵ Aは、A所有の絵画をBに売却したが、錯誤を理由に、Bに対する絵画売却の意思表示を取り消そうと考えている。錯誤がAの重大な過失によるものであった場合には、BがAの錯誤を知っていたという事情が認められない限り、Aが錯誤を理由にBに対する絵画売却の意思表示を取り消すことはできない。
(✕) 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、意思表示の取消しをすることができるのは、①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、あるいは、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときである(民法95条3項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)123ページ)。
⑶ Aは、Bの強迫により、A所有の建物をBに売却し、Bがこの建物をCに売却した。その後、Aが、Bの強迫を理由に、Bに対する建物売却の意思表示を取り消した場合、Bの強迫についてCが善意・無過失であるときは、Aは、この取消しをCに対抗することができない。
(✕) 強迫による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、この取消しの効果は、善意・無過失の第三者にも対抗することができる(同条3項の反対解釈、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)133ページ)。
⑷ Aは、真実は自己所有の腕時計を売却するつもりはないのに、Bに対し、「この腕時計を売ってやる。」と申し向けた。この場合、Bが、Aの意思表示が真意ではないことを知っていたときは、Aの意思表示は無効である。
(○) そのとおり。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(民法93条1項本文)。相手方のある意思表示において、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っているとき又は知ることができる状況にあったときは、その意思表示は無効である(同条1項ただし書)。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)106、107ページ参照
⑸ Aは、Bと通謀して、A所有の土地をBに売却したように仮装し、Bへの所有権移転登記をした。Bは、登記という虚偽の外観があることに乗じて、この土地をCに売却した。Cは、売買契約締結当時、Bの登記が虚偽表示によるものであることを知らなかった。この場合、Aは、Cが登記を備えていないことを理由として、Cの所有権取得を否定することができない。
(○) そのとおり。虚偽表示の効果は無効であるが(民法94条1項)、その無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。本問では、Cが善意の第三者として保護を受けるための要件として、登記を具備している必要があるかが問題となる。判例は、登記がなくても善意の第三者を保護している(最判昭44.5.27民集23・6・998)。なぜなら、虚偽表示者の帰責性は非常に大きく、虚偽表示者が一般の取引参加者よりも不利に扱われるのは当然だからである。よって、Cが善意の第三者として保護を受けるのに、登記は不要である(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)108、109ページ)。
第7問
権利能力及び行為能力に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 成年被後見人が、成年後見人の同意を得ずに日用品を購入した場合、その行為を取り消すことができる。
(✕) 成年被後見人であっても、簡単な法律行為であれば本人自ら行っても自己に不利益となるおそれはないものもあり、また、日常生活に関する法律行為についてまで取り消されるとなれば、自己決定の尊重等に反するおそれがある上、取引の安全を害する。そこで、日用品の購入等、日常生活に関する行為については、取消しの対象から外し、成年被後見人は単独で行うことができる(民法9条)。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)27~29ページ参照
⑵ 不在者の生死が7年間明らかでなく、失踪宣告を受けた場合には、たとえ生存していたとしても権利能力は認められない。
(✕) 民法31条の「死亡したものとみなす」とは、法律上死亡したものとして取り扱うということであって、失踪宣告を受けた者からその権利能力を剥奪してしまう制度ではないから、失踪宣告を受けた者が他の土地で新たに形成した法律関係や、帰来後の法律関係は、失踪宣告の取消しがなくても、有効に成立する(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)18、49ページ)。
⑶ 保佐人は、被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる許可を得ないで相続の放棄をした場合には、相続の放棄を取り消すことができる。
(○) そのとおり。被保佐人が、保佐人の同意を要する行為について、保佐人の同意を得ず、又はこれに代わる許可を得ないでした行為は、取り消すことができるところ(民法13条4項)、「相続の放棄」はこれに当たる(同条1項6号)。その取消権者は、被保佐人及び保佐人である(同法120条1項)。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)35ページ参照
⑷ 未成年者が、契約の相手方に対し、自分が成人であると誤信させようとして詐術を用いた結果、相手方がその詐術によって未成年者が成人であると誤信し、未成年者との間で契約を締結した場合、未成年者は、契約の締結について法定代理人である親の同意を得ていなくても、その契約を取り消すことができない。
(○) そのとおり。制限行為能力者が、相手方に、自分が行為能力者であると誤信させようとして詐術を用い、相手方がその詐術によって行為能力者であると誤信した場合、制限行為能力者の行為を取り消すことができなくなる(民法21条、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)43~45ページ)。
⑸ 家庭裁判所が、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をする場合、その対象行為は、民法13条1項に定める行為の一部に限られる。
(✕) 家庭裁判所は、補助人の同意を要する旨の審判(民法17条1項)又は補助人に代理権を付与する旨の審判(同法876条の9第1項)をすることができる。同意権付与の対象となる行為は、同法13条1項に定められた行為の一部に限られるが(同法17条1項)、代理権付与の対象となる行為に制限はない(同法876条の9)。以上につき、研修敦材・八訂民法Ⅰ(総則)38ページ、研修879号31、33~35ページ参照
第8問
債権の消滅に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 金銭債務において、債務者が債権者に提供した金額に不足がある場合は、いかなるときも債権者がこれを拒んで債務不履行責任を追及することができる。
(✕) 大判昭13.6.11民集17・1249、最判昭35.12.15民集14・14・3060は、金銭債務において提供金額にわずかな不足があるにすぎない場合には、債権者がそれを拒んで債務不履行責任を追及することは信義則上許されない旨判示しており、給付内容の一部だけの提供であっても有効な弁済として認められる場合がある(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)134ページ)。
⑵ 特定物の引渡しが給付の目的となっている場合の弁済をなすべき場所は、別段の意思表示がない限り、債権発生の時にその物が存在した場所である。
(○) そのとおり。民法484条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と規定している(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)135ページ)。
⑶ Aが、Bに対して100万円の金銭債権を有しているところ、この債権をAに対して100万円の金銭債権を有するCが差し押さえた。その後、BがAに弁済をした場合、Cは、これにより損害を受けたとしても、Bに対し、自己に対し弁済するよう請求することはできない。
(✕) AのBに対する債権をAの債権者Cが差し押さえたときは、第三債務者Bは、自己の債権者Aに対して支払をすることを禁じられる(民事執行法145条)。第三債務者Bが自己の債権者Aに弁済をしても、差押債権者Cに対抗することができず、Cは、その受けた損害の限度において、第三債務者Bに対して更に弁済を請求できる(民法481条1項)。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)139、140ページ参照
⑷ 受働債権の弁済期が到来していれば、自働債権の弁済期が到来していなくとも相殺できる。
(✕) 相殺は、自働債権(相殺をしようとする債務者の持つ債権)と受働債権(相殺される相手方の債権)の双方の債務が弁済期にあることが要件とされているが(民法505条1項)、債務者は、原則として期限の利益を放棄することができる(同法136条2項)ことから、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期は必ずしも到来していなくとも相殺することができる(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)149ページ)。
⑸ 受働債権が、医療契約上の債務不履行に基づく人の生命・身体の侵害による損害賠償債権の場合、その債権者が他人からその債権を譲り受けたときでない限り、債務者は、相殺をもって対抗することができない。
(○) そのとおり。平成29年改正前の民法509条は、不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺を全て禁止していたが、改正後の同法509条は、①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と②人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(①を除く。)を受働債権とする相殺の禁止を規定しており、②については、不法行為のみならず債務不履行に基づく損害賠償請求権についても相殺を禁止する旨を定めている。なお、これらの債権を「他人から譲り受けた」ときには、そのような債権を受働債権とする相殺は禁止されていない(同条ただし書)。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)150、151ページ参照
第9問
債権者代位権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有しているが、Bは、弁済期が到来してもこれを弁済しない。Bは、以前Cから買った甲土地を所有しているが、登記名義をCのままにしており、Cに登記の移転を求めることもしない。Bの財産は、甲土地のほか、1000万円の預金債権がある。この場合、Aは、債権者代位権に基づき、BのCに対する移転登記請求権をBに代わって行使することができる。
(✕) 民法423条1項には、「自己の債権を保全するため必要があるとき」と規定されており、債務者に属する権利を行使するためには、債務者の資力が不十分(無資力)であることが必要である(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)57ベージ)。設問ではBには甲土地のほか、1000万円の預金債権があることから、Aは、債務名義を得た上、Bの有する1000万円の預金債権のうち100万円の預金部分を差し押さえ、そこから回収することができるため、債権者Bを代位してBのCに対する移転登記請求権を行使することはできない。
⑵ Aは、Bに対して50万円の債権を有しているが、Bは、弁済期が到来してもこれを弁済しない。Bの財産は、Cに対する100万円の債権しかないところ、Bは、既にその弁済期が到来しているにもかかわらず、その弁済を求めず、Cからの弁済もない。この場合、Aは、50万円の限度において、BのCに対する当該債権を代位行使することができる。
(○) そのとおり。民法423条の2は、「被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」と規定している(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)61ページ)。
⑶ 債権者代位権は、裁判外では行使することができない。
(✕) 債権者代位権は、裁判で行使してもよいし、裁判外で行使してもよい(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)60ページ)。裁判上の行使しかできない詐害行為取消権とは異なる(民法424条1項本文参照)。
⑷ 債権者Aが、債務者BのCに対する債権を代位行使するときは、Cは、Bに対して有する同時履行の抗弁をもって、Aに対抗してAの代位権行使を阻むことができる。
(○) そのとおり。民法423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)60ページ)。債権者代位権が行使されたからといって、相手方が立場の悪化を甘受しなければならない理由はない。
⑸ 債権者Aが、債務者BのCに対する金銭債権を代位行使するときは、Cに対し、自己に直接その支払を求めることはできず、Bへの支払を求めることができるにすぎない。
(✕) 民法423条の3前段は、「被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。」と規定している(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)61ページ)。
第10問
不当利得に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、自己が債務者であると誤信してBのCに対する債務を弁済した。これにより債権者Cが善意でB名義の借用証書を破棄した場合、Aは、Cに対し弁済金の返還請求をすることができない。
(○) そのとおり。債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合に、債権者が善意で証書を滅失させたときは、弁済をした者は返還の請求をすることができない(民法707条1項。研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)240ページ、研修913号64ページ)。
⑵ 強行法規に違反してされた給付であっても、その給付したものの返還を請求することができる場合もある。
(○) そのとおり。民法708条の「不法な原因」の「不法」とは、単なる取締法規違反や強行法規違反では足りず、公序良俗に反する場合に限られると解されている。最判昭37.3.8民集16・3・500は、「民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要」としている(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)241ページ)。
⑶ 未登記の甲建物の所有者Aは、不倫関係を継続させる目的で、愛人Bに対し、甲建物を贈与し、その引渡しをした。後に、AとBは不倫関係を解消し、AはBに甲建物の返還を請求した。甲建物について、AからBへの贈与に基づく引渡しが不法原因給付に当たる場合、AがBに給付した甲建物の返還を請求できないことの反射的効果として、甲建物の所有権は、Bに帰属する。
(○) そのとおり。設問と同様の事案において、最判昭45.10.21民集24・11・1560は、「贈与者において給付した物の返還を請求できなくなったときは、その反射的効果として、目的物の所有権は贈与者の手を離れて受贈者に帰属する」と判示した(研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)242ページ、研修913号67ページ)。
⑷ A所有の土地を、Bが自己に何ら権限がないことを知りながら、Aに無断で駐車場として近隣住民に貸し出し、利用者から駐車料金を得ていた場合、Bは、Aに対し、当該駐車料金相当額を返還すれば足り、これに利息を付して返還する必要はない。
(✕) 受益者が悪意の場合、現存するかどうかにかかわらず、受けた利益(利得)を全て返還する必要があるほか、利得に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段。研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)243ページ、研修913号63ページ)。
⑸ Aは、Bに対する借金50万円を、令和7年11月30日に返す債務を負っていた。しかし、Aは思い違いをして、1年早い令和6年11月30日に返済した。この場合、Bが、まだ弁済期前であることを知りながらその返済を受けたのであれば、Aは、Bに対し、50万円の返還を請求することができる。
(✕) 民法706条本文の規定により、債務者は、弁済期前に弁済してもその返還を請求することはできない。この場合、債権者の善意悪意を問わない。なお、同条ただし書の規定により、債務者が錯誤によって弁済期前であることを知らずに弁済した場合、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。以上につき、研修教材・八訂民法Ⅲ(債権法)239、240ページ、研修913号64ページ参照
刑法
第11問
緊急避難に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 緊急避難における「危難」は、人の行為によって発生したものに限られない。
(○) そのとおり。危難の原因は、自然現象や動物の行動によるものでもよい(研修教材・七訂刑法総論135ページ)。
⑵ 緊急避難における「現在の危難」は、法益の侵害が現実に存在する場合だけでなく、侵害が目前に差し迫っている場合を含む。
(○) そのとおり。緊急避難における危難の現在性の要件は、正当防衛における急迫性の要件と同様に解されている(研修教材・七訂刑法総論135ページ)。
⑶ 緊急避難における「やむを得ずにした行為」の意義は、正当防衛における「やむを得ずにした行為」の意義と同一である。
(✕) 緊急避難における「やむを得ずにした行為」とは、正当防衛におけるそれと異なり、当該避難行為をする以外に方法がなく、かかる行動に出ることが条理上肯定し得る場合を意味し(最判昭24.5.18裁判集刑10・231)、避難行為の補充性が要件となる(研修教材・七訂刑法総論136ページ)。
⑷ 緊急避難は、避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合に限って成立する。
(✕) 緊急避難は、避難行為により「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」(刑法37条1項)に成立するのであるから、生じた害が避けようとした害と同程度であった場合にも成立し得る(研修教材・七訂刑法総論137ページ)。
⑸ 過剰避難が成立する場合、必要的に刑が減軽又は免除される。
(✕) 過剰避難が成立する場合、任意的に刑が減軽又は免除される(刑法37条1項ただし書、研修教材・七訂刑法総論138ページ)。
第12問
共犯に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 共犯者間の意思の連絡が明示的でなくても共謀共同正犯が成立することがある。
(○) そのとおり。判例(最決平15.5.1刑集57・5・507)は、共犯者間で黙示的に意思の連絡があった事案について共謀共同正犯の成立を認めている(研修教材・七訂刑法総論266、277ページ)。
⑵ Aが、既にBの殺害を確定的に決意しているCに対し、Bを殺害するよう働きかけ、これによってCの決意が強固になったとしても、Aに教唆犯は成立しない。
(○) そのとおり。教唆犯が成立するには、教唆行為により被教唆者に特定の犯罪の実行を新たに決意させなければならないから、被教唆者は、その犯罪の実行を決意していないことが必要である。したがって、既にその犯罪実行の決意を有する者に対しては、その意思を強めるという意味での幣助が問題になるにすぎない(研修教材・七訂刑法総論283ページ)。
⑶ A所有の物を業務上預かり占有していたBと、当該物の預かり業務を行っておらず占有もしていないCが共謀して当該物を横領した場合、Cには単純横領罪(刑法252条1項)の共同正犯が成立する。
(✕) 業務上横領罪は、単純横領罪との関係では業務上占有者であるという身分により刑が加重される点で不真正身分犯であるが、全くの非占有者との関係では、占有者という身分を持った真正身分犯であるところ、非占有者が業務上横領罪に加功した場合、判例(最決昭32.11.19刑集11・12・3073等)は、非占有者に刑法65条1項を適用して業務上横領罪の共同正犯が成立するとした上で、同条2項によって単純横領罪の刑を科すべきであるとしている(研修教材・七訂刑法総論296、297ページ)。
⑷ 賭博の常習者Aが非常習者Bの賭博行為を帯助した場合、Aには単純賭博罪の幣助犯が成立する。
(✕) 本問は、不真正身分犯において身分者が非身分者の行為に加担した場合であるところ、非常習者の賭博行為を幣助した常習者について、判例(大判大3.5.18刑録20・932)は、刑法65条2項の趣旨により、常習賭博罪の幣助犯が成立するとしている(研修教材・七訂刑法総論299ページ)。
⑸ Aが、Bに対し、C方に侵入して現金を窃取するように教唆したところ、Bが、誤ってD方に侵入して衣類を窃取した場合、Aには住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯が成立する。
(○) そのとおり。教唆者が教唆に当たって認識していた事実と被教唆者が現実に実行した事実との不一致が同一構成要件内にあるとき、教唆犯の故意は阻却されない(大判大9.3.16刑録26・185、研修教材・七訂刑法総論300ページ、研修887号63~66ページ)。
第13問
生命及び身体に対する罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bの身辺近くで殊更大太鼓・鐘などを強く連打した。この場合、Aの行為は暴行罪の暴行になり得る。
(○) そのとおり。暴行罪の成立要件である「有形力」には、物理力すなわち力学的作用のほか、音響・光・電気・熱などのエネルギー作用も有形力に含まれ、本問のような行為も、不法に空気を強烈に振動させてその振動力を人体に作用させるという意味で、暴行になり得る(最判昭29.8.20刑集8・8・1277、研修教材・三訂刑法各論(その1)17ページ)。
⑵ Aは、Bに対する殺人の予備行為を行い、更に進んでBに対する殺人の実行行為に着手し、Bを殺害した。この場合、Aの殺人予備罪は殺人既遂罪に吸収される。
(○) そのとおり、殺人予備罪は、殺人既遂罪に吸収される(不可罰的事前行為。研修教材・三訂刑法各論(その1)8ページ)。
⑶ Aは、追死の意思がないのに、Bを欺き、BにAが追死するものと誤信させて自殺を決意させ、あらかじめ買い求めてあった毒薬をBに与えて、これをえん下させてBを死亡させた。この場合、もともとBにAが追死しない限り自殺する意思がなかったとしても、Aには殺人罪は成立せず、自殺関与罪が成立する。
(✕) 被害者が本質的事項について欺罔され真意に添わない重大な瑕疵ある意思に基づいて自殺する場合は、自殺関与罪でなく、殺人罪の間接正犯を認めるべきである(研修教材・三訂刑法各論(その1)5、11ページ)。判例(最判昭33.11.21刑集12・15・3519)は、本問同様の事案で、殺人罪の成立を認めた。
⑷ Aは、Bを雇用し、自宅に引き取って同居させていたが、Bがインフルエンザに感染すると突然解雇し、降雪中で寒気が激しかったにもかかわらず、即時強制的に自宅から戸外に退去させた。この場合、Aに保護責任者遺棄罪が成立することはない。
(✕) 雇主と同居の雇人との間で、雇人が病気にかかった際には雇主がこれを保護するという黙契がある場合には、雇主には雇人に対する保護義務があるとされる。判例は、前述のような黙契がある本問同様の事案において、雇主に保護責任者遺棄罪の成立を認めた(大判大8.8.30刑録25・963、研修教材・三訂刑法各論(その1)50~52ページ)。
⑸ 共犯関係にないA及びBの暴行によって傷害結果が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生した事案において、検察官により、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有すること及び同一の機会に行われたことが証明された。この場合、A及びBは、刑法207条により、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害についてだけでなく更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負う。
(○) そのとおり。判例(最決平28.3.24刑集70・3・1)は、本問同様の事案において、設問のように判示した(研修教材・三訂刑法各論(その1)28、29ページ)。
第14問
詐欺及び恐喝の罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、B銀行C支店に開設した自らの預金口座の通帳の記載から、入金される予定のないD株式会社からの75万円の誤った振込みがあり、これにより通帳の残高が75万円となったことを知ったが、これを自己の借金の返済に充てようと考え、前記C支店において、窓口係員に対し、誤った振込みがあった旨を告げることなく、75万円の払戻しを請求し、同係員から即時に現金75万円の交付を受けた。この場合、Aには、B銀行C支店に対する詐欺罪が成立する。
(○) そのとおり。判例(最決平15.3.12刑集57・3・322)は、「銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。」旨判示し、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立するとした(研修教材・三訂刑法各論(その1)209ページ)。
⑵ Aは、タクシーに乗車したが、目的地で停車後、所持金がないことに気が付き、運転手の隙を見て逃走し、運賃の支払を免れた。この場合、Aには、タクシー運賃支払を免れた2項詐欺罪が成立することはない。
(○) そのとおり。Aにはタクシー運転手に対する欺く行為がなく、タクシー運転手の財産的処分行為もないので2項詐欺罪は成立しない(研修教材・三訂刑法各論(その1)220ページ)。
⑶ Aは、B宛ての送達書類を廃棄するだけでほかに何らかの利用、処分する意思がないまま、Bになりすまして郵便局員から同書類を受領した。この場合、Aには詐欺罪が成立する。
(✕) 詐欺罪においても不法領得の意思が必要であるとされているところ、本問の事案では不法領得の意思が欠けることから、詐欺罪は成立しない(最決平16.11.30刑集58・8・1005、研修教材・三訂刑法各論(その1)211ページ)。
⑷ Aは、万引きを行ったBに対し、警察官を装って、「取調べの必要があるから盗んだ物を差し出せ。」と虚偽の事実を言い、もしこれに応じなければ直ちに警察に連行するかもしれない態度を示してBを畏怖させ、Bに窃取品を交付させた。この場合、BがAの前記言動に畏怖して窃取品を交付したとしても、AがBに虚偽の事実を言っている以上、恐喝罪が成立することはない。
(✕) 人を欺く行為と恐喝の両手段が併用された場合、詐欺罪、恐喝罪のいずれが成立するのかについては、財物交付(処分行為)の理由・原因に着目すべきと解される。判例(最判昭24.2.8刑集3・2・83ほか)は、本問同様の事案において、恐喝罪の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その1)232、233ページ)。
⑸ Aは、Bに対し3万円を貸していたが、Bが期限になっても3万円を返済しないことから、Bを脅迫して同3万円分を含む6万円を交付させた。この場合、Aの前記行為が権利行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱じていれば、Aには、6万円全額について恐喝罪が成立する。
(○) そのとおり。判例(最判昭30.10.14刑集9・11・2173)は、本問同様の事案において、社会通念上忍容しなければならない程度を超えた債権者の行為につき、交付を受けた金額全額についての恐喝罪の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その1)154ページ)。
第15問
偽造の罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bの依頼により、Bになりすまして、私立C大学を受験し、同大学の入学試験の答案を、B名義で署名の上作成した。この場合、Aには有印私文書偽造罪が成立する。
(○) そのとおり。判例(最決平6.11.29刑集48・7・453)は、私立大学の入学試験の答案につき、「本件人学試験の答案は、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙に記載する文書であり、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであって、志願者の学力の証明に関するものであることから、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書に当たる。」と判示し、本問同様の事案で、私文書偽造罪の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その2)99ページ)。
⑵ 弁護士資格を有しないAは、自分と同姓同名の弁護士が実在することを利用して、土地調査の依頼を受けた者から弁護士報酬を受けるために、経過報告書及び報酬請求書等の書面に弁護士の肩書を付した上で「A」と署名をした。この場合、Aに私文書偽造罪が成立することはない。
(✕) 判例(最決平5.10.5刑集47.8.7)は、本件同様の事案で、「本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式・内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、……弁護士会に所属する弁護士であって、弁護士資格を有しない被告人とは別の人格の者であることは明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者との人格の同一性に齟齬を生じさせたと言うべき」として、私文書偽造罪の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その2)69、70ページ)。
⑶ 文書作成権限を有する公務員Aが内容虚偽の文書を作成した。この場合、Aが名義を冒用していない以上、現行法上犯罪が成立することはない。
(✕) 虚偽公文書作成等罪(刑法156条)が成立し得る(最決昭33.4.11刑集12・5・886、研修教材・三訂刑法各論(その2)75、87、88ページ)。
⑷ Aは稼働先の経理担当者Bから備品購入に関する領収書のコピーの提出を求められた。Aは、手元にあった、個人で商店を営むC発行D宛ての領収書(Cの記名押印あり)を利用し、宛先を「A」と改ざんしたもののコピーを作成して、真正な領収書のコピーとしてBに提出した場合、Aには、有印私文書偽造・同行使罪が成立する。
(○) そのとおり。判例(最判昭51.4.30刑集30・3・453ほか)は、公文書偽造罪の事案において、(公)文書の写し(コピー)が原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められ得る限り、(公)文書に含まれるとし、その場合には、その写しは原本と同ーの意識内容を保有する原本作成名義人を作成名義人とする公文書に当たるとして、公文書偽造罪の成立を認めている(研修教材・三訂刑法各論(その2)67、68ページ)。
⑸ Aが行使の目的で有価証券を偽造した場合、有価証券偽造罪及び私文書偽造罪が成立する。
(✕) 有価証券も権利・義務に関する文書の一種であるが、刑法は、これについて別個に有価証券偽造の罪を設けてその規制の対象としているので、私文書偽造罪にいう文書に含まれず、有価証券偽造罪が成立する場合、私文書偽造罪は成立しない(研修教材・三訂刑法各論(その2)99、100ページ)。
刑事訴訟法
第16問
令状による捜索・差押え・記録命令付差押えに関する次の記述のうち、正しいもの.には○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 捜査機関が捜索差押えの際に、捜索差押許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当しない物について写真を撮影した場合、その写真撮影は、捜索差押えに付随するものであって、検証としての性質を有するものではない。
(✕) 司法警察員が捜索差押えをするに際し、捜索差押許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当しない物について写真を撮影した場合、その写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解され、検証許可状が必要となる。しかし、検証許可状を請求することなく、捜索差押手続の適法性を担保するためその執行状況を写真に撮影し、あるいは、差押物件の証拠価値を保存するため発見された場所、状態においてその物を写真に撮影することは、捜索差押えに附随するため、捜索差押許可状により許容される行為である(最決平2.6.27刑集44・4・385、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)192ページ)。
⑵ 構造上単一のビルを捜索すべき場所としている捜索差押許可状により、同ビルの一部であって、同ビルの管理権者とは別の者が管理する一室を捜索することができる。
(✕) 構造上単一のビルの一部分であっても、独立の管理権に服し一個の住居と認められる場所は、他の部分と区別して特定される必要があり、個別に令状が必要となる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)179、180ページ)。
⑶ 令状の執行に際し、処分を受ける者に令状を示さなければならないのは、執行手続の公正を担保し、執行を受ける側の権利を保護するためである。
(○) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)182、187ページ)。
⑷ 記録命令付差押えは、捜査機関が必要な電磁的記録を差し押さえるに当たり、被処分者がプロバイダ等の協力的なデータ管理者であって、必要な電磁的記録の他の記録媒体への記録等に応じることが予想され、その記録等が適切に行われることが期待できる場合に適した差押えの方法である。
(○) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)175、176ページ)。
⑸ 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて、差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
(○) そのとおり(刑事訴訟法222条1項、110条の2、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)183、184ページ)。
第17問
告訴に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 申告した犯罪事実が十分特定されており、犯人の処罰を求める意思表示もなされているが、犯人が誰であるかの指定を誤って申告すれば、その告訴は無効である。
(✕) 申告する事実は、いかなる犯罪事実を指すのか、特定できる程度のものでなければならないが、犯罪の日時、場所及び態様などについての詳細な申告は必ずしも必要でない。また、申告した事実が特定されていれば、犯人の指定を誤っていても告訴は有効である(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)39ページ)。
⑵ 公務執行妨害罪は、公務を保護法益とするものであるが、暴行を受けた公務員は告訴をすることができる。
(○) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)41ページ)。
⑶ 被害者の法定代理人は、被害者本人の意思に反して被害者本人のした告訴を取り消すことができる。
(✕) 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができるが、被害者の意思に反して被害者本人のした告訴を取り消すことはできない(高松高判昭27.8.30高刑集5・10・1604、東京高判昭31.6.19(いずれも強姦(当時)事件)、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)43ページ)。
⑷ 牽連犯を構成する住居侵入・器物損壊事件において、住居侵入についてのみ告訴がなされた場合、その告訴の効力は、器物損壊には及ばない。
(○) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)47ページ)。
⑸ 親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができないとされているところ(刑事訴訟法235条)、「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する。
(○) そのとおり(最決昭39.11.10刑集18・9・547、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)49ページ)。
第18問
公判手続に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 裁判長は、被告人、証人等が特定の傍聴人の面前では充分な供述をすることができないと思料するときは、被告人、証人等が供述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
(○) そのとおり。公開主義は、裁判の公正を担保し、刑事裁判に対する国民の信頼を保持しようとするものであり、裁判の公正を維持するため、あるいは法廷の秩序を維持するために、特定の傍聴人の傍聴を禁止することは、公開主義に反するものではない。例えば、被告人、証人等が特定の傍聴人の面前では充分な供述をすることができないと思料するときは、裁判長は、供述をする間その傍聴人を退廷させることができる(刑事訴訟規則202条)。以上につき、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)4ページ参照
⑵ 刑事訴訟法は、公判手続における主導的役割を当事者である検察官と被告人に果たさせる当事者主義を採用しており、裁判所の職権による証拠調べ権を認めていない。
(✕) 刑事訴訟法は、第一次的には当事者主義を採用しているが、補充的に職権主義を採用しており、①職権による証拠調べ権(刑事訴訟法298条2項)、②訴因・罰条の追加・変更の命令権(同法312条2項)、③職権による公務所等への照会権(同法279条)などを認めている(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)6ページ)。
⑶ 被告人が公判廷で起訴事実について有罪であることを自認したとしても、それだけで被告人を有罪とすることはできない。
(○) そのとおり。刑事訴訟法は、被告人が公判廷で起訴事実について有罪であることを自認してもそれだけでは有罪とすることができないとして、当事者処分主義を否定している(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項、3項、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)9ページ)。
⑷ 検察官は、冒頭陳述の段階で被告人の前科調書を証拠調べ請求する意思があったとしても、予断排除の原則により、冒頭陳述で被告人の前科関係を述べることはできない。
(✕) 冒頭陳述では、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない(刑事訴訟法296条ただし書)。冒頭陳述で被告人の前科・前歴などを述べることについては、既に証拠調べの段階に入っていて厳密な意味での予断排除の原則の適用はないこと、情状も検察官が「証明すべき事実」に含まれることから、理論上差し支えなく、裁判例も一般にこれを認めている(東京高判35.4.21高刑集13・4・271)。以上につき、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)15、104、105ページ参照
⑸ 公訴提起後、第1回公判期日までの間、勾留に関する処分(勾留、勾留更新、接見禁止等)は、受訴裁判所が行うのが原則である。
(✕) 予断排除の原則により、公訴提起後第1回公判期日までは、勾留に関する処分(勾留、勾留更新、接見禁止、勾留取消し、勾留理由開示、勾留執行停止、保釈等)は、受訴裁判所ではなく、事件の審判に関与しない裁判官が行うのが原則である(刑事訴訟法280条、刑事訴訟規則187条1項ただし書、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)14ページ)。なお、例外として、急速を要する場合(被告人の急病により緊急に勾留の執行停止をする必要があるような場合等)などには、事件の審判に関与すべき裁判官が自ら処分することを妨げないとされている(同規則187条2項ただし書、大コンメンタール刑事訴訟法第二版第5巻426ページ)。
第19問
裁判に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 裁判所は、親告罪において、告訴がないまま起訴されたことが判明した場合、免訴の判決をしなければならない。
(✕) 告訴・告発を要する事件(親告罪)でこれを欠く起訴がなされた場合、刑事訴訟法338条4号により判決で公訴が棄却される(最判昭32.12.24刑集11・14・3371、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)222、223ページ)。
⑵ 裁判所による裁判である決定に対する上訴方法は、準抗告である。
(✕) 決定は「裁判所」の裁判であり、決定に対する上訴方法は抗告である(刑事訴訟法419条)。命令は「裁判官」の裁判であり、命令に対する上訴方法は準抗告である(同法429条)。裁判所のした判決以外の裁判であれば、名称が命令であっても、実質は決定であるので、抗告の対象となる(大コンメンタール刑事訴訟法第三版第9巻713ページ)。また、1人の裁判官が行う裁判の中には、決定であるか命令であるかはっきりしないものがあるが、その場合は、「裁判所」として行う裁判か、「裁判官」として行う裁判かで、決定か命令かを判断する。以上につき、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)205、206ページ参照
⑶ 訴因が予備的又は択ー的に掲げられている場合、裁判所は、そのいずれかの訴因について有罪判決をしたときは、他の訴因については無罪の言渡しをしなければならない。
(✕) 最判昭29.3.23刑集8・3・305は、「主たる訴因と予備的訴因のある場合に、予備的訴因につき有罪を認定したときは、主文において主たる訴因につき無罪を言渡すべきものでないことは勿論、理由中においても、かならずしもこれに対する判断を明示することを要するものではない」とした(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)218ページ)。
⑷ 確定判決を経た事件について再起訴がなされた場合は、免訴の裁判によって訴訟係属が打ち切られる。
(○) そのとおり。免訴の裁判(刑事訴訟法337条)は、実体的訴訟条件を欠く場合に判決で成される形式裁判である。確定判決のある事件について再起訴がなされた場合は、実体審理ができないから、「免訴」の裁判によって訴訟係属が打ち切られる(同条1号)。以上につき、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)211、219、220ページ参照
⑸ 土地管轄のない事件について公訴提起を受けた裁判所は、当該事件の実体審理をすることができないことが明らかであるから、被告人の申立てがなくても判決で管轄違いの言渡しをすることができる。
(✕) 刑事訴訟法331条。土地管轄は、主として被告人の防御の便宜のためのものであることから、被告人が異議なく審理に応じた場合には、その裁判所に土地管轄が創設される(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)213ページ)。
第20問
証拠に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 刑事訴訟法316条の38第1項による被害者参加人の意見陳述は、情状に関する事実認定のための証拠とすることができる。
(✕) 刑事訴訟法316条の38第4項。なお、同法292条の2による被害者等の意見陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできないが、情状事実として量刑の資料とすることはできる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)162、163ページ)。
⑵ 収集手続に違法がある証拠であっても、証拠能力が認められることがある。
(○) そのとおり。違法収集証拠については、違法の程度が重大でなく、証拠として許容しても将来における違法捜査抑制の見地から問題がないと認められる場合には証拠能力を肯定しているのが判例の基本的立場である(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)28ページ)。
⑶ 任意性が認められない被告人の自白を内容とする供述調書は、被告人の公判における供述の証明力を争うためであっても、証拠とすることができない。
(○) そのとおり。刑事訴訟法328条は伝聞法則との関係で設けられた規定であり、任意性のない証拠あるいは任意性に疑いのある証拠については規定していない。不任意自白の証拠能力の否定は絶対的なものと解されており、そのような証拠は同条の証拠となし得ない(東京高判昭26.7.27高刑集4・13・1715、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)107、108、201ページ、研修904号71ページ)。
⑷ 補強法則に関する刑事訴訟法319条2項の「自白」には共犯者の自白は含まれない。
(○) そのとおり。判例は、補強法則について定めた憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者・共同被告人の自白は含まれず、共犯者の自白は補強証拠を要しないとしており(最判昭33.5.28刑集12・8・1718等)、同条項を受けて規定された刑事訴訟法319条2項の「自白」にも共犯者の自白は含まれない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)127ページ、研修906号63、64ページ)。
⑸ 刑事訴訟法227条の請求により実施された第1回公判期日前の証人尋問の結果が記載された証人尋問調書は、同法321条2項の被告人以外の者の公判準備における供述を録取した書面として証拠能力が認められる。
(✕) 第1回公判期日前の証人尋問調書は、刑事訴訟法321条1項1号の裁判官面前調書に該当し、同号の要件を満たす場合に証拠能力が認められる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)152ページ)。なお、証人等を公判期日外で尋問した場合(同法158条、281条)に作成される証人尋問調書等が同法321条2項前段該当書面である(同164、165ページ)。
証拠品事務
第21問
証拠品の受入れに関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 証拠品事務規程における「所属課長等」には、統括捜査官は含まれない。
(○) そのとおり。証拠品事務規程5条において「所属課長又は検務監理官、統括検務官若しくは検務専門官(以下「所属課長等」という。)」とされていることから、統括捜査官は含まれない。また、検察庁事務章程22条4項において、統括捜査官の職務は、「捜査及び公判に関する事務をつかさどる。」とされ、検務事務が含まれていないことからも明らかである(研修912号55ページ)。
⑵ 領置票の品名欄には、証拠金品総目録に記載された品名をそのまま記入することで足りる。
(✕) 証拠金品総目録に記載してある証拠品の品名だけでは特定に不十分であると考えられるときは、同目録の記載をそのまま領置票に記入することなく、証拠品担当事務官は、証拠品を見分した上、適宜特定に必要な事項を補足して記入する必要がある(研修教材・九訂証拠品事務解説21ページ、研修912号55、56ページ)。
⑶ 領置票の品名・数量欄等を訂正する場合は、取扱者が訂正印を押印するだけでなく、検察官の押印を受ける必要がある。
(✕) 領置票の品名・数最欄等を訂正する場合は、検察官ではなく、所属課長等の押印を受けるべきとされている(研修教材・九訂証拠品事務解説21ページ、研修912号56ページ)。
⑷ 被疑者A及び被疑者Bによる傷害事件で、司法警察員から一件記録と共に、A及びBがそれぞれ犯行に使用した凶器が証拠品として送致されたときは、被疑者ごとに領置票を作成する。
(✕) 証拠品事務規程6条において「領置票又は裁判執行領置票の進行番号(以下「領置番号」という。)は、それぞれ事件記録又は裁判の執行に係る関係書類ごとに進行し、暦年ごとに改める。」とされていることから、一件記録で送致を受けた場合は、被疑者が複数いる事件であっても領置票は一つ作成すれば足りる(研修教材・九訂証拠品事務解説22ページ、研修912号57ページ)。
⑸ 仮還付をした証拠品を再提出させるときは、任意提出書を徴する。
(✕) 仮還付をした証拠品は、いまだ押収が継続しているものと解されるので、これを再提出させる場合には、改めて刑事訴訟法上の差押え又は領置の手続は要しないことから、仮還付証拠品提出書(様式第8号)を徴する(証拠品事務規程12条、研修教材・九訂証拠品事務解説26ページ、研修914号43ページ)。
第22問
証拠品の保管に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 証拠品は、刑事裁判の重要な証明資料又は裁判の執行に関して必要な資料であり、代替性のないものであることから、その保管に際しては、滅失、変質等の防止はもちろんのこと、可能な限り押収時の状態を損なわないよう配意し、その証拠価値の保全に努めなければならない。
(○) そのとおり。証拠品事務規程2条において「証拠品を取り扱う者は、「征拠品が刑事裁判の重要な証明資料又は裁判の執行に関して必要な資料であることに鑑み、常に旺盛な責任感をもって、紛失し、滅失し、毀損し、又は変質する等しないように注意し、その証拠価値の保全に努めなければならない。」とされている(刑事訴訟規則98条、研修教材・九訂証拠品事務解説29ページ、研修914号45、46ページ)。
⑵ 証拠品担当事務官が証拠品の保管に当たり、課せられた注意義務を尽くさないで証拠品を違法に破損して所有者に損害を与えたとしても、証拠品の保管は押収という公権力の行使に基づくものであることから、国は国家賠償法に基づき損害を賠償する必要はない。
(✕) 証拠品の保管者が、「善良な管理者の注意義務」を尽くさないで証拠品を違法に紛失、滅失、毀損等して所有者等に損害を与えたときは、国は国家賠償法に基づき、損害賠償の責任を負うこととなる(国家賠償法1条、研修教材・九訂証拠品事務解説29ページ、研修914号45ページ)。
⑶ 押収物である貴重品のうち、破損が著しく経済的な価値がないものは、特殊証拠品として保管する必要はなく、一般証拠品として取り扱う。
(○) そのとおり。本来貴重品として取り扱うべきものであっても、破損等が著しく、経済的な価値がないと認められるものは、一般証拠品として取り扱う(研修教材・九訂証拠品事務解説34ページ、研修914号48ページ)。
⑷ 換価代金は、特殊証拠品として、金庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠ができる設備に収納して保管しなければならない。
(✕) 換価代金の出納保管は歳入歳出外現金出納官吏が行うこととされており、換価代金はできるだけ速やかに日本銀行に払い込まなければならない(証拠品事務規程18条、研修教材・九訂証拠品事務解説35ページ、研修914号47ページ)。
⑸ 中止処分に付された事件の証拠品は、中止処分後、これを被押収者に還付することはできない。
(✕) 中止処分に付された事件の証拠品は、原則として公訴の時効が完成するまで保管することとなるが、押収の必要のない物を還付又は仮還付し、運搬又は保管に不便な物を保管委託し、危険を生ずるおそれがある物を廃棄し、没収することのできる証拠品で滅失若しくは破損のおそれがある物又は保管に不便な物を換価処分することは可能である(証拠品事務規程59条1項ただし書、研修教材・九訂証拠品事務解説124ページ、研修914号54ページ)。
第23問
証拠品の保管委託に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 運搬又は保管に不便な押収物は、所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができ、その法律的性格は、公法上の一種の寄託契約であると解されている。
(○) そのとおり(民法657~666条、商法595~598条、刑事訴訟法222条1項、513条1項、121条1項等、研修教材・九訂証拠品事務解説140ページ、研修914号51ページ)。
⑵ 甲地方検察庁の検察官から証拠品を保管委託のまま乙地方検察庁の検察官に事件の送致があったときは、乙地方検察庁の証拠品担当事務官は、事件記録中の保管請書の内容を調査した上、保管委託者が乙地方検察庁の検察官に変更されたことを知らせるため、保管者に対し保管委託通知書を送付する。
(○) そのとおり(証拠品事務規程68条2項、69条2項、研修教材・九訂証拠品事務解説135ページ、研修914号49ページ)。
⑶ 検察官が保管中の証拠品を保管委託したときは、検察官の保管責任は軽減され、自己の財産に対するのと同一の注意義務を負うにとどまる。
(✕) 証拠品を保管委託しても、押収の効力や、委託者の管理責任は全く変わらず、委託者は引き続き善良な管理者の注意義務を負う(研修教材・九訂証拠品事務解説140、141ページ、研修914号51ページ)。
⑷ 受託者の保管責任は、その保管委託が有償又は無償のいずれを問わず、自己の財産に対するのと同一の注意義務で足りる。
(✕) 受託者の保管責任は、その保管委託が有償の場合は「善良な管理者の注意義務」が、無償の場合は「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で足りる。ただし、無償委託の場合であっても、受託者が商人で、しかもその証拠品の保管委託を受けたことがその営業の範囲内に属すると認められるときは「善良な管理者の注意義務」が要求される(研修教材・九訂証拠品事務解説142ページ、研修914号53、54ページ)。
⑸ 検察官は、証拠品を保管委託したときは、その保管委託が有償又は無償のいずれを問わず、保管状況を確認する必要がある。
(○) そのとおり。証拠品を保管委託した場合は、有償、無償にかかわらず、検察官は、証拠品担当事務官に当該証拠品の保管状況を確認させる必要がある(証拠品事務規程72条、研修教材・九訂証拠品事務解説143ページ、研修914号52、53ページ)。
第24問
証拠品の処分に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 没収物は、刑事訴訟法496条により検察官がこれを処分することとされているため、その具体的な処分方法は、刑事訴訟規則に定められている。
(✕) 没収物の具体的な処分方法は証拠品事務規程に定められている(証拠品事務規程29~34条、研修教材・九訂証拠品事務解説49~72ページ、研修916号68~72ページ)。
⑵ 一つの領置票で同一日に同一の処分命令を大量になすべきときは、符号の連続する証拠品について検察官の処分命令印を領置票の各葉ごとに一括して受けることができる。
(✕) たとえ大量の証拠品について、同一処分がなされる場合であっても、処分事務の正当性を保持等するため、検察官において、証拠品担当事務官による処分命令案が相当か否か当該証拠品につき1点ずつ確認をした上で、その都度処分命令印を押印することが必要である(研修教材・九訂証拠品事務解説41ページ、研修916号65、66ページ)。
⑶ 没収物の廃棄を専門の業者に依頼したときは、依頼したことをもって没収領置票を処分済として処理することはできない。
(○) そのとおり。没収物の処分については、検察官が執行機関であって執行指揮機関ではないことから、業者に依頼して引き渡しただけでは処分は完了していないので、没収領置票を処分済とすることはできず、廃棄処分を終了した旨の回答を得て初めて領置票を処分済として処理する(研修教材・九訂証拠品事務解説54、55ページ、研修917号74、75ページ)。
⑷ 所有権放棄や還付公告期間満了により、その所有権が国庫に帰属した証拠品の処分は、没収物の処分に関する規定が準用される。
(○) そのとおり(証拠品事務規程45、53条、研修教材・九訂証拠品事務解説90、116ページ、研修917号71ベージ)。
⑸ 検察官は、仮出しした立会封金を開封した後、証拠品担当事務官に返還するときは、封筒に開封した旨を記入して押印し、又は立会封金開封証明書を作成して添付する。
(○) そのとおり(証拠品事務規程23条、研修教材・九訂証拠品事務解説43ページ、研修916号67ページ)。
第25問
証拠品の還付に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 証拠品の所有者が所有権放棄の意思表示をした後、その撤回を申し出ても、意思表示が錯誤に基づくなど、特段の事由がない限り、所有権放棄の撤回は許されない。
(○) そのとおり。判例は「領置の際「被害者に返して下さい。」または「私はいりません」もしくは「いりません」と申し出ているものであって、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証跡もなく、また、本件のような場合、その申出の撤回を許すべきではない」としている(最決昭43.2.29裁判集(刑事)166・305、研修教材・九訂証拠品事務解説87ベージ、研修919号84、85ページ)。
⑵ 受還付人が証拠品の還付を拒否しているときには、還付公告によることができる。
(✕) 刑事訴訟法499条1項は、受還付人の所在不明又はその他の事由によって押収物を還付することができない場合を公告事由としているが、「その他の事由」とは、受還付人の身許不明等の場合であり、受還付人が確定し、かつ、その所在も判明している場合には、受領を拒否しているからといって「その他の事由」には該当しない(新版注釈刑事訴訟法7巻373ページ、研修教材・九訂証拠品事務解説109ページ、研修919号97、98ページ)。
⑶ 証拠品の任意提出書に、単に「適法に処分してください。」と記載されているときは、所有権放棄の意思があったものとすることはできない。
(○) そのとおり。ただし、「私は要りません。」又は「要りません。」と記載してあるときは、所有権放棄とみて差し支えない(研修教材・九訂証拠品事務解説88ページ、研修919号83ページ)。
⑷ 還付公告について、掲示公告と官報公告を併用し、掲示場における14日間の掲示の末日と官報に掲載された日が異なった場合は、証拠品の早期処分を実現するため、いずれか早い方の日の翌日を起算日として6か月の期間を計算する。
(✕) 受還付人の権利を保護する観点から、いずれか遅い方の日の翌日を起算日として6か月の期間を計算する(研修教材・九訂証拠品事務解説112ページ、研修919号99、100ページ)。
⑸ 還付公告期間が満了した後に還付の請求があったときは、証拠品の処分前であれば、請求に応じなければならない。
(✕) 公告期間の満了によって押収物が国庫に帰属しており、公告期間の満了後、処分前に受還付人が判明し、同人から還付の請求があつても、没収物に関する刑事訴訟法497条を類推適用する余地はなく、還付する必要はない(研修教材・九訂証拠品事務解説116ページ、研修919号100ページ)。