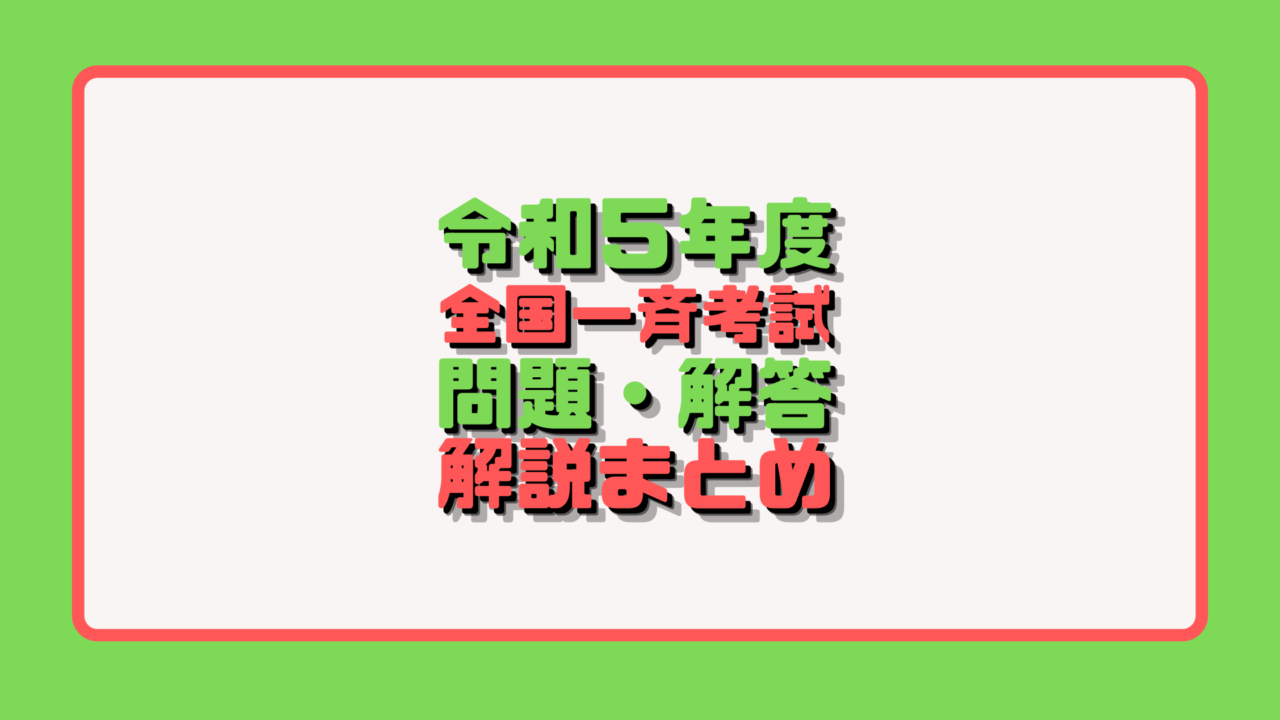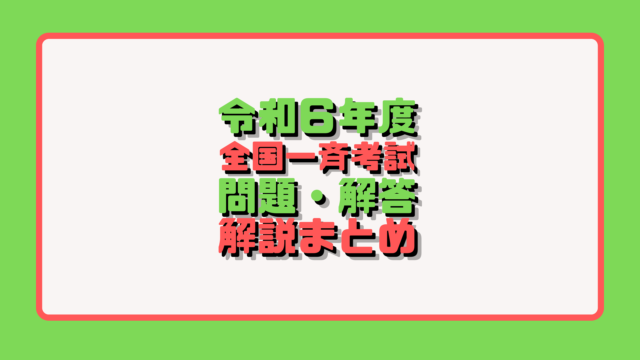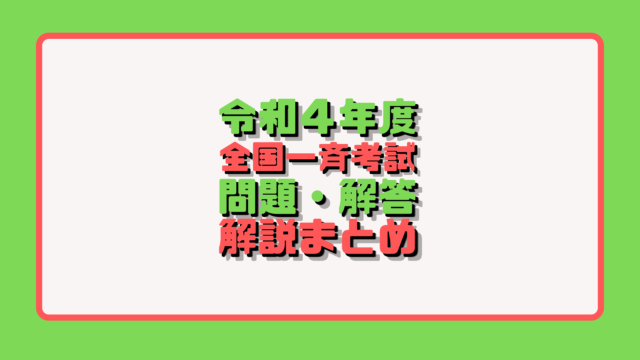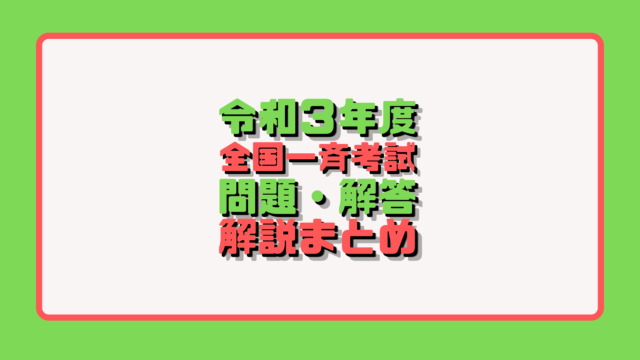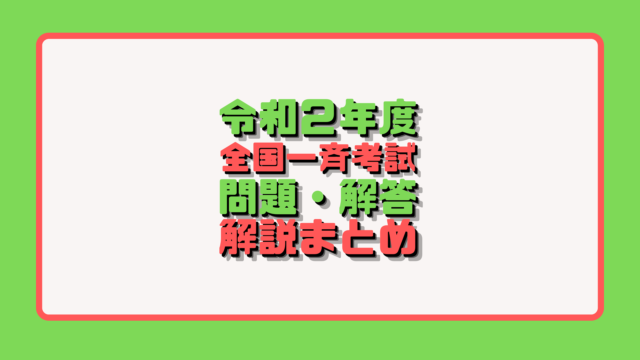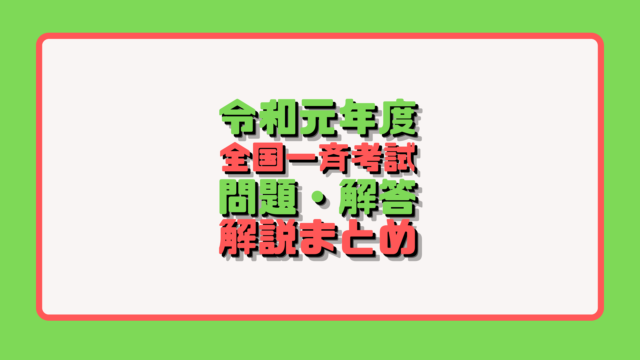憲法・検察庁法
第1問
法の下の平等に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法14条1項にいう「法の下に平等」は、法の適用の平等を意味しており、法の内容の平等の意味はもたない。
(✕) 法の遮用の平等のみで平等が保障されるわけではなく、適用される法それ自体が不平等な内容のものであれば、その適用の結果は常に不平等になることは免れないので、憲法14条1項の「法の下に平等」は、法の適用の平等のみならず、立法の準則として法の定立そのものにおける平等(法の内容の平等)をも意味すると解されている(研修教材・六訂憲法82ページ)。
⑵ 憲法94条は、地方公共団体に条例制定権を認めているが、条例で定められた罰則について地域によって差異が生じるときは、当該条例はその地域差を理由に憲法14条に違反するものとなる。
(✕) 憲法が各地方公共団体の条例制定権を定める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところである。地方公共団体が特定の行為の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、地域差の故をもって違憲ということはできない(最大判33.10.15刑集12・14・3305、研修教材・六訂憲法84ページ)。
⑶ 刑事事件において、被告人自身に対する警察の捜査が刑事訴訟法にのっとり適正に行われ、被告人が、その思想、信条、社会的身分又は門地などを理由に、一般の場合に比べ捜査上不当に不利益に取り扱われたものでないときは、仮に、当該被告入と対向的な共犯関係に立つ疑いのある者の一部が、警察段階の捜査において不当に有利な取扱いを受け、事実上刑事訴追を免れるという事実があったとしても、そのために被告人自身に対する捜査手続が憲法14条に違反することになるものではない。
(○) そのとおり。差別されるとは、一般的基準に反して不利益な扱いをされることであり、一般的基準に従って処遇された結果、ほかにより有利な扱いをされた者がいたとしても、「法の下の平等」に反する不利益な処分とはいえない。公職選挙法違反(受供与、受供応など)被告事件において、最喬裁は、問題文と同様の判断を示した(最判昭56.6.26刑集35・4・426、研修教材・六訂憲法82、84、85ページ)。
⑷ 憲法14条1項に列挙されている「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、例示列挙であり、これら以外を理由とする場合であっても、不合理な差別的取扱いは同条違反となる。
(○) そのとおり(研修教材・六訂憲法85ページ)。
⑸ 憲法14条1項が定める法の下の平等は、選挙人の資格について、人種、信条、性別、社会的身分、門地等による差別を受けずに平等に取り扱われるという普通選挙を要請しているのみでなく、選挙人の投票価値が平等に取り扱われることをも要請している。
(○) そのとおり。憲法14条1項は、普通選挙とともに、選挙人の投票価値が平等に取り扱われる平等選挙も要請している(最大判昭51.4.14民集30・3・223、研修教材・六訂憲法216ページ)。
第2問
精神的自由権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法19条による思想及び良心の自由の保障は、絶対的なものであるから、たとえ民主主義を否定する思想であっても、それが内心にとどまる限り、制限することはできない。
(○) そのとおり(研修教材・六訂憲法97ページ)。
⑵ 判例は、報道機関の報道の自由及び報道のための取材の自由について、いずれも憲法21条によって保障されるとしている。
(✕) 報道機関の報道の自由と取材の自由につき、最高裁は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」とする一方、報道のための取材の自由については、「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」と判示しているにとどまり、憲法21条により保障されるとはしていない(最大決昭44.11.26刑集23・11・1490、研修教材・六訂憲法115、116ページ)。
⑶ 憲法21条1項は言論の自由を無制限に保障しているものではないから、他人の行為に関して無根の事実を公表し、その名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であって、たとえ、かつて公職にあった者を批判するためになしたものであったとしても、言論の自由の範囲内に属するとは認められない。
(○) そのとおり(最大判昭31.7.4民集10・7・785、研修教材・六訂憲法120ページ。
⑷ 憲法21条1項は、結社の自由を保障しているが、犯罪を行うことを目的とする結社は、同条による保障の対象とはならない。
(○) そのとおり(研修教材・六訂憲法113、114ページ)。
⑸ 憲法21条2項前段が定める検閲の禁止は、絶対的なものではなく、わいせつ文書など善良な風俗に反する表現については、検閲によって事前に規制することが許される。
(✕) 憲法21条2項前段は、検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解され(最大判昭59.12.12集民143・305)、物理的力を内包する集団行動による表現は別として、言論・出版等による表現は、たとえその結果善良の風俗に反すると認められるものであっても、検閲によって事前に規制することは許されない。もっとも、表現の事後において司法権による規制(犯罪を構成する場合にこれを処罰し、刑事訴訟法の定める手続によって証拠物として押収するなど)は認められる(研修教材・六訂憲法128、129ページ)。
第3問
国会に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 両議院の議員は、国会の会期中に、院外で現行犯逮捕されることはない。
(✕) 議員の不逮捕特権は、「法律の定める場合」(憲法50条)には認められない。院外における現行犯の場合(国会法33条、100条1項)と所属議院の許諾のある場合は例外である(研修教材・六訂憲法233ページ)。
⑵ 両議院の議員には、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないという免責特権が保障されているところ、議院主催の地方公聴会における発言は、議事堂外での活動なので、免責されることはない。
(✕) 憲法51条の「議院で行った」というのは、議院の活動として職務上行ったという意味であるから、議事堂外であっても、議院の活動と見られるもの(例えば、議院主催の地方公聴会における発言)は、これに含まれる(研修教材・六訂憲法234ページ)。
⑶ 緊急集会中の参議院は、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名など国会の全ての権能を行うことができる。
(✕) 参議院の緊急集会は、衆鏃院の解散による国会の閉会期間中、国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、内閣の求めにより集会されるものである(憲法54条2項ただし書、国会法99条)。緊急集会中の参議院は、法律案の議決、予算の議決、条約の承認など国会の全ての権能を行うことができる(ただし、臨時のものであり、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う(憲法54条3項)。)。
しかし、内閣総理大臣の指名については、総選挙後、新たに国会が召集されたときに、内閣が総辞職し(憲法70条)、国会が新たに内閣総理大臣を指名するのであるから(憲法67条)、緊急集会において行うことはできない(研修教材・六訂憲法237、238ページ)。
⑷ 両院協議会は、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名に際して、衆議院と参議院が対立した場合に必ず開かれる。
(✕) 両院協議会は、予算の議決、条約の承認、内開総理大臣の指名に際して両院が対立した場合には必ず開かれるが(憲法60条2項、61条、67条2項)、法律案の議決を巡って対立が生じた場合に協議会を開くかどうかは、衆議院の判断に委ねられている(憲法59条3項)。
⑸ 衆議院の解散権は内閣に専属しており、衆議院の自律的解散は認められていない。
(○) 衆議院の解散は内閣と議会が対立した場合や、その他重要な政治上の問題に当面した場合に、主権者である国民の意思を問うことを目的とし、また、議会側の内閣不信任決議権に対し、内閣と議会との均衡を維持するための機能も果たしている(憲法69条)。解散権は内閤に専属し、天皇は、国事行為として、衆議院の解散を行うにすぎない(憲法7条3号)。衆議院の自律的解散は認められていない(研修教材・六訂憲法236、237ページ)。
第4問
内閣に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法65条は、「行政権は、内閣に属する。」と規定するのみで、「唯一の」(憲法41条)とか「すべて」(憲法76条1項)といった限定文言がないため、内閣から全く独立した行政機関を設置することも許される。
(✕) 内関から全く独立した行政機関を承認することは、議院内閣制による民主的コントロールを潜脱させることになるとともに、内閣に指揮監督権の及ばないものの行政活動についで責任を負わせ、責任の原理に反することになり、許されない。独立行政委員会である人事院は、「内閣の所轄の下に」(国家公務員法3条1項)置かれているし、国家公安委員会も「内閣総理大臣の所轄の下に」(警察法4条1項)置かれており、公正取引委員会も「内閣総理大臣の所轄に属する」(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27条2項)のである(研修教材・六訂憲法247ページ)。
⑵ 内閣総理大臣が衆議院の解散により議員たる地位を失ったときは、内閣総理大臣としての地位を失うことになり、内閣は直ちに総辞職しなければならない。
(✕) 内闊総理大臣が国会識員であることは在職要件であり、除名などにより議員たる地位を失ったときは、内閣総理大臣としての地位を失い、内閣は総辞職しなければならないことになる(憲法70条。研修教材・六訂憲法250ページ)。衆議院解散の場合は、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合に総辞職する(同条)。
⑶ 「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出」(憲法72条)することができ、「議案」には、条約の締結についての承認を求める議案(憲法73条3号)及び予算案(憲法73条5号)は含まれるが、法律案は、憲法上の規定がないので、含まれない。
(✕) 憲法72条の「議案」には、法律案も含まれる(内閣法5条参照。研修教材・六訂憲法250ページ)。
⑷ 政令(憲法73条6号)は、法律を施行するために必要な細則を定める執行命令か、法律から具体的に委任された事項を定める委任命令に限られる。
(○) そのとおり(研修教材・六訂憲法255ページ)。
⑸ 内閣総理大臣は、内閣の首長であり、他の国務大臣に対する命令権を有している。
(✕) 内閣総理大臣は、内閣の首長であり(憲法66条1項)、他の国務大臣の任免権を有するが(憲法68条)、他の国務大臣に対して命令権を持っているわけではない(研修教材・六訂憲法249、250ページ)。
第5問
検察庁法に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 区検察庁検察官事務取扱検察事務官が窃盗事件を捜査中、当該事案が詐欺罪に該当することが判明しても、そのまま区検察庁検察官事務取扱検察事務官として捜査を継続することは可能である。
(○) そのとおり。捜査については、その性質上、これを完結してみなければ、いかなる罪名に当たる犯罪であるか明らかにならないことが多いので、検察庁法6条において、いかなる犯罪についても捜査をすることができると定めて、事物管轄の制限を解除している。区検察庁検察官事務取扱検察事務官は、その所属する区検察庁の検察官の権限を有していることから、対象の事案が詐欺罪に該当する場合であっても、捜査を行うことは可能である。捜査を遂げた後、これを起訴する場合は、詐欺罪について事物管轄を有する地方裁判所に対応する地方検察庁の検察官に移送した上で行う必要がある(研修教材・七訂検察庁法40、88ページ)。
⑵ 区検察庁検察官事務取扱検察事務官は、検事正から、検察庁法12条に基づいて、地方検察庁検察官事務取扱を命ぜられれば、その地方検察庁に対応する地方裁判所の公判に立ち会うことができる。
(✕) 検察庁法附則2条(令和3年法律第61号による改正前の附則36条)は、「法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。」と定めており、事務引取移転権をもってしても、地方検察庁以上の検察庁の検察官の事務を取り扱わせることはできない(研修教材・七訂検察庁法88ページ)。
⑶ 副検事は、所属する区検察庁を管轄する高等検察庁の検事長から、検察庁法12条に基づいて、高等検察庁検察官事務取扱を命ぜられれば、その高等検察庁に対応する高等裁判所の公判に立ち会うことができる。
(○) そのとおり。検察庁の長は、指揮監督する検察官の事務を、指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる事務引取移転権を有している。検察庁法16条2項において、「副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。」と定められているが、事務引取移転権によって、地方検察庁以上の検察庁の事務を取り扱わせることもできる(研修教材・七訂検察庁法30、33ページ)。
⑷ 検察庁の長は、その権限を指揮監督する検察官に委任することができ、区検察庁の長である上席検察官もこの権限委任をすることができる。
(✕) 検事総長、検事長、検事正は、その指揮監督する検察官に対し、権限委任をすることができるが、区検察庁の長には、この権限はない(研修教材・七訂検察庁法60、61ページ)。
⑸ 地方検察庁の総務課に所属し、行政職俸給表㈠による俸給を受けている検察事務官も、犯罪の捜査に当たる権限を有している。
(○) そのとおり。検察事務官の権限は、所属部署により左右されるものではないし、行政職俸給表㈠の適用により捜査権限が区別されることもない(研修教材・七訂検察庁法86ページ)。
民法(総則・物権)
第6問
未成年者に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 未成年者Aは、法定代理人Bから目的を定めずに渡された小遣い銭を貯めていたところ、その金額が10万円に達したことから、Bの同意を得ることなく、かねてから欲しいと考えていた腕時計をCから10万円で購入する契約を締結した。この場合、Bは、AがCとの間で締結した契約を取り消すことができない。
(○) 法定代理人から処分を許された財産については、末成年者は、法定代理人の同意を得ずに処分することができる。小遣い銭として目的を定めないで処分を許された財産は、これに該当する(民法5条3項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)24ページ)。
⑵ 未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得た上で、知人であるCに金銭を貸し付けた。その後、Aが、Bの同意を得ることなく、同貸金債権についてCから弁済を受けた場合、Bは、Aのこの行為を取り消すことはできない。
(✕) 未成年者が単に利益を得、又は義務を免れる法律行為については、法定代理人の同意を得ずにすることができる(民法5条1項ただし書)が、債権について弁済を受けることは、債権を失うことになるので、これには該当せず、取り消すことができる(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)24ページ)。
⑶ 未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得ずに、Cとの間で、Cから高級腕時計を購入する契約を締結した。その後、Aが未成年者であることを知ったCは、Aが未成年者であるうちに、Bに対し、1か月の期間を定めて、その期間内に同契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合、Bが1か月以内に確答を発しないときは、Bは同契約を追認したものとみなされる。
(○) そのとおり。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、法定代理人がその期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされる(民法20条2項、同条1項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)43ページ)。
⑷ 未成年者が契約の相手方に対して、自己が成年者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、相手方は民法21条によって保護されるので、相手方には、詐欺による意思表示として民法96条による取消しをする余地はない。
(✕) 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、相手方は、民法21条によって保護されるほか、詐欺による意思表示として民法96条による取消しもし得る(研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)44ページ)。
⑸ 末成年者Aは、法定代理人Bに無断で、Cから高級腕時計を購入する契約を締結した際、Cに対して、自己が未成年者であることを告げなかった。この場合、Aの他の言動等とあいまって、Aが成年者であるとCを誤信させ、又はその誤信を強めたものと認められない限り、単に未成年者であることを黙っていたことのみをもって、Aが詐術を用いたとしてA及びBの取消権が否定されるものではない。
(○) 制限行為能力者であることを黙秘することと民法21条にいう「詐術」との関係につき、判例は、「無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが、無能力者の他の言動などとあいまって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たるというべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもって、詐術に当たるとするのは相当ではない」旨判示している(最判昭44.2.13民集23・2・291、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)44ページ)。
第7問
時効に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 金銭債権の債務者は、時効の利益を受けることを潔しとしない場合には、当該債権の消滅時効が完成する前であっても、時効完成により受ける利益を放棄することができる。
(✕) 時効は公益的制度であること、債権者が債務者の弱みにつけ込んで強制的に放棄を約束させるのを防ぐ必要があることなどから、債務者の意思にかかわらず、時効完成前に時効の利益を放棄することは許されない(民法146条、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)197、198ページ)。
⑵ 時効の完成による権利義務得喪の効力は、時効期間の起算日に遡るが、時効によって消滅した債権がその消滅以前に他の債権との相殺に適するようになっていた場合には、時効完成に係る債権の債権者は、これを自働債権として相殺することができる。
(○) そのとおり。時効完成による権利義務得喪の効力には遡及効がある(民法144条)が、その例外として、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(民法508条、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)193、194ページ)。
⑶ 所有権に基づいて自己の物を占有する者にも、民法162条の適用があり、自已の物について取得時効による権利取得を主張することができる。
(○) そのとおり。民法162条は、「他人の物を占有した者」としているが、自己の物についても、所有権取得の立証が困難であったり、所有権の取得を第三者に対抗できないなどの場合において、取得時効による権利取得を主張できると解することが時効制度本来の趣旨に合致することから、所有権に基づいて物を占有する者についても、同条の適用がある(最判昭42.7.21民集21・6・1643、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)206ページ)。
⑷ 金銭債権の消滅時効が完成した後に、債務者が当該債務の一部を弁済した場合において、債務者が時効完成の事実を知らなかったときは、時効の利益を放棄したことにはならないから、債務者は、その後に時効の援用をすることができる。
(✕) 判例は、債権の消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認(その権利の存在を認める行為であり、一部弁済等がこれに当たる。)をした場合は、相手方において債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、たとえ時効完成の事実を知らずに承認をしたとしても、信義則に照らし、その後においては、債務者の時効の援用を認めないとしている(最大判昭41.4.20民集20.4・702、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)198、203ページ)。なお、同判例は、債務の承認時点で既に完成していた消滅時効の援用を否定するにとどまり、債務の承認時点から更に民法所定の時効期間が経過したときは、再び消滅時効により債務は消滅する(最判昭45.5.21民集24・5・393)。
⑸ 催告には、催告があったときから6か月を経過するまでの間、時効の完成を猶予させる効力があるので、催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をすることにより、時効の完成を猶予させ続けることができる。
(✕) 催告によって時効の完成が猶予されている間になされた再度の催告には、時効の完成猶予の効力はない(民法150条2項、研修教材・八訂民法Ⅰ(総則)202ページ)。
第8問
占有に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、その所有する動産甲をBに預けたままCに売却し、Bに対して以後Cのために甲を占有すべき旨を命じ、Cがそれを承諾した。この場合、Cは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
(○) そのとおり。動産に関する物権の譲渡の対抗要件は、動産の引渡し(民法178条)であるところ、この「引渡し」には、現実の引渡し(民法182条1項)、簡易の引渡し(同条2項)、占有改定(民法183条)、指図による占有移転(民法184条)が含まれる。設問は、AC間で、指図による占有移転がされた場合であり、Cは、甲の所有権の取得について対抗要件を備えたものである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)42、43ページ)。
⑵ 占有者が占有物について行使する権利は、遮法に有するものと推定されるので、甲土地の占有者Aが、甲土地の所有者から土地明渡請求訴訟を提起された場合において、Aが甲土地に賃借権を有すると主張すれば、Aが甲土地の適法な賃借権に基づき占有する事実が推定される。
(✕) 民法188条は、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」と規定しているが、本条の推定は、権利の存在・帰属について適用されるものであって、権利の変動に関する事柄については、占有しているという事実だけからそれを推定することはできない。判例(最判昭35.3.1民集14・3・327)は、他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する正権原を主張する場合には、占有者がその権原の立証責任を負い、同条を援用して自己の権原を所有者に対抗することはできないとしている。したがって、Aが甲土地の占有権原を主張する場合には、Aが賃借権を取得し、その賃借権に基づき甲土地を占有する事実を立証する必要がある(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)61ページ)。
⑶ Aは、その所有する動産甲をBに預けていた。Bが死亡した後、その唯一の相続人であるCは、甲がBの相続財産に属すると過失なく信じ、甲の占有を開始した。この場合、Cは、甲を即時取得する。
(✕) 即時取得(民法192条)が成立するためには、占有の取得が取引行為によるものであることを要する。Cは、相続により甲の占有を取得したものであり、取引行為により占有を取得したのではないから、甲を即時取得しない(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)45、46ページ、研修891号73~77ページ)。
⑷ Aは、その所有する動産甲をBに預けていた。Bは、Aに無断で、甲をCに質入れし、Cは、甲はBの所有物であると過失なく信じ、現実の引渡しを受けた。この場合、Cは、即時取得により甲を目的とする質権を取得する。
(○) そのとおり。即時取得(民法192条)の要件を満たした場合の効果について、同条は、「即座にその動産について行使する権利を取得する」と規定している。ここにいう「権利」には、所有権のほか、質権も含まれる(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)48ページ)。
⑸ Aは、Bから、Bの所有する動産甲を買い受け、占有改定の方法で引渡しを受けた。その後、Bは、自己及びAの意思に反して甲をCに奪われ、Cが甲を現に所持している。この場合、Aは、Cに対して占有回収の訴えを提起することはできない。
(✕) 占有の態様には、占有者が物を直接所持する場合(直接占有)と、占有代理人に物を所持させる場合(代理占有・民法181条)がある。占有者がその意思に反して占有を奪われたときは、現に占有を侵害している者に対し、占有回収の訴えを提起することができる(民法200条1項)。占有訴権の主体は、直接占有者であると代理占有者であるとを問わない(川井健著「民法概論2(物権)」〔第2版〕128頁、近江幸治著「民法講義Ⅱ」物権法〔第4版〕198頁)。Aは、Bから占有改定(民法183条)により引渡しを受け、占有代理人Bを通じて、甲を代理占有していたところ、その意思に反してCに甲の占有を奪われたものである。よって、Aは、現に占有を侵害しているCに対し、占有回収の訴えを提起することができる(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)42、43、58、64、65ページ)。
第9問
不動産物権変動に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bに対して有する金銭債務を担保するため、Bとの間で、A所有の甲土地に抵当権を設定することを合意したが、その登記がされていない。この場合、AとBとの間で抵当権の効力はない。
(✕) 抵当権は、抵当権設定契約により発生する。抵当権設定契約は、当事者の合意によって、一定の債権の担保として、ある物の上に抵当権を設定することを目的とする契約である。抵当権設定契約は、諾成契約である(質権のように担保物の占有移転を必要としない。)。抵当権も物権であるから、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)が、登記のない抵当権でも当事者間では効力があり、抵当権に基づく競売の申立てをすることができる(ただし、抵当権の存在を証する確定判決等が必要である(民事執行法181条))。設問は、当事者(A・B)間で抵当権の効力がないとしている点で誤りである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)144、145ページ、研修893号67~71ページ)。
⑵ Aは、その所有する甲土地をBに譲渡したが、その後、Cにも重ねて譲渡し、さらに、Cが甲土地をDに譲渡し、AC間及びCD間の所有権移転登記がされた場合において、CがBとの関係で背信的悪意者に当たるときは、D自身がBとの関係で背信的悪意者に当たらなかったとしても、Dは、甲土地の所有権の取得をBに対抗することができない。
(✕) 民法177条の「第三者」とは、当該物権変動の当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な理由を有する者をいう(大連判明41.12.15民録14・1276)。善意悪意を問わないのが原則であるが、単なる悪意にとどまらず、信義則に反するなどの不当・悪質な悪意者は、もはや保護すべきではなく、判例は、このような者を、いわゆる「背信的悪意者」として、同条の「第三者」から排除すると解している(最判昭43.8.2民集22・8・1571等)。もっとも、背信的悪意者からの善意の転得者については、背信的悪意者は、信義則上未登記権利者に対する登記欠缺の主張が否定されているだけで完全な無権利者ではないから、転得者も物権を承継取得でき、転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、登記の欠缺を主張することができる(最判平8.10.29民集50・9・2506)。Cは背信的悪意者であるが、Cからの転得者Dが背信的悪意者とは評価されない場合には、Dは、Bに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。設問は、対抗することができないとしている点で誤りである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)36~40ページ)。
⑶ AがB所有の甲土地を占有している場合において、CがBから甲土地を譲り受け、その旨の登記がされた後、Aの取得時効が完成したときは、Aは登記なくして甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。
(○) そのとおり。Aが占有しているB所有の不動産(甲土地)について、Aが時効によりその所有権を取得した(民法162条)場合、Aは登記なくしてBにその不動産の所有権の取得を対抗することができ(大判大7.3.2民録24・423)、Aの占有中に、CがBから不動産を譲り受けて登記し、その後にAの時効が完成した場合も、Aは登記なくしてCに不動産の所有権の取得を対抗できる(最判昭41.11.22民集20・9・1901)。これは、時効完成当時における所有者であったBやCは、Aと、取得時効による物権変動の当事者の関係にあると見られるからである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)27ページ、研修855号53、55、56ページ)。
⑷ Aは、その所有する甲士地をBに譲渡したが、その旨の登記がされる前に死亡した。その後、Aの唯一の相続人Cが甲土地を相続し、その旨の登記がされた。この場合、Bは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
(○) そのとおり。相続人は、相続により被相続人の財産に属した一切の権利議務を包括的に承継する(民法896条本文)ので、Cは、Aと同一人格として扱われ、Bのために甲土地の所有権移転登記をする義務を負う。CとBは対抗関係には立たず、Bは、登記なくして甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)28ページ、研修855号53~58ページ)。
⑸ Aはその所有する甲土地を残して死亡し、Aの相続人B及び同Cは、遣産分割協議により、甲土地をBの単独所有とした。その後、Bがその旨の登記をしないでいるうちに、Cが、甲土地につき、Cの単独所有とする旨の登記をした上で、これをDに売却したときは、Bは、Dに対し、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。
(○) そのとおり。Bは、法定相続分(民法900条4号)である二分の一の持ち分については、登記なくして、Dに対抗することができるが、二分の一を超える部分(Cの法定相続分)については、登記がなければDに対抗することができない(民法899条の2第1項、最判昭46.1.26民集25・1・90)(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)28、29ページ、研修855号57、58ページ)。
第10問
担保物権に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bが甲をCに売ったが、Aが甲の占有を続けている。この場合、Aは、Cからの甲の引渡請求に対し、Bから甲の代金の支払を受けるまで、甲について留置権を行使することができる。
(○) そのとおり。留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権について弁済を受けるまで、その物を留置できる権利である(民法295条)。留置権は「物権」であり、絶対性を有するから、何人に対しても主張でき、Aは、契約の当事者ではないCに対しても、留置権を行使することができる(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権法)106、107ページ)。
⑵ Aは、その所有する動産甲をBに売り、これをBに引き渡した。その後、Bは、甲をCに売り、これをCに引き渡した。この場合において、AがBから甲の代金の支払を受けていないときは、Aは、動産先取特権の行使として、甲を差し押さえることができる。
(✕) 民法333条は、動産上の先取特権につき、「債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と規定し、いわゆる追及効を否定している。この場合、先取特権者は、債務者が第三取得者に対して有する代金債権に対して物上代位により優先弁済権を行使し得るにすぎない。よって、設問は、動産先取特権の行使として、甲を差し押さえることができるとしている点で誤りである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)121ページ)。
⑶ 動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることができる。
(✕) 動産質権は、目的物を継続して占有することをもって、第三者に対する対抗要件とされる(民法352条)。したがって、質権者が目的物の占有を失うと、質権は第三者に対抗できなくなる。全くの無権限の第三者に質物の占有を奪われた場合にも、質権に基づいて返還請求できず、占有回収の訴えによる返還請求だけが認められている(民法353条)(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権法)126ページ)。
⑷ Aは、Bに対する債務を担保するため、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。その後、CがAの依頼により甲の倒壊を防止するための工事を行い、その工事費用に関し、工事完了後直ちに甲について不動産保存の先取特権登記がされた。この場合、Cの先取特権は、Bの抵当権に先立って行使することができる。
(○) そのとおり。抵当権者は、抵当権の目的物について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法369条1項)。同一の債務者に対して、抵当権者と不動産の先取特権が競合する場合の順位については次のとおりである。まず、不動産先取特権には、①不動産保存の先取特権(民法325条1号、326条)、②不動産工事の先取特権(民法325条2号、327条)、③不動産売買の先取特権(民法325条3号、328条)の3種類がある。このうち①不動産保存の先取特権と②不動産工事の先取特権は、適法な登記(民法337条、338条)がある限り、常に抵当権に優先する(民法339条)。一方、③不動産売買の先取特権と競合する場合は、一般原則により、登記の前後によると解される。設問において、Cが行った建物の倒壊を防止するための工事は、不動産保存を目的とする工事であり、①不動産保存の先取特権に当たり、民法337条が「保存行為が完了、直ちに登記をしなければならない」と定めるところに従い適法な登記がされている。よって、Cの不動産保存の先取特権は、常に抵当権に優先し、Bの抵当権に先立って行使することができる(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)118~120、154、155ページ、研修893号67~72ページ)。
⑸ 甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAは、甲土地に抵当権を設定した後、乙建物をBに譲渡した。その後、抵当権が実行され、Cが甲土地を取得したときは、法定地上権は成立しない。
(✕) 法定地上権(民法388条)が成立するためには、①抵当権設定当時に土地の上に建物が存在していたこと、②抵当権設定当時同一人がその士地と建物を所有していたこと、③土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと、④競売の結果別々の所有者が土地と建物を所有するようになったことが必要だとされている。設問は、②の要件が問題となるところ、抵当権設定当時士地と建物が同一人の所有に属していれば、抵当権設定後、その一方が第三者に譲渡されても法定地上権が成立すると解されている。設問のように、抵当権が設定された土地が譲渡された場合、譲受人は抵当権設定当時に同一人が所有する土地と建物が存在する以上、利用権の負担を覚悟すべきだからである(研修教材・八訂民法Ⅱ(物権・担保物権)156~158ページ、遠藤浩ほか著「民法⑶担保物権」[第4版]160~164ページ)。
刑法
第11問
正当防衛に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、散歩中に突然ナイフを持ったBに切り付けられそうになったことから、Bから逃れるために、付近にいた無関係のCを押し倒して、Cに傷害を負わせた。この場合、Aの行為は、正当防衛となる。
(✕) 防衛行為は侵害者に向けられた行為でなくてはならず、侵害者以外の第三者に向けられた行為は、緊急避難になることはあっても、正当防衛にはなり得ない(研修教材・七訂刑法総論119ベージ)。
⑵ Aは、降雨に備えて傘を持って歩いていた際、Bの不注意によって檻から逃げ出したBの飼い犬に突然かみつかれそうになったため、自分の身を守るために傘で同犬をたたき、同犬に傷害を負わせた。この場合、Aの行為は、正当防衛となる。
(○) 飼い主の過失による動物の侵害行為は、すなわち飼い主の侵害行為であるから、これに対して正当防衛が許される(研修教材・七訂刑法総論117ページ)。
⑶ 過剰防衛も、急迫不正の侵害に対する防衛行為であるから、違法性が阻却される。
(✕) 「防衛の程度を超えた行為」(過剰防衛、刑法36条2項)は、相当性の要件を欠くことから正当防衛(同条1項)が成立せず、違法性は阻却されない(研修教材・七訂刑法総論126、127ページ)。
⑷ 雑貨店を経営するAは、同店内でBがバッグを万引きするのを現認して、Bを追い掛けたが、逃げられてしまった。翌日、Aは、同バッグを持ち歩いていたBを見付けたが、BがAの姿を見て逃げようとしたため、Bに体当たりをして転倒させ、Bから同バッグを奪い返した。この場合、Aの行為は、正当防衛となる。
(✕) 「急迫」(刑法36条1項)とは、法益侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいい、過去の侵害に対しては、正当防衛は成立しない(研修教材・七訂刑法総論111、112ページ)。
⑸ AがBを殺すために拳銃を発砲したところ、偶然、そのときBもAを殺そうとして拳銃でAを狙い発砲しようとしていたが、一瞬早くAの弾丸がBに命中したためAが自己の生命を防衛することができた。この場合、BがAを狙い発砲しようとしていることにAが気付いていなかったとしても、Aの行為は、正当防衛となる。
(✕) 判例は、正当防衛が成立するためには、防衛行為が防衛の意思をもってなされることが必要であるとしており(最判昭46.11.16刑集25・8・996等)、本問のようないわゆる偶然防衛の場合には、行為者は専ら攻撃の目的で行為に及んでおり、防衛の意思を欠くから、正当防衛は成立しない(研修教材・七訂刑法総論121、122ページ)。
第12問
未遂犯に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bを脅迫しようと考え、Bの住所宛てに脅迫文を郵送したが、Bはこれに気付かず、脅迫の事実を認識するに至らなかった。この湯合、Aは脅迫未遂罪で処罰される。
(✕) 刑法44条は、「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」と規定しており、未遂犯を処罰するためには、個別に各本条の規定がなければならない(研修教材・七訂刑法総論225ページ)。脅迫罪(刑法222条)には、未遂犯処罰規定はなく、末遂犯で処罰されることはない。
⑵ 殺人の予備をしたが自己の意思により殺人の実行に着手しなかった場合、中止未遂の規定は準用されず、その刑が減軽され又は免除されることはない。
(○)(✕)両方正答扱い。
⑶ 刑法は、過失犯の未遂を処罰の対象としている。
(✕) 現行刑法は過失犯の未遂を処罰していない(研修教材・七訂刑法総論227、228ページ)。
⑷ 保険会社から保険金を詐取する目的で火災保険に加入して対象物件に放火しても、保険会社に保険金を請求しなければ、詐欺未遂罪は成立しない。
(○) 保険金詐欺においては、詐欺の目的で保険契約を締結したり、放火しただけではまだ詐欺罪の実行の着手は認められず、保険金の支払を請求したときに初めて実行に着手したといえる(大判昭7.6.15刑集11・859、研修教材・三訂刑法各論(その1)216ページ、研修885号45~50ページ)。
⑸ 犯罪の実行に着手したが、直後に改心して、結果の発生を阻止するため真摯な努力をした場合には、たとえ結果が発生したとしても、中止未遂が成立し得る。
(✕) 刑法43条本文が「これを遂げなかった」と明確に規定している以上、既遂の場合には中止未遂とはならないと考えられている(研修教材・七訂刑法総論241、242ページ)。
第13問
財産犯に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、衣料品販売店で顧客を装い、店主から見せてもらった衣類を試着したまま、便所に行くと偽り、店外に逃げ去った。この場合、Aに、窃盗罪が成立する。
(○) そのとおり。財物を取得するために偽計的な方法が用いられても、相手方の処分行為がなければ、詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立する(広高判昭30.9.6高刑集8・8・1021。研修教材・三訂刑法各論(その1)168ページ)。なお、店主がAに衣類を試着させたのは、Aに一時的に見せるためにすぎず、衣類に対する事実上の支配は失われていないので、横領罪も成立しない(前掲判決)。
⑵ Aは、スーパーマーケットの店内において、代金を支払わず領得する意思で、商品であるカップ酒(180ミリリットル入り)1本を上着のポケットの中に入れた。Aが店内にいる限り、Aに、窃盗罪が成立することはない。
(✕) Aがカップ酒を上着のポケットの中に入れた時点で、目的物を自己又は第三者の占有に移したと認められ、窃盗罪が成立し得る(判例・通説)。いわゆる万引き事犯において、商品を懐中に収めた時に既遂に達するとした判例がある(大判大12.4.9大集2・330、研修教材・三訂刑法各論(その1)170、171ページ)。
⑶ Aは、商店から金品を領得する目的で、夜間閉店後の同商店に侵入し、店内を懐中電灯で照らしながら金品の置いてある場所に近づいた。この場合、物色行為がないから、Aに、窃盗未遂罪が成立することはない。
(✕) 判例は、窃盗の実行の着手時期につき、「他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をなした時」と解している(大判昭9.10.19大集13・1473。研修教材・三訂刑法各論(その1)169ページ)。本問と同種の事例で、「密接な行為」があったとして実行の着手を認めている判例がある(最決昭40.3.9刑集19・2・69)。
⑷ Aは、B方に侵入して金品を窃取する目的で、B方に侵入し、居間のたんすを開けて金目の物を探していた。そうしたところ、物音に気付いたBが居間にやってきたので、Aはテープルの上にあった果物ナイフを手に取り、Bの首に突き付けて、金品を出すように申し向け、Bから現金5万円が在中している財布の交付を受け、B方から逃走した。この場合、Aに、事後強盗罪が成立する。
(✕) 当初窃盗の意思で財物を奪取しょうとしたが、奪取が完了する前に奪取確保のために被害者に暴行・脅迫を加えた場合は居直り強盗となり、強盗罪が成立する(研修教材・三訂刑法各論(その1)187ページ、前田雅英・刑法各論(第7版)198、199ページ)。事後強盗罪(刑法238条)は、窃盗犯人(窃盗が既遂であると未遂であるとを問わない)が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行・脅迫を加えることによって成立する(研修教材・三訂刑法各論(その1)191、192ページ)。
⑸ Aは、貴金属店において、Bに対し、代金を支払う意思も能力もないのに、商品である宝石を購入する旨申し向け、同宝石の交付を受けた。その直後、Aは、Bから代金の支払を求められると、代金支払を免れるためにBの顔面を殴り、Bをその場に転倒させ、店外へ逃走して行方をくらませた。この場合、Aに、強盗既遂罪(刑法236条2項)が成立することはない。
(✕) 判例(最決昭61.11.18刑集40・7・523)は、窃盗又は詐欺が行われた後に、代金支払を免れるために被害者を射殺しようとした事案について、窃盗罪又は詐欺罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪として重い後者の罪で処断すべきとしている(研修教材・七訂刑法総論311、312ページ)。
第14問
放火の罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは、Bが現に居住する家屋(以下「B方」という。)を焼損させようと考え、隣接するC所有の空き家に火を放ち、同空き家を焼損させたが、B方についてはこれに延焼し得る状態に至ったものの、結局、B方には燃え移らなかった。この場合、Aに、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立する。
(✕) 人の住居に延焼するであろうことを予見し、かつ、認容して、これに隣接する物置に放火した場合には、現住建造物等放火罪の故意があると言え、しかもこの場合、空き家に放火したことをもって人の住居に対する放火の着手があると言えるから、現住建造物等放火罪の未遂が成立する(大判大12.11.12大集2・781、研修教材・三訂刑法各論(その2)16ページ)。また、一個の放火行為により処罰規定を異にする数個の異なった目的物を焼損(未遂)したときは、放火罪が公共危険罪であることに鑑み、包括的に観察して最も重い処罰規定に該当する目的物を焼損(末遂)した罪の一罪を認めれば足りる(研修教材・三訂刑法各論(その2)16、17ページ)から、本問では現住建造物等放火未遂罪のみが成立する(大判昭8.7.27刑集12・1388、前田雅英・刑法各論(第7版)334ページ)。
⑵ Aは、自己が所有するごみ箱を、中に入っているごみごと焼却しようと考え、同ごみ箱に火を放ったところ、公共の危険が生じた。Aが公共の危険が生じるとは考えていなかった場合であっても、Aに、自己所有建造物等以外放火罪(刑法110条2項)が成立する。
(○) 判例(大判昭6.7.2大集10・303、最判昭60.3.28刑集39・2・75)は刑法110条1項の事案であるが、公共の危険発生の認識までは不要としている(研修教材・三訂刑法各論(その2)19、20、22ページ)。本問では、自己所有建造物等以外放火罪(110条2項)が成立する。
⑶ Aは、一人暮らしのBを、Bが居住する家屋内で殺害し、犯跡を隠すため、Bの死体が横たわっている同家屋に火を放ち、Bの死体もろとも同家屋を全焼させた。この場合、Aが前記家屋を全焼させた行為には、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立する。
(○) そのとおり。判例(大判大6.4.13録23・312)は、本問と同種の事例で、殺人罪、死体損壊罪のほか、現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物等放火罪(109条1項)の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その2)19ページ)。
⑷ Aは、自己が所有し、Bに賃貸している空き家に火を放ち、同空き家を焼損させるとともに、公共の危険を生じさせた。この場合、Aに、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立する。
(○) 自己の所有に属するものであっても、それが差押えを受け、物件を負担し、賃貸し、又は保険に付したものであるときは、109条1項の客体となる(115条。研修教材・三訂刑法各論(その2)20ページ)。
⑸ AとBは夫婦であるところ、共謀の上、自分たちが共有して住んでいる、保険を付した家屋に火を放ち、保険金をだまし取ろうと考えた。Bがアリバイ作りのために不在にした間に、Aが前記家屋に火を放って全焼させた場合、Aに、現住建造物等放火罪が成立する。
(✕) 現住建造物等放火罪のいう「人」とは、犯人以外の一切の者をいい(最判昭32.6.21刑集11・6・1700)、共犯者は「人」に該当しない。本問で当該家屋に居住しているのは、A及び共犯者であり、当該家屋の共有者でもあるBのみであるから、同家屋は非現住建造物となるが、保険が付されているので、刑法115条により、他人所有非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)の客体となり、Aに、同罪が成立する(研修教材・三訂刑法各論(その2)14、20ページ)。
第15問
公務の執行を妨害する罪に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 刑法95条には、単に「職務」と記載されているにとどまり、適法な職務である旨は記載されていないから、公務執行妨害罪が成立するためには、妨害される公務員の職務執行は適法なものでなくてもよい。
(✕) 公務執行妨害罪は円滑適正な公務の遂行を保護法益とするものであり、職務が違法である場合にまでこれを保護する必要はないから、刑法95条の「職務」は適法なものでなければならない(判例、通説。大判昭7.3.24大集11・296など。研修教材・三訂刑法各論(その2)169、170ページ)。
⑵ Aが、自宅に置いたかめの中で酒を密造していたところ、収税官吏からかめごと酒を差し押さえられた。その直後、Aが収税官吏の目前で前記かめを金属パットでたたき壊して、中に入っていた酒を流出させた場合、Aの暴行は収税官吏の身体に直接向けられたものではないから、Aに、公務執行妨害罪が成立することはない。
(✕) 公務執行妨害罪の暴行は広義のものであり、公務員の身体に対して直接に加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず、公務員の職務の執行に当たりその執行を妨害するに足りる暴行を加えれば足り、人に向けられてはいるが直接人の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)も含む。判例(最判昭33.10.14刑集12・14・3264)も、本問と同種の事例で公務執行妨害罪の成立を認めている(研修教材・三訂刑法各論(その2)175ページ)。
⑶ Aは、警察官Bが職務質問をしようとして近づいてきたところ、Bの顔面を殴って逃走した。この場合、Bの職務質間は開始前であるが、職務質問の要件を満たしていれば、Aに、公務執行妨害罪が成立する。
(○) 「職務を執行するに当たり」とは、まさにその職務の執行に着手しようとする場合も含む(大判明42.4.26録15・513、福高判昭30.3.9裁特2・6・148、研修教材・三訂刑法各論(その2)173ページ)。
⑷ Aは、知人Bが警察官Cによって銃砲刀剣類所持等取締法違反で現行犯逮捕されようとしていたことから、Cに暴行を加えたが、後日、Bは、同法違反被告事件で無罪判決を受けた。この場合、逮捕当時の状況における具体的な状況を客観的に見て、Bの挙動に同法違反の現行犯人と認められる十分な理由があれば、Aに、公務執行妨害罪が成立する。
(○) 判例(最判昭41.4.14判時449・64)は、警察官がAの知人を逮捕しようとした職務行為は適法であるとして、公務執行妨害罪の成立を認めた(研修教材・三訂刑法各論(その2)173ページ)。
⑸ Aは、確定判決を受け、執行官から住居明渡しの強制執行を受けることとなった。Aが、強制執行を免れるため、執行官が来る前に、あらかじめ前記住居の敷地内に猛犬を放し飼いにした場合、Aに、公務執行妨害罪が成立する。
(✕) 強制執行行為妨害罪(刑法96条の3)が成立する。同罪は、本問のような暴行又は脅迫によらない強制執行妨害事案を処罰できるようにするため、平成23年刑法改正により新設されたものである(研修教材・三訂刑法各論(その2)193ページ)。
刑事訴訟法
第16問
逮捕に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 緊急逮捕においては、逮捕後に作成された疎明資料であっても、逮捕時に既に存在した事情で、逮捕者が逮捕時に認識し得た事情が記載されたものであれば、緊急逮捕の要件の有無の判断資料として構わない。
(○) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)123、124ページ)。
⑵ 被疑者を緊急逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で、令状によらずに捜索、差押え、検証をすることができる。
(○) そのとおり。捜査機関が適法に被疑者を逮捕する場合には、その逮捕の種類(通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕)のいかんを問わず、必要があるときは、令状によらずして、人の住居等に入って被疑者を捜索し、逮捕の現場で、物の捜索、差押え又は検証をすることができる(刑訴法220条1、3項、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)202ページ)。
⑶ 刑事訴訟法212条1項の現行犯人は、その犯行を現認した者でなければこれを逮捕することができない。
(✕) 現行犯人を逮捕すべく追跡中の者から依頼を受け、被追跡者が特定の犯罪の現行犯人であると知って追跡し逮捕する場合も、現行犯逮捕に当たる(最判昭50.4.3刑集29・4・132、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)126ページ)。
⑷ 現行犯逮捕された被疑者による窃盗事件が検察官に送致されてきたところ、現行犯逮捕の要件を満たしていないことが判明したため、被疑者を釈放した。この場合、緊急逮捕の要件を満たしていれば、同じ事実について、緊急逮捕することができる。
(○) そのとおり。現行犯逮捕の要件を備えていないのに現行犯逮捕が行われていた場合で引き続き身柄拘束の必要があるときは、緊急逮捕の要件を具備しているかどうかを検討し、具備している場合には、いったん身柄を釈放して、緊急逮捕の措置を採ることがある(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)122、123ページ)。
⑸ 通常逮捕のための逮捕状の請求を一般司法警察員が行う場合、警部以上の警察官であれば、誰でもこれをすることができる。
(✕) 通常逮捕のための逮捕状の請求を警察官である一般司法警察員が行う場合、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限られる(刑事訴訟法199条2項)ので、警部以上の警察官であれば誰でも可能なわけではない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)111ページ)。
第17問
起訴処分に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ いわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人を起訴する場合、行為者と共に起訴しない限り、必ず簡易裁判所に起訴しなければならない。
(○) (✕)とも正解とする。本問は、いわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人については、法定刑が罰金刑とされていることから、行為者が共に起訴されて、刑訴法9条1項2号、3条1項により関連事件の管轄を生ずる場合は別として簡易裁判所の管轄となるという判例に関する知識を問う趣旨から、○を正解とするものであった。
しかし、問題文中、「行為者と共に起訴しない限り・・・」の「共に起訴(する)」という言葉は、行為者と事業主たる法人又は人を同時に起訴することとも、先に行為者を起訴した裁判所に追起訴として事業主たる法人又は人を追起訴して一緒に審理することとも読める。
そして、元々管轄を有する事件(本問でいえば行為者)を起訴した上級裁判所に対し、元々管轄のない事件(本問でいえば事業主たる法人又は人)を関連事件として追起訴できる(大コンメンタール刑事訴訟法第三版第1巻109ページ)。
そうすると、もし、前者と解し、問題文を「行為者と事業主たる法人又は人を同時に起訴しない限り、事業主たる法人又は人は簡易裁判所に起訴しなければならない」と読んだ場合、回答が✕になることになり、✕の回答を不正解とはできないとの結論に達したため、本問については、いずれも正解とすることとした。
⑵ 起訴状の公訴事実には、裁判官に予断を生じさせるような文言を記載することはできないので、被疑者に前科があることを記載することが許されることはない。
(✕) 刑事訴訟法256条6項の規定との関係で、公訴事実の記載に当たり、被告人の経歴、前科等の記載をすることの可否が問題になることがあるが、前科については、それが構成要件となっている場合(常習累犯窃盗)や公訴事実の内容をなしている場合(当該前科がある事実を手段方法として恐喝した場合)は、訴因を明示するために必要な記載であると解される(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)219ページ)。
⑶ 虚偽の氏名を名のっている身柄拘束中の被疑者が、在庁(待命)方式で略式命令を受けたときは、特段の事情がない限り、その虚偽の氏名を名のっている者が被告人となる。
(○) そのとおり。他人の氏名を冒用した者について、身柄拘束のまま略式手続がとられた場合は、特段の事情がない限り、被告人は、身柄を拘束されている冒用者である(大阪高決昭52.3.17刑裁月報9・3・4・212)。この略式命令は、被告人の氏名等の記載を誤った略式命令であるので、冒用者が略式命令の謄本の交付を受けて罰金を仮納付した場合であっても、検察官は、正式裁判を請求して被告人の氏名等を訂正すべきである(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)226ページ)。
⑷ 略式命令においては、100万円以下の罰金及び科料を科することができるだけではなく、没収も科することができる。
(○) そのとおり(刑事訴訟法461条)。
⑸ 公訴の提起が検察官の裁量の逸脱によるものであった場合は、その公訴の提起は直ちに無効となる。
(✕) 裁判所は、「検察官は、現行法制の下では、公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって、公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといつて直ちに無効となるものではないことは明らかである。」「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」と判示していることからすれば、直ちに無効にはならない(最決昭55.12.17刑集34・7・672、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅰ(捜査)211ページ)。
第18問
証拠調べ手続に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 冒頭陳述は、証拠調べ手続の始めに行われるものであり、相手方の冒頭陳述に対して、証拠調べに関する異議を申し立てることができる。
(○) 冒頭陳述は、証拠調べ手続の始めに行われるものであり(刑事訴訟法296条本文)、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめるおそれのある事項を含む冒頭陳述に対しては、証拠調べに関する異議(刑事訴訟法309条1項)を申し立てることができる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)103~106ページ、研修890号76~78ページ)。
⑵ 証拠調べの請求は、公判期日においてしなければならず、公判期日外にはすることができない。
(✕) 証拠調べの請求は、検察官の冒頭陳述が終わった後であれば、弁論終結までいつでもすることができ、公判期日においてはもちろんのこと、公判期日外にもすることができる(刑事訴訟規則188条、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)106ページ)。
⑶ 検察官は、証人尋問を請求する場合、弁護人の異議がないときを除いては、弁護人に対し、証人の氏名及び住居を知る機会を必ず与えなければならない。
(✕) 検察官は、刑事訴訟法299条1項により、証人等の氏名及び住所を知る機会を与えるぺき場合において、証人等又はその親族に対して加害行為等がなされるおそれがあるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除き、①弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居について、被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する措置をとることができ(刑事訴訟法299条の4第1項)、②①の措置によっては加害行為等を防止できないおそれがあるときは、被告人及び弁護人に対し、当該氏名又は住居を知る機会を与えないこととした上で、氏名にあってはこれに代わる呼称を、住居にあってはこれに代わる連絡先をそれぞれ知る機会を与える措置をとることができる(同条2項、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)113、114ページ、研修894号59ページ)。
⑷ 裁判所が、検察官請求証拠につき、その立証趣旨等から取調べの必要性がないと判断した場合であっても、被告人及び弁護人の意見を聴かずに証拠調べ請求を却下することは違法である。
(○) 裁判所は、証拠決定に当たっては、その証拠調べを請求した相手方の意見を聴かなければならず(刑事訴訟規則190条2項)、この意見を聴かないで行った証拠決定は違法となる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)118ページ)。
⑸ 訴訟関係人は、書面や物の成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、その書面や物を証人に示して尋問することができる。
(○) そのとおり。刑事訴訟規則199条の10は、書面や物の成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問するために、その書面や物を証人に示す場合には、裁判長の許可を必要としていない。これに対し、記憶喚起のために書面等を提示する場合(刑事訴訟規則199条の11)、供述明確化のために図面等を利用する場合(刑事訴訟規則199条の12)には、裁判長の許可が必要である(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)124、125ページ)。
第19問
公判準備に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 起訴状の謄本が、公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されないときは、公訴の提起は、遡ってその効力を失い、公訴棄却の決定がなされる。
(○) そのとおり(刑事訴訟法271条2項、同法339条1項1号。研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)65ページ)。
⑵ 裁判所は、訴訟当事者に異議がなければ、やむを得ないと認める場合でなくとも公判期日を変更することができる。
(✕) 公判期日がみだりに変更されると訴訟遅延の原因となるため、公判期日の変更については厳重に規制されている。裁判所は、「やむを得ないと認める場合」のほかは公判期日を変更することができない(刑事訴訟規則182条1項。研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)66、67ページ)。
⑶ 検察官は、裁判所に対し、裁判員裁判非対象事件につき、公判前整理手続に付するよう職権発動を促すことができるのみで、同手続に付するよう請求することはできない。
(✕) 公判前整理手続に付されるか否かは訴訟当事者の公判準備活動に大きな影響を与えることに鑑み、平成28年の刑事訴訟法改正により、訴訟当事者に公判前整理手続の請求権が付与された(刑事訴訟法316条の2第1項。研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)75ページ、研修856号68ページ)。
⑷ 公判前整理手続は、争点や証拠を整理して審理計画を策定するための手続であるから、裁判所は、公判前整理手続期日に出頭した被告人に対し、質問をすることはできない。
(✕) 裁判所は、必要があると認めるときは、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめるため、公判前整理手続期日に出席した被告人に対して質問をすることができる(刑事訴訟法316条の10。研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)77、78ページ)。
⑸ 検察官は、公判前整理手続において、検察官請求証拠を開示した後、被告人又は弁護人からの請求の有無にかかわらず、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならない。
(✕) 刑事訴訟法316条の14第2項は、「被告人又は弁護人から請求があったとき」は、速やかに検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならないとしている。証拠の一覧表の交付は、証拠開示請求が円滑・迅速に行われるようにするための制度であり、被告人側が証拠開示請求をする予定がない場合や、証拠開示請求をするとしても、証拠の一覧表を必要としない場合には、その交付は不要である(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)79、80ページ、研修892号78、79ページ)。
第20問
証拠に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 冒頭手続における被告人の陳述は、証拠とすることができない。
(✕) 判例は、冒頭手続における被告人の陳述は、事実認定の証拠となるとしている(最判昭26.7.26刑集5・8・1652、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)65ページ)。
⑵ 緊急避難の成否に関する挙証責任は、検察官ではなく、被告人が負っている。
(✕) 犯罪構成要件に該当する事実の存在や被告人が犯人であることのみならず、違法性阻却事由(緊急避難を含む。)や責任阻却事由が存在しないことについても、検察官が挙証責任を負っている(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)17ページ)。
⑶ 公判廷における被告人の自白は、任意にされたものであることが明らかであるから、同自白があれば、他に証拠がなくても被告人を有罪にすることができる。
(✕) 公判廷における自白であっても補強証拠が必要である(刑事訴訟法319条2項、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)108、109ページ)。
⑷ 殺人被告事件において、証人Aの「被害者は自らビルの屋上から飛び降りた」との公判供述を弾劾するため、Aと同じ場面を目撃したBの「被告人が、被害者をビルの屋上から突き落とした」旨の供述を録取した検察官調書を、刑事訴訟法328条により証拠とすることができる。
(✕) 刑事訴訟法328条の証拠は、証明力を争う対象となる法廷供述者自身の法廷外における自己矛盾の供述に限られる(最判平18.11.7刑集60・9・561、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)201~203ページ)。
⑸ 被告人が任意に作成した被告人に不利益な事実の承認を内容とする供述書は、被告人の署名及び押印のいずれも欠いている場合でも、刑事訴訟法322条1項により証拠とすることができる。
(○) 供述書に証拠能力を認めるために作成者の署名及び押印はいずれも不要である(刑事訴訟法322条1項、最決昭29.11.25刑集8・11・1888、研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)145、177ページ)。
事件事務
第21問
事件の受理に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 司法警察員ではない収税官吏や税関職員が事件を検察官に告発する場合でも、事件記録等があるときは、事件記録・証拠品送致票(甲)を使用することとされている。
(○) そのとおり(九訂事件事務解説10ページ。研修902号45ページ)。
⑵ 不起訴処分にした事件について、検察審査会において起訴を相当とする議決がなされ、その議決書の謄本の送付を受けた場合でも、再捜査して起訴することができる見込みがないときは、再起して事件の受理手続を行わなくてもよい。
(✕) 不起訴処分にした事件について、検察審査会において起訴を相当とする議決がなされ、その議決書の謄本の送付を受けた場合には、直ちに再起して事件の受理手続を行う必要がある(事件事務規程3条6号、169条1項。九訂事件事務解説7ページ、108ページ。研修900号100、101ページ)。
⑶ 事件事務規程3条により事件の受理手続を行うべきものとされているのは、被疑事件に限られるので、再審開始決定によって事件が対応裁判所の公判に係属した場合は、事件の受理手続は行わず、検察総合情報管理システムにより公判事件としてその旨を管理することとなる。
(○) そのとおり(九訂事件事務解説8ページ。研修900号95ページ)。
⑷ 司法警察員が少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料する事件については、全て直接家庭裁判所に送致されるので、検察庁において事件受理を行うことはない。
(✕) 少年法41条前段において、司法警察員は、少年の被疑事件のうち、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、家庭裁判所に直接送致しなければならない旨規定されているが、特定少年(18歳以上の少年)の場合は、同法67条1項において、同法41条が除外されているため、特定少年が行った罰金以下の刑に当たる罪の事件については、検察官に送致することになり、事件受理を行うことになる(研修900号93、94ページ)。
⑸ 前に公訴の取消しをした事件について、刑事訴訟法340条の規定により更に公訴を提起しようとするときは、事件の受理手続を行わなければならない。
(○) そのとおり(事件事務規程3条8号。九訂事件事務解説8ページ。研修900号102、103ページ)。
第22問
逮捕に係る事務に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 司法警察員は、逮捕状により逮捕した被疑者を留置する必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならないことになっているが、これは48時間以内に検察官に送致する手続をすれば足り、必ずしも同時間内に検察官に到達しなくても構わない。
(○) そのとおり(刑事訴訟法203条1項。研修902号51ページ)。
⑵ 逮捕状は、やむを得ない事情があるときは、最寄りの下級裁判所の裁判官に請求することができるが、この場合の下級裁判所には、高等裁判所は含まれていないと解されている。
(✕) 逮捕状は、やむを得ない事情があるときは、最寄りの下級裁判所の裁判官に請求することができるが、この下級裁判所とは、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所であるものと解されている(刑事訴訟規則299条1項ただし書、裁判所法2条1項、研修904号52ページ)。
⑶ 逮捕状の有効期間は、原則として発付の日から7日とされているが、裁判官が相当と認めるときは、7日を超える期間を定めることができる。
(○) そのとおり(刑事訴訟規則300条。研修902号50ページ)。
⑷ 検察事務官及び司法巡査は、いわゆる緊急逮捕状を請求することができる。
(○) そのとおり。通常逮捕状を請求することができる者は、検察官と司法警察員であり、この場合の司法警察員のうち、警察官たる司法警察員は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限られている。また、検察事務官及び司法巡査は、通常逮捕状を請求することはできないが、いわゆる緊急逮捕をした場合には、上記に類する制限はなく、請求権者に制限はないと解すべきであるとされており、検察事務官や司法巡査も緊急逮捕状を請求することができる(刑事訴訟法210条1項。研修904号51ページ)。
⑸ 捜査機関が捜査の都合上特に必要があるときは、逮捕状請求書に記載する引致場所として、特定の官公署名を記載せず、「○○地方検察庁又は逮捕地を管轄する地方検察庁」のような記載をすることも許されている。
(○) そのとおり。逮捕状請求書に記載する引致すべき場所には、特定の官公署名を記載することになるが、捜査機関が捜査の都合上特に必要があるときは、実務上は、例えば「○○地方検察庁又は逮捕地を管轄する地方検察庁」というように場所の特定性を害しない程度で多少余裕のある記載をすることも法の解釈として許されるものと解されている(研修904号53ページ)。
第23問
勾留請求に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 定まった住居を有する被疑者が強盗罪で逮捕されている場合、当該強盗罪に、逮捕されていない軽犯罪法違反の罪を付加して勾留請求することは許されない。
(○) そのとおり。原則として、甲事実で逮捕した被疑者について、甲事実のほか非逮捕事実である乙事実を付加して、甲・乙両事実で勾留請求することは許されると解されているが、非逮捕事実を付加して勾留請求するには、非逮捕事実だけでも勾留の要件を充たすことが必要であることから、例えば、本件設問のように、法定刑が30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽犯罪法違反の場合、被疑者が定まった住居を有しているときは、その事実については勾留の要件を満たしていないため、逮捕事実である強盗罪に付加して勾留請求することは許されない(研修904号57、58ページ)。
⑵ 検察庁法附則2条(令和3年法律第61号による改正前の附則36条)による検察官事務取扱検察事務官はいかなる事件であっても勾留請求をすることはできない。
(✕) 勾留請求をする権限を有するのは検察官のみであるから、刑事訴訟法上の検察官としての取扱いを受ける検察官事務取扱検察事務官は、その所属する区検察庁に係る事件については、勾留請求を行うことができる(刑事訴訟法204条1項、205条1項、検察庁法附則2条(令和3年法律第61号による改正前の附則36条)。研修904号58、59ページ)。
⑶ 検察官は、18歳未満の少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、勾留請求をすることができない。
(○) そのとおり(少年法43条3項、67条1項。研修904号56ページ)。
⑷ やむを得ない事情によって検察官への送致又は勾留請求についての時間の制限に従うことができなかったときは、勾留請求の際、これを認めるべき資料を提供することとされている。
(○) そのとおり(刑事訴訟法206条1項、刑事訴訟規則148条2項。九訂事件事務解説24ページ。研修904号59ページ)。
⑸ 殺人罪で逮捕された被疑者の勾留請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判官に対してもすることができる。
(○) そのとおり。勾留請求先は、逮捕状請求先と同じであるので、裁判所の事物管轄等に関係なく、請求者の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にすることとされており、上記いずれの裁判所の裁判官でもよい(刑事訴訟規則299条1項。九訂事件事務解説24ページ。研修904号52、59ページ)。
第24問
事件の処理に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 被疑事実が明白な場合において、過剰防衛(刑法36粂2項)のように、刑を「免除することができる」と規定されているときには、「刑の免除」の裁定主文を用いて不起訴処分とすることができる。
(✕) 「刑の免除」の裁定主文は、被疑事実が明白な場合ではあるが、例えば、同居の親族間の相盗(刑法244条1項)などのように、法律上「刑を免除する」ときに用いる。したがって、過剰防衛(同法36条2項)のように、法律上単に「免除することができる」とされている場合は、「刑の免除」の裁定主文は用いてはならない。この場合には、「起訴猶予」を用いることとなる(事件事務規程75条2項19、20号。九訂事件事務解説75ページ。研修907号59ページ)。
⑵ 刑事訴訟法261条の規定による告訴人、告発人又は請求人に対する不起訴理由の告知については、起訴猶予、嫌疑不十分等不起訴裁定主文のみを告知すれば足りると解されている。
(○) そのとおり。ただし、裁定の理由等を告知することが禁止されているものではなく、被害者への配慮の必要上、刑事訴訟法47条の趣旨を踏まえつつ、具体的な不起訴裁定の理由を説明することが適当な場合もある(九訂事件事務解説76ページ。研修907号63ページ)。
⑶ 事件の処理は、起訴、不起訴又は家庭裁判所送致の終局処分と中止又は移送の中間処分に分けることができる。
(○) そのとおり(九訂事件事務解説56ベージ。研修907号49ベージ)。
⑷ 告訴、告発又は請求に係る事件について、検察官が中止、移送又は家庭裁判所送致の処分を行った場合には、告訴人、告発人又は請求人に対する処分通知は不要である。
(✕) 事件事務規程60条に定める告訴人等に対する処分通知について、刑事訴訟法の解釈上は、家庭裁判所送致又は中止の処分については、必ずしも通知を要しないが、事件事務規程は、刑事訴訟法の精神を敷えんして、これについても通知するものとしている(刑事訴訟法260条。九訂事件事務解説57ページ。研修907号61ページ)。
⑸ 逮捕中又は勾留中の被疑者に対し、当該被疑事件について公訴を提起したときは、令状担当事務官は、起訴通知書により速やかにその旨をその者が収容されている刑事施設の長に通知しなければならないが、急速を要するときは、あらかじめ適宜な方法によって通知した上で、起訴通知書を追送しても構わない。
(○) そのとおり(事件事務規程64条。九訂事件事務解説59、60ページ。研修907号51ページ)。
第25問
勾留日数に関する次の記述のうち、正しいものには○の欄に、誤っているものには✕の欄に印を付けなさい。
⑴ 被疑者又は被告人が勾留執行停止により釈放された日に、勾留執行停止が取り消されて収容された場合は、その勾留日数は1日として計算する。
(○) そのとおり(九訂事件事務解説95ページ。研修905号38ページ)。
⑵ 次の事例における被疑者の勾留期間の満了日は、令和6年3月14日である。
【事例】
令和6年3月4日(月)
勾留請求、勾留請求済証明書を交付して留置施設に留置
令和6年3月5日(火)
勾留状発付、勾留状執行、勾留状指定の留置施設に引致
(✕) 被疑者の勾留期間は、勾留の請求をした日から10日間であり、勾留状の発付が勾留請求の翌日となったとしても勾留期間の起算日は勾留請求の日である。勾留の期間は、初日(勾留請求の日)を算入する。したがって、勾留請求の日である3月4日を起算日として10日後の3月13日が勾留期間の満了日となる(刑事訴訟法第208条1項。九訂事件事務解説35ページ。研修905号37ページ)。
⑶ 次の事例における被告人の残勾留日数は、1か月と4日である。
【事例】
令和6年1月17日(水)
逮捕中の被疑者を公訴提起(公訴事実は逮捕の基礎となった事実と同一)
令和6年1月18日(木)
勾留状発付、勾留状執行、勾留状指定の留置施設に引致
令和6年2月13日(火)
保釈により釈放
(✕) 被告人の勾留期間は、公訴提起の翌日に勾留状が発付されて執行されたとしても、「公訴提起の日」が勾留期間の起算日となる。したがって、公訴を提起した1月17日を起算日として暦に従って2か月後の3月16日が当初の勾留期間の満了日である。残勾留期間は、保釈による釈放の日の翌日である2月14日から3月16日までとなり、この期間を暦に従って計算すると、2月14日から3月13日までが1か月となり、3月14日から16日までの3日、つまり、「1か月と3日」が残勾留日数となる(刑事訴訟法60条2項。研修905号42、43ページ)。
⑷ 次の事例における被告人の残勾留日数は、4日と1か月である。
【事例】
令和5年12月20日(水)
勾留中の被疑者を公訴提起(公訴事実は勾留の基礎となった事実と同一)
令和6年2月9日(金)
勾留期間更新決定執行(2月20日から1か月の分)
令和6年2月15日(木)
保釈により釈放
(○) そのとおり。当初の勾留期間に加え、釈放前における勾留期間更新決定の執行がある場合の残勾留日数は「○日と1か月」として算出する。釈放の日の翌日である2月16日から当初の勾留期間満了日である2月19日までの4日と勾留期間更新決定の執行による1か月が存在するので「4日と1か月」となる(九訂事件事務解説96ページ、研修905号46、47ページ)。
⑸ 次の事例における被告人の勾留期間の満了日は、令和6年3月21日である。【事例】
令和5年12月20日(水)
勾留中の被疑者を公訴提起(公訴事実は勾留の基礎となった事実と同一)
令和6年2月9日(金)
勾留期間更新決定執行(2月20日から1か月の分)
令和6年2月15日(木)
保釈により釈放
令和6年2月19日(月)
実刑言渡しにより刑事施設に収容
(✕) 残勾留日数は、⑷のとおり4日と1か月。実刑言渡しにより刑事施設に収容した2月19日を初日として4日を加えた2月22日の翌日(2月23日)から暦に従って1か月を加えて算出した3月22日が、収容後の勾留期間満了日となる(九訂事件事務解説96ページ。研修905号46、47ページ)。