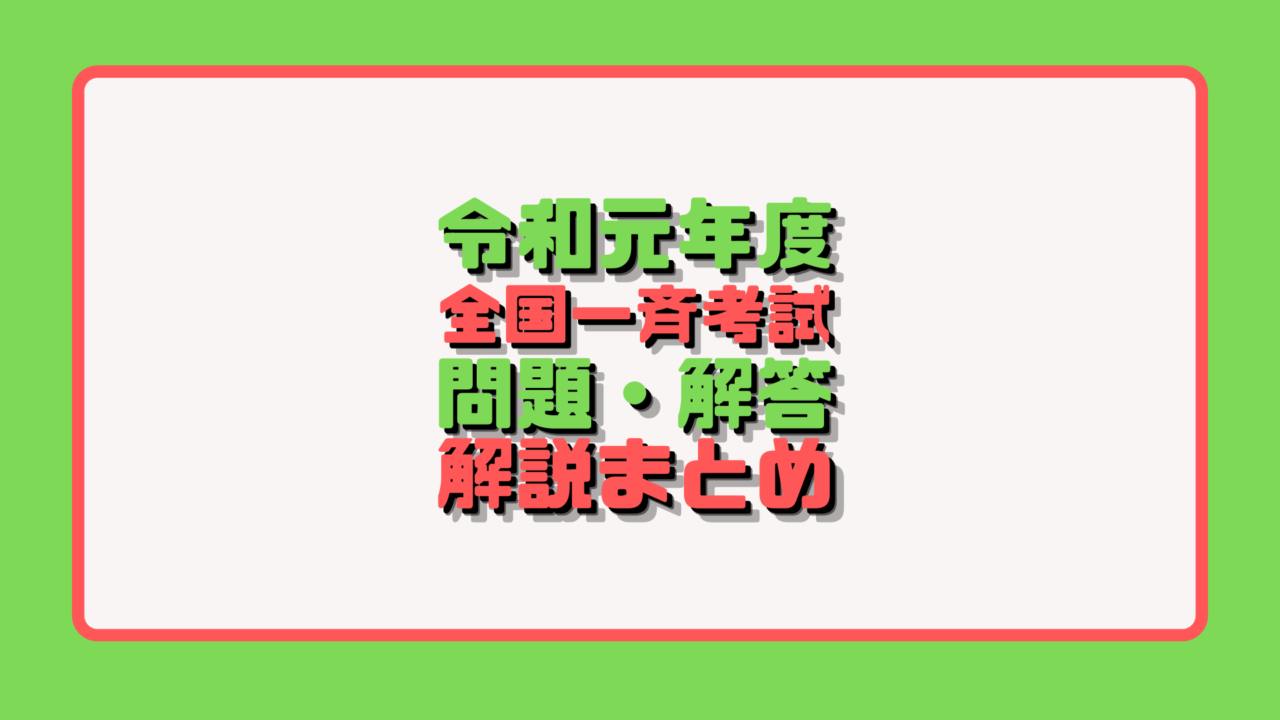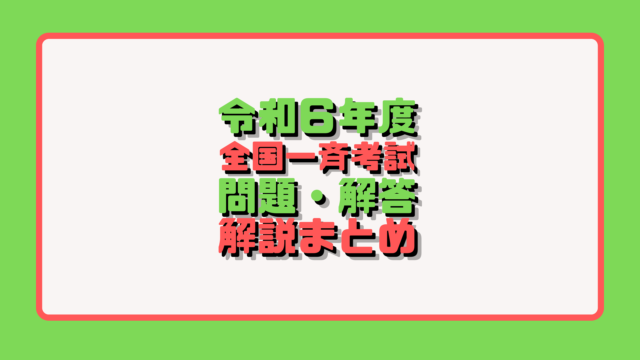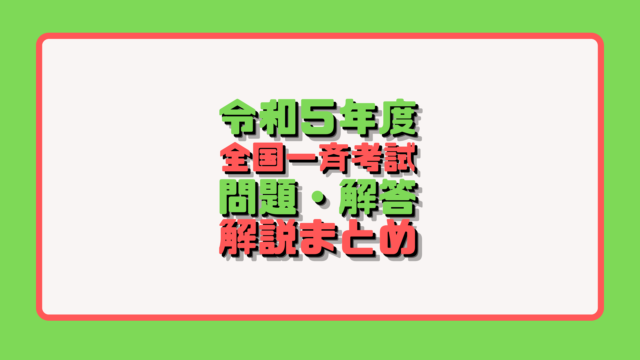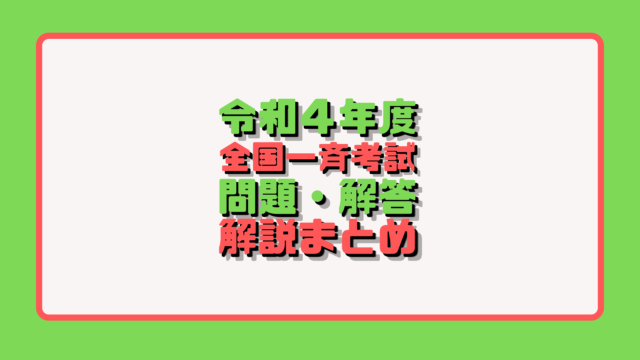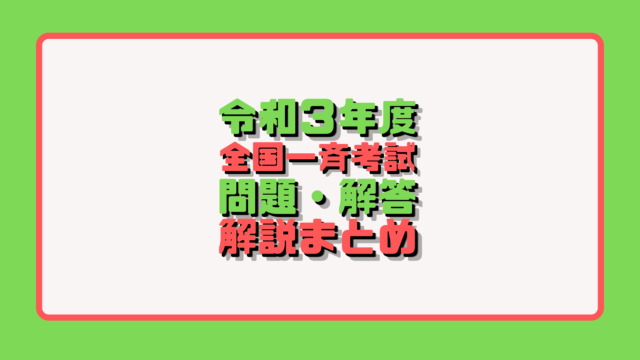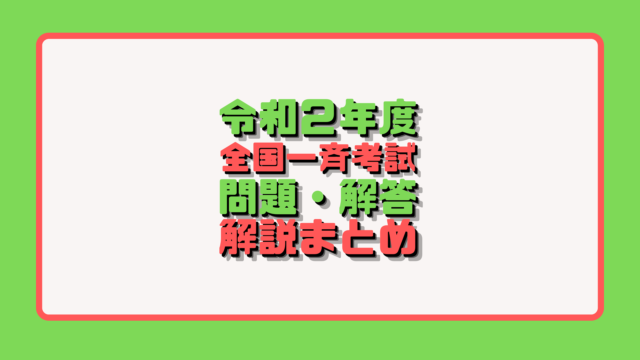憲法・検察庁法
第1問
人身の自由に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 行政手続における一切の強制は,当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで,当然に憲法35条1項による保障の枠外にあることにはならない。
(〇) 判例(いわゆる川崎民商事件,最判昭47.11.22刑集26・9・554)は,旧所得税法70条10号,63条の規定が裁判所の令状なくして強制的に検査することを認めているのは違憲である旨の主張に対し,「憲法35条1項の規定は,本来,主として刑事責任追及の手続における強制について,それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが,当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで,その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」と判示した(研修教材・五訂憲法137ページ,研修814号45ページ,856号63,64ページ)。
⑵ 裁判所は,被告人又は弁護人が請求した証人が事件の審判に必要でない場合であっても,憲法37条2項により,これを採用して尋問しなければならない。
(×) 判例(最判昭23.7.29刑集2・9・1045)は,「刑事裁判における証人の喚問は,被告人にとりても又検察官にとりても重要な関心事であることは言うを待たないが,さればといって被告人又は弁護人からした証人申請に基きすべての証人を喚問し不必要と思われる証人までをも悉く訊問しなければならぬという訳のものではなく,裁判所は当該事件の裁判をなすに必要適切な証人を喚問すればそれでよいものと言うべきである。」と判示した(研修教材・五訂憲法142ページ,研修814号46ページ,856号65,66ページ)。
⑶ 刑事手続以外の手続に憲法38条1項による保障が及ぶことはない。
(×) 判例(いわゆる川崎民商事件,最判昭47.11.22刑集26・9・554)は,「右規定(注:憲法38条1項)による保障は,純然たる刑事手続においてばかりではなく,それ以外の手続においても,実質上,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には,ひとしく及ぶものと解するのを相当とする。」と判示した(研修教材・五訂憲法143,144ページ,研修814号48ページ,856号64,65ページ)。
⑷ 偽計によって被疑者が心理的強制を受け,その結果虚偽の自白が誘発されるおそれがある場合には,このような自白を証拠として採用することは,憲法38条2項に違反する。
(〇) 憲法38条2項の「強制」には,自由な意思決定を抑圧する全ての行為が含まれるところ,判例(最判昭45.11.25刑集24・12・1670)は,「偽計によって被疑者が心理的強制を受け,その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には,右の自白はその任意性に疑いがあるものとして,証拠能力を否定すべきであり,このような自白を証拠に採用することは,刑訴法319条1項の規定に違反し,ひいては憲法38条2項にも違反するものといわなければならない。」と判示した(研修教材・五訂憲法144ページ)。
⑸ 憲法37条1項が刑事事件に関し迅速な公開裁判を受ける権利を保障しているから,憲法32条は,刑事事件に関する裁判を受ける権利を保障していない。
(×) 裁判を受ける権利(憲法32条)とは,民事及び行政事件においては,何人も自ら裁判所へ訴訟を提起し救済を求め得る権利であり,刑事事件においては,裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないこと,すなわち,裁判所以外の機関によって裁判を受け,刑罰に処せられることのない権利であるところ,刑事裁判は人身の自由に関わることが大であることに鑑み,特に憲法37条1項が設けられた(研修教材・五訂憲法186,140ページ)。
第2問
経済的自由に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 外国へ一時旅行する自由は憲法で保障されている。
(〇) 判例(最判昭33.9.10民集12・13・1969)は,「憲法22条2項の『外国に移住する自由』には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきである」と判示した(研修教材・五訂憲法147ページ,研修858号84ページ)。
⑵ 職業選択の自由には,選択した職業を任意に営む自由は含まれない。
(×) 職業選択の自由とは,国民がどのような職業に就くかを選択する自由をいうが,選択した職業を任意に営むことの自由(職業活動の自由)を含むものであり,いわゆる営業の自由をも包含する。判例(最判昭47.11.22刑集26・9・586)は,「憲法22条1項は,国民の基本的人権の一つとして,職業選択の自由を保障しており,そこで職業選択の自由を保障するというなかには,広く一般に,いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包合しているものと解すべきであり,ひいては,憲法が,個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。」と判示した(研修教材・五訂憲法149ページ,研修858号83,84ページ)。
⑶ 憲法は,個々の財産権を保障しているが,私有財産制度を保障しているわけではない。
(×) 憲法29条1項が「侵してはならない。」,すなわち,保障するというのは,個人の現有する具体的な財産権の保障と同時に,個人が財産権を享有し得る法制度の保障を意味する(研修教材・五訂憲法155ページ)。判例(最判昭62.4.22民集41・3・408)も,「憲法29条は,(中略)私有財産制度を保障しているのみでなく,社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」と判示した。
⑷ 条例により財産権を制約することはできない。
(×) 判例(最判昭38.6.26刑集17・5・521)は,ため池の破損,決壊を招く原因となると判断された,ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植え,又は建物その他の工作物を設置する行為を禁止する条例が問題となった事案について,「ため池の破損,決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は,憲法でも,民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって,憲法,民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく,従って,これらの行為を条例をもって禁止,処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえないし,また右条項に規定するような事項を,既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから,これを条例で定めたからといって,違憲または違法の点は認められない。(中略)本条例は,憲法29条2項に違反して条例をもつては規定し得ない事項を規定したものではない」と判示した(研修教材・五訂憲法155,156ページ)。
⑸ 経済的自由を制約する法律の合憲性を判断する基準と精神的自由を制約する法律の合憲性を判断する基準に異なる点はない。
(×) 精神的自由は,経済的自由に比べて優越的地位を占めるので,裁判所において,これらを規制する法律の違憲性を審査する際には,経済的自由の規制立法の場合はより緩やかな合理性の基準で足りるが,精神的自由の規制立法の場合はより厳格な基準によって審査するべきであると考えられている(二重の基準の理論)(研修教材・五訂憲法66~71,116,117ページ)。
第3問
内閣に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 内閣総理大臣が自らの意思で辞職したときは,内閣総辞職の必要はない。
(×) 憲法70条は,「内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは,内閣は,総辞職をしなければならない。」と規定する。この「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡,内閣総理大臣となる資格の喪失,辞職などの場合を指すと解されている(研修教材・五訂憲法234ページ,研修758号45~48ページ)。
⑵ 内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で指名される。したがって,内閣総理大臣が除名により議員たる地位を失ったときは,内閣総理大臣としての地位を失うことになる。
(〇) 内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法67条1項),これに基づき,天皇が任命する(憲法6条1項)。内閣総理大臣が国会議員であることは在職要件でもあると解されている。したがって,除名などにより議員たる地位を失ったときは,内閣総理大臣としての地位を失うことになる。この場合,内閣は,総辞職しなければならない(研修教材・五訂憲法26,230,231ページ)。
⑶ 内閣は,最高裁判所長官を任命する。
(×) 最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律で定める員数のその他の裁判官で構成され,最高裁判所長官以外の裁判官は,内閣が任命する(憲法79条1項)。これに対し,最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて,天皇が任命する(憲法6条2項,研修教材・五訂憲法26,236ページ)。
⑷ 内閣は,恩赦を決定することができるが,その旨の憲法上の規定はない。
(×) 内閣は,恩赦(大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権)の決定をすることができる(憲法73条7号,研修教材・五訂憲法236ページ)。
⑸ 国務大臣は,心身の故障のために職務を行うことができない場合を除いては,内閣総理大臣により罷免されることはない。
(×) 内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる(憲法68条2項,研修教材・五訂憲法232,233ページ)。
第4問
財政に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法83条の趣旨は,国家財政の処理を国民の代表機関である国会の監督下に置くことにある。
(〇) そのとおり(研修教材・五訂憲法274ページ)。
⑵ 憲法85条には,「国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必要とする。」と規定されている。しかし,国に新たな行政機関を設けることについて法律で認められているならば,国がこれに伴う支出をすることについて,別途国会の議決を要しない。
(×) 国は,各種の行政機関を設けたり,公務員を任命したりする場合,これらに伴って国費を支出する義務を負う。これらの義務は,法律に基づいて定められるが,それに伴う支出については,別途国会の議決を要する(研修教材・五訂憲法276ページ)。
⑶ 憲法84条には,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されている。「租税」とは,国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,一定の要件に該当する全ての者に対して課する金銭給付のことであって,市町村が行う国民健康保険の保険料の徴収についても,憲法84条が直接適用される。
(×) 租税の意義については,「国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてでなく,一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんにかかわらず,憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」とされている。他方,市町村が行う国民健康保険の保険料は,被保険者において保険給付を受けうることに対する反対給付として徴収されるものであるから,憲法84条が直接適用されることはない(最判平18.3.1民集60・2・587,研修教材・五訂憲法275ページ)。
⑷ 国の収入支出の決算は,毎年会計検査院の検査を受け,内閣が次の年度に会計検査院の検査報告とともに,国会に提出しなければならない。
(〇) そのとおり(憲法90条,研修教材・五訂憲法281ページ)。
⑸ 憲法88条には,「すべて皇室財産は,国に属する。すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と規定されている。これに対し,皇室が一般国民から財産を譲り受ける場合に国会の議決を必要とする旨の憲法上の規定はない。
(×) 皇室の費用は国の負担とされており,予算に計上して国会の議決を経なければならない(憲法88条後段)。皇室が一般国民から財産を譲り受ける場合であっても,国会の議決が必要である旨の憲法上の規定がある(憲法8条,研修教材・五訂憲法34ページ)。
第5問
検察庁法に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察権は,行政権の一部を成すものである。
(〇) 検察権は,国家刑罰権の実現等の国家目的を追求して行使されるもので,立法権でも司法権でもない。行政とは,国家作用のうち,立法と司法とを除いた残余の国家機能をいうとされ,検察権は,行政権に属する(研修教材・七訂検察庁法8,20ページ)。
⑵ 憲法によって司法権の独立が保障されていれば,検察権の独立が損なわれても,刑事司法の公平性に影響しない。
(×) 裁判所は,起訴されない事件を審判することはできず(不告不理の原則),検察官が検察審査会制度等の例外を除いて公訴権を独占し(刑事訴訟法247条),あるいは裁量により公訴を提起しないことも認められる(起訴便宜主義・刑事訴訟法248条)制度の下では,いかなる事件が裁判所の審理に持ち込まれるかは,検察官の手中にある。そうすると,いかに司法権が独立していても,検察権の行使が外部的圧力等により公正を欠くならば,刑事司法の公平性は失われる(研修教材・七訂検察庁法21ページ)。
⑶ 検察官は,その上司の指揮監督に服するので,上司の決裁を受けずに事件を起訴した場合,その起訴は無効になる。
(×) 検察官は独任制官庁であり,個々の検察官が自ら国家意思を決定表示する権限を有しているので(検察庁法4,6条),上司の決裁がないまま事件を起訴しても,それがためにその起訴が無効となることはない。ただ,検察権は行政権の一部であるから,検察権の行使は,国の正しい行政意思が統一的に反映され,全国均整になされる必要があるので,そのための方策の1つとして,上司の指揮監督権がある(検察庁法7条1項,8条,9条2項,10条2項,研修教材・七訂検察庁法28~30ページ)。
⑷ 甲県内所在の甲地方検察庁の検察官が,乙県内において,たまたま傷害事件を目撃した。この場合,同検察官は,直ちに乙県内においてその被疑者を同事件につき取り調べることができる。
(×) 検察官は,いずれかの検察庁に属し,他の法令に特別の定めのある場合を除いて,その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において,その裁判所の管轄に属する事項について検察官の職務を行うこととされているが(検察庁法5条),本件傷害事件の発生地は,甲地方検察庁の対応する甲地方裁判所の管轄区域外だから,同地において同検察官が捜査権を行使することはできない。例外として,刑事訴訟法195条は,捜査のため必要がある場合は,検察官は,管轄区域外でも捜査をすることができると規定しているが,「捜査のため必要がある場合」とは,本来当該検察官が所属する検察庁において有効に捜査に着手された事件が存在していることが必要であると解されている(研修教材・七訂検察庁法35,41,43,44ページ)。
⑸ 検察庁法4条に規定された検察官の職務である「刑事について,公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求」することには,より重い処分の実現自体を成果とみなすことも含まれる。
(×) 検察が目指すのは,事案の真相に見合った国民の良識にかなう相応の処分,相応の科刑の実現であり,あたかも常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。このことは,「検察の理念」で明確に表明されている。
民法(総則・物権)
第6問
権利能力及び行為能力に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 未成年者が,相手方に対して自分が成人であるかのような記載に改ざんした戸籍謄本を示し,相手方に自分が成人であると信じさせた上,相手方との間で契約を締結した場合,契約の締結について法定代理人である親の同意を得ていなくても,その契約を取り消すことができない。
(〇) 制限行為能力者が相手方に,自分が能力者であると誤信させようとして詐術を用い,相手方がその詐術によって能力者であると誤信した場合,制限行為能力者の行為を取り消すことができなくなる(民法21条,研修教材・七訂民法I(総則)38,39ページ)。
⑵ 成年被後見人が,成年後見人の同意を得て土地を購入する契約を締結した。この場合,成年被後見人はこの契約を取り消すことができない。
(×) 成年被後見人がした財産上の法律行為は,取り消すことができる(民法9条)。これは,常に取り消すことができるという意味であって,成年後見人の同意を得た行為も取り消すことができる(研修教材・七訂民法I(総則)24ページ)。
⑶ 未成年者が,法定代理人である親の同意を得ずに,自転車店から代金5万円の自転車を購入する契約を締結し,親からもらっていた小遣い銭をためたものの中から5万円を代金として自転車店に支払った。この場合,未成年者は,自転車の購入契約を取り消すことができる。
(×) 未成年者が親から小遣い銭として目的を定めないで処分を許された財産は,自由に処分することができる(民法5条3項,研修教材・七訂民法I(総則)20ページ)。
⑷ 未成年者が,法定代理人である親の同意を得ずに,自己が有している貸金債権につき弁済を受けた。この場合,未成年者は,この行為を取り消すことができる。
(〇) 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした行為は,これを取り消すことができる(民法5条1項本文,2項)。ただし,単に権利を得,又は義務を免れる行為については,取り消すことができない(民法5条1項ただし書)。これに対し,債務の弁済を受けることは,債権を失うことになるので,「単に権利を得,又は義務を免れる」に該当せず,原則どおり,取り消すことができる(研修教材・七訂民法I(総則)20ページ)。
⑸ 未成年者が,法定代理人である親の同意を得ずに,自己が所有する自転車を第三者に売却する契約を締結した。その後,未成年者の親は,未成年者に無断で,異議をとどめずに,第三者に代金の支払を請求した。この場合,未成年者はこの契約を取り消すことができる。
(×) 未成年者の親が第三者に代金の支払を請求したことにより,追認をしたものとみなされる(民法124条3項,125条2号,研修教材・七訂民法I(総則)151,152ページ)。したがって,未成年者はこの契約を取り消すことはできない(民法122条,研修教材・七訂民法I(総則)151ページ)。なお,民法124条3項は,改正により124条2項1号とされることとなった。
第7問
代理に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aの代理人として土地を買う契約の代理権を与えられたBは,Aのためにすることを示さないまま,Cに対して土地を買う旨の意思表示を行い,売買契約を締結した。この場合,Bの意思表示は,B自身のためにしたものとみなされるから,売買契約の効果がAに帰属することはない。
(×) 代理人が本人のためにすることを示して意思表示することを顕名という(民法99条1項)。具体的には,「A代理人B」と表示するような場合である。顕名しないときは,その意思表示は自己のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。しかし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,又は知ることができたときは,本人に効果が生じる(民法100条ただし書,研修教材・七訂民法I(総則)126ページ)。
⑵ Aの代理人であるBが後見開始の審判を受けた場合,その代理権が消滅することはない。
(×) 代理人は行為能力者であることを要しない(民法102条)。しかし,代理権は,代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことにより消滅する(民法111条1項2号,研修教材・七訂民法I(総則)127,131ページ)。
⑶ Aの代理人であるBは,Cにだまされ,AのためにA所有の土地をCに売却する旨の意思表示をした。この場合,Aは,Cにだまされていないので,土地を売却する旨の意思表示を詐欺を理由に取り消すことができない。
(×) 代理の場合に法律行為をする者は,代理人自身であるから,意思と表示の不一致(心裡留保,虚偽表示,錯誤)があったり,詐欺,強迫を受けたり,又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって法律効果に影響を受ける場合には,これらの事情は,代理人について決せられる(民法101条1項)。したがって,Aは,この意思表示を取り消すことができる(民法96条1項,研修教材・七訂民法I(総則)127ページ)。なお,民法101条1項は,代理行為の瑕疵について定めているが,代理人が意思表示をする場合と,代理人が相手方の意思表示を受ける場合を区別せず規定していた。これに対し,改正法では,代理人が意思表示をする場合を101条1項に,代理人が相手方の意思表示を受ける場合を101条2項にそれぞれ規定している。本問の場合は,新法施行後は101条2項が適用されることとなる。
⑷ Aの一人息子であるBは,A所有の甲土地につき何ら権限がないのに,Aの代理人と称し,甲土地を,Bに代理権がないことを知らず,かつ,そのことに過失がないCに売却した。その後,Aが死亡し,BがAを単独相続した。この場合,Bは,甲土地の売買が無権代理行為であることを主張することは許されない。
(〇) 判例は,「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合においては,本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当であ」るとしている(最判昭40.6.18民集19・4・986)。その結果,無権代理行為を行ったBは,土地の売買契約が無権代理行為であることを主張することは許されない(研修教材・七訂民法I(総則)144ページ,研修849号49ページ)。
⑸ 無権代理行為の追認は,相手方に対してのみならず無権代理人に対してもすることができる。したがって,本人をAとする無権代理行為をBが行った場合,Aが追認を無権代理人Bに対して行ったときには,相手方Cが追認の事実を知らなかったとしても,Aは,Cに対して追認の事実を主張できる。
(×) 追認は,相手方又は無権代理人に対してなすことを要する。ただし,追認を無権代理人に対してした場合には,相手方がその事実を知るまでは,相手方に対して追認したことを主張できない(民法113条2項,研修教材・七訂民法I(総則)140ページ)。
第8問
物権変動に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,その所有する甲土地にBのために抵当権を設定したが,その登記をする前に,Cに甲土地を譲渡した。この場合,BはCに対し,抵当権の取得を対抗することができない。
(〇) 民法177条は,「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(略)の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。」と規定する。抵当権の設定(不動産登記法3条7号)は,「不動産に関する物権の得喪及び変更」に含まれ,登記をしなければ第三者に対抗することができない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)52ページ,研修855号55ページ)。
⑵ A所有の甲土地を占有していたBに甲土地の所有権の取得時効が完成した。Aは,Bの取得時効完成前に甲土地をCに譲渡し,Bの取得時効完成後にAからCへの所有権移転登記をした。CがBに対して甲土地の明渡しを請求してきた場合,Bは,取得時効を援用して甲土地の明渡しを拒絶することができる。
(〇) 不動産の所有権を時効取得した場合において,例えば,A所有名義の不動産をBが時効で取得した場合,Bは登記なくしてAに対抗することができ,Bの占有中に,CがAから不動産を譲り受けて登記し,その後にBの時効が完成した場合も,Bは登記なくしてCに対抗することができる。そのCが移転登記をBの時効完成後になした場合も同様である。設問のCは,Bの時効完成時の当事者であり,民法177条にいう「第三者」には該当せず,Bは登記がなくても時効取得をCに対抗することができる(最判昭41.11.22民集20・9・1901,最判昭42.7.21民集21・6・1653等,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)32,33ページ,研修741号77,78ページ,855号55,56ページ)。
⑶ Aは,所有する乙建物をBに譲渡して引き渡したが,AからBへの所有権移転登記をする前に急死した。その直後,Aの唯一の相続人であるCは,乙建物を相続したと登記し,乙建物をDに譲渡して移転登記をした。DはBに対して所有権に基づき乙建物の明渡しを請求することができる。
(〇) 相続開始前に被相続人から不動産の所有権を取得した者と相続人から取得した者との優劣関係について,判例は,相続人は被相続人と法律上同一の地位にあるとして,相続人が同一不動産を二重に譲渡した場合と同様に考える。設問のBとDの優劣は登記の先後によって決まり,登記を有するDは,Bに対し,乙建物の所有権の取得を対抗することができ,乙建物の明渡しを請求することができる(最判昭33.10.14民集12・14・3111,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)34ページ,研修741号74ページ,855号57ページ)。
⑷ Aがその所有する乙建物をBに譲渡したが,Bへの所有権移転登記がされていないことに乗じて,CがAから乙建物を譲り受けてDに転売し,AからCへ,CからDへ,順次移転登記がされた。CがBとの関係で背信的悪意者と認められれば,Dが背信的悪意者と認められない場合であっても,Bは,乙建物の所有権の取得をDに対抗することができる。
(×) 民法177条により不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗することができないが,同条の「第三者」とは,当事者又は包括承継人以外の者で,登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有するものをいう。また,「第三者」の善意・悪意については,基本的にこれを問わないが,単なる悪意者の域を超えて,信義則に反するような不当・悪質な悪意者であると認められるような場合は,いわゆる背信的悪意者として,登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に該当しない。なお,信義則に基づく法理によって「第三者」から排除されるかどうかは相対的に判断されるべき事柄である。設問のDは,背信的悪意者Cからの転得者であるが,DがBとの関係で背信的悪意者と認められなければ,「第三者」から排除されず,Bは登記がなければ乙建物の所有権の取得をDに対抗することができない(大判明41.12.15民録14・12・76,最判昭43.8.2民集22・8・1571,最判平8.10.29民集50・9・2506等,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)43~49ページ,研修819号49~56ページ,855号58,59ページ)。
⑸ Aは,Bから借用して占有していたB所有のカメラをBから買い受けた。Aは,当該カメラを一旦Bに返還した上で改めてBから現実の引渡しを受けない限り,その所有権の取得を第三者に対抗することができない。
(×) 動産の物権の譲渡は,その動産の引渡しが対抗要件であり(民法178条),引渡しの態様には,現実の引渡し(民法182条1項),簡易の引渡し(民法182条2項),占有改定(民法183条),指図による占有移転(民法184条)がある。設問では,AB間で占有移転の合意をすれば,引渡しの効力を生じ(民法182条2項),その場合,Aは,第三者にカメラの所有権の取得を対抗することができる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)56ページ,研修855号59,60ページ)。
第9問
物権の効力に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ A所有の甲土地は,隣接する乙土地の所有者Bが境界に沿って土地を深く掘り下げたため,崩壊する危険が生じ,それから20年経過したが,なおその危険が継続している。AがBに対し,所有権に基づいて妨害予防請求権を行使してきた場合,Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。
(×) 設問の甲土地について崩壊の危険が生じている場合は,AはBに対し所有権に基づき妨害予防請求権を行使できる。物権的請求権は,物権から派生する権利であり,物権と運命を共にするから,物権が存在する限り物権的請求権も存在し,物権的請求権が独立して時効により消滅することはない。所有権は消滅時効にかからないから(民法167条2項,改正により166条2項),所有権に基づく妨害予防請求権は消滅時効にかからない。BはAの妨害予防請求権の消滅時効を援用することはできない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)15ページ,研修781号47ページ,研修853号53,54ページ)。
⑵ A所有の甲土地上に建築された未登記の乙建物は,甲土地を利用する権原のないBが所有する建物であり,CがBから賃借して居住している。この場合,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,乙建物の収去・甲土地の明渡しを請求することができる。
(〇) 物権的請求権の相手方は,占有すべき法律上の権原がないのに現にその物を占有している者(返還請求権の場合),又はその侵害状態を除去し得べき者(妨害排除請求権,妨害予防請求権の場合)である。Aの甲土地に対する所有権は,乙建物の存在により侵害されており,Bは,乙建物の所有者であるから,その侵害状態を除去し得べき者といえ,物権的請求権の相手方となる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)15ページ,研修781号47,48ページ)。
⑶ Aは,B所有の甲土地に竹木を所有するための地上権を有していても,Bの承諾を得なければ,甲土地上のA所有の竹木を伐採して売却することができない。
(×) 地上権は,他人の土地において工作物又は竹木を所有するため,その土地を使用する権利であり(民法265条),所有する竹木の処分は自由にできる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)104,106ページ)。
⑷ Aは,Bの依頼によりB所有の自転車を預かって修理をし,引き続き留置していたが,Bが支払期限までに修理費用を支払わなかったので,Bの承諾を得て当該自転車をCに賃貸して賃料の支払を受けた。この場合,Aは,その賃料を修理費用の弁済に優先的に充当することができる。
(〇) 留置権は,他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合,その債権について弁済を受けるまで,その物を留置することを本来の効力とする担保物権であり,目的物の交換価値から優先的に弁済を受ける効力を有しない。もっとも,留置物から生ずる果実(天然果実・法定果実)について,特に他の債権者に優先して自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。留置権者は,債務者の承諾がなければ,留置物を賃貸することはできないが(民法298条2項),債務者の承諾を得て留置物を賃貸した場合は,そこから生ずる賃料(法定果実)を収取し,自己の債権の弁済に優先的に充当することができる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)128,129ページ,研修857号53ページ)。
⑸ Aは,その所有する乙建物にBのために抵当権を設定してその登記をした。その後,Aは,Cに対して乙建物の増築工事を依頼し,その工事費用に関し,Cのために乙建物に不動産工事の先取特権の保存登記をした。この場合,Cは,Bに先立って先取特権を行使することができる。
(〇) 同一不動産に不動産工事の先取特権と抵当権が競合する場合,当該先取特権について登記がなされれば,常に抵当権に優先する(民法339条)。設問のCの不動産工事の先取特権の登記は,抵当権の登記よりも後にされているが,登記がされた以上,抵当権に優先する(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)138ページ,研修857号57ページ)。
第10問
占有権に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 所有権があるものと誤信して甲土地を占有していたAが,甲土地に自生した野菜を収穫した。その後,甲土地の所有者がAに対し,その野菜の返還を請求してきた場合,Aは,この請求を拒絶することができない。
(×) 民法189条1項は,「善意の占有者は,占有物から生ずる果実を取得する。」と規定する。善意の占有とは,占有すべき権利(本権)があると誤信してなされる占有のことをいう。設問のAは,善意の占有者に該当し,甲土地に自生した野菜は果実に該当するから,Aは果実取得権が認められ,収穫した野菜の引渡しを拒絶することができる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)73,78ページ,研修851号83ページ)。
⑵ 甲土地を占有していたAが死亡した場合,Aの唯一の相続人であるBは,甲土地を現実に占有するに至らなければ,その占有権を承継しない。
(×) 相続は被相続人の地位を相続人が包括的に承継するものであり,被相続人が,相続開始時に占有していた物は,被相続人の死亡により,相続人が所持ないし管理しているか否か,相続の開始を知っているか否かにかかわりなく,相続人の占有に承継される。相続人Bは甲土地を現実に占有しなくても,被相続人Aが有していた甲土地の占有権を承継する(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)75,76ページ)。
⑶ 甲土地の他主占有者であったAが死亡した場合,Aの相続人Bが新たな権原により所有の意思をもって甲土地の占有を開始したものと認められるときには,Bは自主占有者であると主張することができる。
(〇) 所有の意思とは,所有者がなし得ると同様の排他的支配を事実上行おうとする意思のことであり,所有の意思をもってする占有を自主占有といい,占有者が他人の所有権の存在を認めながら物を支配する占有を他主占有という。判例は,相続人が被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりではなく,新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し,その占有に所有の意思があるとみられる場合においては,被相続人の占有が所有の意思がないものであったときでも,相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を開始したものというべきであるとしている(最判昭46.11.30民集25・8・1437)。被相続人Aの占有が他主占有であった場合でも,相続人Bが新たな権原により所有の意思をもって甲土地の占有を開始したものと認められる場合には,Bは自主占有者であると主張することができる(研修851号82~85ページ)。
⑷ Aは,Bから絵画を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,当該絵画をCに奪われてしまった。この場合,Aは,Cに対して占有回収の訴えを提起することができる。
(〇) 占有回収の訴え(民法200条1項)は,占有者がその意思に反して占有を奪われたときに提起することができる。占有の形態には,占有者が物を直接所持する直接占有と,他人を介して所持する代理占有(民法181条)があり,占有改定により本人は占有権を取得する(民法183条)。占有改定の方法で絵画の引渡しを受けたAは,その意思に反してCにより占有を奪われた占有者であり,Cに対して占有回収の訴えを提起することができる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)81ページ,研修855号59,60ページ)。
⑸ Aが所有し,占有していた絵画を奪ったBが,その絵画をCに譲渡して引き渡した場合,CがBによる侵奪の事実を知っていたときでなければ,AはCに対し占有回収の訴えを提起することができない。
(〇) 民法200条2項は,「占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし,その承継人が侵奪の事実を知っていたときは,この限りでない。」と規定する。設問のCは,占有を侵奪した者であるBの特定承継人であり,AはCに対して占有回収の訴えを提起できないのが原則であるが,CがBによる占有侵奪の事実を知っていたときは,占有回収の訴えを提起できる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)81ページ,研修859号98ページ)。
刑法
第11問
違法性阻却事由に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,路上で前方から近づいてきたBからすれ違いざまにいきなり足を蹴られたので,逃げて行くBを追い掛けて,Bの背後から両手でその背中を突き飛ばした。Aの行為は,Bからの「急迫不正の侵害」に対してなされたものであるから,Aには正当防衛が成立する。
(×) 正当防衛が成立する要件の一つとして侵害の「急迫」性が求められる(刑法36条1項)。「急迫」とは,法益侵害が現に存在するか,目前に差し迫っていることをいい,過去の侵害に対しては,正当防衛は成立しない(研修教材・七訂刑法総論111,112ページ)。本問では,Bが「逃げて行く」のをAが「追い掛け」たという点からすると,Bからの侵害は過去のものとなったと認められ,Aに正当防衛は成立しない(研修847号84ページ)。
⑵ 正当防衛が成立するためには,防衛行為が専ら防衛の意思をもってなされることが必要であり,防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合には正当防衛は成立し得ない。
(×) 正当防衛が成立するためには,判例は,防衛行為が防衛の意思に基づくことを要するとしつつ,防衛の意思があれば,憤激,憎悪などの感情や攻撃の意思が併存していても正当防衛の成立を妨げないとする(最判昭46.11.16等,研修教材・七訂刑法総論121~123ページ,研修847号84~86ページ)。
⑶ 緊急避難は,自己の生命や身体に対する現在の危難を避けるためにした行為については成立する余地があるが,自己の財産に対する現在の危難を避けるためにした行為については成立する余地がない。
(×) 刑法37条1項は「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため」と規定しており,「財産」についても緊急避難が成立し得る(研修教材・七訂刑法総論135ページ)。
⑷ 緊急避難は,避難行為により避けようとした害の程度と避難行為から生じた害の程度とが同程度であったとしても成立することがある。
(〇) そのとおり。刑法37条1項は,避難行為によって生じた害が「避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」と規定しており,避難行為によって生じた害と避けようとした害が同程度の場合も緊急避難が成立し得る(研修809号85ページ)。
⑸ 刑法に規定されている違法性阻却事由は,正当防衛と緊急避難の2つのみである。
(×) 刑法は,正当防衛,緊急避難のほか,法令による行為及び正当業務行為も違法性阻却事由として規定している(刑法35条,研修教材・七訂刑法総論110ページ)。
第12問
刑罰に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合,中止未遂が成立しなかったとしても,刑が必ず減軽又は免除される。
(×) 中止未遂が成立せず障害未遂が成立するときは,刑は情状によっては減軽されることがある(刑法43条本文)だけで,必ず減軽又は免除されるわけではない(研修教材・七訂刑法総論340ページ,研修849号58ページ)。
⑵ 成人である被告人に対し罰金の言渡しをするときは,その言渡しとともに,罰金を完納することができない場合における労役場留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
(〇) そのとおり(刑法18条4項)。なお,少年に対しては,労役場留置の言渡をしない(少年法54条)。
⑶ 懲役刑の全部の執行を猶予するためには,3年以下の懲役の言渡しを受けたことが必要であるから,懲役3年6月,5年間執行猶予という判決を言い渡すことはできない。
(〇) そのとおり(刑法25条1項,研修教材・七訂刑法総論348ページ)。
⑷ 前に窃盗罪により懲役1年6月に処せられたことがある者に対し,詐欺罪により懲役2年の刑を言い渡す場合,その判決言渡し時において,前刑の執行を終わった日から5年経過していれば,新たに言い渡す刑の全部の執行を猶予することができる。
(〇) そのとおり(刑法25条1項2号,研修教材・七訂刑法総論348ページ)。
⑸ 傷害罪により懲役刑を言い渡す場合において,その刑の一部の執行を猶予するときは,その猶予の期間中保護観察に付さなければならない。
(×) 刑法27条の3第1項により,刑の一部の執行を猶予する場合においては,その猶予の期間中保護観察に付することができると規定されており,保護観察に付することは必要的とされていない。なお,同条項には,薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律4条に特則があり,この特則が適用されて刑の一部の執行の執行が猶予される場合においては猶予の期間中保護観察に付することが必要的とされている(研修教材・七訂刑法総論353ページ)。
第13問
強制わいせつ及び強制性交等の罪に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,Bに対し,その反抗を著しく困難にする暴行を加え,Bの肛門に自己の陰茎を挿入した。この場合,Bが男性であっても,Aには,強制性交等罪が成立する。
(〇) 強制性交等の行為には,いわゆる膣性交のほか,肛門内に陰茎を入れる「肛門性交」と口腔内に陰茎を入れる「口腔性交」が含まれ(刑法177条),客体は,女子に限られず,男子も含まれる(研修教材・三訂刑法各論(その1)89ページ)。
⑵ Aは,児童ポルノを製造して対価を得る目的で,13歳未満のBに対し,その陰部を直接触った。この場合,Aに自己の性欲を満たす目的がないので,Aには,強制わいせつ罪は成立しない。
(×) 同様の事案で,判例は,刑法176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の要件ではないとして,性的意図が認められない場合にも強制わいせつ罪の成立を認めている(最判平29.11.29刑集71・9・467,研修教材・三訂刑法各論(その1)87ページ)。
⑶ Aは,Bに暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,金品を強取した上,その機会にBと性交し,前記暴行によりBに傷害を負わせた。この場合,Aには,強盗・強制性交等罪のみが成立する。
(〇) 平成29年改正前の強姦罪(同改正前の刑法177条)について,判例は,強盗犯人が女子を強姦して傷害を負わせた場合,単に強盗強姦罪(同改正前の刑法241条前段)のみが成立し,致傷の結果は重要な量刑事情として考慮すれば足りるとしており(大判昭8.6.29大集12・1269),改正後も,強盗・強制性交等罪(刑法241条1項)に当たる行為により傷害を負わせた場合は,同罪のみが成立すると解されている(研修教材・三訂刑法各論(その1)205,206ページ)。
⑷ Aは,現に監護している17歳の実子Bに対し,わいせつな行為をした。Aが,このとき,現に監護する者であることによる影響力を利用する具体的な行為を行わなかった場合,Aには,監護者わいせつ罪は成立し得ない。
(×) 監護者わいせつ罪(刑法179条1項)における「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」とは,18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で,わいせつな行為をすることをいうが,「乗じて」といえるために,わいせつ行為を行う特定の場面において,影響力を利用するための具体的な行為は通常必要ないと解されている(研修教材・三訂刑法各論(その1)97ページ)。
⑸ Aは,Bに暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bと性交をした後,畏怖しているBを見て強盗の犯意を生じ,Bの金品を強取した。この場合,強盗犯人が強制性交等を行ったものではないので,Aには,強盗・強制性交等罪は成立せず,強制性交等罪と強盗罪がそれぞれ成立する。
(×) 平成29年改正前の強盗強姦罪(同改正前の刑法241条前段)は,強盗犯人が強姦をした場合に成立し,強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗の行為をした場合は,強盗強姦罪は成立せず,強姦罪(同改正前の刑法177条)と強盗罪(刑法236条)がそれぞれ成立して併合罪となると解されていたが,改正後の刑法241条1項により,同一の機会に強盗の行為と強制性交等の行為を行った場合は,その行為の先後関係にかかわらず,強盗・強制性交等罪が成立することとなった(研修教材・三訂刑法各論(その1)203ページ)。
第14問
窃盗及び強盗の罪に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,金品を強奪する意思で,通行人Bの顔面等を多数回殴る暴行を加え,その反抗を抑圧したが,通行人に発見されたため,金品を奪えずにその場から逃走し,その際,前記暴行によりBに傷害を負わせた。この場合,金品奪取は未遂でも,強盗傷人罪又は強盗致傷罪が成立する。
(〇) 強盗自体が未遂にとどまっても,傷害の結果が生じれば,強盗傷人又は強盗致傷の罪は既遂に達する(研修教材・三訂刑法各論(その1)202ページ)。
⑵ Aは,深夜,人通りのない路上において,通行人Bに対し,その目の前に大型の包丁を突き付けながら「金を出せ。」と言って現金を強奪しようとした。Bは,腕力に自信があり,反抗を抑圧されるまでには至らなかったが,恐怖を感じたので,Aに財布を差し出し,Aがその財布を奪った。この場合でも,通常人ならば反抗を抑圧される程度の暴行・脅迫が加えられているので,Aには,強盗罪が成立する。
(〇) 強盗罪の手段としての暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるが,現にそれによって相手方が反抗を抑圧されたことは必要でなく,通常人であれば反抗を抑圧される程度の暴行・脅迫が加えられれば足りる(最判昭23.11.18刑集2・12・1614,研修教材・三訂刑法各論(その1)183,184ページ)。
⑶ Aは,コンビニエンスストアの店内において,代金を払わずに領得する意思で,商品のたばこ1個を上着の内ポケットに入れた。Aが前記たばこをいまだ店外に持ち出していない場合,窃盗罪は,既遂に達していない。
(×) 窃盗罪の既遂時期は,目的物を自己又は第三者の占有に移した時点と解するのが判例・通説であり(最判昭23.10.23刑集2・11・1396),判例は,万引きについては,商品を懐中におさめたときに既遂に達するとしている(大判大12.4.9大審院刑事判例集2・330,研修教材・三訂刑法各論(その1)170,171ページ)。
⑷ Aは,B方で金品を盗み,誰からも発見・追跡されることなく,一旦B方から1キロメートル離れたA方まで逃げた。その後,Aは,再度B方に盗みに入ろうと考え,最初の窃取の翌日にB方に戻り,玄関ドアを開けたところ,屋内に人気を感じたため,窃盗に着手せず,直ちに逃走した。Aは,気付いたBに追跡され,逮捕を免れるため,Bにナイフを突き付けてその反抗を抑圧し,そのまま逃走した。この場合,最初の窃盗の機会が継続していたとはいえないので,Aには,事後強盗罪は成立しない。
(〇) 事後強盗罪の暴行・脅迫は,窃盗の現場又は少なくとも「窃盗の機会」が継続している間に行われることが必要である(最決昭33.10.31刑集12・14・3421等)。判例は,窃盗の後,誰からも発見・追跡されることなく,一旦犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごした場合,この間に,被害者等から容易に発見されて,金品を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきであるから,再度窃盗をする目的で現場に戻っても,その際に行われた脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとしている(最判平16.12.10刑集58・9・1047,研修教材・三訂刑法各論(その1)193~195ページ)。
⑸ Aは,わいせつ行為をする目的で,Bに睡眠薬を飲ませて昏睡させた後,Bの財布を奪う犯意を生じ,昏睡に乗じてBの財布を奪取した。この場合,Aには,Bを昏睡させて財布を奪取した行為につき,窃盗罪ではなく,昏睡強盗罪が成立する。
(×) 行為者が他の目的で昏睡させた後,財物奪取の犯意を生じ,昏睡に乗じて財物を奪取した場合,行為者自身が財物を奪取するために昏睡させたものではない以上,昏睡強盗罪ではなく,窃盗罪が成立する(研修教材・三訂刑法各論(その1)197ページ)。
第15問
国家の作用に対する罪に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,コンビニエンスストアで万引きをした窃盗罪により,警察官に同店で現行犯逮捕されたが,警察官の隙を見て,その場から逃走した。この場合,Aには,単純逃走罪が成立する。
(×) 単純逃走罪の主体は,裁判の執行により拘禁された未決又は既決の者であり,逮捕中の者はこれに含まれない(研修教材・三訂刑法各論(その2)207ページ,研修857号65ページ)。
⑵ 殺人事件の犯人のAは,友人Bを唆し,当該事件の当日,Aが別の場所でBと一緒にいたという内容のアリバイ証拠を偽造させた。この場合,Aには,証拠偽造罪の教唆犯が成立する。
(〇) 証拠隠滅罪の客体は,「他人の刑事事件に関する証拠」であるから,犯人自身が自己の刑事事件に関する証拠の隠滅,偽造等をしても同罪は成立しないが,犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を偽造するなどした場合については,判例は,犯人に証拠隠滅罪の教唆犯が成立するとしている(最決平18.11.21刑集60・9・770等,研修教材・三訂刑法各論(その2)219~221ページ)。
⑶ Aは,BがCに対して恐喝行為を行うところを目撃していなかったにもかかわらず,Bを被告人とする恐喝被告事件の公判において,証人として宣誓した上,BがCに恐喝行為を行うのを目撃したと証言した。このとき,BがCに対して恐喝行為を行ったのが真実だった場合は,Aの証言は「虚偽の陳述」に当たらないので,Aには,偽証罪は成立しない。
(×) 偽証罪の行為である「虚偽の陳述」について,判例・通説は,自己の記憶に反することの陳述を意味し,記憶に反する陳述がたまたま客観的事実に合致しても,偽証罪が成立すると解している(大判大3.4.29録20・654,研修教材・三訂刑法各論(その2)226,227ページ)。
⑷ Aは,Bが殺人事件を犯した犯人であることを知りながら,自宅においてBをかくまったが,警察は,その時点で,前記殺人事件を全く把握しておらず,捜査を開始していなかった。この場合,Aには,犯人蔵匿罪は成立しない。
(×) 判例は,罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることを知りながら,官憲による発見・逮捕を免れるように,真犯人をかくまった場合には,その犯罪に対する官憲の捜査が既に開始しているかどうかにかかわらず,犯人蔵匿罪が成立するとしている(最判昭28.10.2刑集7・10・1879,研修教材・三訂刑法各論(その2)214ページ)。
⑸ Aは,交番前で立番勤務中の警察官Bを狙って石を投げ付けたが,その石はBの耳付近をかすめただけで命中せず,Bの職務の執行が妨害されることはなかった。この場合,Aに公務執行妨害罪が成立することはない。
(×) 判例は,公務執行妨害罪の暴行・脅迫は,職務執行の妨害となるべき程度のもので足り,それによって現実に職務執行妨害の結果が発生したことを要しないとしており(最判昭25.10.20刑集4・10・2115),警備中の警察官に対して1回だけ投石したが命中しなかった行為につき,相手方の職務の執行の妨害となるべき性質のものであり,本罪の暴行に当たるとしている(最判昭33.9.30刑集12・13・3151,研修教材・三訂刑法各論(その2)176ページ)。
刑事訴訟法
第16問
逮捕・勾留に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 侮辱事件の被疑者を同事件で通常逮捕することが許されることはない。
(×) 侮辱罪(刑法231条)の法定刑は,拘留又は科料であるが,拘留又は科料に当たる罪であっても,被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合には通常逮捕することができる(刑事訴訟法199条1項ただし書,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)110ページ)。
⑵ 軽犯罪法違反事件の現行犯人が逃亡するおそれがあるときは,これを同事件で現行犯逮捕することができる。
(〇) 軽犯罪法違反の罪の法定刑は,拘留又は科料であるところ,拘留又は科料に当たる罪の現行犯については,犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り,現行犯逮捕することができる(刑事訴訟法217条,213条,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)125ページ,研修846号49,50ページ)。
⑶ 脅迫事件の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合において,急速を要し,逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を同事件で緊急逮捕することができる。
(×) 脅迫罪(刑法222条)の法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金であるところ,緊急逮捕することができるのは,法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に限られている。また,緊急逮捕が許される嫌疑の程度は,通常逮捕の場合の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」より高い「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」である(刑事訴訟法210条1項,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)121ページ,研修846号47ページ)。
⑷ 軽犯罪法違反事件で逮捕された被疑者が定まった住居を有する場合には,被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときであっても,これを同事件で勾留することはできない。
(〇) 軽犯罪法違反の罪の法定刑は,拘留又は科料であるところ,拘留又は科料に当たる事件については,被疑者が定まった住居を有しない場合に限り勾留することができる(刑事訴訟法207条1項,60条3項,1項,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)136ページ)。
⑸ 窃盗事件で勾留中の被疑者について,勾留期間の満了日に,5日間の勾留期間の延長を請求し,これが認められた場合には,やむを得ない事由があるときであっても,延長後の勾留期間中に,更に勾留期間の延長を請求することはできない。
(×) やむを得ない事由があるときは,勾留期間の延長を請求することができるところ,その期間の延長は通じて10日を超えることができないとされており,通じて10日以内であれば2回以上繰り返して行ってもよい(刑事訴訟法208条2項,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)142ページ)。
第17問
令状による捜索差押えに関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 被疑者方居室を捜索場所とする捜索差押許可状に基づき捜索を実施する際,同居室で被疑者と同居する者がその場で携帯しているバッグを捜索することが許されることはない。
(×) 判例(最決平6.9.8刑集48・6・263)は,「被告人の内妻(中略)に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,同女及び被告人が居住するマンションの居室を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を受け,(中略)右許可状に基づき右居室の捜索を実施したが,その際,同室に居た被告人が携帯するボストンバッグの中を捜索したというのであって,右のような事実関係の下においては,前記捜索差押許可状に基づき被告人が携帯する右ボストンバッグについても捜索できるものと解するのが相当である」と判示した(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)186,191ページ,研修848号75,76ページ)。
⑵ 身柄を拘束されていない被疑者について,強制採尿のための捜索差押許可状の発付を受けて採尿場所まで同行しようとしたが,同人が任意に同所に赴かず,同人を同所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には,同許可状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで同人を連行することができる。
(〇) 判例(最決平6.9.16刑集48・6・420)は,被疑者が任意同行を頑なに拒否する態度を取り続け,警察車両内で強制採尿令状を呈示された後も暴れて激しく抵抗したため,警察官らが被疑者の両腕を制圧して被疑者を病院まで連行した事案について,「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には,強制採尿令状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ,その際,必要最小限度の有形力を行使することができる」と判示した(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)193~195ページ,研修814号55,56ページ)。
⑶ 令状により差し押さえようとするパソコンの中に被疑事実に関する情報が記録されきている蓋然性が認められる場合において,そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは,内容を確認することなしに同パソコンを差し押さえることが許される。
(〇) 判例(最決平10.5.1刑集52・4・275)は,「差し押さえられたパソコン,フロッピーディスク等は,本件の組織的背景及び組織的関与を裏付ける情報が記録されている蓋然性が高いと認められた上,申立人らが記録された情報を瞬時に消去するコンピュータソフトを開発しているとの情報もあったことから,捜索差押えの現場で内容を確認することなく差し押さえられたものである。」とした上で,「令状により差し押さえようとするパソコン,フロッピーディスク等の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において,そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは,内容を確認することなしに右パソコン,フロッピーディスク等を差し押さえることが許されるものと解される。」と判示した。なお,関連する裁判例(大阪高判平3.11.6判タ796・264)として,「フロッピーディスクの一部に被疑事実に関連する記載が含まれていると疑うに足りる合理的な理由があり,かつ,捜索差押の現場で被疑事実との関連性がないものを選別することが容易でなく,選別に長時間を費やす間に,被押収者側から罪証隠滅をされる虞れがあるようなときには,全部のフロッピーディスクを包括的に差し押さえることもやむを得ない措置として許容される」と判示したものがあるほか(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)187,191,192ページ),リモートアクセスにより,メールサーバ等に保存されていたメールデータ等を複写するに当たり,対象となるデータについて被疑事実との関連性の有無を個別に確認することなく一括して複写することが違法ではないとした裁判例(大阪高判平30.9.11,研修849号25~30ページ)がある。
⑷ 被疑者方居室に対する捜索差押許可状により同居室を捜索中,宅配便の配達員によって被疑者宛てに配達され,同居室玄関で同人が受領した荷物についても,同許可状に基づき捜索することができる。
(〇) 判例(最決平19.2.8刑集61・1・1)は,「被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,被告人立会いの下に上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって被告人あてに配達され,被告人が受領した荷物について,警察官において,これを開封したところ,中から覚せい剤が発見されたため,被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し,逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。(中略)警察官は,このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である」と判示した(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)186,191ページ,研修848号75ページ)。
⑸ 捜索差押許可状に差し押さえべるき物として記載されていない物であっても,捜索場所から発見された物が法禁物の覚せい剤である場合には,同許可状によりこれを差し押さえることができる。
(×) 捜索差押許可状に差し押さえるべき物として記載されていない物については,その許可状により差し押さえることはできず,任意提出を受けるか,別に差押令状の発付を得てこれを差し押さえることが必要である。発見された物が覚せい剤であって,立会人等を所持事犯の現行犯人として逮捕する場合には,逮捕に伴う令状によらない差押え(刑事訴訟法220条1項)として押収することはできる(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)187ページ。なお,研修816号66,67ページ参照)。
第18問
公訴の提起に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 起訴状の公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならないが,その趣旨は,審判の対象・範囲を明確にさせ,被告人の防御に不利益を与えないようにすることにある。
(〇) 公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない(刑事訴訟法256条3項前段)。これは,検察官に訴因を掲げさせることによって,審判の対象・範囲を明確にさせ,被告人の防御に不利益を与えないようにしたものである(最判昭29.1.21刑集8・1・71,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)172ページ)。
⑵ 予断排除の原則から,公訴提起後第1回公判期日までは,勾留に関する処分は,受訴裁判所ではなく,事件の審判に関与しない裁判官が行う。
(〇) 予断排除の原則とは,裁判所は,第1回公判期日には,起訴された事件についての偏見又は予断を持たずに審理に臨まなければならないとする原則である。この原則は,憲法37条1項が規定する公平な裁判を実現させるためにある。公訴提起後第1回公判期日までは,勾留に関する処分は,受訴裁判所ではなく,事件の審判に関与しない裁判官が行う(刑事訴訟法280条1項)ことは,予断排除の原則の表れである(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)11~15ページ,研修854号68~70ページ)。
⑶ 起訴状一本主義の原則から,検察官は,略式命令の請求と同時に,裁判所に証拠書類を差し出すことはできない。
(×) 検察官は,公訴の提起と同時に書面で略式命令の請求を行い,略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない(刑事訴訟法462条1項,刑事訴訟規則289条1項)。なお,そのことで,起訴状一本主義が働かず,予断排除の原則に照らし,憲法37条1項に定める「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を害するのではないかとの議論もあったが,憲法上の「公平な裁判所の裁判」とは,偏頗や不公平のおそれのない組織・構成の裁判所による裁判をいうのであり(最判昭23.5.5刑集2・5・447),略式手続は,「公判前の手続」であって(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)241ページ),略式命令を受けた後に正式裁判の請求をして通常の規定に従った審判を求めることができることなどから,公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害するものではない。
⑷ 不告不理の原則から,共犯者のうち1人のみを起訴しても,起訴されていない共犯者については,公訴提起の効力が及ばず,公訴時効の進行も停止しない。
(×) 不告不理の原則とは,裁判所は検察官からの公訴提起のない事件について審理・裁判をすることは許されないとの原則である(研修教材・七訂検察庁法11ページ)。公訴の提起においては,起訴状により被告人及び公訴事実が特定され(刑事訴訟法256条2項及び3項),公訴提起の効力は,検察官の指定した被告人以外の者には及ばないが(刑事訴訟法249条),このことは共犯事件であっても同じである。ただし,共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を有する(刑事訴訟法254条2項)。
⑸ 親告罪につき,告訴のないまま公訴提起した場合,判決で公訴が棄却されるが,その後,有効な告訴が得られれば,再び公訴提起することができる。
(〇) 親告罪につき,告訴のないまま公訴提起した場合,公訴提起の手続が,その規定に違反したため無効であるから,裁判所は,実体審理に入らず,形式裁判である公訴棄却の裁判で訴訟係属を打ち切ることになり,判決で公訴が棄却される(刑事訴訟法338条4号)。その後,有効な告訴を受理すれば,再び公訴提起することができる(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)222,223ページ)。
第19問
公判における被害者保護等の制度に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 裁判所は,強制わいせつ罪の事件を取り扱う場合において,被害者からあらかじめ検察官に被害者特定事項秘匿の申出があり,これに検察官が相当意見を付して裁判所に通知したときは,被害者特定事項の秘匿決定をしなければならない。
(×) 裁判所は,刑事訴訟法290条の2第1項各号に規定された事件を取り扱う場合において,被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。裁判所が被害者特定事項を明らかにしない旨の決定をすることが適当でないと認めるときは,特段の決定をする必要はない。なお,この申出は,あらかじめ検察官にしなければならず,この場合において,検察官は,意見を付してこれを裁判所に通知する(刑事訴訟法290条の2第1項及び第2項,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)96,97ページ)。
⑵ 被害者特定事項の秘匿決定があったときは,起訴状朗読の手続は不要となる。
(×) 被害者特定事項の秘匿決定があった場合には,検察官による起訴状朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法で行う。この場合において,検察官は,被告人に起訴状を示さなければならない(刑事訴訟法291条2項,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)101ページ)。
⑶ 被害者特定事項の秘匿決定があったときは,証拠調べ手続において,証拠書類の朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法で行う。
(〇) 被害者特定事項の秘匿決定があった場合には,証拠書類の朗読は,被害者特定事項を明らかにしない方法で行う(刑事訴訟法305条3項,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)139ページ)。
⑷ ビデオリンク方式による証人尋問については,被告人の在任する裁判所の建物と同一の構内に当該証人が在席しているときにおいてのみすることができる。
(×) ビデオリンク方式による証人尋問については,以前は,被告人及び当該証人を同一構内に出頭させることとしていたが,平成28年の刑事訴訟法改正により,同一構内以外の場所であって,裁判所規則で定めるものに証人を在席させ,法庭にいる裁判官や訴訟関係人は,テレビモニターに映る証人の姿や声を見聞きしながら証人尋問を行うといういわゆる構外ビデオリンク方式による証人尋問の規定が設けられた(刑事訴訟法157条の6第2項,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)130ページ)。
⑸ 被害者参加人は,事実又は法律の適用について意見を陳述することができるから,過失運転致死罪で起訴された事件の公判期日において,法律の適用について,危険運転致死罪が成立するとの意見を陳述することも許される。
(×) 裁判所は,被害者参加人が事実又は法律の適用について意見を陳述することは,訴因として特定された事実の範囲内においてのみ許すとされているので,過失運転致死が訴因とされている被告事件において,危険運転致死罪が成立するとの意見を陳述することは,訴因として特定された事実の範囲を超えるものとして許されない(刑事訴訟法316条の38第1項,研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)162ページ)。
第20問
証拠に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 任意性が認められない被告人の自白を内容とする供述調書であっても,被告人の公判における供述の証明力を争うためであれば,証拠とすることができる。
(×) 任意性が認められない被告人の自白を内容とする供述調書は,刑事訴訟法328条によっても証拠とすることはできない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)201ページ,研修836号71ページ)。
⑵ 自白の補強証拠は,本人の供述以外の証拠でなければならないので,捜査機関に対する自白を公判廷における自白の補強証拠とすることはできない。
(〇) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)113ページ,研修834号84,85ページ)。
⑶ A及びBを共犯者とする詐欺事件の捜査の過程で作成されたAの自白を内容とする検察官面前調書は,当該詐欺事件に係るBの公判において,刑事訴訟法326条の同意がなくても,同法321条1項2号の要件を充たせば,証拠とすることができる。
(〇) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法125,126ページ)。
⑷ 司法警察職員がAの犯行を現認したことが記載されている当該司法警察職員作成の現行犯人逮捕手続書を,Aの犯行を立証するために用いる場合,この現行犯人逮捕手統書は公務員の作成した書面であるから,刑事訴訟法323条1号によって証拠とすることができる。
(×) 捜査機関が作成する捜査報告書は,一般に刑事訴訟法323条書面には該当せず,同法321条1項3号書面に該当するにすぎない(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)184ページ,研修838号74,75ページ。最決昭24.4.25裁判集9・447も,司法警察職員の作成した捜査報告書が刑訴法323条書面に当たらない旨を判示している。)。
⑸ 正当防衛の成否に関する挙証責任は,検察官ではなく,被告人が負っている。
(×) 犯罪構成要件に該当する事実の存在や被告人が犯人であることのみならず,違法性阻却事由(正当防衛を含む。)や責任阻却事由が存在しないことについても,検察官が挙証責任を負っている(研修教材・八訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)17ページ)。
事件事務(令状事務含む)
第21問
事件の受理に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 事件の受理手続は,事件事務規程3条各号に掲げられた事由が生じた場合に行うこととされており,同条各号に掲げられた事由は,被疑事件の受理事由を全て網羅している。
(〇) そのとおり(研修教材九訂・事件事務解説5ページ,研修852号49ページ)。
⑵ 裁判所による移送の裁判によって事件が対応裁判所の公判に係属した場合,事件の受理手続を行う必要はない。
(〇) そのとおり。裁判所による移送の裁判によって事件が対応する裁判所の公判に係属した場合には,事件の受理手続は行わず,「公判事件の管理」として検察システムによる管理をする(事件事務規程91条1項,研修教材・九訂事件事務解説8ページ,研修852号49ページ)。
⑶ 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けた場合,これは検察庁間におけるいわゆる移送であるから,事件の受理手続を行う必要はない。
(×) 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたときは,事件事務規程3条2号により事件の受理手続を行う(研修852号52ページ)。
⑷ 不起訴処分に付した事件について,検察審査会において不起訴不当の議決がなされ,その議決書の謄本の送付を受けた場合,起訴する見込みがないときには,事件の受理手続を行う必要はない。
(×) 検察審査会において不起訴不当の議決があり,その議決書の謄本の送付を受けたときは,事件事務規程169条2項により事件を再起し同規程3条6号により事件の受理手続を行う(研修教材・九訂事件事務解説7,108ページ,研修852号54ページ)。
⑸ 中止処分に付した事件について,公訴時効が完成した場合は,改めて事件の受理手続を行う必要はない。
(×) 中間処分である中止処分に付した事件について,公訴時効が完成するなどの不起訴処分に付する事由が生じた場合には,事件を再起した上,終局処分である不起訴処分を行うが,その事件再起の際は,事件事務規程3条6号により事件の受理手続を行う(研修852号55ページ)。
第22問
逮捕に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 逮捕状の請求は,やむを得ない事情があるときは,最寄りの下級裁判所の裁判官にこれをすることができるが,この場合の下級裁判所には,地方裁判所,簡易裁判所のみならず,高等裁判所及び家庭裁判所も含まれると解されている。
(〇) そのとおり。刑事訴訟規則299条1項に規定する「下級裁判所」とは,裁判所法2条1項にいう下級裁判所の全て,すなわち,地方裁判所,簡易裁判所のみならず,高等裁判所及び家庭裁判所を含むと解されている(研修856号46ページ,増補令状基本問題上27,28ページ)。
⑵ 検察事務官は,いわゆる緊急逮捕状を請求することはできないが,いわゆる通常逮捕状の請求をすることはできる。
(×) 検察事務官は,いわゆる通常逮捕状の請求をすることはできないが,いわゆる緊急逮捕状の請求をすることはできる(刑事訴訟法199条2項,210条1項,研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)111,123ページ,研修教材・九訂事件事務解説19ページ,研修856号45ページ)。
⑶ 逮捕状は,裁判官が捜査機関に対して一定の強制処分を行う権限を付与する許可状の性質を持つものであるから,逮捕状が発付されたとしても,逮捕をするかどうかについては,捜査機関の裁量に委ねられている。
(〇) そのとおり(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)108,109ページ,研修856号45ページ)。
⑷ 司法警察員は,逮捕状により逮捕した被疑者を留置する必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならないとされているので,48時間以内に身柄が検察官に到達することが必要である。
(×) 被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に検察官に送致する手続をすれば足り,48時間以内に検察官に到達していなくても構わないとされている(研修854号54ページ)。
⑸ 逮捕状が発付された後,逮捕状に記載された引致場所を変更する必要が生じたときは,逮捕状の記載事項の変更であるから,改めて逮捕状を請求する必要がある。
(×) 引致場所の変更については,引致場所変更請求書により裁判官に対し,その変更を求める(事件事務規程17条,研修教材・九訂事件事務解説20,21ページ,研修856号48ページ)。
第23問
勾留に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 甲事実で逮捕した被疑者について,甲事実のほか乙事実を付加して勾留請求することは,逮捕前置主義に反するので許されない。
(×) 甲事実については逮捕が先行している以上,乙事実について改めて逮捕手続から逮捕・勾留の司法審査を繰り返す実益はなく,拘束時間の観点からも乙事実を付加することによる被疑者の不利益はないことから,逮捕されている甲事実に逮捕されていない乙事実を付加して勾留請求することは,一般的に許されると解されている(研修教材・八訂刑事訴訟法I(捜査)138ページ,研修856号51,52ページ。)。
⑵ 勾留状の執行については,令状を所持していないためこれを被告人に示すことができない場合には,急速を要するときであっても,執行することができない。
(×) 勾留状を所持しないためこれを被告人に示すことができない場合において,急速を要するときは,被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げてその執行をすることができる(刑事訴訟法73条3項,研修856号55ページ)。
⑶ 勾留期間延長の裁判は,所定の勾留状を検察官に交付することによってその効力を生じ,検察官の執行指揮は不要である。
(〇) そのとおり(刑事訴訟規則153条1項・2項,研修教材・九訂事件事務解説27ページ,研修856号57ページ)。
⑷ 被告人の勾留期間更新決定の執行は,更新前の勾留期間内になされなければならない。
(〇) そのとおり(研修教材・九訂事件事務解説93ページ,研修857号41ページ)。
⑸ 勾留中の被告人について,刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは,勾留状は効力を失うので,検察官は,直ちに「釈放指揮書」により釈放の指揮をしなければならない。
(×) 刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは,勾留状はその効力を失う(刑事訴訟法345条)ので,検察官の釈放指揮の手続を要せず,直ちに被告人の身柄の拘束が解かれるが,同条により被告人が釈放されたときは,検察官は,直ちに釈放通知書(丁)により,その者が収容されていた刑事施設の長に対してその旨を通知する(事件事務規程143条。研修教材・九訂事件事務解説101ページ,研修857号46,47ページ)。
第24問
事件の処理等に関する次の記述のうち,正しいものには〇の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なときの不起訴裁定の主文は,「嫌疑なし」とする。
(×) 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なときは,「罪とならず」とする(ただし,刑事未成年又は心神喪失に該当する場合を除く。)(事件事務規程75条2項16号,研修教材・九訂事件事務解説74ページ)。
⑵ 公訴の時効が完成したときの不起訴裁定の主文は,「刑の免除」とする。
(×) 公訴時効が完成したときは,「時効完成」とする(事件事務規程75条2項13号,研修教材・九訂事件事務解説73ページ)。
⑶ 勾留されている被告人について公訴を提起したときは,速やかに裁判所の裁判官に逮捕状及び勾留状を差し出さなければならないが,A事実で逮捕及び勾留された後釈放された被告人についてA事実で公訴を提起したときは,A事実の逮捕状及び勾留状を差し出す必要はない。
(×) 逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも,逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない(刑事訴訟規則167条1項,研修教材・九訂事件事務解説61ページ)。
⑷ 刑事訴訟法261条の規定による告訴人,告発人又は請求人に対する不起訴理由の告知に当たっては,裁定主文のみならず,不起訴裁定書記載の理由も必ず告知しなければならない。
(×) 刑事訴訟法261条の規定による告訴人,告発人又は請求人に対する不起訴理由の告知については,裁定主文のみを告知すれば足りる。ただし,裁定の理由等を告知することが禁止されているものではなく,被害者への配慮の必要上,刑事訴訟法47条の趣旨を踏まえつつ,具体的な不起訴裁定の理由を説明することが適当な場合もある(研修教材・九訂事件事務解説76ページ,研修859号91ページ)。
⑸ 刑事訴訟法259条の規定による被疑者に対する不起訴処分の告知に当たっては,不起訴処分に付したことを告知すれば足り,裁定主文まで告げる必要はない。
(〇) そのとおり(研修教材・九訂事件事務解説76ページ,研修859号91,92ページ)。
第25問
被疑者又は被告人の勾留に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 次の設例における被疑者の勾留期間の満了日は,令和2年2月14日(金)である。
【設例】
令和2年2月4日(火) 勾留請求,勾留請求済証明書を交付して留置施設に留置
令和2年2月5日(水) 勾留状発付,勾留状執行,勾留状指定の留置施設に引致
(×) 被疑者の勾留期間は,勾請の請求をした日から10日間であり,勾留状の発付が勾留請求の翌日となったとしても勾留期間の起算日は勾留請求の日である。勾留の期間は,初日(勾留請求の日)を算入する。したがって,勾留請求の日である令和2年(以下,全て令和2年)2月4日を起算日として10日後の2月13日が勾留期間の満了日となる(刑事訴訟法208条1項,55条,研修教材・九訂事件事務解説35ページ,研修856号55,56ページ)。
⑵ 次の設例における被告人の勾留期間の満了日は,令和2年3月14日(土)である。
【設例】
令和2年1月15日(水) 逮捕中の被疑者を公訴提起(公訴事実は逮捕の基礎となった事実と同一)
令和2年1月16日(木) 勾留状発付,勾留状執行,勾留状指定の留置施設に引致
(〇) 被告人の勾留期間は,公訴提起の日から2か月であり,逮捕中の被疑者に対し,逮捕の基礎となった犯罪事実と同一の事実について公訴が提起された場合も同様である。2か月の期間は,暦に従ってこれを計算する。末日が日曜日,土曜日その他休日に当たっても,期間に算入する。したがって,公訴提起の日である1月15日を起算日として2か月後の3月14日が勾留期間の満了日となる(刑事訴訟法60条2項,55条,研修教材・九訂事件事務解説94ページ,研修857号38~40ページ)。
⑶ 次の設例における残勾留日数は,1か月と15日である。
【設例】
令和2年1月20日(月) 勾留中の被疑者を公訴提起(公訴事実は勾留の基礎となった事実と同一)
令和2年2月4日(火) 保釈により釈放
(〇) 残勾留日数の算出方法は,釈放の日の翌日から当初の勾留期間の満了日までの日数を算出し,その日数が1か月を超えるときは「1か月と○日」として算出する。釈放の日,収容の日は,ともに勾留日数に含まれる。釈放の日の翌日である2月5日から当初の勾留期間満了日である3月19日までの日数を計算すると,2月5日から3月4日まで1か月,3月5日から3月19日までが15日であるので,残勾留日数は,「1か月と15日」となる(研修教材・九訂事件事務解説95,96ページ,研修857号41~43ページ)。
⑷ 次の設例における残勾留日数は,1か月と3日である。
【設例】
令和元年12月18日(水) 勾留中の被疑者を公訴提起(公訴事実は勾留の基礎となった事実と同一)
令和2年2月10日(月) 勾留期間更新決定(2月18日から1か月の分),同執行
令和2年2月14日(金) 保釈により釈放
(×) 当初の勾留期間に加え,釈放前における勾留期間更新決定の執行がある場合の残勾留日数は「○日と1か月」として算出する。釈放の日の翌日である2月15日から当初の勾留期間満了日である2月17日までの3日と勾留期間更新決定の執行による1か月が存在するので「3日と1か月」となる(研修教材・九訂事件事務解説96ページ,研修857号41~44ページ)。
⑸ 次の設例における被告人を刑事施設に収容した後の勾留期間の満了日は令和2年3月15日(日)である。
【設例】
令和2年1月10日(金) 勾留中の被疑者を公訴提起(公訴事実は勾留の基礎となった事実と同一)
令和2年2月29日(土) 勾留執行停止決定により釈放
令和2年3月6日(金) 勾留執行停止期間満了により刑事施設に収容
(×) 釈放の日の翌日である3月1日から当初の勾留期間満了日である3月9日までを算出すると,残勾留日数は9日となる。刑事施設に収容された日である3月6日を初日として,9日目の3月14日が勾留期間満了日となる(研修教材・九訂事件事務解説94~96ページ,研修857号41~44ページ)。