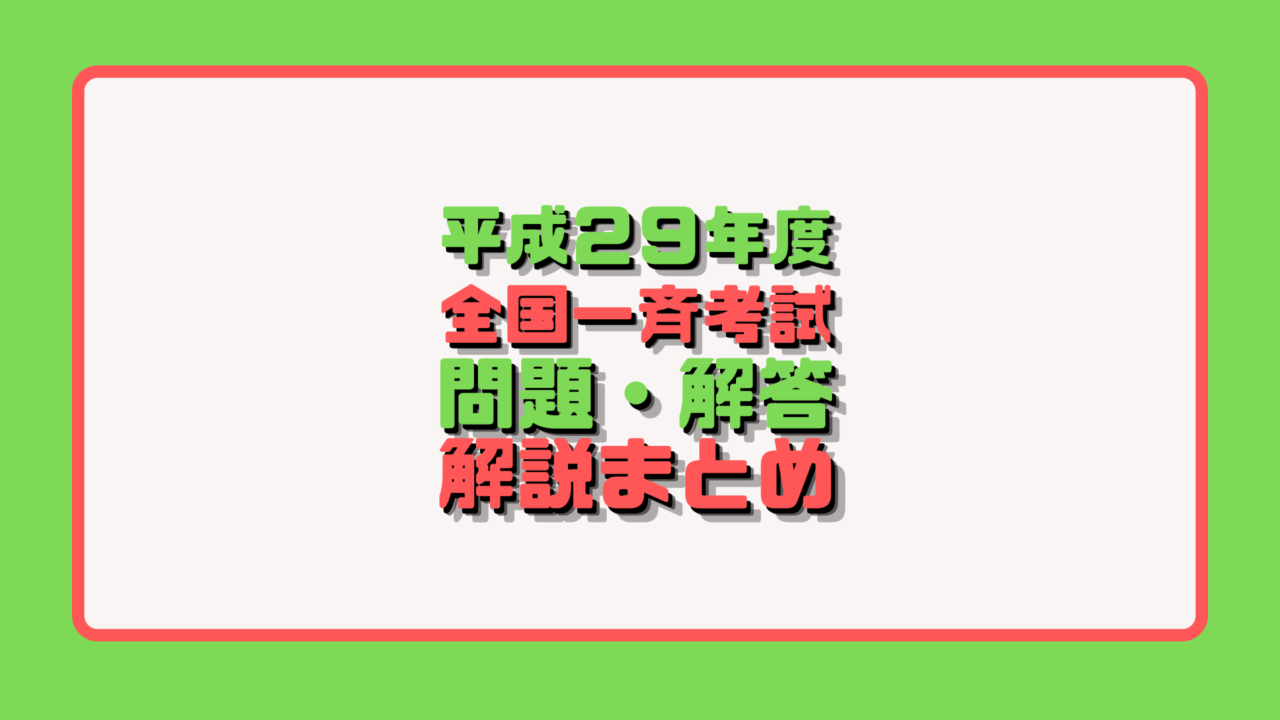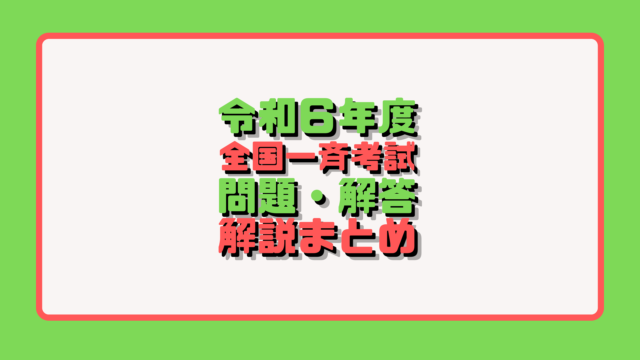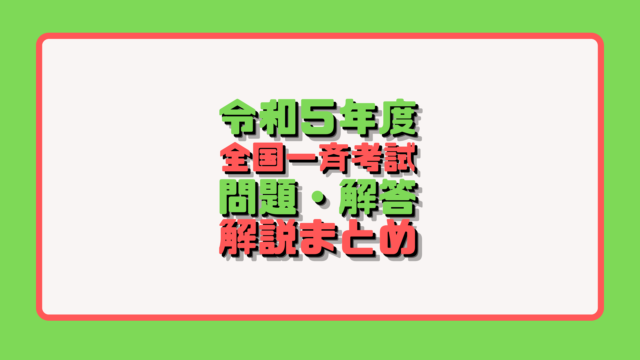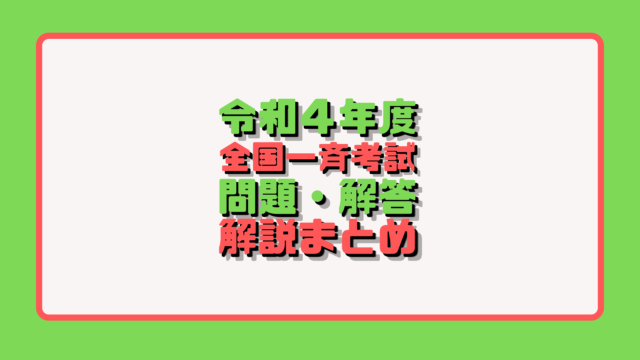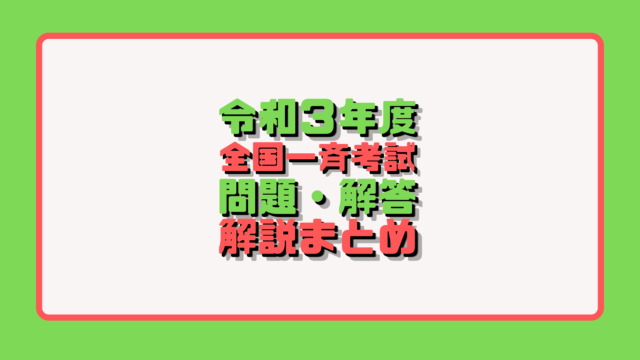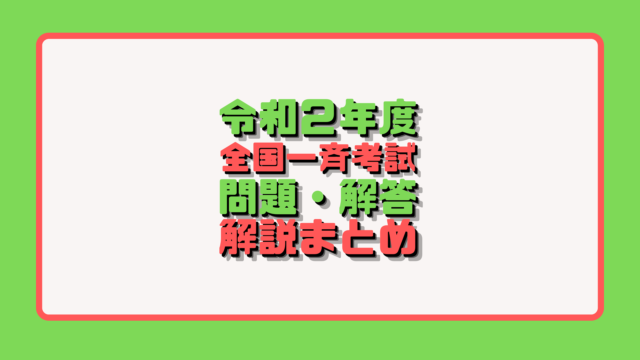憲法・検察庁法
第1問
基本的人権に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 内国の法人には,憲法が保障する人権は,性質上可能な限り保障されるが,政治活動の自由は,その性質上,保障されない。
(×) 判例(いわゆる八幡製鉄事件,最大判昭45.6.24民集24・6・625)は,「憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は,性質上可能な限り,内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから,会社は,自然人たる国民と同様,国や政党の特定の政策を支持,推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するものである。」旨判示し,法人に政治活動の自由が保障されることを認めている。なお,この判例に対しては,会社の政治的行為の自由に何ら特別の制約を認めなかったのは行き過ぎであり,妥当ではないとの批判があり,どのような人権について,どのような法人に対し,どのような程度で保障を認めるかに関しては,なお検討の余地があるといわれている(研修教材・五訂憲法53~56ページ,研修822号61〜65ページ)。
⑵ 憲法第3章の各規定は,国又は公共団体と個人との関係のみならず,私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から一方が他方に優越し事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合には,直接適用される。
(×) 憲法の基本的人権の規定が私人間にどのように適用されるかの問題について,判例(いわゆる三菱樹脂事件,最判昭48.12.12民集27・11・1536,研修教材・五訂憲法71~73ページ)は,憲法19条及び14条は,「同法第3章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく,国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので,もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。」とし「私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から,一方が他方に優越し,事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合があり,このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは,劣位者の自由や平等を著しく侵害又は制限することとなるおそれがあることは否み難いが,そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用又は類推適用を認めるべきであるとする見解もまた,採用することはできない。」とし「私的支配関係においては,個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは,これに対する立法措置によってその是正を図ることが可能であるし,また,場合によっては,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって,一面で私的自治の原則を尊重しながら,他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し,その間の適切な調整を図る方途も存する」などと判示し,間接適用説を採ったとみられる判断を示している。
⑶ 国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは,憲法13条の趣旨に反して許されない。
(〇) 判例(いわゆる指紋押なつ拒否事件,最判平7.12.15刑集49・10・842,研修教材・五訂憲法64,65ページ)は,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり,国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは,憲法13条の趣旨に反して許され」ない旨判示している。
⑷ 裁判所が,他人の名誉を毀損した者に対し,当該名誉を回復する手段として,新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は,その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものであれば,憲法19条に違反しない。
(〇) 判例(最判昭31.7.4民集10・7・785,研修教材・五訂憲法96,97ページ)は,裁判所が他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復するに適当な処分として新聞紙に謝罪広告を掲載すべきことを命ずる判決について単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものであれば,憲法19条に違反しない旨判示している。
⑸ 公立高校の校長が,信仰上の理由により必須科目である体育の剣道実技に参加しなかった生徒に対し,代替措置として,他の体育実技を履修させるなどした上でその成果に応じて評価をすることは,その目的において宗教的意義を有し,特定の宗教を援助,助長,促進する効果を有するものであり,憲法20条3項に違反する。
(×) 判例(最判平成8.3.8民集50・3・469,研修教材・五訂憲法99,100ページ)は,本問と同様の事案において,信仰上の理由により必須科目である体育の剣道実技に参加しなかった生徒に対し,公立高等専門学校の校長が退学処分としたことについて,裁量権の範囲を超える違法なものと判断し,さらに,当該生徒に特別な措置を採ることが政教分離の原則に違反しないかの問題について,代替措置として,他の体育実技の履修等を求めた上で,その成果に応じた評価をすることが,その目的において宗教的意義を有し,特定の宗教を援助,助長,促進する効果を有するものということはできず,他の宗教者又は無宗教者に圧迫,干渉を与える効果があるものともいえないとして,憲法20条3項に違反しない旨判示している。
第2問
経済的自由権に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 「市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明した場合,市は当該入居者に対し市営住宅の明渡しを請求することができる」旨を定めた条例の規定は,憲法22条1項に違反する。
(×) 判例は,市営住宅の入居者が暴力団員であると判明した場合,市は当該入居者に対し市営住宅の明渡しを請求することができる旨定めた条例につき,憲法22条1項に違反しないとしている(最判平27.3.27民集69・2・419,研修816号57ページ)。
⑵ 海外渡航の自由は,憲法22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるが,外務大臣において,あらかじめ法務大臣と協議の上,旅券の発給を受けようとする者が,著しく,かつ,直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があると認定した場合に旅券の発給を拒否することは,憲法22条2項に違反しない。
(〇) 海外渡航の自由は,憲法22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるが,公共の福祉による制約があり(最大判昭33・9・10民集12・13・1965,研修教材・五訂憲法147ページ),旅券法13条1項7号,2項により,外務大臣において,あらかじめ法務大臣と協議の上,著しく,かつ,直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者と認定した場合は,旅券の発給を拒否することができる。
⑶ 憲法29条1項の「財産権」に,著作権,特許権は含まれない。
(×) 憲法29条1項は,個人が現有する具体的な財産権の保障と同時に,個人が財産権を享有し得る法制度の保障を意味し,「財産権」は,所有権のほか物権・債権・無体財産権(特許権・著作権等)・営業権・漁業権及び公益上の権利である水利権などを含む(研修教材・五訂憲法155ページ)。
⑷ ため池の破損,決壊による災害を未然に防止するためであっても,条例により,ため池に財産上の権利を有する者に対して,農作物の種類を限定せず,ため池の堤とうに農作物を植える行為を禁止することは,憲法29条に違反する。
(×) 判例(いわゆる奈良県ため池条例事件,最大判昭和38.6.26刑集17・5・521,研修教材・五訂憲法156ページ)は,設問同様の条例による規制について,結果的に,堤とうを使用する権利を有する者の財産権行使が殆ど全面的に禁止されることになるが,災害を未然に防止するという社会生活上やむを得ない必要から来ることであって,公共の福祉のため,当然これを受忍しなければならない旨,これらを条例で禁止しても憲法及び法律に抵触も逸脱もしておらず,また,当該条例により規定するような事項を既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから,これを条例で定めるからといって違憲でも違法でもない旨判示し,当該規制が公共の福祉に適合する規制であると判断するとともに,条例による財産権の制限を合憲としている。
⑸ 被告人以外の第三者の所有物について,当該第三者に対し,告知,弁解,防禦の機会を与えずに没収することは,憲法29条及び31条に違反する。
(〇) 判例(最大判昭37.11.28刑集16・11・1593,研修教材・五訂憲法132ページ)は,関税法による第三者の所有物の没収手続の合憲性が争われた事案につき,「所有物を没収せられる第三者についても,告知,弁解,防禦の機会を与えることが必要であって,これなくして第三者の所有物を没収することは,適正な法律手続によらないで,財産権を侵害する制裁を科するに外ならない」旨判示し,当時の関税法による第三者の所有物の没収手続が憲法31条,29条に違反するとした。この判決を契機として「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定された。
第3問
国会等に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 参議院の緊急集会が開かれている期間中に内閣総理大臣が欠けた場合でも,緊急集会において,内閣総理大臣を指名することはできない。
(〇) 内閣総理大臣の指名は,総選挙後,新たに国会が召集されたときに,国会が行うものであり,緊急集会において行うことはできない(研修教材・五訂憲法219ページ)。
⑵ 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための弾劾裁判所は,衆議院議員のみをもって組織することができる。
(×) 弾劾裁判所は,両議院の議員によって組織されるものである(憲法64条)。
⑶ 国務大臣は,答弁又は説明のため出席を求められない限り,議院に出席することができない。
(×) 国務大臣は,何時でも議案について発言するため議院に出席することができる(憲法63条)から,答弁又は説明のため出席を求められていなくても,議院に出席することは可能である。
⑷ 両議院は,それぞれの総議員の3分の1以上の出席がない場合,議決することができないが,議事を開くことはできる。
(×) 議決するのみならず,議事を開くに当たっても,総議員の3分の1以上の出席が必要である(憲法56条1項)。
⑸ 内閣が予備費を支出した後,国会がこれを承諾しなかった場合でも,既に行われた予備費の支出は有効である。
(〇) そのとおり(研修教材・五訂憲法279,280ページ)。
第4問
地方自治に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 憲法上の地方公共団体と言い得るためには,単に法律で地方公共団体として取り扱われているというだけでは足りず,事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,現実の行政の上でも,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。
(〇) そのとおり(最大判昭38.3.27刑集17・2・121)。
⑵ 地方公共団体は,条例制定権を有するが,これは,国会単独立法の原則に対する憲法上の例外である。
(×) 地方公共団体の条例制定権は,国会中心立法の原則に対する例外である(研修教材・五訂憲法196ページ)。
⑶ 条例は,公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であるので,法律の授権がなくても,条例によって刑罰を定めることができる。
(×) 最大判昭37.5.30刑集16・5・577は,「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく,法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきである。(中略)条例は,法律以下の法令といっても上述のように,公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって,行政府の制定する命令等とは性質を異にし,むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから,条例によつて刑罰を定める場合には,法律の授権が相当な程度に具体的であり,限定されておれば足りると解するのが正当である」と判示している。
⑷ 条例で,都道府県知事を,都道府県議会の議員の中から議会の議決によって選出する制度を創設することは,憲法に違反する。
(〇) そのとおり。憲法93条2項は,地方公共団体の長については,その地方公共団体の住民による直接選挙を要請している。
⑸ 一つの地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することはできない。
(〇) そのとおり(憲法95条)。
第5問
検察庁法に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察庁法4条に定める裁判の執行を監督する権限には,勾引状や勾留状の執行を指揮する権限は含まれない。
(×) 研修教材・6訂検察庁法12~13ページ。
⑵ 地方裁判所の支部が設けられても,法務大臣が必要と認めなければ,これに対応する地方検察庁の支部を設けなくてもよい。
(〇) 研修教材52ページ。
⑶ 検事総長及び検事長の任免は,内閣が行い,天皇がこれを認証し,次長検事,検事及び副検事の任免は,法務大臣が行う。
(×) 研修教材69ページ。
⑷ 検事正は,検察庁法12条に定める事務引取移転権をもってすれば,同法附則36条に定める検察官事務取扱検察事務官に,地方検察庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。
(×) 研修教材85~86ページ。
⑸ 検察庁法附則36条に定める検察官事務取扱検察事務官は,その属する区検察庁に検察官が配置されていない場合には,当該区検察庁の庁務の掌理,職員の監督その他の検察行政事務をも取り扱うことができる。
(〇) 研修教材85ページ。
民法(総則・物権)
第6問
未成年者がした契約の取消しに関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 未成年者Aは法定代理人Bの同意を得ないで,自転車をCから購入する契約をした。この場合,Cは当該契約を取り消すことができる。
(×) 未成年者がした契約の相手方は,当該契約の取消権者に当たらない(民法120条1項,研修教材・七訂民法I(総則)20ページ)。
⑵ 未成年者Aは法定代理人Bの同意を得ないで,自転車をCから購入する契約をした。その際,Aは自己が成年者であると信じさせるため詐術を用いたが,そのことをBは知らなかった。この場合,Bは当該契約を取り消すことができる。
(×) 契約締結に際して詐術が用いられた場合,当該契約は取り消すことができなくなり(民法21条),法定代理人もそのことについての知・不知を問わず,取り消すことはできない(研修教材・七訂民法I(総則)39ページ)。
⑶ 未成年者Aは法定代理人Bの同意を得ないで,友人Cから自由に使ってよいとしてもらった現金で代金を支払うつもりで,自転車をDから購入する契約をした。この場合,Bは当該契約を取り消すことができる。
(〇) 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は未成年者が自由に処分することができるが(民法5条3項後段),法定代理人ではない者が同様にした財産はこれに当たらない(研修教材・七訂民法I(総則)20ページ)ので,原則どおり取り消すことができる。
⑷ 未成年者Aは法定代理人Bの同意を得ないで,自転車をCに売却する契約をした。その後,BはAに無断で,異議をとどめずに,Cに代金の支払を請求した。この場合,Aは当該契約を取り消すことができる。
(×) 法定代理人が契約の相手方に代金の支払を請求したことにより,追認をしたものとみなされる(民法124条3項,125条2号,研修教材・七訂民法I(総則)151,152ページ)ので,以後,取り消すことはできない(同法122条本文,同書151ページ)。
⑸ 未成年者Aは法定代理人Bの同意を得ないで,自転車をCから購入する契約をした。その後,Aが未成年者の間に,CはBに対し当該契約を追認するかどうかを1か月間以内に確答するよう催告したが,Bはその期間内に確答を発しなかった。この場合,Bは当該契約を取り消したものとみなされる。
(×) 当該契約を取り消したものではなく,追認したものとみなされる(民法20条2項,1項後段,研修教材・七訂民法I(総則)38ページ)。
第7問
AはBの代理人としてCとの間でB所有の土地の売買契約をしたが,Aは当該土地の賃貸借契約をする代理権は有していたものの,その売買契約をする代理権は有していなかったという無権代理の事例に関する次の記述のうち,正しいものには〇の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 当該売買契約の時,CがAは当該売買契約をする代理権を有していると過失なく信じていた場合,CはBに対し,当該土地の引渡しを請求することができる。
(〇) 民法110条の表見代理が成立する(研修教材・七訂民法I(総則)135ページ)。
⑵ 当該売買契約の時,CがAは当該売買契約をする代理権を有していると過失なく信じていた場合,Cは,Aに対し,損害賠償を請求することはできない。
(×) 民法117条1項の無権代理人の責任を追及できる。これは民法110条の表見代理が成立する場合でも可能である(最判昭62.7.7民集41・5・1133,研修教材・七訂民法I(総則)142ページ)。
⑶ 当該売買契約の時,CがAは当該売買契約をする代理権を有していると過失により信じていた場合,Bが当該売買契約を追認する前であっても,Cは,当該売買契約を取り消すことはできない。
(×) 善意なので過失があっても,Bが追認をしない間は,取り消すことができる(民法115条ただし書,研修教材・七訂民法I(総則)141ページ)。
⑷ 当該売買契約の時,CがAは当該売買契約をする代理権を有していると信じていたか否かにかかわらず,Aは,当該売買契約を取り消すことはできない。
(〇) 無権代理人は,取消権者に当たらない(民法115条本文,研修教材・七訂民法I(総則)141ページ)。
⑸ 当該売買契約の時,CがAは当該売買契約をする代理権を有していると過失により信じていた場合,Cが,Bに対し,相当の期間を定めて,その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたところ,Bがその期間内に確答をしなかったときは,CはBに対し,当該土地の引渡しを請求することができる。
(×) 善意だが有過失なので,民法110条の表見代理は成立しない(研修教材・七訂民法I(総則)135ページ)。また,本人が確答をしなかったことによって当該売買契約の追認を拒絶したものとみなされる(民法114条,同書141ページ)。その結果,無権代理が確定する。
第8問
不動産物権変動に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,自己の所有する甲土地をBに売却した。その後,Aは,甲土地をCにも売却した。甲土地についてAからBへの所有権移転登記がない場合,Cは,AからCへの所有権移転登記がなくても,Bに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
(×) 甲土地についてAからB,AからCへの二重譲渡が行われているので,両者は対抗関係に立つ。Cが甲土地の所有権をBに主張できるかどうかは,C自身が甲土地の所有権移転登記を備えているかどうかで決せられ,Bに登記がないことは関係がない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)28~53ページ,研修819号50,51ページ)。
⑵ Aの所有する甲土地について,Bが所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を開始した。その後,Aは甲土地をCに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。更にその後,甲土地についてBの前記占有開始から20年が経過し,Bの取得時効が完成した。Bは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
(×) 不動産の時効取得者は,取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受け,その旨の移転登記を経由した者に対しては,登記がなくても,時効による所有権の取得を主張することができる(最判昭41.11.21民集20・9・1901,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)32ページ)。
⑶ Aは,自己の所有する甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。その後,Aは,Bの詐欺を理由に甲土地の売買契約を取り消したが,その旨の登記手続がされる前に,Bが甲土地をCに売却して,BからCへの所有権移転登記がされた。Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
(〇) 取消し又は解除後の第三取得者に対抗するためには登記を要し,これらの者との優劣は二重譲渡と同様の関係に立つと見て,登記の前後によって決定すべきであるとするのが判例である(大判昭17.9.30民集21・911等)。したがって,本問の場合,登記を備えていないAは,Cに対して所有権を主張できない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)30,31ページ)。
⑷ Aは,自己の所有する甲土地をBに売却したが,その旨の所有権移転登記がされる前にAが死亡し,Aの唯一の相続人Cが甲土地の相続登記を備えた。Bは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
(〇) 相続は,被相続人の地位が包括的に相続人に移転する包括承継であるから(民法896条),本問のCは,原則としてAと一体とみられ,Bのために甲土地の所有権移転登記をする義務が生じることとなるので,BとCは対抗関係にはならず,Bは,Cに対し,登記なくして所有権を主張することができる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)34ページ,研修819号52,53ページ)。
⑸ Aは,自己の所有する甲土地をBに売却し,その後,Bが,甲土地をCに売却したが,登記名義はいまだAのままである。Cは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
(×) 不動産がAからB,BからCへと転々譲渡された場合のAは,BC間の当該不動産の譲渡について登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に当たらない。したがって,本問のCはAに対して,登記なくして所有権を主張することができる(最判昭39.2.13裁判集民72・145,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)45ページ,研修819号50~52ページ)。
第9問
即時取得に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,Bから甲宝石を預かって保管していた。その後Aが死亡し,Aの唯一の相続人Cは,Aが甲宝石の所有者であると過失なく信じ,平穏かつ公然に甲宝石の占有を開始した。Cは,甲宝石の所有権を即時取得する。
(×) 即時取得は動産取引の安全を図るものであり,保護されるのは,「取引行為によって」「占有を始めた者」である(民法192条)。したがって,相続による取得(包括承継)のように法律上当然に取得の効果が発生する場合には適用がない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)60ページ)。
⑵ Aは,Bから甲宝石を購入して引渡しを受けた。その後,Bは,Aの強迫を理由に甲宝石の売買契約を取り消したが,BがAから甲宝石の返還を受ける前に,AがCに甲宝石を売却して現実に引き渡し,CはAが甲宝石の所有者であると過失なく信じ,平穏かつ公然に甲宝石の占有を開始した。Cは,甲宝石の所有権を即時取得する。
(〇) 強迫による取消しの効果は遡及的無効であり(民法96条1項,122条),取消しの結果,Aは甲宝石について無権利者となるから,Aから宝石を譲り受けたCには,民法192条の適用がある(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)61,62ページ,研修教材・七訂民法I(総則)115ページ)。
⑶ Aは,Bから甲宝石を預かっていた。Aは,Cから金を借りる際,甲宝石をCに質入れして現実に引き渡し,Cは,Aが甲宝石の所有者であると過失なく信じ,平穏かつ公然に甲宝石の占有を開始した。Cは,甲宝石の質権を即時取得する。
(〇) 民法192条の「その動産について行使する権利」には質権も含まれる。質権設定行為に基づき占有の移転を受け,192条の要件を満たせば,即時に質権を取得することとなる(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)63ページ)。
⑷ Aは,BがCから預かっていたC所有の甲宝石をBから窃取した。その後,Aは,Dに甲宝石を売却して現実に引き渡し,DはAが甲宝石の所有者であると過失なく信じ,平穏かつ公然に甲宝石の占有を開始した。Cは,Bが甲宝石を盗まれてから2年間は,Dに対し,甲宝石の回復を請求することができる。
(〇) 即時取得の要件を満たす場合でも,その占有物が盗品又は遺失物であるときは,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対してその回復を請求できる(民法193条)。この「被害者」には,所有者も含まれると解されている(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)64ページ)。
⑸ Aは,Bから甲宝石を預かっていた。Aは,Bから何らの代理権も与えられていないのに,Bから甲宝石の処分を依頼された代理人である旨うそを言ってCに甲宝石を売却して現実に引き渡し,Cは,Aが甲宝石の売却権限がある代理人であると過失なく信じ,平穏かつ公然に甲宝石の占有を開始した。Cは,甲宝石の所有権を即時取得する。
(×) 相手方が無権代理人の場合に,権限ある代理人と誤信しても即時取得の適用はない(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)62ページ,研修785号61ページ)。
第10問
法定地上権に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,自己の所有する更地である甲土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権を設定した。その後,Aは甲土地上に乙建物を建設し,所有権保存登記をした。甲土地の抵当権が実行され,Cが甲土地の所有権を取得した場合,甲土地には,乙建物のための法定地上権が成立する。
(×) 土地を更地として抵当権を設定したのに,後日築造された建物のために法定地上権が認められると,土地の価値は大幅に下落し,土地の抵当権者を害することになる。したがってこの場合は法定地上権は成立しない(最判昭36.2.10民集15・2・219,最判昭44.2.27裁判集民94・477,研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)178頁,研修823号75,76ページ)。
⑵ Aは,自己の所有する甲土地上に乙建物を建設して所有権保存登記をした後,甲土地にBのための抵当権を設定した。その後,Aは乙建物をCに売却した。甲土地の抵当権が実行され,Dが甲土地の所有権を取得した場合,甲土地には,乙建物のための法定地上権が成立する。
(〇) 土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定した後に建物を第三者に売り渡した場合にも民法388条の適用がある(大連判大12.12.14民集2・676参照)ので,法定地上権は成立する(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)178,179ページ,研修823号79ページ)。
⑶ Aは,自己の所有する甲土地をBに賃貸した。Bは,甲土地上に乙建物を建設し,所有権保存登記をした。その後,Bは,乙建物にCのための抵当権を設定した。乙建物の抵当権が実行され,Dが乙建物の所有権を取得した場合,甲土地には,乙建物のための法定地上権が成立する。
(×) 抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なる場合には,法定地上権は成立しない(最判昭和44.2.14民集33・2・357参照)。このような場合は,抵当権設定の時点で建物の所有者と土地の所有者との間に何らかの用益関係(土地の地上権又は賃借権)があるはずで,建物の抵当権が実行された場合,建物の新所有者は,土地の用益関係を承継してこれを土地の所有者に主張しうるので,法定地上権を成立させる必要はないからである(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)178,179ページ,研修第823号78,79ページ)。
⑷ Aは,自己の所有する甲土地上に乙建物を建設し,所有権保存登記をした。その後,Aは,甲土地及び乙建物にBのための抵当権を同時に設定した。甲土地の抵当権のみが実行され,Cが甲土地の所有権を取得した場合,甲土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
(〇) 同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となった場合においても,民法388条の適用がある(最判昭37.9.4民集16・9・1854,大判昭6.10.29民集10・931)研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)179ページ)。
⑸ Aは,自己の所有する甲土地上に乙建物を建設して所有しているが,乙建物の所有権保存登記はしていない。Aが,甲土地にBのための抵当権を設定し,その後,甲土地の抵当権が実行されてCが甲土地の所有権を取得した場合,甲土地に,乙建物のための法定地上権が成立する。
(〇) 土地の抵当権設定当時その土地上の建物に保存登記がなかった場合にも,土地の抵当権者又は競落人は法定地上権の成立を否定できない(大判昭14.12.19民集18・1583)。土地の抵当権者は抵当地上に建物が存在することは通常知っているはずであるので,法定地上権の成立を予期すべきであるからである(研修教材・七訂民法Ⅱ(物権・担保物権)179ページ)。
刑法
第11問
刑罰に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 前に窃盗罪により懲役1年6月に処せられたことがある者に対し,占有離脱物横領罪により懲役1年の刑を言い渡す場合,その判決言渡し時において,前刑の執行を終わった日から5年経過していれば,新たに言い渡す刑の全部の執行を猶予することができる。
(〇) 刑法25条1項2号により,前刑の執行を終わった日から5年経過していれば,刑の全部の執行を猶予することができる(研修教材・六訂刑法総論349,350ページ)。
⑵ 前に詐欺罪により懲役1年6月に処せられたことがある者に対し,窃盗罪により懲役2年の刑を言い渡す場合,その判決言渡し時において,前刑の執行を終わった日から3年経過していれば,新たに言い渡す刑の一部の執行を猶予することができる。
(×) 刑法27条の2第1項3号により,前刑の執行を終わった日から5年経過していない場合は,刑の一部の執行を猶予することができない。この要件は,刑の全部執行猶予の場合(同法25条1項2号)と同じである。なお,同法27条の2第1項には,薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律3条に特則があり,薬物使用等の罪を犯した者に刑の一部の執行猶予の言渡しをする場合は,前刑の執行を終わった日から5年経過していなくても刑の一部の執行を猶予することができる。
⑶ 窃盗罪により懲役刑を言い渡す場合において,その刑の一部の執行を猶予するときは,その猶予の期間中保護観察に付さなければならない。
(×) 刑法27条の3第1項により,刑の一部の執行を猶予する場合においては,その猶予の期間中保護観察に付することができると規定されており,保護観察を付すことが必要的とされていない。同条項には,薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律4条に特則があり,薬物使用等の罪を犯した者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは,その猶予の期間中保護観察に付することが必要的とされている。設問は,窃盗罪を犯した者に刑の一部の執行猶予の言渡しをする場合の問題であるので,その猶予の期間中保護観察に付することが必要的ではない。
⑷ 科料の言渡しをするときは,その言渡しとともに,科料を完納することができない場合における労役場留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
(〇) 刑法18条4項。科料の言渡しをするときは,その言渡しとともに,科料を完納することができない場合における労役場留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
⑸ 犯罪行為の用に供された物であっても,それが無主物であるときは,没収することができない。
(×) 刑法19条2項本文。没収は,犯人以外の者に属しない物に限り,これをすることができるのであって,無主物は犯人以外の者に属していないので,没収できる(研修教材・六訂刑法総論332ページ)。
第12問
因果関係に関する次の記述のうち,正しいものには〇の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,Bの腹部を蹴って転倒させた。Bは,心臓疾患により心臓発作を起こしやすい状態であったところ,Aに腹部を蹴られて転倒したショックにより心臓発作を起こして死亡したが,心臓疾患という特殊事情がなければBは死亡しなかったと認められる。この場合,Aが行為当時その特殊事情のあることを知らなくても,Aの暴行とBの死亡との間に因果関係を認めることができる。
(〇) 設問は,行為時に行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したために結果が発生した場合の問題である。判例(最判昭和25.3.31刑集4・3・469)は,被害者の左目を蹴って傷を負わせたところ(それだけでは全治約10日間程度の傷害),被害者が脳梅毒に冒されていて脳に高度の病的変化があったため,脳の組織が崩壊して死亡した事案において,「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度な病的変化という特殊な事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができる」と判示しており(さらに,最判昭46.6.17刑集25・4・56 7は,強盗犯人が被害者に加えた暴行は必ずしも通常死の結果を招くほど強度なものではなかったが,たまたま被害者の心臓に高度の病変があったため,急性心臓死に至ったという強盗致死事件につき,前記判例と同様に判示している。研修教材・六訂刑法総論90~100ページ。),設問の事例において,判例の立場によれば,Aが行為当時に,Bが心臓疾患であるという特殊事情を知らなかったとしても,因果関係が認められる。
⑵ Aは,Bを普通乗用自動車の後部トランクに閉じ込めて監禁した状態で同車を道路上に停車させた。その数分後,Cが前方不注視により,自己が運転する普通貨物自動車前部を当該普通乗用自動車後部に追突させたため,Bは,頸髄挫傷の傷害を負って死亡した。Bの死亡原因は直接的には追突事故を起こしたCの甚だしい過失行為にある。この場合,Aの監禁行為とBの死亡との間に因果関係を認めることができる。
(〇) 設問は,行為後に第三者の過失行為が介在したがために結果が発生した場合の問題である。判例(最決平18.3.27刑集60・3・382)は,設問同様の事案で,「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部トランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間に因果関係を肯定することができる。」としており(研修教材・六訂刑法総論105ページ,研修807号55~60ページ),設問の事例において,判例の立場によれば,因果関係が認められる。
⑶ Aは,自宅においてBの頭部を多数回殴り,Bに脳出血の傷害を負わせた後,意識を失ったBを自動車で公園に運んで放置した。その数時間後,Bは,公園において,Aの暴行により生じた脳出血が原因で死亡したが,Bが死亡する前に,公園をたまたま通りかかったCが,意識を失って倒れていたBの頭部を更に殴った。Cの暴行は,既にBに発生していた脳出血を拡大させ,幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合,Aの暴行とBの死亡との間に因果関係を認めることができる。
(〇) 設問は,行為後に第三者の故意行為が介在した場合の問題である。判例(最決平2.11.20刑集44・8・837)は,被告人が被害者の頭部等を洗面器の底等で多数回殴打するなどの暴行を加えた結果,恐怖心による心理的圧迫等によって被害者の血圧を上昇させ,内因性高血圧性橋脳出血を発症させて意識消失状態に陥らせた上,被害者を資材置場に放置して立ち去ったところ,被害者は程なく前記橋脳出血により死亡したが,被告人による放置後いまだ被害者が生存している間に,何者かがその頭頂部を角材で数回殴打する暴行を加えており,当該暴行が,既に発生していた前記橋脳出血を拡大させ,幾分か死期を早める影響を与えるものであった事案において,「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には,仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても,犯人の暴行と被害者の死亡との間に因果関係を肯定することができ」ると判示しており(研修教材・六訂刑法総論100ページ),設問の事例において,判例の立場によれば,因果関係が認められる。
⑷ Aは,マンション居室内において,Bに対し,長時間にわたり激しい暴行を繰り返した。Bは,隙を見つけて同室から逃げ出し,追跡を免れるため高速道路に進入したが,走行してきた自動車に衝突されて全身打撲により死亡した。Bは,Aから長時間激しくかつ執ような暴行を受けたことにより,Aに対し極度の恐怖心を抱き,必死に逃走を図る過程でとっさに高速道路に進入するという行動を選択したと認められる。この場合,Aの暴行とBの死亡との間に因果関係を認めることができる。
(〇) 設問は,行為後に被害者の行為が介在したがために結果が発生した場合の問題である。判例(最決平15.7.16刑集57・7・950)は,設問同様の事案で,「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは,それ自体極めて危険な行為であるというほかないが,被害者は,被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け,被告人らに対し極度の恐怖心を抱き,必死に逃走を図る過程で,とっさにそのような行動を選択したものと認められ,その行動が被告人らの暴行から逃れる方法として著しく,不相当であったとはいえない」として因果関係を認めており(研修教材・六訂刑法総論106ページ),設問の事例において,判例の立場によれば,Bが自ら高速道路に進入するという危険な行動を取っているとはいえ,Aから長時間激しくかつ執ような暴行を受け,Aに対し極度の恐怖心を抱き,必死に逃走を図る過程で,とっさにそのような行動を選択したものと認められる場合には,因果関係を認めることができる。
⑸ Aは,ホテル客室内で少年Bに求められてその身体に覚せい剤を注射したところ,Bが錯乱状態に陥ったため,Bを同室内に放置して逃走した。その後,Bは,覚せい剤を注射されたことが原因で急性心不全により死亡した。Bが錯乱状態に陥った時点でAがBに適切な治療を受けさせていればBを救命できた可能性が僅かながらあった。この場合,AがBを放置した行為とBの死亡との間に因果関係を認めることができる。
(×) 設問は,不作為の因果関係の問題である。判例(最決平元.12.15刑集43・13・879)は,設問同様の事案で,「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った時点において,直ちに被告人が救急医療を要請していれば,同女が年若く(当時13歳),生命力が旺盛で,特段の疾病がなかったことなどから,十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であった」として因果関係を認めており(研修教材・六訂刑法総論88,89ページ),設問の事例において,判例の立場によれば,結果回避が合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる場合には因果関係を肯定できるものの,結果回避可能性が僅かながらあったにとどまるのであるから,因果関係を認めることはできない。
第13問
自由に対する罪に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,通りすがりのBの荷物がぶつかったことに腹を立て,脅してやろうと思って,Bに「お前,殺すぞ。」と言った。しかし,Bは,冗談だと思い,一切怖がらなかった。この場合,Aには,脅迫罪は成立しない。
(×) 脅迫罪は,危険犯であり,人を畏怖させるに足りる害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手が畏怖したことは必要でない(大判明43.11.15刑録16・1973,研修教材・改訂刑法各論(その1)72ページ)。
⑵ 新聞記者Aは,B経営の飲食店の椅子をAが壊したことにつき,BがAを器物損壊の事実で告訴しようとしていると聞き付け,これを阻止するため,Bに「俺は新聞記者だ。告訴をやめろ。やめなければ,店に不利益な事項を新聞に掲載するぞ。」と申し向けて告訴を断念させた。この場合,Aには,強要罪が成立する。
(〇) 刑法223条1項にいう「権利の行使を妨害」するとは,相手方が法律上許されている作為・不作為に出ることを妨害することであって,告訴をしようと思っていた器物損壊の被害者に対し,その加害者が脅迫して告訴することを思いとどまらせた場合には,強要罪が成立する(大判昭7.7.20大集11・1104,研修教材・改訂刑法各論(その1)75ページ)。
⑶ Aは,自動車を高速度で走行させることにより,その車内にBを監禁中,Bから馬鹿にされたことに腹を立て,Bの顔面を殴打してBに全治1週間の顔面打撲の傷害を負わせた。この場合,Aには,監禁罪と傷害罪ではなく,監禁致傷罪が成立する。
(×) 暴行が逮捕・監禁中になされた場合であっても,逮捕・監禁の状態を維持・継続させるためにその手段としてなされたものではないときには,逮捕・監禁致傷罪は成立せず,逮捕・監禁罪と傷害罪とが成立し,両者は併合罪となる(最判昭28.11.27刑集7・11・2344,最決昭42.12.21裁判集165・551研修教材・改訂刑法各論(その1)80,81ページ,研修829号64ページ)。
⑷ Aは,離婚係争中の妻Bが養育している長男C(2歳)を連れ去ることを企て,保育園から祖母Dに連れられて帰宅しようとしていたCを抱きかかえて,付近に駐車中の乗用車にCを同乗させ,同車を発進させてCを連れ去った。この場合,Aが,Cに対して,Bとともに共同親権者として親権を行使することができる者であれば,Aに,未成年者略取罪が成立することはない。
(×) 判例は,本問同様の事案で,「別居中の共同親権者である父が行ったとしても(中略)違法性が阻却されるものではない。」とし,未成年者の保護監督者も未成年者略取罪の主体たり得るとしている(最決平17.12.6刑集59・10・1901,研修教材・改訂刑法各論(その1)85ページ)。
⑸ Aは,夜道を通行中のBに強いてわいせつな行為をしようと企て,Bを背後から突き飛ばして路上に転倒させたが,Bに激しく抵抗されたため,一切わいせつな行為をすることなく逃走した。Aの突き飛ばし行為により,Bは全治1週間の右下腿挫傷の傷害を負った。この場合,Aには,強制わいせつ未遂罪と傷害罪ではなく,強制わいせつ致傷罪が成立する。
(〇) 強制わいせつ致傷の結果は,わいせつ行為そのものからはもとより,その手段である暴行・脅迫から生じたものでもよい(最決昭43.9.17刑集22・9・862)。また,強制わいせっそのものが未遂に終わっても,死傷の結果が生じた場合は,強制わいせつ致傷罪が成立する(最判昭和23.11.6刑集2・12・1535,最判昭24.7.9刑集3・8・1174,最判昭34.7.7裁判集130・515等,研修教材・改訂刑法各論(その1)110~112ページ)。
第14問
財産犯に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,旅館建物内の宿泊客用トイレに置き忘れられた財布を見付け,これを領得する意思で持ち帰った。当該財布は,旅館の宿泊客Bが置き忘れたものであったが,Aが持ち帰った時点で,Bはその1時間前に退館手続を終えて出発しており,かつ,Bも旅館の経営者Cも,当該財布がそのトイレ内にあることを認識していなかった。この場合,Aには,占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
(〇) 他人の排他的管理・支配下にある場所に物を忘れた場合は,その物の占有は,その場所の管理者に移ると解されている。設問同様の事案で,判例は,財布は,客の事実上の支配を離脱したものであるが,客が宿泊した旅館の旅館主の事実上の支配の及ぶ旅館内の便所に現在しているときは,客が置き忘れている事実を旅館主が認識しているか否かにかかわらず,旅館主の支配内に属するとして,これを持ち去った行為について窃盗罪の成立を認めている(大判大8.4.4刑録25・382,研修教材・改訂刑法各論(その1)178ページ)。
⑵ Aは,通行中のBに暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧して金品を奪取しようと考えた。Aは,まず,Bの背後から近付き,Bが脇に抱えていたセカンドバッグを奪い取った。Bは,すぐにこれを取り戻そうとした。そこで,Aは,Bの顔面を殴打した上,持参していたナイフを突き付けて「殺すぞ。」と言ってその反抗を抑圧し,セカンドバッグを持って逃走した。この場合,Aには,強盗罪は成立せず,事後強盗罪が成立する。
(×) 「強取」とは,暴行・脅迫により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者の占有に移すことをいうが,被害者の犯行が抑圧された状態で財物の奪取が行われたと認められる限り,暴行・脅迫と奪取行為との前後を問わないとされている。判例は,暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に,まず他人の手にする財物を奪取し,次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合には,強盗罪を構成するのであり,事後強盗罪ではないとしている(最判昭24.2.15刑集3・2・164,研修教材・改訂刑法各論(その1)203ページ)。
⑶ Aは,書店でBが文庫本を万引きするのを目撃し口止め料としてBに金を出させようと考え,Bに「万引きしたのを見た。警察に通報してもいいが,3万円くれれば見なかったことにしてやる。」と言った。Bは,警察に通報されると会社を懲戒解雇になるかもしれないと思い怖くなり,その場でAに3万円を渡した。この場合,Aには,恐喝罪が成立する。
(〇) 恐喝罪における「害悪の告知」は,必ずしもそれ自体違法なものであることを要しない。設問同様の事案で,判例は,他人の犯罪事実を知る者が,これを捜査官憲に申告すること自体はもとより違法でなくとも,これをたねにして,犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けてその他人を畏怖させ,「口止め料として金品を提供させれば,恐喝罪が成立するとしている(最判昭和29.4.6刑集8・4・407,研修教材・改訂刑法各論(その1)244ページ,研修823号81ページ以下)。
⑷ Aは,Bの経営する飲食店に初めて入店して飲食した。Aは,十分な所持金を持っていたが,飲食後になって代金を支払うのが惜しくなり,Bの隙を見て黙って店を出て逃走した。Bは,Aの素性を知らなかったので,その後代金の請求をすることを諦めた。この場合,Aには,刑法246条2項の詐欺罪が成立する。
(×) 刑法246条2項の詐欺罪において,財産上不法の利益が,債務の支払を免れたことであるとするには,相手方たる債権者を欺倒して債務免除の意思表示をさせることを要し,単に逃走して事実上支払をしなかっただけで足りるものではないとされている(最判昭30.7.7刑集9・9・1856,研修教材・改訂刑法各論(その1)234ページ)。すなわち,飲食後に代金支払の意思がなくなり,飲食者が店主の隙を見て逃走したような場合は,店主らの財産的処分行為に向けられた欺く行為があったとはいえないから,刑法246条2項の詐欺にはならない。
⑸ Aは,公務員であるBがCから賄賂としてもらい受けた高級腕時計であると知りながら,Bから当該腕時計を格安で譲り受けた。この場合,Aには盗品等有償譲受け罪が成立する。
(×) 盗品等有償譲受け罪の客体は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であり,賄賂は客体にならない(研修教材・改訂刑法各論(その1)282ページ)。
第15問
国家の作用に対する罪に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ Aは,警察官BがAの妻Cを覚せい剤取締法違反の現行犯人と認めて逮捕した際,Bが逮捕の現場で証拠物として適法に差し押さえた上,整理のために床に置いていた覚せい剤注射液入りアンプルをわざと足で踏み付けて損壊した。この場合,Aには,公務執行妨害罪が成立する。
(〇) 公務執行妨害罪の手段である暴行は,公務員に向けられた有形力の行使であるが,その身体に対して直接に加えられる有形力の行使(直接暴行)に限らず,公務員の職務の執行に当たりその執行を妨害するに足りる暴行を加えれば足り,人に向けられてはいるが直接人の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むとされている。設問同様の事案において,判例は公務執行妨害罪の成立を認めている(最決昭34.8.27刑集13・10・2769,研修教材・改訂刑法各論(その2)164ページ)。
⑵ Aは,友人BによるC殺害の現場にDが居合わせてその状況を目撃したことを知っていたが,Bに対する捜査が進展し,警察がDの所在を探していることを察知し,Dが警察による取調べを受けないようにするため,Dを約1週間にわたりホテルに宿泊させて隠匿した。この場合,Aには,証拠隠滅罪が成立する。
(〇) 捜査段階における参考人も他人の刑事被告事件に関する証拠に該当し,これを隠匿すれば証拠隠滅罪が成立する(最決昭36.8.17刑集15・7・1293,研修教材・改訂刑法各論(その2)194ページ)。
⑶ Aは,Bの殺人被告事件の公判に証人として出廷し,宣誓の上,実際には目撃していなかったのに,「BがCを殺害するのを見た」旨の記憶に反する証言をした。その後,客観的にはBがCを殺害していたことが判明した。この場合,Aには,偽証罪が成立する。
(〇) 「虚偽の陳述」の意義について,判例・通説は,自己の記憶に反することの陳述が虚偽の陳述であり,客観的には誤りであっても記憶を忠実に述べさえすれば偽証罪は成立しない反面,記憶に反する陳述がたまたま客観的事実に合致しても本罪を構成するとする主観説を採っている。したがって,設問のAには 偽証罪が成立する(大判昭7.3.10刑集11・286,研修教材・改訂刑法各論(その2)203ページ)。
⑷ Aは,憎んでいたBに刑事処分を受けさせる目的で,警察官に対し,虚偽の事実であると認識しながら「BがCの財布を盗んだ」旨の申告をした。その後,客観的にはAの申告どおりBがCの財布を盗んでいたことが判明した。この場合,Aには,虚偽告訴罪が成立する。
(×) 虚偽告訴罪にいう「虚偽」とは,申告の内容をなすところの刑事・懲戒処分の原因となる事実が,客観的事実に反することである(最決昭33.7.31刑集12・12・2805)。したがって,客観的事実に合致している以上,たとえ虚偽告訴者が主観的に虚偽だと信じていても,虚偽告訴罪を構成しない(研修教材・改訂刑法各論(その2)207ページ)。
⑸ Aは,東北地方の甲税務署に勤務していた当時,その職務に関し,管内の納税者であるBに納税手続上の便宜を図ったことがあった。その後,Aは,人事異動により,九州地方の乙財務局に勤務することとなったが,異動後に,Bから,納税手続上の便宜を図ったことの謝礼として現金をもらった。この場合,Aには,収賄罪が成立する。
(〇) 判例は,公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に,前の職務に関して賄賂を収受した場合には収賄罪を構成し,賄賂に関する職務を現に担任することは収賄罪の要件ではないとしている(最決昭28.4.25刑集7・4・881ページ,研修教材・改訂刑法各論(その2)223ページ)。
刑事訴訟法
第16問
告訴に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 未成年者である被害者には告訴の意思がなくても,被害者の親権者は告訴をすることができる。
(〇) そのとおり。被害者の法定代理人は,独立して告訴をすることができる(刑事訴訟法231条1項)。「独立して」とは,被害者本人に告訴の意思があるかどうかに関係なく,また,被害者本人の告訴権が消滅しても独立の立場で告訴できるという意味である(研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)43ページ)。
⑵ 口頭による告訴は,検察官又は司法警察員に対してしなければならないが,書面による告訴は,検察事務官や司法巡査に対してもすることができる。
(×) 告訴は,その方法を問わず,検察官又は司法警察員に対してしなければならず,検察事務官や司法巡査に対してすることはできない(刑事訴訟法241条1項)。
⑶ 検察官に告訴する場合は,その事件について管轄を有する裁判所に対応する検察庁の検察官に対してしなければならない。
(×) 検察官に告訴をする場合,必ずしもその事件について管轄を有する裁判所に対応する検察庁の検察官に対して行うことを要しない(大判昭11.11.24大刑集15・21・1511,研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)45ページ)。
⑷ 親告罪について,いまだ告訴がなされていなくても,捜査機関は捜査を行うことができる。
(〇) そのとおり(研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)47,48ページ)。
⑸ 特別公務員暴行陵虐被疑事件について告訴した被害者は,検察官による不起訴処分に不服があるときは,その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に,事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法262条1項)。
第17問
逮捕・勾留に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察事務官は,自ら緊急逮捕をすることができるし,その後に行われる逮捕状の請求も,自らすることができる。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法210条1項,研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)123ページ)。
⑵ 定まった住居を有する被疑者を,法定刑が拘留又は科料のみの罪名に当たる被疑事実で逮捕した。この場合,罪証隠滅のおそれが強く認められても,被疑者を勾留することはできない。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法207条1項,60条3項)。
⑶ 窃盗目的の住居侵入罪の被疑事実で逮捕した被疑者について,更に侵入先の住居で金品を窃取していたことが判明した場合,住居侵入罪の被疑事実に窃盗罪の被疑事実を追加して勾留することができる。
(〇) 住居侵入罪の被疑事実で逮捕された被疑者を,住居侵入罪に加えて窃盗罪の被疑事実で勾留することは,逮捕前置主義に反しないので許される(研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)137ページ)。
⑷ 検察官が,裁判官に被疑者の勾留を請求した場合において,検察官が司法警察員から被疑者を受け取ってから24時間が経過しても,裁判官が勾留に関する裁判をしないときは,検察官は,被疑者を釈放しなければならない。
(×) 勾留に関する裁判がなされるまでの間は,逮捕の効力により,被疑者の身体の拘束を継続することができる(刑事訴訟法204条3項,205条4項,207条,研修教材・七訂刑事訴訟法I(捜査)138ページ)。
⑸ 検察官による被疑者の勾留請求を受けた地方裁判所の裁判官が,当該勾留請求を却下した場合,当該勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立ては,当該地方裁判所を管轄する高等裁判所に対してしなければならない。
(×) 地方裁判所の裁判官がした勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立先は,当該裁判官所属の地方裁判所である(刑事訴訟法429条1項)。
第18問
公判前整理手続に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察官,被告人又は弁護人は,事件を公判前整理手続に付するよう裁判所に請求することはできない。
(×) 刑事訴訟法316条の2第1項,研修824号80ページ。
⑵ 公判前整理手続期日において,裁判所は,出頭した被告人に対して質問することはできない。
(×) 刑事訴訟法316条の10。
⑶ 検察官は,事件が公判前整理手続に付された場合において,検察官請求証拠を被告人又は弁護人に開示した後,被告人又は弁護人から請求があったときは,速やかに,被告人又は弁護人に対し,検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
(〇) 刑事訴訟法316条の14第2項,研修824号81~83ページ。
⑷ 証拠物の差押調書や領置調書は,類型証拠として開示すべき対象ではない。
(×) 刑事訴訟法316条の15第1項9号,研修824号83,84ページ。
⑸ 裁判所は,被告人に弁護人がなければ,事件を公判前整理手続に付する決定をすることはできない。
(×) 弁護人選任前であっても,事件を公判前整理手続に付する決定をすることは差し支えない。刑事訴訟法316条の2第1項,316条の4第2項,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)74ページ。
第19問
証拠に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 検察官請求に係る供述調書は,証拠とすることに弁護人が同意しなければ,被告人が同意しても,刑事訴訟法326条1項により証拠とすることはできない。
(×) 弁護人が同意しなくても,被告人が同意すればよい(刑事訴訟法326条1項,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)179ページ)。
⑵ 冒頭手続における被告人の陳述は,証拠とすることができる。
(〇) そのとおり(最判昭26.7.26刑集5・8・1652,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)64ページ)。
⑶ Aに対する窃盗被告事件の公判において,Aは共犯者Bの検察官調書を証拠とすることに同意せず,Bは証人尋問で自己が有罪判決を受けるおそれがあるとして一切の証言を拒み,今後翻意して証言をする見込みはない。この場合,Bの検察官調書は,刑事訴訟法321条1項2号前段により証拠とすることができる。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法321条1項2号前段,最大判昭27.4.9刑集6・4・584,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)139ページ)。なお,証人が翻意して証言をする見込みの有無を考慮すべきかについて判例は判示していないが,これを考慮すべきとする下級審裁判例(東高判平22.5.27判タ1341号250ページ等)はある。
⑷ 被告人が作成した供述書で被告人の署名及び押印のいずれもないものは,刑事訴訟法322条1項により証拠とすることはできない。
(×) 供述書に証拠能力を認めるために作成者の署名及び押印はいずれも不要である(刑事訴訟法322条1項,最決昭29.11.25刑集8.11.1888,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)134,164ページ)。
⑸ 被告人の任意性のない自白は,被告人の公判期日における供述の証明力を争うためであれば,証拠とすることができる。
(×) 任意性のない自白は,弾劾証拠としても証拠とすることはできない(刑事訴訟法319条1項,328条,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅱ(証拠法)98ページ)。
第20問
被害者参加制度に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 詐欺被告事件において,巨額の被害を被った被害者は,当該被告事件の手続に参加することができる。
(×) 被害者参加の対象事件につき,刑事訴訟法316条の33第1項,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)140ページ。
⑵ 検察官は,被害者参加の申出を受けたときは,意見を付して,これを裁判所に通知する。
(〇) 刑事訴訟法316の33第2項,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)140,141ページ。
⑶ 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士(以下「被害者参加人等」という。)が,被告人に質問を発することを申し出たときは,裁判所は,これを許さなければならない。
(×) 刑事訴訟法316条の37第1項は必要性・相当性があるときに許すとしている。研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)141,142ページ。
⑷ 被害者参加人は,公判期日に出席して被告人に質問する場合において,被告人の面前においては圧迫を受け,精神の平穏を著しく害するおそれがあるときは,法廷以外の同一構内にある場所から,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話する方法によって,質問することができる。
(×) 被害者参加制度においては,被害者参加人に不安又は緊張を緩和するのに適当な者を付き添わせること(刑事訴訟法316条の39第1項),被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置(同条5項)ができるが,いわゆるビデオリンク方式(刑事訴訟法157条の6第2項)は認められていない。
⑸ 被害者参加人等が,公判期日において,検察官の論告の後に,事実又は法律の適用について,意見を陳述したときは,これを証拠とすることができる。
(×) 刑事訴訟法316の38第4項,研修教材・七訂刑事訴訟法Ⅲ(公判)142ページ。なお,同法292条の2による意見陳述と区別すること。
徴収事務
第21問
徴収金に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 徴収主任は,収入官吏を兼ねてはならないとされており,その例外は認められない。
(×) 徴収主任は,原則として,収入官吏を兼ねてはならないが,少人数配置の区検察庁にあってやむを得ず兼職しなければならない場合などの例外が認められている(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説32ページ,研修828号63ページ)。
⑵ 罰金,科料又は追徴の裁判の言渡しと同時に仮納付の裁判が言い渡されたときは,直ちに仮納付の裁判を執行することができる。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法471条,348,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説13,14,121ページ,研修828号66,67ページ)。
⑶ 訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した場合において,訴訟費用についての執行免除の申立てがあり,執行免除申立期間中にこれが取り下げられたときは,その取下げの日から当該裁判を執行することができる。
(×) 訴訟費用について執行免除の申立てがあり,執行免除申立期間中(裁判確定後20日)にこれを取り下げたときは,執行免除の申立てがないときと同様に,20日目の翌日に執行力が生じることとなる(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説52,53ページ,研修830号74ページ)。
⑷ 裁判所に現金で納付されている保釈保証金の没取の裁判の執行は,裁判所又は裁判官がこれを指揮する。
(〇) そのとおり。なお,保証書をもって保釈保証金の納付に代えた場合の没取の裁判の執行については,検察官が執行を指揮する(刑事訴訟法472条1項ただし書,96条2項,3項,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説11,50ページ,研修828号60,61,66ページ)。
⑸ 非訟事件手続法の手続による過料の裁判(略式手続の場合を除く。)について,終局決定に対する即時抗告の提起期間は,裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。
(×) 非訟事件手続法の手続による過料の裁判(略式手続の場合を除く。)について,終局決定に対する即時抗告の提起期間は,裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間とされている(非訟事件手続法67条1項,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説47ページ,研修830号77,78ページ)。
第22問
徴収金の時効に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 罰金の時効期間の起算日は,その裁判の確定日である。
(〇) そのとおり(刑法32条,22条,24条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説16ページ,研修832号63ページ)。
⑵ 罰金,科料又は追徴金に係る徴収金について,納付義務者から一部納付願が検察庁に送付され,検察官がその一部納付の申出を許可したときは,時効が中断する。
(×) 罰金,科料又は追徴に係る徴収金について,時効が中断するためには現実の執行行為が必要となるところ,一部納付は,現実に納付があることを必要とし,一部納付願が検察庁に送付され,検察官がその一部納付の申出を許可しても現実に納付があったとはいえず,時効は中断しない(刑法34条2項,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説17,65ページ,研修832号68ページ)。
⑶ 過料に係る徴収金について,納付義務者から一部納付願が検察庁に送付され,これが受理されたときは,時効が中断する。
(〇) 民法147条の規定により,承認のあった場合は時効が中断することとなるが,徴収事務規程上の一部納付願はこの承認に当たることから,検察庁において一部納付願を受理した日に時効は中断する(会計法31条2項,民法147条,156条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説20ページ,研修832号70,71ページ)。
⑷ 訴訟費用に係る徴収金について,その連帯債務者のうちの一人が一部納付したときは,他の連帯債務者に対して時効の中断の効力が生じる。
(×) 訴訟費用の連帯債務者のうちの一人が一部納付した場合は,民法147条の規定による承認があったとして時効が中断するものの,民法440条の規定により,その効果はその者についてのみ生じ,他の連帯債務者には及ばないため,他の連帯債務者に対して時効の中断の効力は生じない(民法440条,会計法31条,民法147条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説21,22,65,66ページ,研修832号71ページ)。
⑸ 罰金又は科料について,検察官が労役場留置の執行を指揮したのみでは,時効は中断しない。
(〇) そのとおり。労役場留置の執行指揮のみでは執行行為があったものとは解されず,時効が中断するには,労役場留置の執行に着手することが必要である(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説18,19ページ,研修832号69ページ)。
第23問
罰金刑に対する未決勾留日数の通算(算入)に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 罰金刑に未決勾留日数を法定通算する場合及び裁定算入する場合は,全て判決で言い渡さなければならない。
(×) 罰金刑に未決勾留日数を裁定算入する場合は,判決で言い渡さなければならないが,罰金刑に未決勾留日数を法定通算する場合は,判決では言い渡されず,刑事訴訟法495条の規定に基づいて通算すべき日数を算出することとなる(刑法21条,刑事訴訟法495条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説39,40ページ,研修833号44,45ページ)。
⑵ 未決勾留日数を罰金刑に法定通算する場合,未決勾留日数1日の折算額は,4,000円である。
(〇) そのとおり(刑事訴訟法495条3項,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説40ページ,研修833号45ページ)。
⑶ 自由刑と罰金刑とが併科され,いずれについても執行猶予の言渡しがなされていない場合において,未決勾留日数の法定通算があるときは,まず,自由刑に通算し,なお余剰があるときは,その余剰日数を罰金刑に通算する。
(〇) そのとおり(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説40ページ,研修833号45,46ページ)。
⑷ 自由刑と罰金刑とが併科され,自由刑について執行猶予の言渡しがなされている場合において,未決勾留日数の法定通算があるときは,直ちに罰金刑に通算する。
(〇) そのとおり(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説40ページ,研修833号45ページ)。
⑸ 徴収担当事務官は,罰金刑に未決勾留日数を通算(算入)した結果,執行すべき金額がなくなったときは,訴訟記録等に適宜その旨を記入して押印するとともに検察総合情報管理システムにより執行すべき金額がない旨を管理する。
(〇) そのとおり(徴収事務規程12条2項。九訂特別研修資料3号・徴収事務解説56ページ,研修833号47,48ページ)。
第24問
労役場留置の執行及び強制執行に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 罰金,科料又は追徴に係る徴収金について,納付義務者に資力がなく完納できない場合は,納付義務者を労役場に留置してこれらの徴収金の裁判の執行をすることができる。
(×) 罰金又は科料に係る徴収金について,納付義務者に資力がなく完納できない場合は,納付義務者を労役場に留置してこれらの徴収金の裁判の執行をすることができるが,追徴に係る徴収金については,納付義務者を労役場に留置することができない(刑法18条1項,2項,刑事訴訟法505条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説99ページ,研修835号62ページ)。
⑵ 納付義務者が,罰金に係る徴収金を納付することができるだけの多額の現金を有しながら,その納付に応じない場合は,強制執行をする必要はなく,労役場留置の執行をすることができる。
(×) 納付義務者が財産を有しながら罰金又は科料の納付に応じない場合において,財産を有するなど完納の資力があるときは労役場留置の執行をすることはできないため,財産刑の本旨にのっとり,まず強制執行により徴収すべきである(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説87,99,100ページ,刑法18条1項,2項,研修835号62ページ)。
⑶ 少年に対しては,原則として労役場留置の執行はできないが,本人が承諾し労役場留置承諾書を提出した場合に限り,労役場留置の執行をすることができる。
(×) 少年(20歳未満の者)に対しては,少年法54条の規定により労役場留置の言渡しはできないことから,納付義務者が少年であるときは,本人が労役場留置を承諾したとしても,労役場留置を執行することはできない(少年法54条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説100ページ,研修835号62ページ)。
⑷ 労役場留置の執行を指揮した後,その執行着手前に納付すべき金額の一部について納付があったときは,検察官は,労役場留置執行変更指揮書により労役場留置の執行指揮を変更する。
(〇) そのとおり(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説107ページ,徴収事務規程35条1項,研修835号65ページ)。
⑸ 労役場留置の執行中に代納の申出があり,その残日数に相当する金額の全部について納付をさせて釈放する場合には,釈放当日分を含めて徴収しなければならない。
(〇) そのとおり(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説108ページ,研修835号65ページ)。
第25問
徴収金の不能決定に関する次の記述のうち,正しいものには○の欄に,誤っているものには×の欄に印を付けなさい。
⑴ 徴収不能決定は,徴収金について法律上又は事実上執行することが不能の場合に検察官が行う処分であるが,一旦徴収不能決定をした徴収金についても,その後の事情によっては,当該決定を取り消し,徴収することができる。
(〇) そのとおり(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説116ページ,研修835号69ページ)。
⑵ 検察官が罰金15万円の裁判を執行指揮したところ,本来は罰金10万円の裁判を執行すべきであったことが判明した場合,検察官は,差額の5万円について徴収不能決定の処分をする。
(×) 徴収不能決定は,過誤なく裁判の執行指揮をした徴収金について徴収事務規程40条又は41条に定める事由が生じた場合に限ってこれをなし得る趣旨であって,同規程10条1項又は11条1項の規定により検察官の指揮を受けた徴収金及び同規程44条の規定により手続をした仮納付金について執行すべき金額に過誤があることが判明したときは,過誤の訂正手続(徴収事務規程67条)によって処理されることとなる(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説116,151ページ,徴収事務規程67条,研修835号69ページ)。
⑶ 傷害罪で罰金刑の言渡しを受けた者が判決の確定後死亡した場合,その者の相続財産に対して執行することができる。
(×) 一身専属の原則により,納付義務者の死亡によって徴収金に係る裁判の執行は不能となるところ,その例外として,刑事訴訟法491条は,「没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は,刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には,相続財産についてこれを執行することができる。」と規定するが,傷害罪により言い渡した罰金刑は当該規定には該当しない(刑事訴訟法491条,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説116,117ページ,研修835号70ページ)。
⑷ 罰金刑の言渡しと同時に訴訟費用の負担を命ずる裁判が言い渡された者に対し,罰金刑について刑の執行の免除があったときは,罰金及び訴訟費用に係る徴収金について徴収不能決定の処分をする。
(×) 訴訟費用に係る徴収金について,その本案の裁判によって有罪の言渡しを受けた者に対し,刑の執行の免除があったときでも,当然には徴収不能とはならない(九訂特別研修資料3号・徴収事務解説117,118ページ,研修835号70ページ)。
⑸ 解散した法人に対する徴収金について,当該法人が無資力であるとして地方検察庁の検察官が徴収不能決定の処分をするときは,検事長の許可を受けなければならない。
(〇) そのとおり(徴収事務規程41条1項,2項,九訂特別研修資料3号・徴収事務解説118ページ,研修835号71ページ)。