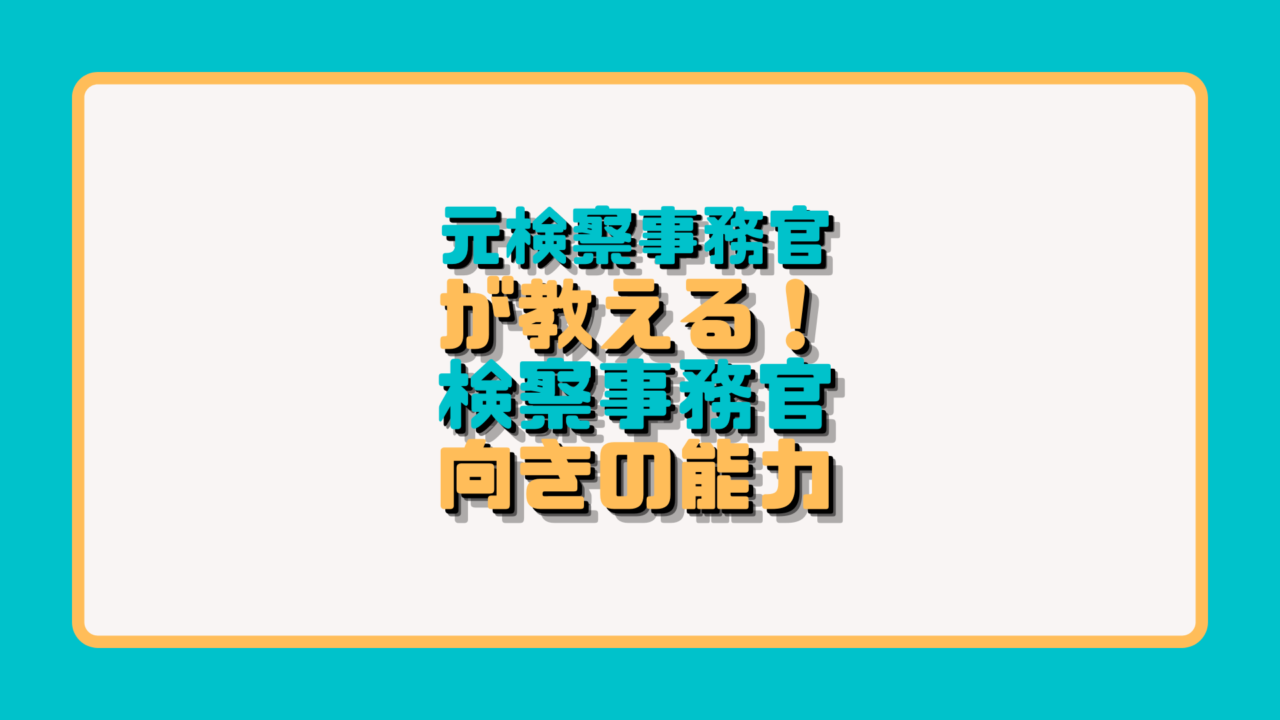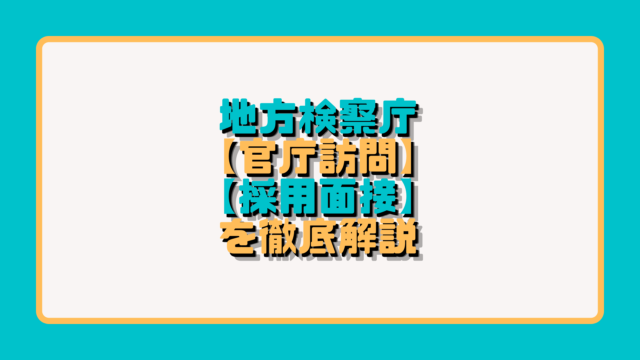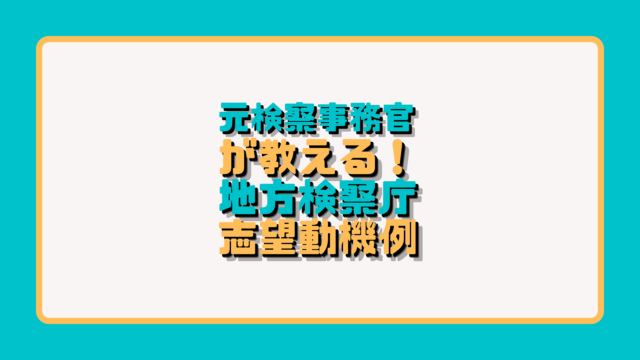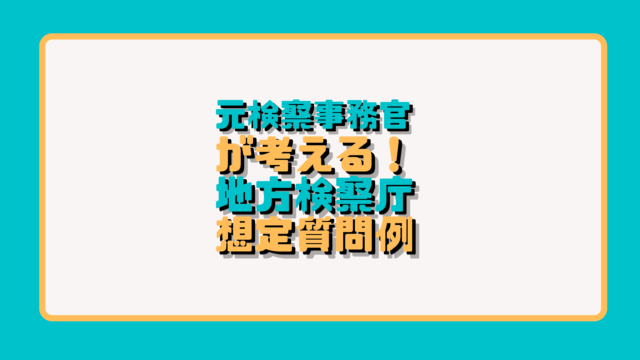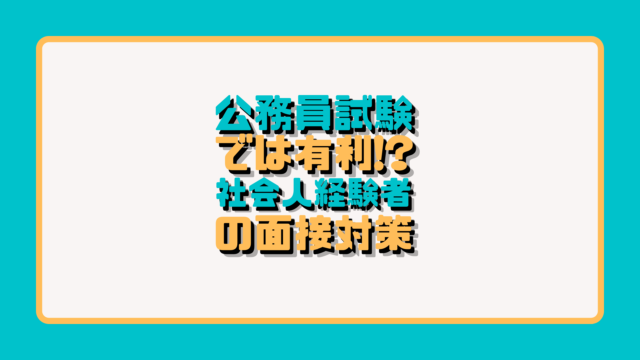こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今この記事を見ている方は以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
自身のアピールってどうすれば…
検察事務官の適性って何だろう…
考えてみたけど合ってるのかな…
私も地方検察庁の官庁訪問を経験しているので、皆さんの悩みは痛いほど分かります。
そんな皆さんの悩みを解決すべく、元検察事務官の経験を基に官庁訪問で検察事務官の適性をアピールできる能力と例文を考案しましたので、検察事務官になりたい方は是非参考にしてもらえればと思います。
- 本記事は一部有料※となります。
※5,231文字中3,527文字有料
検察事務官の適性をアピールするポイントについて
ガクチカや長所などでどのような能力をアピールしようか悩んでいる人も多いと思いますが、以下のポイントを意識することでがガクチカ等を作りやすくなります。
検察事務官の適性に合わせてアピールする能力を選ぶ!
当たり前のことと思われた方もいると思いますが、話したいエピソードとアピールしたい能力ありきでガクチカ等を作る方が多いので注意が必要になります。
ひとくくりに公務員といっても国家公務員と地方公務員、まして同じ国家公務員の中でも官庁が変われば仕事は全く異なります。
そのため、検察事務官の適性をアピールするためのエピソードの選び方、能力の選び方が重要となりますので、それぞれ見ていきたいと思います。
話すエピソードの選び方
自身の頑張った経験などのエピソードについてですが、志望先によって話すエピソードを変えられるほど複数のエピソードを持っている人は少ないと思います。
そうなると、検察事務官の適性をアピールできるエピソードが無いと悩む人もいるかと思いますが、その場合は手持ちのエピソードの切り口を変えることで解決することができます。
例えば、部活のキャプテンとして全国大会に出場したというエピソードの切り口例は以下のようになります。
- 部員の指導とチームのまとめ役として目標を達成した。
→リーダーシップ
→マネジメント能力・調整力 - 部員の中の誰よりも遅くまで練習してきた。
→根気強さ・粘り強さ
→責任感 - 部員の意見を聞きながら前例踏襲の練習方法を抜本的に見直した。
→問題発見能力
→傾聴力
ざっと挙げるだけでも一つのエピソードから多くの能力を見出すことができます。
ですので、複数あるエピソードから選ぶだけでなく一つのエピソードの切り口を変えるという方法も駆使して検察事務官の適性に適うエピソードを選んでください。
エピソードの切り口を変えることで検察事務官の適性に適う能力をアピールすることができる。
アピールする能力の選び方
アピールする能力の選び方についてですが、検察事務官の仕事を理解した上で検察事務官に求められる能力を選ぶ必要があります。
検察事務官の仕事を理解するためには以下の視点で見ることがポイントとなります。
- 「捜査官」としての検察事務官
- 「事務官」としての検察事務官
ドラマのイメージからか、検察事務官の仕事は捜査が中心と思う方も少なくありませんが、実際は事務処理がメインの仕事となります。
ただ、検察庁全庁的に捜査系事務官(副検事任官希望者)を増やしたいという課題がありますので、両方バランスよくアピールすることがお勧めとなります。
- 自身の長所では「捜査官」としての適性をアピール。
- ガクチカでは「事務官」としての適性をアピール。
「捜査官」としての適性と「事務官」としての適性をバランスよくアピールすることで、検察事務官の仕事の理解度もアピールすることができます。
- 検察事務官を「捜査官」と「事務官」という二つの視点で捉える。
- バランスよくアピールすることで検察事務官の仕事の理解度が伝わる。
では次に、検察事務官の適性をアピールできる能力について具体的に紹介していきたいと思います。
検察事務官の適性をアピールできる能力について
検察事務官の適性をアピールする方法については、エピソードの選び方・アピールする能力の選び方について理解できたと思います。
では具体的にどのような能力をアピールすればいいのか、元検察事務官の経験からお勧めする能力とその理由を紹介していきます。