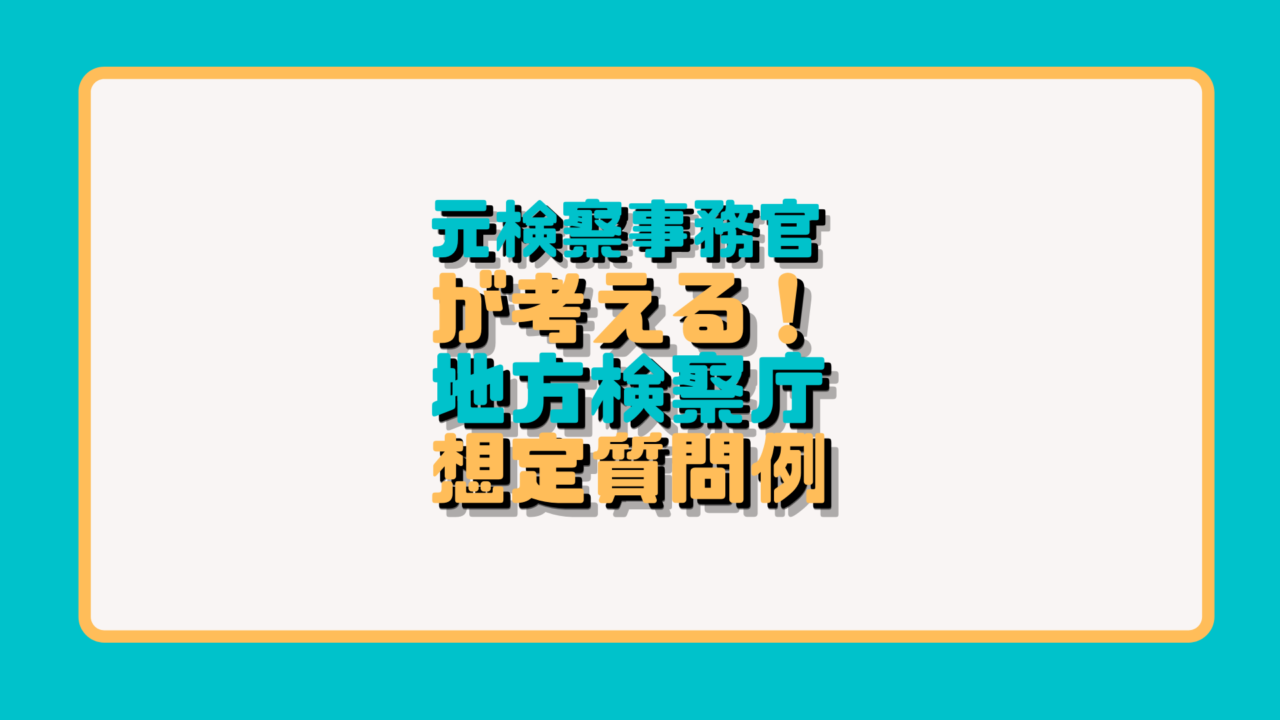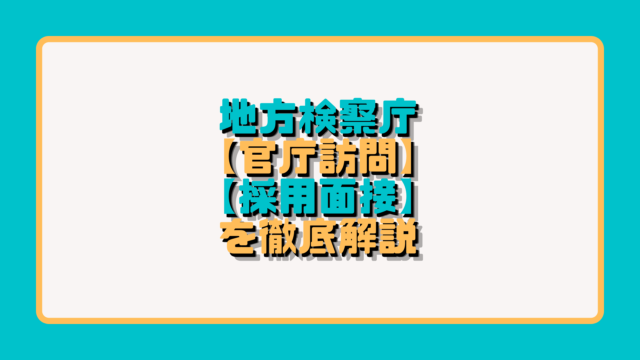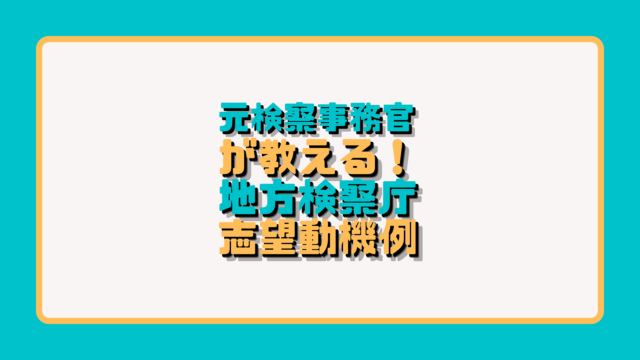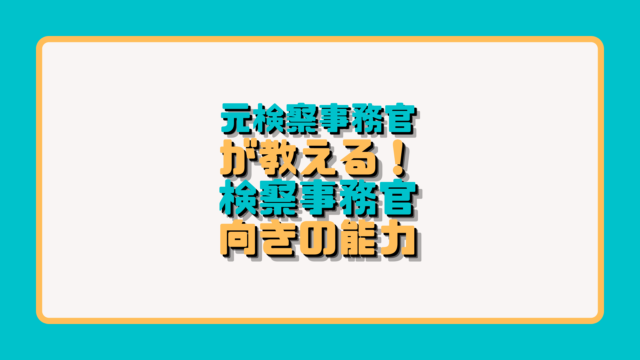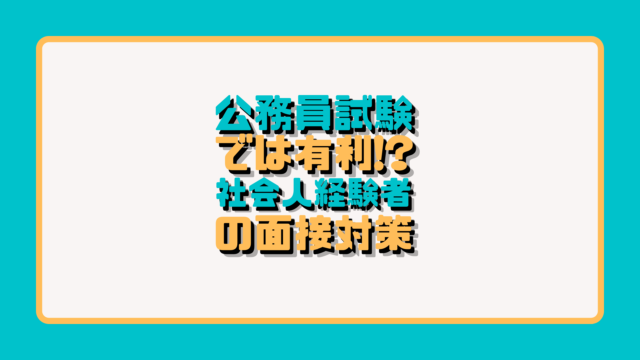こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今この記事を見ている方は以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
官庁訪問で何聞かれるんだろう…
想定質問が全然思いつかない…
回答を考えてみたけど自信が…
私も地方検察庁の官庁訪問を経験しているので、皆さんの悩みは痛いほど分かります。
そんな皆さんの悩みを解決すべく、元検察事務官の経験を基に想定質問と回答例を考案しましたので、検察事務官になりたい方は是非参考にしてもらえればと思います。
- 本記事は一部有料※となります。
※8,647文字中6,925文字有料
地方検察庁の想定質問で意識するポイントについて
地方検察庁の想定質問を考えることが難しいと感じている人も多いと思いますが、以下のポイントを意識することで地方検察庁の想定質問を作りやすくなります。
地方検察庁が採用したい人物像をイメージしてから想定質問を考える!
採用担当者は受験生が採用したい人物かどうかを見極めるために様々な質問をしてきます。
ですので、地方検察庁が採用したい人物像から逆算して想定質問を考えるという方法がお勧めです。
では、元検察事務官である私が想定する地方検察庁が採用したい人物像について見ていきたいと思います。
志望度が高い人物
公務員試験は複数の試験種を受験することが当たり前の試験で、国家一般職では様々な官庁を訪問できるので、検察庁が第一志望かどうかはかなり深堀して確認されます。
当たり前の話ですが、たとえどんなに能力が高く検察事務官への適性がある人物に内々定を出したとしても、実際に入庁してくれないと意味がないですよね。
そのため、採用担当者は受験生の志望度の高さを重視しますので、志望度に関する想定質問は念入りな準備が必要となります。
- 志望動機について
- やりたい仕事について
- 併願先・志望順序について
志望動機の作り方については下記記事で説明していますので、是非参考にしてみてください。
適正・能力がある人物
検察事務官の仕事は刑事手続きに関わる特殊な仕事になりますので、適正があるかどうか、能力があるかどうかは念入りに確認される事項となります。
そのため、受験生が話す内容の真偽を確認するために、特に具体的エピソードについては深堀して質問してきます。
ですので、検察事務官に必要な能力をアピールするために説得力のある具体的なエピソード作りが必要となります。
- 自己PRについて
- ガクチカについて
- 長所、短所について
なお、適正・能力に関する質問は受験生によって異なりますので、本記事では想定質問と回答例を挙げることはできません。
アピールしたい能力については下記記事で説明していますので、是非参考にしてみてください。
退職しなさそうな人物
国家公務員の採用は民間企業みたいにフレキシブルに行うことができませんので、職員が急に退職するという事態は死活問題となります。
そのため、受験生が入庁後に思っていたのと違うと思って退職しないかどうか、仕事のストレスに耐えられるかどうか確認してきます。
退職しなさそうかどうかは志望度や適性・能力より重要度は落ちると思いますが、勤務内容や条件の理解度は志望動機の裏付けにもつながるので、入念な準備が必要となります。
- 勤務内容の理解度について
- 勤務条件の理解度について
- ストレス耐性について
では次に、上記ポイントを踏まえどのように地方検察庁の想定質問に答えたらいいのか具体的に紹介していきたいと思います。
地方検察庁の想定質問の答え方について
官庁訪問で聞かれる質問ですが、採用したい人物かどうかを見極めるために質問されているということはイメージできたと思います。
ではどのように回答すればいいのか、元検察事務官の経験から具体的な想定質問の答え方を紹介していきます。
なお、社会人経験者の想定質問では追加で聞かれる事項もありますので、社会人経験者の方は下記記事も参考にしてもらえればと思います。