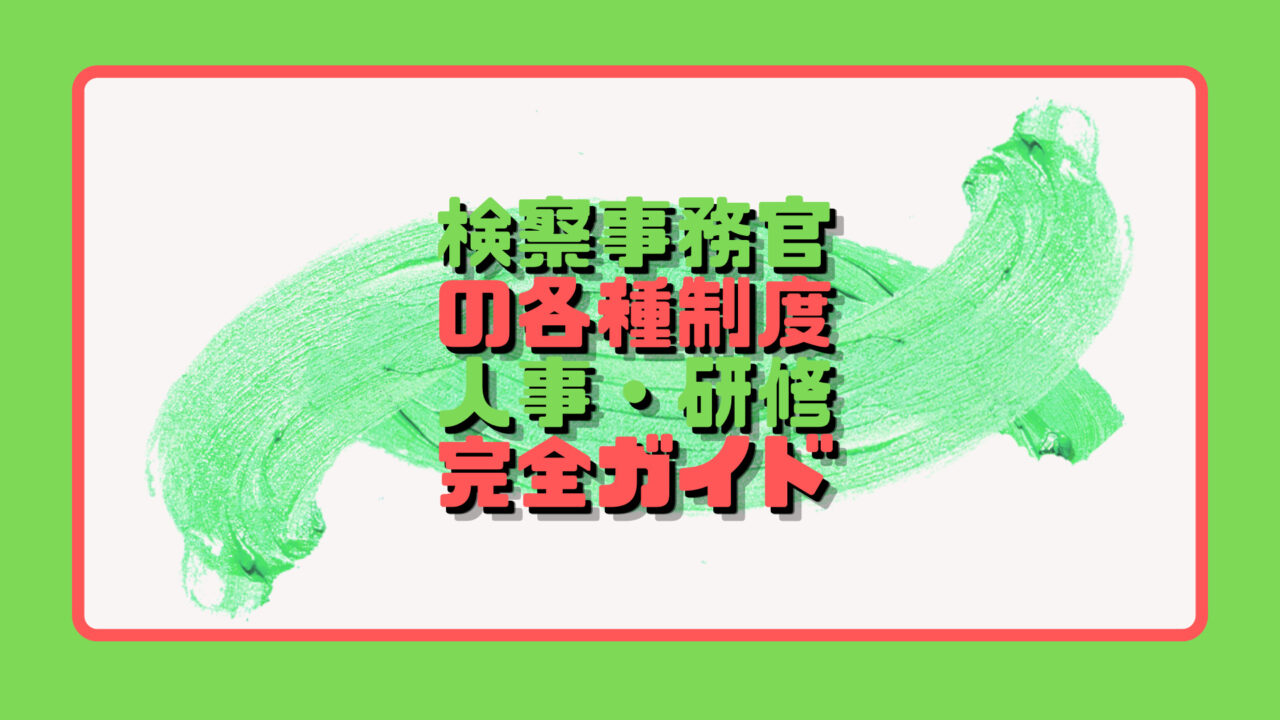こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は,私が検察事務官として実際に働いていた経験から,検察事務官の人事や研修といった各種制度について,詳しく紹介していきたいと思います。
ちなみに,私のプロフィールの詳細については下記記事でご確認いただけますので,是非チェックしてみてください。
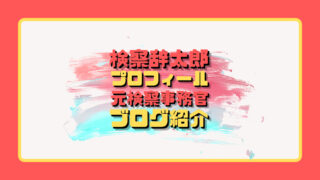
検察事務官の人事制度
検察事務官の人事制度については,役職・出世,配属・異動,出向について詳しく見ていきたいと思います。
役職・キャリア
検察事務官の役職については,「○○捜査官」という役職の人もいれば「課長」や「係長」という役職の人もいるため,序列がどのようになっているか非常に分かりにくくなっています。
検察庁では捜査・公判部門,検務部門,事務局部門と分かれていますが,所属する部門によって呼び方が異なりますが,整理すると以下の表のとおりとなります。
| 事務局部門 | 捜査公判部門 | 検務部門 |
| 事務局長 | 主席捜査官 | |
| 事務局次長 | 次席捜査官 | 検務管理官 |
| 課長 | 統括捜査官 |
統括検務官 |
| 課長補佐 | ||
| 係長 |
||
| 上席 主任捜査官 |
上席 検務専門官 |
|
| 主任 | 主任捜査官 | 検務専門官 |
| 一般職員 | ||
ただ,同じ役職でも職務の級が異なる場合がありますので,一概にどちらの役職の方が上とは言い難いですが,大体のイメージとして持ってもらえればと思います。
役職と職務の級の関係の詳細については下記記事にまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
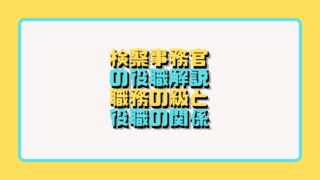
検察事務官のキャリアとしては,以下の2通りがあります。
- 検察事務官として出世する。
- 副検事・特任検事に任官する。
検察事務官として出世するということは,上記役職名をまとめた表でいうと事務局長を目指すということになりますが,本当に一握りの人しかなれないため,中々に険しい道となります。
副検事・特任検事に任官するというのは,下記「検察事務官の内部試験制度」で詳しく説明しますが,内部試験によって副検事・特任検事に任官することを目指すということになります。
副検事に任官すると最終的には誰でも1号まで昇格することができ,地域手当がない地域でも年収が1,000万円を超えることができますので,非常に魅力的なキャリアとなります。
副検事の詳細については下記記事でまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
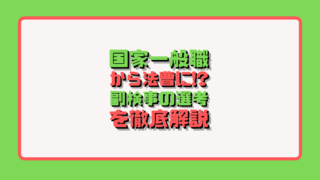
異動
検察事務官の異動についてですが,基本は採用された地方検察庁の内部での異動となり,若手の内は各部門をジョブローテーションで異動することになります。
採用庁以外の異動では,高検管内の他地検への異動と最高検・法務省といった東京への異動があります。
高検管内の他地検への異動については,基本的に係長級以上の職員からが異動対象となりますし,最高検・法務省への異動については,早くて採用3年目からあり得ますが,基本的には希望した職員が異動対象となります。
異動の詳細については下記記事にまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。
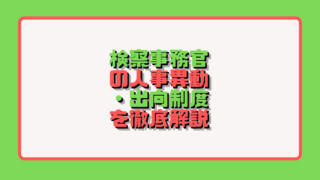
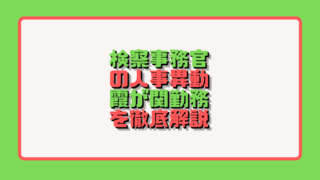
出向
検察事務官の出向についてですが,検察庁は法務省の特別の機関であることから,同じ法務省内の他官庁への出向があります。
この法務省内の他官庁への出向は「法務省内組織間人事交流」と言いますが,出向期間は2年間で,保護観察所や出入国管理局などに出向することができます。
法務省内組織間人事交流の詳細については下記記事でまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。
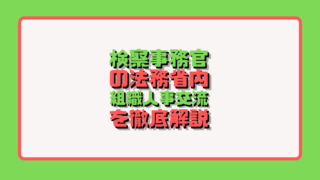
また,法務省内の他官庁以外にも出向先は多くあり,例えば,国税局や証券取引等監視委員会(通称「SESC」)などにも出向するルートが存在します。
ですので,出向ルートが数多く存在するということも検察事務官の魅力の一つとなります。
では,次に,検察事務官の研修制度について見ていきたいと思います。
検察事務官の研修制度
検察事務官の研修制度については,法務省の施設等機関にあたる法務総合研究所(通称「法総研」)が取り行う中央研修,法総研が各高等検察庁に委託して各高検単位で取り行う地方研修,法総研以外が主催するその他の研修がありますので,それぞれ見ていきたいと思います。
地方研修
地方研修についてですが,在籍年数に応じて全検察事務官が参加する研修になり,以下の研修が用意されています。
- 初等科研修
→採用1年目 - 中等科研修
→採用3年目(大卒)
→採用5年目(高卒) - 専修科研修
→中等科研修の4年後
各地方研修は各高等検察庁単位で行われるため,採用庁の同期だけでなく高検管内の他地検との同期とも交流を深めることができるので,非常に楽しい研修となります。
期間は研修によって若干異なりますが,期間は概ね40日前後の泊まり込みの研修となります。
中央研修
中央研修については,全ての検察事務官が受講するという研修ではなく,全国の地方検察庁から選ばれた職員しか参加することができない研修で,以下の研修があります。
- 組織間人事交流研修
法務省内組織間人事交流対象者 - 特別専攻科研修
→副検事任官希望者 - 裁判員裁判担当中核事務官研修
→中核事務官 - 高等科研修
→将来の幹部候補生 - 統括捜査科研修
→統括捜査官になった者 - 管理科研修
→課長になった者 - 管理研修科研修
→事務局長になった者
中央研修は全国各地の検察事務官が一同に会して集合を行うため,研修は法務省内で行われ,研修期間は千葉県浦安市にある法務省浦安総合センターで宿泊することになります。
高検管内の同期とは地方研修で交流がありますが,他高検管内の職員とはなかなか交流する機会がありませんので,非常に有意義な研修となります。
何より,検察事務官として出世するためには高等科研修への参加は必須となりますので,出世を目指す方は高等科研修に参加させてもらえるよう,日々の職務に励んでもらえればと思います。
その他研修
法総研が主催する地方研修・中央研修以外にも,検察事務官が参加することができる研修はたくさんあります。
私自身が全てを把握しているわけではありませんが,他の省庁が主催する研修として会計事務職員研修というものや,各地方検察庁が主催する簿記研修や外国語研修というものもあります。
どんな研修があるか気になる方は,是非入庁後に調べてみて,参加したい研修があれば是非手を挙げてみてみてください。
地方研修・中央研修・その他の研修の各詳細については下記記事にまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。
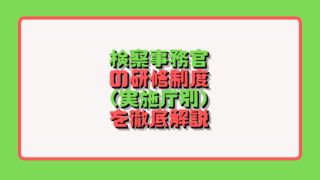
検察事務官の内部試験制度
検察事務官になると,若手の内は必ず受講しなければいけない検察官等全国一斉考試(通称「一斉考試」)というテストや,検察事務官から検察官になれる副検事の選考や検察官特別考試といった内部試験制度がありますので,それぞれ見ていきたいと思います。
検察事務官等全国一斉考試
一斉考試とは,職務の級が1級と2級の全検察事務官が受講しなければならないテストのことで,3級に昇格できるのは早くても30代前半のため,20代の内は毎年受講しなければならないテストになります。
試験科目については下記のとおりとなります。
- 憲法・検察庁法
- 民法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 検務事務
この一斉考試の成績と人事評価の関係についてですが,直接は関係ないとも言われていますが,普段の業務と違い目に見えて順位が付きますし,地方検察庁によっては一斉考試の成績を重視するところもあるみたいです。
ですので,検察事務官になるとある程度は一斉考試の勉強はしないといけないかなと思います。
一斉考試の詳細や過去問については下記記事でまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。
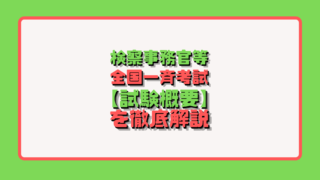
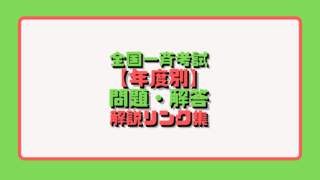
副検事の選考
副検事の選考についてですが,一定の在籍要件を満たした検察事務官が選考に合格すると副検事(検察官)に任官することができるという制度になります。
この副検事の選考は,実は検察事務官だけではなく警察官,裁判所事務官,国税査察官なども受験することができますが,合格者のほとんどは検察事務官ですので,副検事を目指すのであれば検察事務官からが望ましいかなと思います。
試験科目については,以下の通りとなります。
- 憲法
- 民法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 検察庁法
回答方法は,1次試験は論述,2次試験は口述試験となるため,一斉考試や公務員試験と比べてはるかに難しい試験になりますが,司法試験や予備試験よりは簡単であるため,しっかり勉強すれば合格が不可能な試験ではないかなと思います。
副検事になると検察官の職務を行うため非常に責任が重くなりますが,その分やりがいもありますし,給与も大幅に上がりますので,検察事務官にとっての魅力的なキャリアの一つとなります。
副検事の選考の詳細については下記記事にまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。
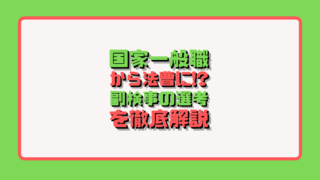
検察官特別考試
検察官特別考試についてですが,副検事に3年在籍すると受験することができ,合格すると特任検事となります。
試験科目については,以下の通りとなります。
- 憲法
- 民法
- 商法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 検察の実務
- 選択科目
民事訴訟法・法医学・刑事政策のうち1科目
副検事の選考より試験科目は増えますが,特任検事になると司法試験に合格して任官した検事と全く同じ立場になることができ,最終的には規模の小さい地方検察庁の検事正にまで出世できます。
また,特任検事に5年在籍すると弁護士資格認定制度に申請することができ,司法試験に合格せずとも弁護士資格を取得することもできます。
つまり,検察事務官から副検事,副検事から特任検事,特任検事から弁護士というステップを踏むことで検察事務官から弁護士になることもできますので,検察事務官にとっての魅力的なキャリアの一つとなります。
公務員で弁護士資格を取得できるまでのキャリアがあるところは他には無いですので,興味がある方は是非検察事務官を目指してもらえればと思います。
おわりに
今回は,検察事務官の各種制度(人事・研修・内部試験制度)について紹介してきました。
就職先のキャリアパスを理解するということは進路を決めるうえで重要な要素となりますので,検察事務官志望の方は是非参考にして,自身のキャリアプランを思い描いてもらえればと思います。
今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。