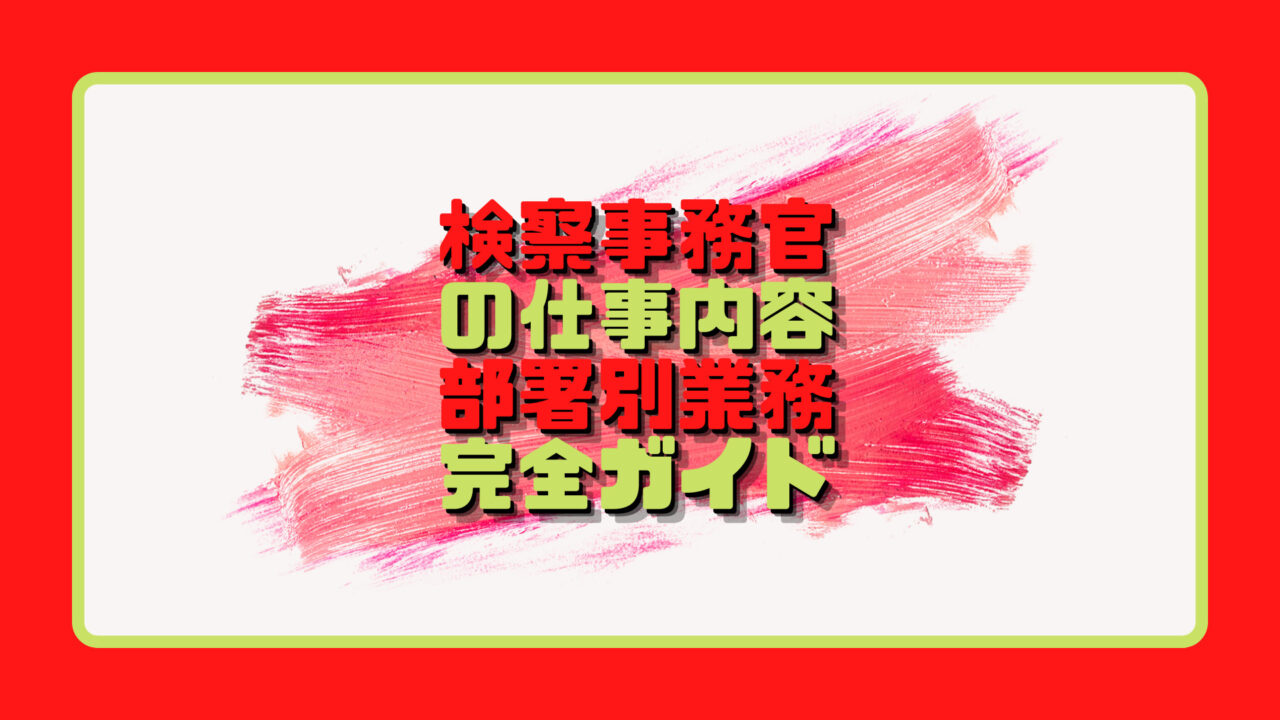こんにちは。
元検察事務官の検察辞太郎(やめたろう)(@moto_jimukan)です。
今回は,私が検察事務官として実際に働いていた経験から,検察事務官の仕事内容について,詳しく紹介していきたいと思います。
ちなみに,私のプロフィールの詳細については下記記事でご確認いただけますので,是非チェックしてみてください。
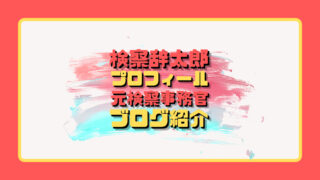
立会事務官の仕事内容
検察事務官の仕事は幅広くありますが,ドラマ『HERO』で松たか子や北川景子が役を演じていたことから「検察事務官=立会事務官」と思われている方も多いと思います。
実際,検察事務官人生の中で10年は立会事務官をやると言われているので,検察事務官のメインの仕事と言っても差支えがありません。
そんな立会事務官の仕事内容ですが,大きく分けると捜査事務と公判事務の2種類がありますので,それぞれの業務について詳しく説明していきます。
捜査事務
捜査担当検察官は警察等の捜査機関から送致される事件等を捜査し,起訴するかどうかの事件処理を行いますが,その検察官の捜査活動をサポートする仕事が捜査事務になります。
どのような捜査を行うかは事件によって千差万別ですが,立会事務官のメインの捜査事務として,①取調べ立会い,②事件捜査,③事務処理の3つの業務があります。
①取調べ立会い
検察庁における事件捜査は被疑者や参考人等の取調べがメインとなりますので,立会事務官の取調べ立会いは毎日のようにあります。
立会事務官の具体的な業務としては,被疑者・参考人の呼出しなどの日程調整,取調べに必要な通訳人や証拠品などを用意する事前準備,取調べで検察官が聴き取った内容を書面とする供述調書の作成などがあります。
場合によっては,立会事務官も取調べで聴取対象者に質問をしてもいいとする検察官もいますので,気になった点を直接質問したり内々に検察官に知らせるなど,立会事務官も積極的に取調べに参加することもできます。
取調べ立会いの詳細や出張取調べの詳細については下記記事にまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。

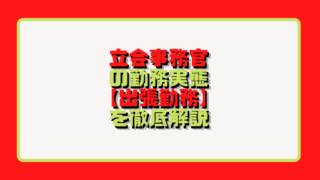
②事件捜査
先ほど,検察庁における事件捜査の中心は取調べと説明しましたが,取調べ以外にも証拠品の精査や事件現場の確認などの事件捜査捜査も行っています。
証拠品の精査で多いのが防犯カメラの映像チェックになりますが,検察官だけでなく立会事務官も確認し,場合によっては立会事務官が捜査報告書の作成を行ったりもします。
また,逃亡している被疑者の所在捜査や検察庁独自捜査事件での捜査など,ズバリ皆さんがイメージする事件捜査も立会事務官は業務として行いますので,なかなか体験できない経験をすることができます。
事件捜査の詳細や事件捜査の一環である司法解剖の立会いの詳細については下記記事にまとめていますので,是非参考にしてもらえればと思います。


③事務処理
立会事務官は①②の業務を行う捜査官ですが,あくまで「事務官」ですので,事務処理もメイン業務の一つとしてあり,主に事件配点時と事件処理時で事務処理が行われます。
事件配点時では刑事手続き上の不備がないかの確認や捜査に必要な事項の照会などを行い,事件処理時では決裁準備や事件記録などの体裁を整えて回付するなどを行っています。
①②の業務はパートナーである検察官しか立会事務官の仕事ぶりを把握できませんが,事務処理は色んな部署の事務官がチェックしますので,事務処理の仕事ぶりによって仕事ができるできないの評価をされがちな部分となります。
ですので,立会事務官にはきめ細かさや正確性というものが求められますね。
事務処理の詳細については下記記事でまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。

公判事務
公判事務は検察官の公判活動をサポートする仕事になります。
具体的には,捜査部から回付された起訴状・事件記録・証拠品の精査や整理,被害者や目撃者などの証人テスト,裁判所に提出する書類の作成などがあります。
仕事内容の詳細については改めて記事にまとめる予定ですので,また参考にしてもらえればと思います。
では,次に,地方検察庁の機構別の業務内容について見ていきたいと思います。
検察事務官の部署別業務内容
地方検察庁の機構についてですが,主に以下3つの部門で構成されています。
では,それぞれの仕事内容について詳しく説明していきたいと思います。
捜査・公判部門
捜査・公判部門での検察事務官の仕事は,主に,検察官とペアとなり捜査・公判をサポートする立会事務官,比較的軽微な事件捜査を単独で行う検察官事務取扱検察事務官(通称「検取」),裁判員裁判の公判をサポートする公判支援,庶務などを担当する事件管理などの仕事があります。
立会事務官の仕事内容については上述していますので,そのほかの職種の仕事内容について詳しく説明していきます。
検察官事務取扱検察事務官
検察官事務取扱検察事務官(通称「検取」)とは,「検察官が行う事務」の「取扱い」を命ぜられた検察事務官のことで,比較的軽微な事件(区検送致事件)を単独で捜査し,事件処理まで行います。
要は,捜査部の検察官の仕事と立会事務官の仕事を一人でやるということです。
ですので,検取には立会事務官の経験も必要となりますので,早くても30歳前後の任命となります。
また,検取になることで検察官の仕事を経験することができ,副検事試験の受験資格も取得できることから,副検事任官希望者が検取発令を受けることが多いです。
ちなみに,自分で取調べの日程調整ができ,比較的勉強時間を確保しやすいという点も,副検事任官希望者を検取にする理由の一つみたいですね。
副検事試験の詳細については下記記事にまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
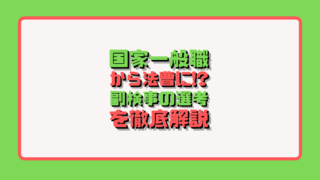
捜査公判支援
捜査公判支援とは,名前の通り捜査公判に従事する検察官及び検察事務官を支援する仕事で,非部制庁だと捜査公判支援,部制庁だと捜査支援・公判支援と分かれています。
捜査支援では被疑者の簡易鑑定などを担当し,公判支援では裁判員裁判で使用する統合捜査報告書の作成などを担当しています。
ちなみに,統合捜査報告書とは警察などの捜査機関が作成した捜査資料や証拠品を一般市民から選ばれる裁判員に理解し易いように組み合わせた報告書のことを言います。
事件管理
事件管理は,その中でも,庶務・下見・配点などの仕事に分かれていますが,簡単に説明すると,捜査・公判を担当する検察官と検察事務官をサポートする仕事になります。
庶務担当は名前の通り庶務業務を行いますが,下見担当は事件処理で立会事務官から回付される記録等のチェックを担当し,配点担当は新件の事件を配点登録するなどの仕事を行っています。
そのほかにも,事件数や処理件数をまとめる統計業務や,精神診断や被害者支援を行う仕事など多岐に渡りますが,規模の小さい検察庁だと一人で複数の業務を担当し,規模の大きい検察庁だと一人一業務の担当となりますね。
検務部門
検務部門とは,事件の受理から処理までの一連の刑事手続きを行う検察事務を担当する部署になりますが,以下7つの検察事務があります。
では,それぞれの検察事務の仕事内容について見ていきたいと思います。
事件事務
事件事務では,警察等の捜査機関から送致される事件記録を確認して受理手続を行う事務と,検察官の捜査が終了した事件の処理手続きに関する事務を行っています。
受理と処理の仕事を行っていることから,刑事手続きの入口と出口と言われています。
事件事務の仕事内容の詳細については下記記事にまとめていますので,参考にしてもらえればと思います。
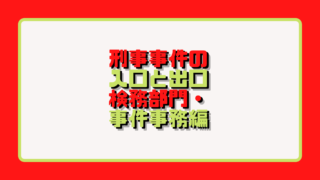
令状事務
令状事務では,裁判所に対する逮捕状や勾留状などの令状請求や令状執行に関する事務を行っています。
検察事務官の仕事は刑事手続きに関わる仕事なのでどれも重要ですが,令状事務は被疑者や被告人の身体拘束に関わる仕事なので,検察事務の中でも特に責任の重たい仕事となります。
証拠品事務
証拠品事務では,警察等の捜査機関から送られてきた証拠品の受入事務,保管事務,処分事務を行っています。
証拠品は,事件の真相解明のための重要な資料であり,また,所有者の財産でもありますので,適正に管理する必要があります。
また,証拠品の中には多額の現金や麻薬等の禁制品もありますので,より一層高い倫理観を持って仕事をする必要があります。
執行事務
執行事務では,判決確定後の自由刑の執行に関する事務と,実刑が確定した者が所在不明になった際の所在調査・身体拘束に関する事務を行っています。
実刑が確定して逃亡している者をとん刑者と言いますが,所在捜査でとん刑者の居所を掴めば遠隔地でも身体拘束しに行くなど,危険と隣り合わせのスリリングな仕事もあります。
徴収事務
徴収事務では,罰金等の刑が確定した後の罰金等の徴収,未納者に対する督促,未納者が所在不明になった際の所在調査・身体拘束に関する事務を行っています。
地方自治体や国税局においても税金の徴収事務や督促業務を行っていますが,検察庁では罰金未納者を労役場に収監できるという点で大きな違いがあります。
犯歴事務
犯歴事務では,有罪の確定判決を受けた者の前科や犯罪歴の調査・管理に関する事務を行っています。
警察などの捜査機関や検察事務官からの前科照会への回答や市町村への裁判内容の通知が主な業務ですが,地方検察庁の中では比較的業務量の少ない部署となります。
記録事務
記録事務では,事件終結後の記録等の保管・管理に関する事務と,保管記録等の閲覧に関する事務を行っています。
被疑者の過去の事件記録は捜査方針を決める重要な資料となるため,記録の貸出は頻繁に行われますが,事件によっては記録が段ボール箱数十箱なんてものもありますので,意外と体力が必要な仕事となります。
事務局部門
事務局部門は,検察庁組織を円滑に運営するための仕事を行う部門で,民間企業にもあるよう総務・会計事務を行う部署があります。
では,総務事務と会計事務についてそれぞれ見ていきたいと思います。
総務事務
総務事務は,職員の勤務時間や健康管理に関する事務,人事・給与に関する事務,職員の福利厚生に関する事務,文書の受付・発想に関する事務を行っています。
部署名で言うと,総務課や人事課などが総務事務を担当しています。
会計事務
会計事務は,罰金等の納付などに関する歳入事務,業務に必要な物品の調達や職員の出張旅費支給等に関する歳出事務,検察庁庁舎の維持管理などに関する事務を行っています。
部署名で言うと,会計課,庁舎管理課などが会計事務を担当しています。
では,最後に,検察事務官の働き方について見ていきたいと思います。
検察事務官に共通する仕事内容
これまで所属別の仕事内容について見てきましたが,一般的に検察事務官全般に共通する働き方として時間外勤務,宿直・日直勤務,応援勤務,運転業務について説明していきます。
時間外勤務
検察事務官の時間外勤務として超過勤務と休日勤務がありますが,どのような場合に時間外勤務が発生するのか,それぞれ見ていきたいと思います。
超過勤務
超過勤務とはいわゆる残業のことをいいますが,検察事務官の超過勤務の多い少ないは所属する部署によります。
超過勤務が比較的多い部署は以下となります。
- 捜査部門の立会事務官
- 捜査部門の事件管理・下見担当
- 検務部門の令状担当
- 事務局部門
比較的多いといっても常にというわけではなく,事件数や繁忙期等によって異なってきます。
超過勤務の詳細については下記記事にまとめていますので,参考に見てもらえればと思います。
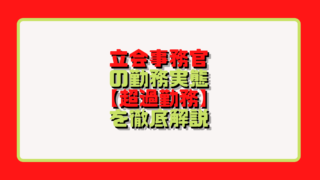
休日勤務
休日勤務とは土日祝日の勤務になりますが,休日勤務をするのはほぼほぼ捜査部の立会事務官となります。
立会事務官の休日出勤は平日に来庁できない参考人等の取調べの場合がほとんどで,刑事のように事件現場に呼出されるなんてことはほとんどありません。
ちなみに,本部係検事担当の立会事務官だけは重大事件が発生した場合に現場臨場しなければなりませんが,ほぼ全ての立会事務官にとっては関係のない話となりますね。
休日出勤の詳細については下記記事にまとめていますので,参考に見てもらえればと思います。

宿直・日直勤務
地方検察庁では,24時間・365日,事件に対応できるよう宿直勤務と日直勤務が存在しますので,それぞれの仕事について見ていきたいと思います。。
宿直勤務
宿直勤務ですが,地方検察庁に寝泊まりし,警察からの連絡に対応するという業務を行っています。
具体的には,事件性が疑われる変死体を発見した警察から事情を確認し,当番検察官に司法解剖の要否を確認した上で警察にその旨を伝えるという業務になります。
ただ,基本的には当番検察官への電話取次ぎと経過の報告書作成だけになりますので,当番検察官に専用の携帯を支給するなど,宿直勤務自体を廃止する地方検察庁が増えているみたいです。
おそらく業務説明会等で説明があると思いますので,是非自身が志望する地方検察庁の宿直勤務の有無を確認してみてください。
ちなみに,宿直勤務があるのは男性のみとなります。
宿直勤務の業務内容の詳細については下記記事にまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
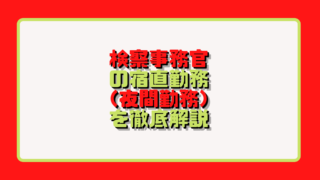
日直勤務
刑事手続きでは被疑者の逮捕から48時間以内に検察庁に事件送致しなければならないとされていますので,土日祝日でも身柄事件の送致に対応するため日直勤務があります。
具体的には,身柄拘束されている被疑者から弁解を録取し,勾留請求するか釈放するかを判断します。
若手の検察事務官だと立会事務官の役割が多くなりますが,年次が上がると事件事務や令状事務などのチェックの役割を担うことになります。
ちなみに,宿直勤務は男性のみでしたが,日直勤務は男女関係なく全ての検察事務官が従事する業務となります。
日直勤務の詳細については改めて記事にまとめる予定ですので,また参考にしてもらえればと思います。
応援勤務
地方検察庁での応援勤務は主に事件応援と立会応援となりますが,どのような場合に応援勤務が発生するのかについて,それぞれ見ていきたいと思います。
事件応援
検察庁の捜査では,基本は担当検察官と立会事務官のワンペアで捜査に当たりますが,聴取対象者が多い場合や事案が複雑な重要事件などは他のペアに応援勤務に入ってもらう場合があります。
応援勤務の範囲は,同じ地方検察庁の同じ部署への応援,同じ地方検察庁で違う部署への応援,他の地方検察庁への応援があります。
代表的な応援勤務は特別捜査部への応援勤務になりますが,詳細については下記記事にまとめていますので,参考にしてもらえればと思います。
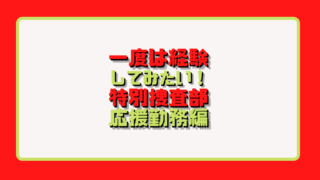
立会応援
検察事務官には採用年度に応じて受講する集合研修がありますが,研修参加者が立会事務官の場合は,研修期間中の間,代わりに立会事務官をやる応援勤務が必要となります。
特に,採用3年目(高卒は5年目)に行われる中等科研修では研修参加者が立会事務官をやっていることが多いため,立会応援の人数は多くなります。
この立会応援に入る人の基準については各地方検察庁によって異なりますが,一般的に,立会事務官の仕事を経験する良い機会なので,採用1年目の新規採用職員が立会応援に入ることが多いです。
仕事内容については上記で説明した立会事務官の仕事と同じになりますが,立会応援の詳細については下記記事にまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
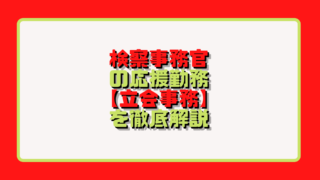
運転業務
検察事務官の運転業務についてですが,捜査部の立会事務官や検務部門の徴収や執行担当者などは業務で車を運転する場面はあります。
ただ,地方検察庁には車の運転業務を専門にする検察技官がいますし,要件を満たせばタクシーの利用もできますので,車の運転スキルが必須というわけではありません。
ただ,車の運転ができた方が仕事をするうえで自身が楽になる場合が多いので,運転できるに越したことはないかなと思います。
運転業務の詳細については下記記事にまとめていますので,是非見て参考にしてもらえればと思います。
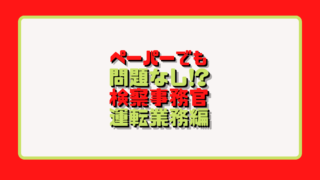
おわりに
今回は,検察事務官の仕事内容について紹介してきました。
検察事務官になるためには,検察事務官の仕事に対する理解が何よりも大事となりますので,検察事務官志望の方は是非繰り返し見て参考にしてもらえればと思います。
今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。